男女平等 の検索結果 標準 順 約 180 件中 1 から 20 件目(9 頁中 1 頁目) 

- 男女平等への長い列 私の履歴書
- 赤松良子
- 日経BP 日本経済新聞出版
- ¥1870
- 2022年07月21日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.25(5)
均等法の母と呼ばれてーー
2021年末に日経新聞朝刊に元文相・赤松良子氏が連載した「私の履歴書」を大幅加筆のうえ書籍化。女性官僚のさきがけとして歩んできた半生は、戦後日本の女性の地位向上の歴史と軌を一にする。連載時には、特に男性と同等に働きたくても働けなかった世代の女性から、書籍化を望む声が相次いだ。
赤松氏の官僚人生の集大成が1985年の男女雇用機会均等法の成立である。労働省で53年にキャリアをスタートさせるも、旧弊な組織と社会の中で様々な壁にぶつかってきた。しかし持ち前のガッツと知恵で立ち向かい、大きな仕事を成し遂げた。イクメンが当たり前になった世代にとっては、かつて企業に女性の結婚退職制や男女で異なる定年制があった歴史など知る由もないだろう。「育児休業」という言葉も72年の勤労婦人福祉法に初めて盛り込まれた。
法律で社会に制度化されなければ、世の中は動かない。志を高く持ち、強い信念とバランス感覚で、ついに歴史を動かした。女性活躍の地平を切り開いたパイオニアの歩みには、未来を担う女性たちへの熱いエールが詰まっている。
第1部 私の履歴書
長い列に加わって
1
父のアトリエ
あこがれの職業婦人
夢は東京へ
津田塾
東大へ
2
労働省
結婚
人事の壁
雌伏
初めての海外
国際的な視点
3
男女平等
群馬労基局
婦人参政権25周年
勤労婦人福祉法
国際婦人年
4
国連公使
女子差別撤廃条約
男女平等法制
労働側の反発
男女雇用機会均等法成立
世界婦人会議
5
ウルグアイ大使
官僚を辞す
文相
文化活動
女性たちの恩人
列は続く
6
均等法の父
市川房枝さんのこと
津田に息づく思い
人と人との不思議な縁
母への恩返し
猫のいる暮らし
「きょうよう」と「きょういく」
あとがき
年譜
第2部 資料編
各種指標で見る男女平等の現在
関係法令
日本国憲法(抜粋)
女子差別撤廃条約
男女雇用機会均等法(1986年施行当時のもの抜粋)
男女雇用機会均等法の主なあゆみ

- 男女平等はどこまで進んだか
- 山下 泰子/矢澤 澄子/国際女性の地位協会
- 岩波書店
- ¥990
- 2018年06月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
日本が女性差別撤廃条約を批准して30年余。この間、批准した内容に沿って女性の地位や権利の向上は進んだでしょうか。そうとは言い難い現実をふまえ、条約の理念と条文の内容を身近なテーマやトピックスを入り口にやさしく解説し、家庭や職場、地域での課題を明らかにします。巻末には条約(対訳)・選択議定書を収録。

- 現代版「男女平等」の考えは正しいのか!!
- 堂前雄平
- 文芸社
- ¥1210
- 2022年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 「助けて」と言える社会へ
- 大沢 真知子
- 西日本出版社
- ¥1980
- 2023年05月31日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
本書は、長年、非正規・ワーキングプア・ワークライフバランスなど、特に女性キャリア研究に打ち込んできた著者がさまざまな現場取材や研究プロジェクトで明らかになった問題と提言をまとめた野心作です。
コロナ禍でより顕在化した性暴力、男女不平等社会の実態
性暴力被害者の実態を社会に伝え、性暴力が生じるメカニズムを解明するとともに、性暴力のない社会を目指ために、私たち一人ひとりがどう取り組んでいくべきか……。
セクシャル・ハラスメントや性暴力問題に関心があったり、深刻な悩みを抱えている全ての人たちに強くお勧めします。
【目次】
はじめに
第1章 追い込まれる女性たち
1 女性を直撃したコロナ渦ーDVとその実態
2 ドメスティックバイオレンス(DV)とは何か
3 コロナ下で増加するDV相談と「DV相談プラス」
4 DV被害者の支援
第2章 性暴力被害者支援のために
1 「性暴力救援センター 日赤なごやなごみ」の設立
2 長江美代子さんのお話
3 片岡笑美子さんのお話
4 なごみの活動からわかったこと
5 女性のための女性による相談会
6 共依存という問題
第3章 三万八三八三件の被害者から見えてきた性暴力の実態
1 性暴力とは何か
2 ある性被害者の証言
3 アンケート調査の結果から見えてきたこと
4 刑法の改正と今後
5 強姦神話と不十分な被害者への支援
6 声を上げた被害者たちによって変化が始まっている
第4章 職場における性暴力
1 セクシャル・ハラスメントの規制
2 増える就活セクハラ
3 実態調査の結果から見えてきたこと
4 NHKのアンケート調査の結果から見えたこと
5 男性の被害者の経験から見えてくるもの
6 セクハラは男性問題
第5章 男女不平等社会とDV・性暴力
1 平成は失われた時代だったのか
2 コロナ渦が浮き彫りにした男女不平等社会日本
3 性被害による社会的・経済的損失
4 幼少期の被害がその後に与える深刻な影響
5 「助けて」と言える社会へ
あとがき
参考文献
付録 相談先一覧

- 経済学者たちの女性論
- 柳田芳伸/原伸子
- 昭和堂
- ¥7370
- 2025年11月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
資本主義の成立と発展のなかで、過去の経済学者たちは女性や家族をどのように描いてきたのか。本書では、18世紀末から20世紀初頭の経済学者たちの思想をたどり、家事やケア労働の価値にも光をあてながら、これまで見過ごされてきたジェンダーの視点で経済思想を問い直す。
序章 経済学者の女性論に見るジェンダー思想史
ーー近代社会と「ジェンダー秩序」 柳田芳伸、原伸子
第1部 産業革命期における女性解放の主導者たち
第1章 商業社会と女性
ーーヒュームからトンプソンまで 山尾忠弘
第2章 イギリス産業革命期の結婚と女性
ーーマルサスの所論 柳田芳伸
第3章 ベンサムにおける性的快楽主義と女性
ーー同性愛行為・宗教批判・結婚制度 板井広明
第4章 J. S.ミルの『経済学原理』における女性
ーー男女の平等から労働者の境遇改善へ 小沢佳史
第5章 ハリエット・マーティノゥの経済学
ーーヴィクトリア時代の異端派エコノミスト 船木恵子
第2部 福祉国家黎明期におけるフェミニズム運動の展開
第6章 ミリセント・フォーセットの賃金論
ーー賃金基金説から同一労働同一賃金の提唱へ 松山直樹
第7章 「性の貴族制」から条件付き競争へ
ーーエッジワースにおける女性労働論の思想的変容 上宮智之
第8章 母性手当から家族手当へ
ーーエレノア・ラスボーンによる貧困調査とその解釈を中心に 赤木 誠
第9章 「革新主義時代」のフェミニズムと家政学
ーー無償労働の「発見」とジェンダー平等 原 伸子
第3部 20世紀初頭の日本における女性平等思想
第10章 河田嗣郎の家族崩壊論の特徴
ーー高田保馬による批評を手がかりに 吉野浩司
第11章 永井享の婦人論
ーー社会が求める女性像をめぐって 杉田菜穂
第12章 石橋湛山の消費論と女性
ーー婦人経済会との関係を中心に 牧野邦昭

- 男尊女子
- 酒井 順子
- 集英社
- ¥1540
- 2017年05月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.38(45)
「働け、産め、輝け!」安倍政権の下、女性が輝ける社会をと叫ばれながらも、日本の男女平等度ランキングは世界101位(2015年)。その根に潜む、女性自身の男女差別意識をあぶりだすエッセイ20章。

- やってよかった育児パパ
- 谷沢英夫
- 新評論
- ¥1980
- 2023年04月26日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
50年にわたる在住経験で体感した北欧ジェンダー先進社会の理念と実践。
自らの意識を変革しつつ子と向き合う育児の真髄
「育児に携わり、日々、子どもが成長する様子を見届ける生活は、このうえなく楽しいものでした。それを可能にしてくれたのがスウェーデンの社会なのです」
そんな社会に50年間暮らし続けた著者は、自らの子育てを振り返って、スウェーデンという国の「男女平等原則が大きく影響した」としている。著者が日本の父親に対して育児をすすめるのは、それが「幸せなこと」であるからだ。彼の妻はスウェーデン人でプレスクールの園長。それゆえ、一般の保護者よりも育児というものが身近にあったのだろう。日々の営みのなかで家族の「幸福」に焦点を当てているところが本書の特徴となっている。
1960年代より欧州社会は「男女共同参画」を発展的な課題として受け入れ、多様な人々が暮らしやすい環境を模索してきた。そのような社会的うねりのなかで、父親たちは真っ直ぐな眼差しでその変化を見つめてきた。他者のケアに携わっている人は「無意識にもっている偏見」を常に問い返される。そのよき例として、「プレスクールのビデオ観察」についても触れている。この観察は、子どもと向き合うトレーニングを積んだ人たちでさえ、男女役割分担という思考の枠組みから解放されていないことを示していた。だからこそ、私たち一人ひとりもそのことを意識しようと著者は言っている。
「男・女らしさとは何だろう?」、「子どもたちとどのように接するの?」--後半では、子どもと過ごした日々から得られたヒントが示されている。読み進めれば、読者自身の日常がそこに重なっていくだろう。示された言葉は、家族と向き合った時間から紡がれた「本当に大切なもの」ばかりだ。だからこそ、その思いが私たちを優しく包んでくれる。
結びとして掲載された「スウェーデンの子どもたちへの調査結果」において子どもたちは、大人に対して語りかけている。「スウェーデン社会の選択は成功であった。私たちの声こそが、希望ある未来を切り開いた社会である!」(株式会社アネビー 藤井薫)

- 高島道枝選集 [第3巻]雇用・労働における男女平等をめざして
- 高島 道枝/高島 千代
- 日本評論社
- ¥7700
- 2025年01月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
性別による賃金・雇用格差問題を扱った論稿を収録。「第1部賃金の平等へ」「第2部雇用の平等へ」「第3部賃金格差の理論など」。全4巻。

- 男女別学の倫理とイスラーム
- 小野 仁美/服部 美奈
- 地平社
- ¥3080
- 2026年03月10日頃
- 予約受付中
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
文化的富の継承のあり方を再考する。
ジェンダー不平等の象徴とみなされがちな男女別学。だが、それは教育現場が何をいかに伝えるかによる。イスラーム諸国の多様な事例をもとに、別学・共学の文化的富の継承のあり方を再考し、学校教育の課題に挑む画期的研究。

- 誰もがその人らしく 男女共同参画
- 21世紀男女平等を進める会
- 岩波書店
- ¥528
- 2003年04月18日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)

- データから読む 都道府県別ジェンダー・ギャップ
- 共同通信社会部ジェンダー取材班
- 岩波書店
- ¥748
- 2024年07月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.33(5)
世界経済フォーラムが公表する男女平等度の指標で、日本はG7最下位、世界でも最低レベルが続く。根本原因を地域から探り、底上げできないかーー。フォーラムに準じた手法で、47都道府県ごとに分析し、政治、行政、教育、経済の4分野で強みや課題を可視化した。データや現場取材から誰もが生きやすい社会へのヒントを示す。
はじめにーー都道府県版ジェンダー・ギャップ指数が目指すこと……………三浦まり
第1章 ジェンダー・ギャップを可視化するーー世界の中の日本、そして地域へ
第2章 都道府県ごとの特徴を知ろうーー2024年版指数が映す「強みと課題」
第3章 日本国内の変化の兆しーー自治体、企業、若者、新聞社の挑戦
コラム 誰もが自分らしく歩める地域に……………赤間早也香
第4章 海外の現状ーー北欧と東アジアは今
おわりにーー地域から、この国のジェンダー平等実現を……………山脇絵里子
関連サイト紹介
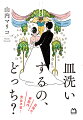
- 皿洗いするの、どっち? 目指せ、家庭内男女平等!
- 山内マリコ
- マガジンハウス
- ¥1320
- 2017年02月27日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.6(29)
結婚って、超ハッピー?
それとも、地獄?
男と女の果てなき心理戦を痛快レポート!
アラサー期に恋愛モードを迎え、
「同棲→結婚」のパターンをたどった
人気女子作家の超個人的実況レポートで
男と女の真実がまるわかり!
・男がいると家事は3倍?
・男手問題は同棲で解決する?
・猫と暮らす女の弱点は?
・女が本当に欲しいものは?
・「男は大型犬」説の真実とは?
・・・etc.
婚前男女の9割が気づかない
男の実態、女の言い分が満載。
結婚を考える女子必読!
既婚女子には共感指数MAX!

- 1945年のクリスマス
- ベアテ・シロタ・ゴードン/平岡磨紀子
- 朝日新聞出版
- ¥1100
- 2016年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.44(18)
「女性が幸せにならなければ、日本は平和にならないと思った。男女平等は、その大前提だった」10年間日本で育ち、アメリカで終戦を迎えた著者は、22歳の若さで日本国憲法GHQ草案の作成に参加、現在の人権条項の原型を書いた。文庫化に際し、ジョン・ダワーの寄稿を増補。

- 私はいま自由なの?
- リン スタルスベルグ/枇谷 玲子
- 柏書房
- ¥2420
- 2021年09月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(10)
ジェンダー先進国とされるノルウェー。
だが、そこに住む女性たちは幸福なのか。
労働問題を扱うジャーナリストが、
「先進国」ができるまでの過程を点検し、
仕事と家事、両方の負担に押しつぶされそうな
ノルウェー女性たちの肉声を拾い集める。
「ジェンダーギャップ」を埋めただけでは解決しない、
日本もいずれ直面する本質的な課題を
浮かび上がらせる渾身のレポート。
はじめに 胸騒ぎ
第一章 「仕事と家庭の両立」という難問
第二章 70年代の神話と社会変革の夢
第三章 仕事をすれば自由を得られる?
第四章 キャリア・フェミニズムと市場の力学
第五章 可能性の時代は続く
謝辞
原注

- 歴史,文化,慣習から考える開発経済学
- 山田 浩之
- 勁草書房
- ¥5720
- 2025年01月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
「歴史、文化、慣習」といった要素に着目し社会経済や人々の行動にどのような影響を及ぼすのかを綿密な実証分析を用いて解き明かす。
標準的な経済理論や実証研究において、ややもすると組み込み難い要素である「歴史、文化、慣習」が、人々の社会経済活動にいかように影響を及ぼしているかに関する実証分析を東・東南アジアの国々のケーススタディを用いて示す。多くのケースで、人間は歴史、文化、慣習といった要因から無関係ではいられないことが明らかとなった。
まえがき
初出一覧
第1章 イントロダクション
第2章 ベトナムの皇帝試験の遺産(1075年から1919年まで)--儒教文化の教育投資及び男女不平等への影響
1.はじめに
2.データ
3.皇帝試験(1075-1919)の合格者数の出身地区(district)レベルでの持続的相関関係
4.計量経済学的手法
5.儒教文化の現代の教育投資への影響:推計結果及びメカニズム
6.儒教文化の現代の男女不平等への影響:推計結果及びメカニズム
7.結論:研究の限界及び残された課題
補論1.ベトナム皇帝試験(1075年から1919年まで)
補論2.現在の教育制度(1992年以降)
補論3.2009年のNEEU
第3章 仏教における輪廻感と商業的性行為の関連
1.はじめに
2.仏教と輪廻転生
3.データと実証モデル
4.推計結果
5.結論
第4章 共産党中央部の幹部による出身地贔屓・縁故主義ーーベトナムにおける企業活動との関係からの証拠
1.はじめに
2.政治家による出身地贔屓とCPV中央委員会
3.データ
4.計量経済学的手法と定式化
5.推計結果と潜在的メカニズム及び動機
6.結論
補論 データ構築に関して
第5章 医療現場における賄賂の慣習ーー患者の厚生及び公的医療保険加入との関係
1.はじめに
2.既存研究と本章の貢献
3.本研究の背景
4.データと分析手法
5.推計結果
6.考察及び政策的含意
7.結論
第6章 家庭内出生順序効果の変遷ーー3回の国勢調査を用いたカンボジアの事例
1.はじめに
2.出生順序効果の潜在的メカニズム
3.データ
4.グラフを用いた分析
5.計量経済学的手法
6.分析結果
7.結果の考察及び議論
8.結論
補論1.サンプルの構築
補論2.もともとの出生順序と相対的出生順序
第7章 丙午年における出生行動への影響ーー親の子に対する性別嗜好の研究
1.はじめに
2.データ
3.歴史的背景と記述的データの結果から得られる情報
4.概念的枠組み
5.計量経済的モデル及び手法
6.実証分析結果
7.結論
補 論 丙午年に生まれた女性は本当に不運なのか?--1966年の丙午年生まれの女性の社会・経済的環境に関する分析
1.はじめに
2.1996年の丙午年,概念的枠組み,関連文献
3.データ
4.丙午年生まれの女性は,その周辺の年に生まれた女性と大きく異なるのだろうか?
5.差の差分析を用いた丙午年生まれの男女間の比較
6.ディスカッション:予想通りか,不可解か,それとも何か考慮が欠けているのか?
7.結論
第8章 歴史,文化,慣習と開発経済学
参考文献
索 引

- フランスのワーク・ライフ・バランス
- 石田 久仁子
- パド・ウィメンズ・オフィス
- ¥3080
- 2013年12月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 1.0(1)

- 学習まんが 世界の伝記NEXT ルース・ベイダー・ギンズバーグ
- 二尋 鴇彦/堀ノ内 雅一/大林 啓吾 (慶応義塾大学教授)
- 集英社
- ¥1210
- 2025年03月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
おもしろくてわかりやすい! 集英社版・学習まんが『世界の伝記NEXT』から展開中の「伝記×SDGs」は、偉人の生き方からSDGsの目標達成のヒントがもらえる新シリーズ。
第3弾は性差別とたたかった裁判官ルース・ベイダー・ギンズバーグです。
ルース・ベイダー・ギンズバーグは2020年になくなるまでの27年間にわたり、アメリカの連邦最高裁判所で裁判官をつとめた女性です。
ルースは1933年、ニューヨークに住むユダヤ系の両親のもとに生まれ、幼いころからとても優秀でした。しかし、当時のアメリカでは教育や職業をめぐる女性差別やユダヤ人差別がひどく、若いルースもたびたび差別に悩まされます。それでも「女性の自立」を説いた母の教えを胸に、法のもとで平等な社会を実現するために法律家を志します。
弁護士となったルースは男女平等が問われたいくつもの裁判で実績を上げ、弱い立場にあった女性、ときに男性を助けます。その後、裁判官として判決をくだす立場となり、1993年には最も重要である連邦最高裁判所の裁判官に指名されました。最高裁判所では、男女の賃金格差に異議を唱えたり、マイノリティの権利を守ったり、多くの判決や意見で注目を集めつづけました。ルースは法のもとの平等を目指す「正義の象徴」として、アメリカじゅうの人びとから尊敬される存在になったのです。
【本書の特長】
●まんがだから読みやすく、わかりやすい!
●すべてふりがな付きなので、小学校低学年から楽しく読める!
●Q&Aや年表など、よりくわしく知ることができる記事ページも充実!
【もくじより】
広がる好奇心
認め合うパートナー
わたしは負けない
差別とのたたかい方
わたしは反対します
解説:R・B・Gは法のもとの平等が正義だと考えました

- 男女平等原則の普遍性
- 植野 妙実子
- 中央大学出版部
- ¥7590
- 2021年03月25日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
女性政策の日仏比較を通して、現状の分析を行い、男女平等の観念、法整備、政策のあり方を検討し、展望を示す好著。日本では性別役割分担の意識がまだ強く、夫婦別氏制の成立や女性天皇の出現も見通せないが、日本国憲法の平等の基本に立ち返り対応を提示する。他方で、パリテ(男女同数)の観念を憲法に導入し積極的に男女平等政策を推進したフランスにおいては、女性にとって働くことは当然のことであり、女性の議員や公務員も多い。さらに現在では、女性の管理職・幹部職を増やすための法整備や政策を進めている。こうしたフランスのあり方を紹介して、日本の女性の一層の活躍のために何が必要かを示す、研究者にも一般読者にも参考となる本。
1部 日本における男女平等
第1章 個人の尊重と三つの自立
第2章 憲法制定過程・民法改正過程の男女平等
第3章 氏名権の憲法的意義
第4章 選択的夫婦別氏制の必要性
第5章 「家庭教育」支援と男女平等
第6章 女性天皇をめぐる問題
第7章 女性天皇問題の光と陰
2部 フランスにおける男女平等
第8章 男女平等を推進する平等概念
第9章 平等概念の変容とその実質化
第10章 パリテの成立と実施
第11章 パリテの現在
第12章 フランスの公職における男女平等
第13章 公職における基本原則
第14章 公職における男女平等の現在
第15章 フランスにおける女性の氏名権
終章 フランスにおける女性政策

- 【バーゲン本】男女平等教育阻害の要因 明治期女学校教育の考察
- 櫛田 眞澄
- (株)明石書店
- ¥3410
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
跡見学園や東洋女学校など明治期から現在まで続く女子高校、女子大学を中心に、その建学の理念、当時の授業内容をつぶさに調査。「和洋裁伝習」などの職業訓練や「良妻賢母」の養成など、現代の教育に通じる男女不平等の要素を詳細に検証する。

- 現代の語彙
- 田中 牧郎
- 朝倉書店
- ¥4070
- 2019年04月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
女性の地位が向上しインターネットで未曾有の変化を続ける現代の語彙を探る。〔内容〕性差/待遇場面/外来語/商品命名/作家の語彙創造/アニメキャラクター/Jポップ/テレビ放送/ネット集団語/医療/司法/やさしい日本語/国語政策
序 現代の語彙への誘い (田中牧郎)
第1部 変貌する現代社会と語彙
1. 言葉の性差の背景とゆくえ(森山由紀子)
2. 待遇場面による語の選択 (西尾純二)
3. 外来語の氾濫と定着 (茂木俊伸)
4. 商品命名という言語行為 (蓑川惠理子)
第2部 メディアによる語彙の創造と広がり
5. 作家による語彙の創造 (半澤幹一)
6. アニメキャラクーの言葉 (金水 敏)
7. 流行歌・Jポップの言葉 (伊藤雅光)
8. テレビ放送による言葉の広がり (加藤昌男)
9. 新しいコミュニケーションツールとネット集団語(三宅和子)
第3部 語彙の規範と改良
10. 医学用語の特徴と医療の言葉 (笹原宏之)
11. 裁判員制度の導入と司法の言葉 (大河原眞美)
12. 外国人のための「やさしい日本語」における言葉の基準 (森 篤嗣)
13. 語彙はなぜ国語施策に取り上げられないのか (関根健一)