ジェンダー の検索結果 標準 順 約 2000 件中 181 から 200 件目(100 頁中 10 頁目) 

- ラストジェンダー 〜何者でもない私たち〜(1)
- 多喜 れい
- 講談社
- ¥715
- 2021年05月21日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
とあるハプニングバーに集まるセクシャルマイノリティの人々の物語ーー。
ハプニングバー「BAR California」。ここは性別・性癖・性的指向も異なる人々が集まる場所。
人々は「何か」になるためにこのバーを訪れるーー。
他人の声に傷ついてきたトランスジェンダーのバイセクシャル。
本当の恋を探すパンセクシャル(全性愛者)。
男女二つの性自認を持つ両性ーー。
人の数だけセクシャリティがある。
性と愛にまつわる珠玉のオムニバスストーリー!

- 2ひと2 教育/ジェンダー/安全な水とトイレ
- 松葉口玲子
- 学研プラス
- ¥2750
- 2022年02月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
SDGsの17の目標をおはなしで楽しめる絵本。2巻は、目標4教育、目標5ジェンダー、目標6水とトイレのテーマで、男らしさ女らしさ、もしもトイレがなかったらなどのおはなしを紹介。やさしい絵が中心なので低学年からの読み聞かせ・ひとり読みに。

- 【謝恩価格本】〈体育会系女子〉のポリティクスー身体・ジェンダー・セクシュアリティ
- 井谷 聡子
- 関西大学出版部
- ¥2200
- 2021年03月22日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
日本の女子選手たちは、男子選手ならば経験することのない、こうした矛盾した要求を突きつけられる。なでしこジャパン、女子レスリング……2000年代以降、かつて「男の領域」とされたスポーツで活躍する女子選手の姿をメディアで多く目にするようになった。
強靭な身体と高度な技能、苦しい練習を耐えるタフな精神力や自律が要求されるエリートスポーツの世界。その中でも「男らしいスポーツ」とされるサッカーとレスリングの世界で活躍するたくましい「女性アスリート」たちはどう語られたのか。メディアの語りから見えてくる「想像の」日本人の姿とは。そこに潜むコロニアリティとは。また、トランスジェンダーへの差別が絶えない社会で、トランスジェンダーやシスジェンダーでない選手たちは、女子スポーツの空間や「体育会系女子」をめぐる言説とどのように折り合いをつけ、スポーツ界に居場所を見出してきたのだろうか。
本書は、日本の女子スポーツ界を取り囲む家父長制的、国民主義的、異性愛主義的、そしてシスジェンダー主義的言説を明らかにし、抑圧の構造に迫る。同時に、その抑圧的環境を創造的に克服してきた選手たちにスポットライトを当てることで、「生きることのできるアイデンティティ(livable identity)」、そしてより多くの可能性に開かれた主体性(subjectivity)のあり方を探る。

- 「世界」をどう問うか?
- 井野瀬久美惠/粟屋利江/長志珠絵
- 大阪大学出版会
- ¥2640
- 2024年04月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
ジェンダー視点で見る新しい世界史通史
現代のグローバルな課題を捉え直す
現代性の歴史的文脈をたどり、暴力・環境・災害・疫病・最新科学に切り込む!
今ここから見えている「世界」は、他の人たちが別の場所から見ている「世界」と同じだろうか。「世界」を問い、「世界を問う私」を問うーこの双方向性のなかに身を置くとき、私たちは「世界」が決して自明のものでないことを再認識させられる。だとしたら、「世界」の歴史、「世界史」とは何だろうと、西洋中心、成人男性中心に描かれてきた従来の「世界史」を見直さざるをえなくなる。時間軸と空間軸とを交差させ、比較と関係性を考えるジェンダー史の視点で考察していく。
本巻のもう一つの目的は、現代的諸課題と向き合うことである。私たちは今、地球規模で考え、協力して取り組まねばならない問題を数多く抱えている。新型コロナウィルス・パンデミックを経験し、ロシア・ウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻といった20世紀の分断を引きずりながら、私たちは、ビッグデータやIoT、生成AIといったデジタル技術が人間の諸関係を左右する21世紀を生きている。そのなかで、諸課題の解決に向かう端緒を開くためには、適切な問いを発し、その問いを根拠(史料/ 資料)に基づいて多角的・多層的に掘り下げていかなければならない。
本巻では、シリーズ全体を貫くジェンダー史の視点から現代世界に斬り込み、その「現代性」の本質を熟考する。換言すれば、それは、20世紀という時代をジェンダー史の視点で「歴史化」し、「相対化」する作業にほかならない。
第1章では、私たちが知る「世界」がどのように創られ、語られてきたのかを、「世界」を構成する「地域」との関係性で考察する。
第2章では、「世界」と「地域」の関係性が創られ、創り直されていく大きな契機となった植民地化と脱植民地化をジェンダー視点で検証する。
そこに絡まるのが、20世紀末の技術革新で急速に進展したグローバル化の問題であり、第3章ではその諸相が議論される。ひとの移動とそれに伴う運動や思想、とくにフェミニズムの変化、戦争や紛争といった数々の暴力に抗う人々の連帯と異議申し立ての多様性が、各地域の具体的な出来事とともに解剖される。
第4 章と第5 章では、SDGs で可視化された地球規模の課題と直接的に関わるテーマや論点が俎上にあげられる。いずれも、現代の時空間で考えられがちな問題に「歴史的文脈を与える」という重要な役割を担っており、本巻のオリジナリティもここにある。
(本巻総論より)

- プロレタリア文学とジェンダー
- 飯田 祐子/中谷 いずみ/笹尾 佳代
- 青弓社
- ¥4400
- 2022年10月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
階級闘争が内包してきたジェンダー構造に着目し、小林多喜二や徳永直、葉山嘉樹、佐多稲子らの作品から、プロレタリア文学の実践を読み直す。民族やコロニアリズムなどの論点と階級闘争との交差にも着目して、プロレタリア文学の可能性と問題点を析出する。

- 新版 教育社会とジェンダー
- 河野 銀子/藤田 由美子
- 学文社
- ¥2310
- 2018年03月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
幼児期、メディア、学校教育、部活動や進路選択等、
私たちの世界にはどのようなジェンダー(社会的性)が埋め込まれているのか。
男女の性差のみならずLGBTの人々への視点を取り入れ新たに編まれた教育社会学テキスト。
【執筆者】
*河野銀子、*藤田由美子、岩本健良、木村松子、池上 徹、木村育恵(*は編者)

- ジェンダー平等社会の実現へ
- 杉井 静子
- 日本評論社
- ¥2640
- 2023年02月01日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
なぜ夫婦は同姓でなければならないのか? 「家」制度から社会の仕組みに内包するジェンダー不平等を明らかにし、憲法を手がかりに解決を探る。

- 沖縄ジェンダー学(第2巻)
- 大月書店
- ¥3740
- 2015年02月27日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって5年計画で進めてきたプロジェクトの成果を集成する全3巻シリーズ。第2巻では、沖縄の社会制度とジェンダー観の関わりについて考え、現代沖縄社会のなかに存在する抑圧の構造を見極める。

- ジェンダー化された家庭内役割の平等化と母親ゲートキーピング
- 中川まり
- 風間書房
- ¥7700
- 2021年11月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
父親の育児・家事参加に母親ゲートキーピングや就業はいかに作用するか。ジェンダー化された家庭役割の平等化をジェンダー理論で解明。
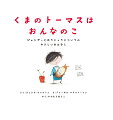
- くまのトーマスはおんなのこ
- ジェシカ・ウォルトン/ドゥーガル・マクファーソン/かわむら あさこ
- ポット出版プラス
- ¥1650
- 2016年12月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(5)
女の子になりたいとずっと悩んでいたテディベアのトーマス。
それを打ち明けたら、大好きなエロールはもう友だちじゃなくなってしまうだろうか…。
本当の自分を打ち明ける勇気を持ったテディベアと、
そしてそれを知らされた親友のエロールの返事は……。
「大事なのはきみがぼくの友だちだってことさ」
ジェンダーと友情についてのやさしいお話。
作者のジェシカ・ウォルトンの父は男性から女性に性別移行したトランスジェンダーだった。ジェシカは、自分の息子エロールに読んで聞かせるトランスジェンダーをテーマにした絵本を作りたいと思ったことがきっかけで、自分でこの絵本を制作した。
本文は、すべてひらがなとカタカナ。幼い読者がひとりでも読める絵本です。

- ジェンダー暴力の文化人類学
- 田中 雅一/嶺崎 寛子
- 昭和堂
- ¥6930
- 2021年03月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
世界的に関心の高まる女性への暴力。その実態は地域や社会によって多様で、その差異を無視しては解決どころか深刻化しかねない。さらにグローバル化のなか地域社会が変容し暴力の構造はますます複雑化している。本書では現地調査をもとに歴史・文化・社会的文脈を考慮しつつ実態を描き出す。
序章 ジェンダー暴力とは何か?
第1部 家族の名誉にかけて
第1章 南アジアにおける強制結婚ーー規定婚、幼児婚、非人間との結婚
第2章 二重の暴力ーーネパールにおける売春とカースト
第3章 名誉は暴力を語るーーエジプト西部砂漠ベドウィンの血讐と醜聞
第4章 ジェンダー暴力の回避ーーエジプトのムスリムの試み
第5章 噂、監視、密告ーーモロッコのベルベル人にみる名誉と日常的暴力の周辺
第6章 復讐するは誰のため?--ギリシャのロマ社会における名誉をめぐる抗争
第2部 国家に抗するジェンダー
第7章 揺れ動くジェンダー規範ーー旧ソ連中央アジアにおける世俗主義とイスラーム化
第8章 抑圧された苦悩の可視化ーー韓国の烈女と鬼神
第9章 ある「母」の生成ーーアルゼンチン強制失踪者の哀悼と変わりゆく家族
第10章 痛みと記憶ーーチリ・軍政下を生き抜く女性たち
第11章 自由、さもなくば罪人ーー性の多様性をめぐるインド刑法の攻防
第3部 ディアスポラ社会の苦悩
第12章 名誉をよみかえるーーイスタンブルの移住者社会における日常の暴力と抵抗
第13章 トランスローカルなジェンダー暴力ーーインド・パンジャーブ出身女性の経験
第14章 暴力と移動が交錯する生ーーメキシコにおける中米女性移民たち
第15章 越境する「強制結婚」--ノルウェーのパキスタン系移民女性とNGO活動
第16章 眼差しの暴力への抵抗ーーノルウェーのアラブ系難民女性をめぐって
第17章 仕事・恋愛・暴力が交錯する場ーーカラオケパブで出会うフィリピン人女性と日本人男性

- 沖縄ジェンダー学(第1巻)
- 大月書店
- ¥3740
- 2014年03月31日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって5年計画で進めてきたプロジェクトの成果を集成する全3巻シリーズ。第1巻では、沖縄の伝統文化とジェンダー研究の接点を探る。

- 【謝恩価格本】ジェンダー法研究第6号
- 浅倉 むつ子
- 信山社
- ¥4180
- 2019年12月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
第6号は2つの特集、1「LGBT/SOGI施策」に6論文(谷口、遠藤、神谷、二宮、鈴木賢/TAKACO、鈴木秀洋)、2「子の面会交流」に企画趣旨と3論文(山崎、高田、光本)、シリーズ「比較家族法(2)」では4論文(二宮、渡邊、小門、石嶋)、「立法・司法の動向」は、敗訴判決にスポットを当てて一石を投じる浅倉論文と、選択的夫婦別姓の動向(二宮)を掲載。最新テーマで迫る。

- フロベールと<ジェンダー>
- ジャンヌ・ベム
- 水声社
- ¥3850
- 2022年12月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
フロベール、その女たち、その書物。フロベールの文体から生みだされた女性像にはジェンダー問題が投影されていた…愛人たちと交わした書簡を読み解きながら、社会規範を逸脱していくエクリチュールの潜勢力を見極める。
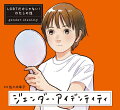
- ジェンダー・アイデンティティ
- 佐々木掌子
- 国土社
- ¥3080
- 2022年07月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(4)
思春期の読者が自分と他者の性を大切にしていけるよう、さまざまな性のありかたを学ぶことができるシリーズ。手にとるのが恥ずかしくない大きさやデザインを採用し、柔らかいイラストやマンガを通して、学校や友人関係などで生じる具体的な悩みや疑問を1つずつ丁寧に紹介していきます。シリーズ第1弾のテーマは「ジェンダー・アイデンティティ」です。
第1章 ジェンダー・アイデンティティってなんだろう? 「男子って言われるとモヤモヤするのはなぜ?」/ジェンダー・アイデンティティってなんだろう?/ジェンダー・アイデンティティのきほん/いろいろなジェンダー・アイデンティティ/「その性別」としてどうありたいか/シスジェンダーとトランスジェンダー/「モヤモヤしたままでもいい。自分は自分」
第2章 みんなが気持ちよく過ごすために 「制服を選ぶことは性別を選ぶこと?」/あなたとまわりの人、みんなが気持ちよく過ごすために/「絶対に差別をしない人」って本当にいるの?/性の違和感を緩和するために医療や法律でできること/カミングアウトする?しない?/カミングアウトされたとき/もしも、あなたがアウティングを……
第3章 性の多様性ってなんだろう? 「LGBTの人がいるから性は多様?」/あなたとわたしも多様性をつくるひとり/自分の性についてもっと知るために/性にかかわることば/もっと知りたい・話を聞きたい ほか

- 現代日本の仏教と女性
- 那須 英勝/本多 彩/碧海 寿広
- 法藏館
- ¥2420
- 2019年04月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
日本仏教、その未来を考えるーー。
仏教界に今なお根強く残る性差別の実態に、国内外の研究者と現場の僧侶たちが鋭く迫る。
多文化共生が求められる現代社会に、ジェンダーの視点から日本仏教の未来を問う革新的な1冊。
****************
寺院は、日本仏教の基盤であり、日本の伝統文化を継承する主要な場の一つでもある。その裏面として、日本の負の伝統(因襲とも言える)もまた、一般社会より色濃く伝えてきてしまったところがある。古臭い女性観や、周囲の人間に対するハラスメント意識の希薄さは、その典型的な例だろう。
こうした負の伝統をどう理解し、いかに克服しうるか。学問的にも実践的にも、大きな課題としてある。本書は、その課題に応えるための論文や提言を集めた研究書であり、実践のための手引き書である。
(中略)
ジェンダーは国際的な視野から検討したほうが、理解が深まりやすい。社会や文化ごとの違いが重要なため、自己とは異なる社会や文化の事例や視点を得ることで、問題の所在が際立ち、また別の可能性も見えてくるのである。
そのため、本書は国際性を重視する。国外の事例を取り上げるだけではない。イギリスから日本に来て、僧侶として活動してきた女性の体験談や、あるいは寺院でのフィールドワークを積み重ねるカナダの研究者の論文も掲載する。こうした「異邦人」の目線からの現代日本仏教に関する所感や考察は、現状では、あまり多くは存在しない。それらは一種の日本文化論としても興味深く、新鮮な見解に満ちている。(「はじめに」より)
****************
執筆者一覧(50音順):飯島惠道/池田行信/碧海寿広/岡田真水(真美子)/川橋範子/那須英勝/本多彩/横井桃子/吉村ヴィクトリア/マーク・ロウ
【本書のポイント】
・「ジェンダー」と「国際性」というこれまで日本仏教に関する著作において同時に押し出されることのなかった二つのキーワードから、「現代日本仏教と女性」という仏教界が抱える重要な問題に切り込む画期的試み。
・研究者による調査報告だけでなく、実際に現場で活動する女性僧侶たちの体験談までを収録。
はじめに(碧海寿広)
序 章 越境する「仏教とジェンダー」研究(川橋範子)
第一部 研究篇
第一章 女性の出家と成仏(岡田真水〈真美子〉)
第二章 米国本土の女性仏教徒と越境
-米国開教区の動向ー(本多 彩)
第三章 越境する寺族女性たち
-日本とハワイの調査からー(横井桃子)
第二部 実践篇
第一章 ジェンダー不平等な現場からのレポート
-伝統的出家型尼僧の視座からー(飯島惠道)
第二章 ニッポンの田舎における英国人女性僧侶の冒険(吉村ヴィクトリア)
第三章 真宗教団における「性」をめぐる諸問題(池田行信)
特別収録
仏教人類学とジェンダー
-女性僧侶の体験からー(マーク・ロウ)
おわりに(那須英勝)
「龍谷大学アジア仏教文化研究叢書」刊行について(楠 淳證)
編者・執筆者紹介

- 0歳からのジェンダー・フリー
- 山梨県立女子短大ジェンダー研究プロジェクト&私らしく、あなたらしく*やまなし
- 生活思想社
- ¥2530
- 2014年09月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ジェンダーの視点で保育現場を観察すると、保育士の言葉や行動だけでなく、3、4歳児の保育園児の言動にもジェンダーにとらわれた場面を発見! 「ピンクは女の子が着るものなんだよ」「戦闘ごっこは女はやらないの」…。そんなことを言う子ども達。文科省委嘱事業「0才からのジェンダー教育推進事業」に参画した保育士・幼稚園教諭・子育て支援スタッフ・行政職員らは、どのようにジェンダーを理解し、自分のものとしていったのか、ジェンダーの視点をどう活かしていったのか。市民と地域の大学研究者がネットワークした、山梨県の、男女共同参画社会づくりを支える市民活動が満載の実践記録。

- アカデミズムとジェンダー
- 歴史学研究会編 有信 真美菜・大江 洋代・清水 領・芹口 真結子・高野 友理香・寺本 敬子・三枝 暁子 著
- 績文堂出版
- ¥1980
- 2022年05月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
キャリア形成、結婚・出産の壁、さまざまなハラスメントーー女性研究者が抱える「生きづらさ」の背景をアンケート調査・資料などをもとに明らかにするとともに、男性研究者を交えた座談会を収録し、困難な状況を共に克服する方途を探る。
第1部 女性歴史学研究者の現在
第1章 女性研究者のキャリア形成をめぐる現状と課題
1 大学・大学院におけるジェンダーをめぐる壁
2 非常勤講師のおかれている現状
3 女性の「研究時間」をめぐる現状
4 再生産労働と女性の「研究時間」
5 ハラスメントをめぐる現状
第2章 結婚・出産・育児と女性研究者
1 女性研究者の就業と結婚・出産・育児
2 世帯形成と妊娠・出産の壁
3 育児支援とその不足
4 女性と家庭をめぐるジェンダー・バイアス
第2部 歴史学に参入する女性研究者の歴史
第1章 女性が歴史学を研究するということーー西洋編
第2章 女性が歴史学を研究するということーー日本編
第3部 座談会ーー歴史学におけるジェンダー平等を展望する

- おしえてジェンダー! 「女の子だから」のない世界へ
- 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
- 合同出版
- ¥1980
- 2023年05月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(6)
世界中の、強くて、賢くて、勇気ある女の子たちへ。
「女の子だから」という呪いの言葉を捨てて、もっと自由に生きよう!
「女の子の力を、世界を変える力にする。」
世界中のジェンダー平等の実現に取り組むプラン・インターナショナルから
日本の女の子たちにむけたメッセージ
プロローグ ジェンダーって何?
第1章 身のまわりにあるジェンダー
第2章 ジェンダーと暴力
第3章 世界の女の子が直面するジェンダー問題
第4章 ジェンダーフリーな社会をつくろう
エピローグ ジェンダー平等な世界へ

- 女人禁制の人類学
- 鈴木 正崇
- 法藏館
- ¥2750
- 2021年08月31日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
本書は「女人禁制」に関する問題点を読み解く実践的な試みである。賛成か反対か、伝統か差別かの二者択一を乗り越えて、開かれた対話と議論を促す。文化人類学の立場からの考察を主軸に、民俗学や宗教学、歴史学や国文学の成果も取り込んで、総合的に考察する。女人禁制の問題を考える人にとって長く活用される必読書となるべき1冊。
○第一章 相撲と女人禁制
2018年に大相撲の舞鶴巡業の際に、土俵上で倒れた市長を助けるために女性が土俵に上がって「女人禁制」が問題視された出来事を取り上げる。「土俵の女人禁制」について、その起源と展開を考察する。近代の国技館開設以後、表彰式などの「近代の儀式」を創出した大相撲は、「国技」としての権威を高めてナショナリズムと同調していった。戦後は、前近代以来の「土俵祭」の伝統を維持する一方で、表彰式を男性参加に限定して土俵上で行うという矛盾が露呈して、「土俵の女人禁制」が問題視されることになった。
○第二章 穢れと女人禁制
「女人禁制」を古代・中世・近世・近代の穢れの変化と関連付けて検討。古代では、戒律に基づき、仏教寺院の「結界」として女性を排除した。一方、山と里の間の「山の境界」は、仏教の影響を受けて「山の結界」となり、「女人結界」へと変化。女性の穢れ観も歴史的に変化し、中世後期には『血盆経』の影響で罪業観や血穢の強調ともに展開し、近世には民衆の間に広がって定着。明治5年に女人結界は解禁されてほぼ消滅した。またスリランカやインドの事例など人類学の理論をふまえて、穢れ論の再構築と一般化の可能性を探った。
○第三章 山岳信仰とジェンダー
女人禁制の言説を、歴史の中の女人禁制、習俗としての女人禁制、社会運動の中の女人禁制、差別としての女人禁制に分け、ジェンダーの問題を視野に入れて論じる。地域社会の事例として、現在も女人禁制を維持する大峯山の山上ケ岳山麓の洞川を取り上げた。神仏分離以後の再編成、国立公園の登録、交通路の整備、山麓寺院の女人解禁、禁制地区の縮小、女性による新たな動き、伝統の再発見、禁制解禁の胎動、世界遺産、日本遺産などを関連付けて、女人禁制の行方を展望する。
○「現代の相撲の女人禁制関連の出来事」「近代女人禁制関係年表」などの年表や、詳細な索引を附した。
○著者は、文化人類学の碩学であり、大相撲や大峯山の女人禁制に関して、常にマスコミから識見を求められてきた。『女人禁制』(吉川弘文館、2002年)以降の研究の進展を踏まえ、現時点の思索の到達点として世に問う。