ジェンダー の検索結果 標準 順 約 2000 件中 221 から 240 件目(100 頁中 12 頁目) 

- 続ジェンダー労働論
- 川東英子
- ドメス出版
- ¥2200
- 2019年03月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 戦時期日本の働く女たち
- 堀川 祐里
- 晃洋書房
- ¥4950
- 2022年03月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
生理休暇が〈消える〉ためには?
「第49回赤松賞」を受賞した著者が、戦時期の女性労務動員についての歴史的・実証的研究から、現代にも通じる女性労働者の稼得労働と妊娠、出産、育児に関する課題を照射する。
「総力戦」が強調された戦時期における女性労務動員の展開は、グローバル経済下で競争力の維持を目指す現代日本の労働政策と相通ずる点があるのではないだろうか。赤松常子は敗戦直後に「日本女性の戦ひはこれからである」と残した。現代を生き抜くために今知っておきたい戦時期日本の働く女たちの姿がここにある。
はしがき
序 章 戦時期日本の働く女たちに関する研究のこれまでとこれから
1 戦時期日本の働く女たちに関する研究の到達点
2 女性労働者の労務動員が生じさせた摩擦
第一章 一九二〇年代から一九三〇年代の女性の就業状態
--労働運動の指導者と研究者の視点から見た働く女たち
1 一九二〇年代から一九三〇年代の女性労働者の就業状態
--稼得労働と妊娠、出産、育児との両立
2 稼得の必要性から働かざるを得ない未婚の女性労働者
--赤松常子の問題意識
3 労働環境が及ぼす健康への影響
--研究者たちの視点から見た女性労働者
第二章 未婚女性の労務動員のための「戦時女子労務管理研究」
--労働科学研究所の古沢嘉夫の視点から
1 戦争の開始と「戦時女子労務管理研究」の必要性
2 労働科学研究所の「戦時女子労務管理研究」
--古沢嘉夫が訴えた女性労働者の健康
3 女性労働者の出身階層と健康状態
--月経に関する調査研究
4 生き抜くために働く既婚女性と研究者の制約
第三章 既婚女性労働者の困難
--妊娠、出産、育児期の女性たち
1 既婚女性は労働力の対象ではなかったのか
2 救貧対策としての母子保護法の制定
3 貧困家庭の母親たちに向けられた政府の二重の期待
4 働く母親たちと保育環境
第四章 女性たちの労務動員に対する態度の多様性と政府の対応策
1 階層格差から生まれた女女格差
2 職場における男女格差
--男女同一労働同一賃金の議論のゆくえ
3 女性の労務動員の最終手段
--女子挺身隊から現員徴用へ
第五章 赤松常子の主張と産業報国会の取り組みとの齟齬
--既婚女性の労働環境をめぐって
1 使用者たちに抵抗する産業報国会女性指導者
2 女子挺身隊に対する未婚女性の母親たちの心配
--産業報国会に求められた未婚女性への「生活指導」
3 働かざるを得ない既婚女性を守ろうとした赤松常子
--言説に見られる制約
第六章 戦時体制が残した女性労働者の健康への視点
--生理休暇の現代的意義
1 戦時期がもたらした敗戦直後の女性労働への影響
2 生理休暇制定を主張した赤松常子
3 消えかけた生理休暇
4 生理休暇が本当に〈消える〉ために必要なこと
終 章 戦時期日本を生き抜いた働く女たち
あとがき
参考文献

- フィギュアスケートとジェンダー
- 後藤太輔
- 現代書館
- ¥1980
- 2018年04月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(2)
浅田真央、小塚崇彦らを指導した佐藤信夫コーチ推薦!
フィギュアスケート界では男女選手の交流・協力活動が多く、引退後も、コーチ、プロスケーター、振付師、衣装デザイナーなど多ジャンルで活躍している。インストラクター協会理事にも女性が多く、他のスポーツと比べ、ジェンダーバイアスが少ない競技といえる。海外では、現役選手による同性愛カミングアウト、アラブの選手によるヒジャブ着用など、社会に対して積極的にアピールする選手も多い。本書は、フィギュアスケートを切り口に、スポーツと社会の繫がり、2020年東京五輪パラリンピックへの向き合い方を伝える。 現役記者ならではの豊富な取材に基づく逸話が満載!

- 新たな時代のジェンダー・イシュー
- 信田理奈/村上涼
- 三恵社
- ¥1980
- 2020年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)

- 沖縄ジェンダー学(第2巻)
- 大月書店
- ¥3740
- 2015年02月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって5年計画で進めてきたプロジェクトの成果を集成する全3巻シリーズ。第2巻では、沖縄の社会制度とジェンダー観の関わりについて考え、現代沖縄社会のなかに存在する抑圧の構造を見極める。
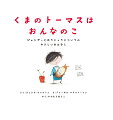
- くまのトーマスはおんなのこ
- ジェシカ・ウォルトン/ドゥーガル・マクファーソン/かわむら あさこ
- ポット出版プラス
- ¥1650
- 2016年12月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(5)
女の子になりたいとずっと悩んでいたテディベアのトーマス。
それを打ち明けたら、大好きなエロールはもう友だちじゃなくなってしまうだろうか…。
本当の自分を打ち明ける勇気を持ったテディベアと、
そしてそれを知らされた親友のエロールの返事は……。
「大事なのはきみがぼくの友だちだってことさ」
ジェンダーと友情についてのやさしいお話。
作者のジェシカ・ウォルトンの父は男性から女性に性別移行したトランスジェンダーだった。ジェシカは、自分の息子エロールに読んで聞かせるトランスジェンダーをテーマにした絵本を作りたいと思ったことがきっかけで、自分でこの絵本を制作した。
本文は、すべてひらがなとカタカナ。幼い読者がひとりでも読める絵本です。

- 「男らしさ」のイデオロギーへの挑戦
- 高橋 愛
- 晃洋書房
- ¥3300
- 2022年02月01日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ミドルクラスの白人で異性愛の男という地位への抗い。男らしさの諸相を描き続け、男らしさを覇権的な理念に固定させまいとした作家への新照射。
オルタナティブなものが存立する可能性に目を向けようとはせずに特定の規範を押し付けてくる社会への抵抗の書。
序章
ハーマン・メルヴィルの人生と作品
ジェンダーおよびセクシュアリティの観点からみたメルヴィルの文学
北部ミドルクラス社会における男らしさ
本論の概要
第一章 トンモとは何者か
--『タイピー』における男の主体
はじめに
一.『タイピー』はどう読まれてきたのか
二.名無しの平水夫から「トンモ」へ
三.要としての顔
四.トンモの「逃走」が示すもの
第二章 身体の傷と男の主体
--『ホワイト・ジャケット』における男らしさ
はじめに
一.「手間仕事」と呼ばれた文学作品
二.笞で打たれるということ
三.笞を打たせるということ
四.肉を切らせて
第三章 畏怖される男
--『白鯨』におけるエイハブの主体
はじめに
一. 船長の帆柱
二. 鯨捕りのひとつではない男らしさ
三. エイハブの主体
第四章 クィークェグの不定形の男性像
--『白鯨』における男らしさのオルタナティブ
はじめに
一. クィークェグの身体
二. クィークェグの性の逸脱
三. クィークェグは何者なのか
第五章 ピエール・グレンディニングの性
--『ピエール』における曖昧なもの
はじめに
一.「姉」がもたらす性の曖昧
二.「妻」がもたらす性の混乱
三.従兄弟との再会で露呈する性的な曖昧さ
第六章 ケアが揺るがす男らしさ
--「ベニト・セレノ」における男のケア
はじめに
一. ケアを受ける男
二. ケアを行う男
三. ケアを眺める男
第七章 「平和の使者」と彼を取り巻く男たち
--『水夫ビリー・バッド』における男らしさの混乱
はじめに
一. 海の上の「幸福」な家族
二. 先任衛兵伍長の偏執
三. 艦長の揺れる思い
四. バラッドに託されたもの
終章
おわりに
引用文献
索引

- 中国のメディア・表象とジェンダー
- 中国女性史研究会
- 研文出版
- ¥4950
- 2016年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- イスラーム法の子ども観
- 小野 仁美
- 慶應義塾大学出版会
- ¥6380
- 2019年11月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
▼ムスリムの日常の生活を規定するイスラーム法(フィクフ)を、ジェンダー視点で読み解く。
▼ムスリムの家庭における、父と母、子どもの関係やあり方を知るための重要な一冊。
イスラーム教徒の社会生活の規範を形作ったイスラーム法が、いかに「子ども」や「家族」を規定していたのか。
神の教えに基づく共同体の形成が目指されたイスラーム社会においては、共同体の未来たる子どもたちをいかに育てるかは重要な関心事であり、本書ではその具体的な生活指針を記す古典イスラーム法学書を中心に、子どもと周囲の人々をめぐる記述を分析。ジェンダー視点から、イスラーム法における家族像を探る。
序論
1 法学書を子ども観から読み解くーー本書の目的
2 本書の特徴と意義
3 イスラーム法学書の歴史と概要
第一章 人間の成長段階と法的能力
1 イスラーム法における子どもの概念
2 身体的成熟と法的能力の変化
3 弁識能力という指標
4 未成年者としての「子ども」と法的能力
第二章 父の権限と子への義務
1 実子の確定
2 子の宗教と新生児儀礼
3 父子相互の権利と義務
4 父は子に対して絶対の権限をもつのか
5 父という存在の考察
第三章 母の役割と「子の利益」
1 母の授乳は義務なのか
2 乳母の雇用をめぐる問題
3 監護をめぐる母の権利と子の権利
4 「子の利益」を守るという価値観
第四章 子どもへのクルアーン教育
1 子どもへの教育を示す言葉
2 クルアーン教師の雇用規定
3 マーリク派法学者による教育専門書
4 マーリク派法学者の教育論
5 ムスリム社会の担い手としての子どもたち
結論ーーイスラーム法の子ども観が映すもの
あとがき
注
参考文献
索引

- 英語のジェンダー
- 神崎 高明
- 開拓社
- ¥2200
- 2022年03月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
本書は英語のジェンダーについて、文法的観点から考察している。英語はフェミニズムの影響でジェンダー中立的言語にダイナミックに変化している。たとえば、everyoneなどの不定代名詞を従来はheで受けていたが、現在はhe or sheやtheyで受けることが普通になりつつある。新しい通性代名詞としてzeを提案する人もいる。変化する英語のジェンダーの実態を明らかにしてゆく。
第1章 英語のジェンダー:序論
第2章 フェミニズム:英語の通性代名詞
第3章 manの語法
第4章 Ms.の意味
第5章 英語の女性接尾辞
第6章 聖書とジェンダー
第7章 Jespersenと女性語

- 沖縄ジェンダー学(第1巻)
- 大月書店
- ¥3740
- 2014年03月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって5年計画で進めてきたプロジェクトの成果を集成する全3巻シリーズ。第1巻では、沖縄の伝統文化とジェンダー研究の接点を探る。

- ジェンダー平等社会の実現と発展的プロセスに関する研究
- 山口典子
- 三恵社
- ¥2530
- 2022年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 【謝恩価格本】ジェンダー法研究第2号
- 浅倉むつ子
- 信山社
- ¥3080
- 2015年12月04日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
実務と研究を架橋し、新たな共生社会への展開をはかる、待望のジェンダー法学の研究雑誌。既存の法律学との対立軸から、オルタナティブな法理を構築。第2号は特集「労働法とジェンダー」と題し、この30年間のジェンダー平等・障害者雇用差別禁止法制の発展と現状を検討する8本の論稿を収録したほか、「立法と司法の新動向」として、第4次男女共同参画基本計画策定作業のモニタリンと第3次のそれと比較・検討する論稿も収録。

- ジェンダー法研究 第7号
- 浅倉 むつ子/二宮 周平/秋月 弘子/山下 泰子/軽部 恵子/矢野 恵美
- 信山社出版
- ¥4180
- 2020年12月28日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
◆実務と研究を架橋し、新たな共生社会を拓く【ジェンダー法学】の専門誌◆
第7号は3つの特集から成る。〈特集1〉女性差別撤廃条約40周年に4論文(秋月、山下、浅倉、軽部)、〈特集2〉ノルウェーにおける性の多様性に1論文(矢野)と講演の翻訳(矢野・齋藤)、〈特集3〉DSDsを考えるに2論文(ヨ・ヘイル、石嶋)を掲載。「立法・司法の動向」は、「日本学術会議の提言の意義」として性暴力に対する今後の刑法改正に向けた重要な提言(後藤)。最新テーマで迫る。

- 新しい労働世界とジェンダー平等
- 浅倉 むつ子
- かもがわ出版
- ¥1870
- 2022年09月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
立ち後れる日本のジェンダー平等。コロナ禍のしわ寄せを受けるケア労働を始め、格差是正を求める新しい労働世界実現の道を拓く。
第1章 コロナ化の生活の変化
第2章 労働分野のジェンダー格差と「ケアレス・マン」モデル
第3章 エッセンシャル・ワーカーの困難
第4章 ジェンダー平等に関わる労働法制の展開
第5章 時間と資金の新しい考え方 「ケアレス・マン」モデルからの脱却
第6章 暴力とハラスメントのない世界を
第7章 日本のジェンダー平等を国際基準に

- 近世感染症の生活史
- 鈴木 則子
- 吉川弘文館
- ¥3520
- 2022年03月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
江戸時代の日常生活には、つねに感染症の脅威があった。梅毒・結核・インフルエンザ・コレラ・麻疹・疱瘡…。これらは日々の暮らしにいかなる影響を与えたのか。医療の進歩や都市生活と商業主義の展開、出版メディアの発達など、生活環境の移り変わりによる感染症へのまなざしの変化を描き、現代にも通じる社会と感染症との共生する姿を考える。
序章 「須佐之男命厄神退治之図」(葛飾北斎画)の世界/1 慢性感染症(黴毒(梅毒)-性感染症をめぐるディスクール〈「大風に類する」病/黴毒の広がりと警戒/黴毒への羞恥/病原としての下層社会と遊廓〉/労瘵(結核)-「恋の病」考〈はじめにー「恋の病」という言説/明清医学の導入/医学書の中のジェンダー/心を病む人々/文芸史料の中の労瘵〉/「癩」-「家筋」とされた病〈中世から近世への転換/病者の特定化ー一七世紀後半/「悪血」の排出ー一八世紀以降〉/2 急性感染症(流行り風邪(インフルエンザ)-江戸の町の疫病対策〈医学史からみた流行り風邪/流行り風邪の通称と背景/疫病対策の転換〉/麻疹ー情報氾濫が生む社会不安〈麻疹養生法の広がりー享和三年(一八〇三)/麻疹がもたらす特需ー文政六年(一八二三)/文久二年(一八六二)の流行)以下細目略/疱瘡(天然痘)-共生から予防へ/コレラー新興輸入感染症の脅威

- 他者の影
- ジェシカ・ベンジャミン/北村婦美
- みすず書房
- ¥4950
- 2018年11月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
〈他者は「私」の影でしかないのでも、「私」が他者の影でしかないのでもない。他者はその人自身の影を持つ、もう一人の人間なのだ〉
フロイトのエディプス・コンプレックス論にも見られるとおり、草創期の精神分析では、男性を主体(=能動)とし、女性を客体(=受動)とする構図で理論が積み上げられた。しかし、時代とともに女性をとりまく環境と女性のあり方が変化し、フロイトの女性論は今日まで多くの対立を生んできた。
ベンジャミンはこうした精神分析の男性中心主義の乗り越えに、女性固有の優位点を謳い上げ、女性の権利を振りかざすことはない。問題の根源は、精神分析の「一人の人間がどのように環境や周囲の人間を利用し、うまく折り合いをつけ、最終的に自分の欲望を満たすか」という一者心理学的な基本姿勢にあるのである。
フロイトの女性論、そしてそれに向けられたフェミニズム思想の批判的言説を再検討し、対立を乗り越える共通の基盤を切り開く。精神分析における「ジェンダーの戦争」の終結への序章となる重要書。
謝辞
はじめに
第1章 身体から発話へ、精神分析の最初の跳躍ーーフロイト、フェミニズム、そして転移の変遷
第2章 「内容の不確かな構築物」--エディパルな相補性を超える、ジェンダーと主体
第3章 他者という主体の影ーー間主観性とフェミニズム理論
補論 精神分析と女性ーージェシカ・ベンジャミンの登場まで 北村婦美
解説 北村婦美
文献
索引
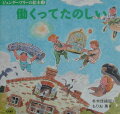
- ジェンダー・フリーの絵本(3)
- 橋本紀子/朴木佳緒留
- 大月書店
- ¥1980
- 2001年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
あなたは、将来どんな仕事をしたいと思っていますか?本巻では、「女性用の仕事」「男性用の仕事」という区別はないということを述べました。男女とも、自由に職業を選ぶことができる力をつけてほしいのです。今までは、女の人は家庭を守り、男の人は家族を養うことがよいと思われていました。しかし、世界中の国々で、それはおかしいと思う人が増えています。あなたも性にとらわれず、自由に自分の人生を描いてください。本当に自分に合う仕事が見つかるといいですね。

- 男はスカートをはいてはいけないのか? キャリコン視点のジェンダー論
- 神田くみ/橘亜季
- 日本橋出版
- ¥1540
- 2023年04月21日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ここ10数年で社会環境は大きく変化し1つの企業・組織で継続的・安定的に「キャリア」を築くことは困難となり、自らの価値観・職業観・人生観に基づいてキャリアを形成する必要が出てきました。価値観の多様化した時代に自分らしいライフキャリアを手に入れるにはどうしたらよいのでしょうか?日本はジェンダーギャップ指数が低いことが話題に上りますが女性より男性の方が幸福度が低い珍しい国でもあります。課題解決の上で着目すべき視点が、「男性はスカートをはいてはいけないのか」問題なのです。本書では、2名のキャリアコンサルタントが社会事象の中でのジェンダーについて過去・現在・未来を展望してジェンダーを取り巻く「今」を知り、ジェンダーに対する考え方のアップデートにつなげることを目的に作られました。社会通念としてのジェンダー規範は、ある時代のある場所における、考え方のひとつであり、常にアップデートされるものなのです。

- 【バーゲン本】暴力と戦争ージェンダー史叢書5
- 加藤 千香子 他
- (株)明石書店
- ¥2640
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
暴力や戦争を批判的にとらえ、考察していく上で、フェミニズムやジェンダー論のもつ意味は大きい。本巻は、「暴力」の歴史を問い直し、その構造や行使される過程をジェンダーの視点から明らかにすることにより、歴史の新たな側面に光をあてる。