芸術 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 321 から 340 件目(100 頁中 17 頁目) 

- デ・キリコ大特集
- 朝日新聞出版
- 朝日新聞出版
- ¥1848
- 2024年04月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
20世紀の美術界に衝撃を与えたデ・キリコ。世界各地から100点以上の作品が集まり、画家の全体像に迫る大回顧展が開催決定!! 東京都美術館4月27日〜8月29日、神戸市立博物館9月14日〜12月8日。入場料金100円割引券付き。CONTENTS岡田准一インタビュー「美術館は自分と向き合える場所です」又吉直樹がデ・キリコの絵を物語にする!「瞑想する人」横尾忠則「インタビュー何を描くかではなく、いかに描くかを追求」Aマッソ加納 「デ・キリコって何だ?」展覧会観どころ? 長い影が何かを物語っている《バラ色の塔のあるイタリア広場》映画・舞台美術監督、種田陽平インタビュー「デ・キリコが予言した世界」展覧会観どころ? この部屋に住んでみたいですか?《「ダヴィデ」の手がある形而上的室内》展覧会観どころ? デ・キリコの発明、表情のないマネキン絵画《形而上的なミューズたち》展覧会観どころ? なぜ、デ・キリコはコスプレしたのか?《17世紀の衣装をまとった公園での自画像》精神科医岡野憲一郎インタビュー「イタリア広場を実際に体験したかもしれません」展覧会観どころ? 違和感だらけ? 汚れた足の裏をみせる裸婦 《風景の中で水浴する女たちと赤い布》展覧会観どころ? 画業の集大成として描かれた、自伝的な作品《オデュッセウスの帰還》東京都美術館学芸員高城靖之インタビュー 「実物を自由に観て感じてほしい」信州大学教授金井直インタビュー 「デ・キリコは20 世紀美術のもう一つの動脈です」「デ・キリコ展」チケット情報キーワードで辿るデ・キリコ90年の物語来日しないデ・キリコ ギャラリー 作品解説:鮫島圭代日動画廊副社長・長谷川智恵子インタビュー「デ・キリコ邸訪問記」西洋美術史の初級講座ローマ デ・キリコ散歩 文・ナカムラクニオデ・キリコが生きた時代哲学入門 ニーチェとショーペンハウアー図解 シュルレアリスムの世界いつかは観たい!「この1枚」 文・アートテラー・とに〜現代アートの楽園直島大解剖

- 虫めづる美術家たち
- 芸術新聞社
- 芸術新聞社
- ¥2750
- 2023年07月26日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(3)

- 集中力のひみつ
- 伊藤丈泰
- 芸術新聞社
- ¥1760
- 2018年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(3)
集中力を無視したら集中できる。演劇的アプローチによる集中力の“作り方”と“使い方”を物語形式で紹介。創造性を高める集中力のひみつは“感受性の集中”と“論理性の集中”にある!

- すっきりわかる! 超訳「芸術用語」事典
- 中川右介
- PHP研究所
- ¥880
- 2014年11月04日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
ルネサンス、ロココ、アリア、ラプソディ、スピンオフ、千秋楽……。▼美術館や演奏会といった場面で、頻繁に出てくる芸術用語。分かったような気になっていても、いざ「説明を」と言われるとなかなか答えられないのでは?▼そこで本書では、そんな難解な言葉を、誰でも理解できるように超訳し、解説を加えました。知れば知るほど、芸術の世界が今より200%愉しめることウケあいの1冊!▼【主な超訳例】▼◎シュールレアリスム⇒現実を超えた不思議な世界▼◎アヴァンギャルド⇒美術の先頭の戦闘的な人々▼◎ロマン主義⇒夢みたいなお話こそ、すばらしい▼◎エコール・ド・パリ⇒パリにいた芸術家のタマゴの外国人▼◎ヌーベル・バーグ→フランスの難しい映画▼◎未来派⇒未来は明るい、と信じられた人々▼◎ダダ⇒あらゆるものを否定せよ!▼◎キュレーター⇒品のいい画商▼文庫書き下ろし。

- おもしろサイエンス 折り紙の科学(B&Tブックス)
- 萩原 一郎、奈良 知惠
- 日刊工業新聞社
- ¥1760
- 2019年03月26日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(2)
折紙工学に期待される産業への応用と課題、その対策について述べるとともに、折り紙のさまざまなな折り方、デザインを数理的に解説する

- 【バーゲン本】現代かな概説
- 田宮 文平
- (株)芸術新聞社
- ¥1430
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「かな」を書くーー。そこにどんな意味があるのか?日本の美意識の粋、それが「かな」文字。元来、ちいさく繊細な文字を、掌で愛でるという歴史を経て、戦後、展覧会の隆盛により、壁面芸術として新しい美意識の地平が開かれた。そして、今・・・。「かな」書はどこに向かおうとしているのか、どこに向かうべきなのか。「現代のかな」の意義を問いかける、田宮文平、渾身の一冊。

- 【バーゲン本】歌舞伎四〇〇年の言葉ー学ぶ・演じる・育てる
- 堀越 一寿
- (株)芸術新聞社
- ¥935
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
歌舞伎の名優たちが残した言葉は、優れた演劇論であるばかりでなく、現代人にとっての学習論、仕事論、教育論、リーダー論といった叡智が詰まっている。

- ルネサンス歴史と芸術の物語
- 池上英洋
- 光文社
- ¥1045
- 2012年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.9(12)
ルネサンスとは、一五世紀のイタリア・フィレンツェを中心に、古代ギリシャ・ローマ世界の秩序を規範として古典復興を目指した一大ムーブメントを指す。しかし、古代の文化が復興した理由、あるいは中世的世界観から脱する流れに至った理由を明確に答えることはできるだろうか。ルネサンスとは本来、何を意味し、なぜ始まり、なぜ終わったのかー。皇帝と教皇による「二重権力構造」をもち、圧倒的な存在として人々を支配していた中世キリスト教社会は、いかにして変革していったのか。美術との関係だけで語られることの多い「ルネサンスという現象」を社会構造の動きの中で読み解き、西洋史の舞台裏を歩く。

- 【バーゲン本】今日もフツーにごはんを食べる
- 枝元 なほみ
- (株)芸術新聞社
- ¥880
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
いま変わらないで、いつ変わる?食から考える脱原発。台所の窓をあけて社会とつながることをめざした3.11後のエッセイとツイッター上のつぶやき。「炊き出しレシピ」付き

- なぞって覚えるパースドリル
- イマジネーション・クリエイティブ
- 芸術新聞社
- ¥2640
- 2022年07月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
理論はあと!まず手に覚えさせる!!プロの線画を何度もなぞって感覚を養えば、スキルは自然についてくる!!3つのSTEPでらくらくパースマスター!STEP1プロ作家が写真から起こした50の練習用線画を使って、まずは徹底的になぞる!STEP2「パースの基礎知識」などを参考に、写真からパース線を引く練習をする!STEP3本書掲載のプロ作家の作画手順を参考に、写真から線画を起こしてみる!

- 直島から瀬戸内国際芸術祭へ
- 北川フラム/福武總一郎
- 現代企画室
- ¥1760
- 2016年10月22日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
瀬戸内アート本の決定版!「アートによる地域づくり」を切り開いてきた福武總一郎(プロデューサー)+北川フラム(ディレクター)初の共著、ついに刊行!
「海の復権」を掲げ、近代化の負の遺産を負い、過疎・高齢化が進んできた島の活性化を目指す芸術祭の歴史は、すでに四半世紀前のベネッセアートサイト直島の誕生から始まっていた。
「お年寄りの笑顔」を謳い「よく生きる」ための理想の地をアートによってつくろうとしてきた福武總一郎が、里山の過疎化・越後妻有でアートに寄る地域づく理に奮闘していた北川フラムと出会ったとき、瀬戸内国歳芸術祭の構想は生まれた。
香川県と市町村を巻き込んで展開する瀬戸内国際芸術祭は、観光地としての再生、島への移住、休校の再開、ハンセン病患者の島の開放などさまざまな成果を生みだし、さらにアジア・アートプラットフォーム、アジア・アート・フォーラムへと、海を介したアジアとのダイナミックな交流の場へと展開しようとしている。
その歴史と現在、そして未来を、プロジェクトを牽引してきた二人の立役者が語り、書きおろす。安藤忠雄、新旧の香川県知事の証言なども織り込みながら、瀬戸内海を舞台に繰り広げられる地域づくりの過去・現在・未来を描き出す。
はじめに
第1章 ベネッセアートサイト直島から瀬戸内国際芸術祭へ 福武總一郎
第2章 瀬戸内国際芸術祭の展開 北川フラム
第3章 瀬戸内物語 北川フラム
第4章 瀬戸内からアジアへ 北川フラム
参考資料

- 芸術新潮 2025年 12月号 [雑誌]
- 新潮社
- ¥1899
- 2025年11月25日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 【バーゲン本】人体の描き方実践トレーニングーデッサンの基礎から、人物クロッキーまで
- 広田 稔
- (株)芸術新聞社
- ¥1265
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ポーズ集付き立・座・寝・動き×ヌード・着衣デッサンの基本的な描き方から、人物クロッキーの方法、作品化の過程まで、ステップアップするためのコツを順を追って紹介します。第 1 章 | デッサンとは何か?第 2 章 | 人体の構造をとらえよう第 3 章 | 人体の動きをとらえる第 4 章 | 人体の部位 をとらえる第 5 章 | ポーズと構図を学ぶ第 6 章 | 制作過程と作品化へ
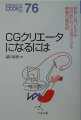
- CGクリエータになるには
- 越川彰彦
- ぺりかん社
- ¥1397
- 2004年09月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「CG」と聞いて、どんな職場を思い浮かべるでしょう?TV業界?それとも映画の現場でしょうか。もちろん、映像業界では大活躍です。でも、コンピュータグラフィックスの活躍の場はそれにとどまりません。インダストリアルデザイン、ファッション、ウェブ…。業界横断的なCGクリエータの仕事を紹介しましょう。

- 炎芸術No.143
- 阿部出版
- ¥2200
- 2020年08月01日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
特集 新・現代陶芸入門
監修・外舘和子(多摩美術大学教授・工芸史家)
現代日本の陶芸の表現は、実に多彩な展開をみせている。
かつては現代の陶芸を、「うつわ」と
実用性を持たない「オブジェ」の2つに大別して語ることが多かった。
しかし、現代の陶芸家の作る「うつわ」を見てみると、
作品タイトルには花器や鉢などとあっても、実際には鑑賞的要素の高い作品が多い。
それらは、実用的なうつわと同じジャンルのものと考えてよいのだろうか。
また、「オブジェ」も、抽象から具象的なものまで幅広く、
近年は特に、人物や動植物をテーマにした作品を目にする機会が増えた。
そこで、現代の陶芸をすっきりと見渡す、新たな分類のための視点が必要となる。
本特集では、多摩美術大学教授であり、
工芸史家として国内外で活躍する外舘和子氏を監修者に迎え、
現代陶芸の基準を提示した上で、鑑賞者の視点から外見上の分類を改めて試みる。
そして“現代陶芸とは何か”を明らかにしてみたい。
2020年という節目の今年、現代日本の陶芸を総覧する。
特集 新・現代陶芸入門
監修・外舘和子(多摩美術大学教授・工芸史家)
●現代陶芸の2つの基準
●現代陶芸の4分類
1 鑑賞主体のうつわ
鑑賞主体のうつわーうつわの構造を持つ造形表現
2 具象的陶芸
具象的陶芸ー具体的なモチーフをどう生かすのか
3 自由造形的陶芸
自由造形的陶芸ー表現の探究と手法の拡がり
4 用途の陶芸(食器などの実用の陶磁器)
用途の陶芸ー実用陶磁器の5分類
●陶芸家を取り巻く環境と未来への展望
陶芸家ヒストリー 三代宮永東山
彫刻と陶芸のはざまで
フォーカス・アイ 水元かよこ
エキセントリックな少女と冷静な開拓者の眼
文・米田晴子(石川県能登島ガラス美術館学芸員)
期待の新人作家 釣 光穂
現代工芸の作り手たち 第16回 漆芸 藤野征一郎
漆塗の隠蔽力ー藤野征一郎の造形思考
文・金子賢治(茨城県陶芸美術館館長)
展覧会スポットライト 和巧絶佳展ー令和時代の超工芸ー
文・岩井美恵子(パナソニック汐留美術館学芸員)
展覧会スポットライト 三輪龍氣生展ー行け、熱き陶の想いよ。
文・石崎泰之(山口県立萩美術館・浦上記念館副館長)
展覧会スポットライト 英国で始まりー濱田・リーチ 二つの道ー
文・横堀 聡(益子陶芸美術館学芸員)
展覧会スポットライト 菊池コレクションー継ぐ
今泉今右衛門、酒井田柿右衛門、三輪休雪、樂吉左衞門
文・島崎慶子(菊池寛実記念 智美術館主任学芸員)
陶芸実践講座 陶芸家と作る小物 第9回
タタラで作るカップ 講師・由良りえこ
陶芸マーケットプライス
展覧会スケジュール
展覧会プレビュー
HONOHO GEIJUTSU English Summary
他

- 【バーゲン本】みんなの建築ミニチュアー子供も大人も楽しめる世界の建造物1000
- 橋爪 紳也 他
- (株)芸術新聞社
- ¥1100
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ページをめくりながら世界一周の旅を楽しみませんか?手のひらサイズのカワイイ建築物が1000以上!

- 日本政策投資銀行 Business Research アートの創造性が地域をひらく
- 日本政策投資銀行
- ダイヤモンド社
- ¥2200
- 2020年01月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)

- 【バーゲン本】だれでも書けるシナリオ教室
- 岸川 真
- (株)芸術新聞社
- ¥1017
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
既存の技法書は、難しすぎる!先輩口調でやさしく指南します2時間映画のシナリオを3日間で書く! そんな仰天の脚本術と、その根にあるメソッドを紹介。シナリオとは大袈裟な「テーマ」が先にあるのではなく、「映画を撮ってみたい」という素朴な欲求さえあれば書けるものだと著者は考えます。

- 天守
- 三浦 正幸
- 吉川弘文館
- ¥2640
- 2022年10月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
近世大名の権威の象徴である天守。安土城を築いた織田信長が創始し、日本の伝統文化の根本を覆した革命的な造りは、軍事建築でありながら壮麗な造形で多くの人を魅了し続けている。姫路城をはじめ現存天守の構造と意匠を分析し、その創造性や芸術性、籠城戦での機能、建築的工夫の豊かさを詳説。失われた天守にも触れつつその歴史と魅力に迫る。
プロローグ/天守の概要(天守という名称/天守の規模形式/天守の定義/天守型式と構成/現存天守と再建天守)/天守の平面と構造(一階の平面形式/平面の逓減/最上階の形式/重・階/構造)/天守の意匠と防備(外壁と窓/防御装置/天守の品格)/姫路城天守の構造と意匠(概要と沿革/規模形式と構造/豊かな創造性)/現存する天守の構造と意匠(犬山城天守/彦根城天守/松江城天守/松本城天守・乾小天守/丸岡城天守/丸亀城天守/宇和島城天守/備中松山城天守/高知城天守/弘前城天守/(伊予)松山城天守/熊本城宇土櫓)/天守の歴史(天守の創始(永禄・元亀・天正)/天守建築の確立と分化(天正八年〜慶長四年)/天守の発展(慶長五年〜二十年)/天守建築の規制(慶長十四年〜)/天守の喪失(天正十年〜昭和二十四年))/エピローグ/既発表論文・著書ほか/参考文献一覧

- 【バーゲン本】ボクのじてんしゃ
- きむら ゆういち
- (株)芸術新聞社
- ¥880
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ひとからもらったクセのついたオンボロ自転車。ひん曲がっているから、ねじ伏せようとするとすぐに転んでしまう。はじめは嫌だったけど、ボクの方で自転車のクセに合わせることを知ってからは、頼もしい相棒になった……大事なのは、長所も短所も知ったうえで、愛情を注ぐこと。それはきっと、相手が自転車であっても、友だちであっても、同じはずです。