錯覚 の検索結果 標準 順 約 660 件中 321 から 340 件目(33 頁中 17 頁目) 

- 動的平衡2
- 福岡 伸一
- 木楽舎
- ¥1676
- 2011年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.07(103)
生命よ、自由であれ
生命の本質は、自己複製ではなく、絶え間のない流れ、すなわち動的平衡にある。鮮やかに喝破した前著から2年。生物学の新しい潮流エピジェネティクスは、ダーウィン進化論の旧弊を打ち破るか。動物を動物たらしめた必須アミノ酸の意味とは? 美は動的平衡にこそ宿り、遺伝子は生命に対して、自由であれと命じている。さらなる深化を遂げた福岡生命理論の決定版がついに登場。
第1章 「自由であれ」という命令ー遺伝子は生命の楽譜にすぎない
第2章 なぜ、多様性が必要かー「分際」を知ることが長持ちの秘訣
第3章 植物が動物になった日ー動物の必須アミノ酸は何を意味しているか
第4章 時間を止めて何が見えるかー世界のあらゆる要素は繋がりあっている
第5章 バイオテクノロジーの恩人ー大腸菌の驚くべき遺伝子交換能力
第6章 生命は宇宙からやって来たかーパンスペルミア説の根拠
第7章 ヒトフェロモンを探してー異性を惹き付ける物質とその感知器官
第8章 遺伝は本当に遺伝子の仕業か?-エピジェネティックスが開く遺伝学の新時代
第9章 木を見て森を見ずー私たちは錯覚に陥っていないか

- 文系でもよくわかる 宇宙最大の謎!時間の本質を物理学で知る
- 松原 隆彦
- 山と溪谷社
- ¥1650
- 2023年09月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
物理学では時間の向きは存在しない。
なぜ時間は60進法なのか。
超ひも理論とループ量子重力理論の時間の違い。
サイクリック宇宙=終わりのない宇宙。
意識は粒子でできているー時間の流れの中で、同一の意識が再生する可能性。
時間はこの先も永遠に存在し続けていくのか。
そもそも時間はどうやって生まれたのか。なぜ生まれたのか。時間とは一体何なのかーー。
この本では、
・物理学者はどのように時間を扱ってきたのか(1章)
・今につながる時間はどのように始まったのか(2章)
・時間の終わり、つまり宇宙の終わりはどのように訪れるのか(3章)
・時間を計る道具によって私たちの生活はどのように変わってきたのか(4章)
・「1日24時間」はずっと変わらないのか(5章)
と、時間というものをいろいろな角度から見ていきます。
そうすることで時間とはいつも変わらずに存在し、一方向に流れ続けているだけの存在ではないことがわかってくるはずです。
そもそも物理学では「過去から未来に時間が流れる」ということさえ、まったく自明なことではないのです。
本書を読むことで、当たり前のように感じられていた時間の流れが実は当たり前ではないことを体感し、時間という概念が揺らぐことを楽しむことができるでしょう。
1章 「物理学」の時間ーー物理学者は時間をどう扱ってきたのか
2章 時間の「はじまり」--それは宇宙のはじまり
3章 時間の「おわり」--宇宙に終わりは訪れるのか
4章 時間の「道具」--時計が人々の生活を変えた
5章 身の回りの時間ーー1日はいつも24時間か

- 科学マジックサイエンスエンターテイメント
- チャーリー西村
- ワニブックス
- ¥1047
- 2006年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
話題のサイエンスマジックをイラスト&解説つきで伝授!“科学のうんちく”も満載!!この1冊があればあなたもサイエンステイナーになれる。

- サクッと学べるデザイン心理法則108
- 321web(三井 将之)
- 翔泳社
- ¥1848
- 2023年02月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(11)
心理効果を使った広告・デザインで自然に売れる広告やデザインの仕組みがわかる。

- 香りアロマを五感で味わう
- 廣瀬 清一
- フレグランスジャーナル社
- ¥1760
- 2017年05月24日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
・人だけが味わえる世界 ・隠れた脳力 ・香りの表現 ・柔軟な五感 ・身の回りの香りアロマ

- 攻めと守りの競争価格戦略
- 窪田千貫
- 中央経済社
- ¥2530
- 2016年04月26日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
消費者の商品に対する低価格志向は根強いものがあるが、商品を購入する動機は「お得感」であり、価格が高い商品でも価値が伝われば購買に結びつく。利幅の高い商品を売って利益を伸ばしている企業は、この「お得感」の演出が上手い。本書は、攻めと守りのバランスを重視した価格競争戦略を、簡単な図表と計算式、具体例を用いてわかりやすく解説する。

- たまたま
- レナード・ムロディナウ/田中三彦
- ダイヤモンド社
- ¥2200
- 2009年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.82(69)
なぜヒトは「偶然(たまたま)」を「必然(やっぱり)」と勘違いしてしまうのか?確率、統計をうまく用え、日常に潜む「たまたま」の働きを理解する。

- 第八作品集『無題』
- downy
- rhenium records
- ¥3267
- 2025年03月05日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
25年の進化、5年ぶりの衝撃──downyが描く未踏の音世界。
結成25周年イヤーの2025年3月に
5年振りのフルアルバム第八作品集『無題』をリリース!
今年で結成25周年を迎えたdownyが、5年ぶりとなるフルアルバム第八作品集『無題』を3月5日にリリースが決定!
本作は、ミックスエンジニアに美濃隆章(toe)を迎え、製作陣には若命優仁(eksperimentoj)、manukan (zezeco)が参加。
空間を歪める不穏なドラムとギター、5次元へ到達した予測不能な展開、ハードコアと非線形エレクトロニックの融合。
飽くなき実験精神を更新し続けるdownyの新境地。
またアルバムのアートワークは『攻殻機動隊 SAC_2045』のキャラクターデザイン、
『Cyberpunk: Edgerunners』のMUSIC VIDEO『Let You Down』を手がける
ロシア出身のイラストレーター”イリヤ・クブシノブ”を起用。
CD盤にはボーナストラックとして、2022年6月にデジタルリリースした「喘鳴」と、未発表曲「紙の朝」の2曲が収録!
そして New Album Release Tour 2025『夜の背骨』と題し、
札幌、東京、名古屋、大阪、広島の5都市でのワンマンライブ開催も決定
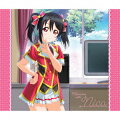
- Solo Live! 3 from μ's 矢澤にこ(CV.徳井青空)
- 矢澤にこ
- (株)バンダイナムコアーツ
- ¥3187
- 2018年03月28日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 2025年の薬局・薬剤師
- 藤田道男
- じほう
- ¥2200
- 2015年04月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 数学トリック=だまされまいぞ!
- 仲田 紀夫
- 講談社
- ¥968
- 1992年02月17日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
平安時代絶世の美女といわれていた小野小町。彼女に求婚した男は多数いたが、最も熱心だったのが深草少将。小町から「百夜続けて通ったら結婚しよう」と言われた彼は、九九夜熱心に通ったものの、あと一夜というときに急死してしまったという。後に老いて友人のいなくなった彼女は、「1 2 3 4 5 6 7 8 9」の数列の間に「+、-、×、÷」を入れ、「99」や「100」を作って少将を思い出すことに熱中したという
数学トリックに挑戦!
平安時代、絶世の美女といわれていた小野小町。彼女に求婚した男は多数いたが、最も熱心だったのが深草の少将。小町から「百夜続けて通ったら結婚しよう」と言われた彼は、九九夜熱心に通ったものの、あと一夜というときに急死してしまったという。後に老いて友人のいなくなった彼女は、「1 2 3 4 5 6 7 8 9」の数列の間に「+、-、×、÷」を入れ、「99」や「100」を作って少将を思い出すことに熱中したという。さて、どうやったのでしょうか?
1 数ーーイ、スイスイとすり抜けよう
1.語呂と手拍子
2.数に意味あり!
3.数の不思議
2 計算、退散、もうたくさん?
1.計算オモチャ箱
2.速算術と社会
3.計算の効用
3 三角が、四角四面の櫓(やぐら)の上で
1.昔の名前で出ています
2.生活への知恵
3.ピラミッドからの誕生図形
4 円は異なもの 不思議なもの
1.円が転がると……
2.円の特徴とその仲間
3.円にかかわる問題へ挑戦
5 無限は有限のナレの果てか?
1.“算数”の中の無限
2.無限のヘンな問題
3.“無限”の感覚
6 論理が通れば、ムリは引っ込む
1.証明とは何か
2.「でない」「できない」という説得
3.裁判と証明は似ている
7 錯覚、錯騒だまされまいぞ!
1.錯図の秘密を暴く
2.トポロジーという手品数学
3.“意外な結果”への探偵

- 進化論はいかに進化したか
- 更科 功
- 新潮社
- ¥1815
- 2019年01月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.78(20)
ダーウィンのどこが正しく、何が間違いだったのか? 『種の起源』が出版されたのは160年前、日本では幕末のことである。ダーウィンが進化論の礎を築いたことは間違いないが、今でも通用することと、誤りとがある。それゆえ、進化論の歩みを誤解している人は意外に多い。生物進化に詳しい気鋭の古生物学者が、改めてダーウィンの説を整理し、進化論の発展を明らかにする。

- 機動戦士Vガンダム SCORE.2
- 千住明/KARAK/小峰公子
- キングレコード(株)
- ¥1706
- 1999年03月05日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本作品の音楽集第2弾がリリースされた。今回はシリーズ中盤より使用された、センチメンタルなイメージの楽曲を中心に収録している。BGMのタイトルを富野総監督がネーミングしており、独特のイメージがガンダムシリーズの新境地を感じさせる。

- In Science Curiosity
- 大塚生子/瀧川宏樹
- 金星堂
- ¥2200
- 2021年01月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 直感力を高める数学脳のつくりかた
- バーバラ・オークレイ/沼尻由起子
- 河出書房新社
- ¥2090
- 2016年05月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.43(7)
アタマを使うにはコツがある!難問を解くときは「集中モード」とリラックスした「拡散モード」を切り替える、バラバラの情報をまとめて記憶する、ありありと目に浮かぶものにたとえてみる…元数学オンチの工学教授が明かす、脳の取扱説明書!

- ジエンド・オブ・イルネス
- デイビッド・B.エイガス/クリスティン・ロバーグ
- 日経BP
- ¥2200
- 2013年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
スティーブ・ジョブズの医師も務めた米国第一線がん研究者による医者に殺されないための「最新養生法」。

- ファーマゲドン
- フィリップ・リンベリー/イザベル・オークショット
- 日経BP
- ¥2200
- 2015年02月06日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.71(11)
まるで工場のような家畜飼育、養殖、穀類・豆の単一栽培……。
一見すると、安価な食料を効率的に大量生産する素晴らしい手段のように見える。
しかし、現実はまったく逆だ。現代的集約農業は、公害をまき散らし、生態系を乱し、貧困層を拡大する。
その先に待ち構えているのは、ファーマゲドン(農業がもたらすハルマゲドン)だ。

- AIとSF
- 日本SF作家クラブ
- 早川書房
- ¥1452
- 2023年05月23日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.26(23)
画像生成ソフトからChatGPTまで、人間とAIの関わりは歴史的な転換点を迎えようとしている。22人のSF作家が見通す未来とは?

- 食品工場改善入門 集大成
- 小杉直輝
- 水産タイムズ社
- ¥4400
- 2021年01月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「コストカットはやり尽くした」。そう断言できますか?
世界的レベルで効率化を追求した自動車工場ですら、乾いたタオルを絞るように現場改善を継続しています。まして多品種少量生産、労働集約型の食品工場において現場改善に終わりはないといえます。
本編は40年間にわたり生産現場で指導を行ってきた著者が最新事例を取り上げながら無駄を顕在化し、改善した成功例の数々を集め、写真や図面を多用して分かりやすく解説しております。多くの食品企業の絶大な支持を得ている小杉氏が長年の改善ノウハウを集大成した一冊です。
・生産活動の基本 目からウロコが落ちる ・物づくりの錯覚と改善の進め方 機械化すれば生産性が上がる?コンベアラインでラインスピードを上げたほうがいい? ・ムダの見つけ方 7つのムダの発生原因と改善策 ・金をかけないコストダウンの手法 ・より改善を進めるために マヨネーズの多工程持ち作業による活人事例 ・物の流れをよくする 長年赤字の事業を短期間で黒字化 ・屋台生産とは 成功のポイント ・工程再編と新工場建設の成功例

- 魍魎の匣 オリジナル・サウンドトラック
- 村井秀清/ナイトメア
- (株)バップ
- ¥2356
- 2008年12月21日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
京極夏彦原作のベストセラーを基にしたTVアニメのサントラ。ナイトメアの主題歌のほか、INFINITECIRCLEなどでも活躍する村井秀清が音楽を担当。昭和20年代末期を舞台にした怪奇ミステリーの場面場面を、クラシカルを基調とした切ない音楽でドラマティックに盛り上げる。