インターネット の検索結果 標準 順 約 2000 件中 341 から 360 件目(100 頁中 18 頁目) 

- ネットの英語術
- ディビッド・セイン/小松アテナ
- 実務教育出版
- ¥1760
- 2008年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(4)

- レイシズムを解剖する
- 高 史明
- 勁草書房
- ¥2530
- 2015年09月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(5)
「行儀が悪い」ものであった、在日コリアンへの差別・偏見が再び繰り返されているのはなぜなのか。レイシズムの実態を明らかに。
「在日コリアンは日本人より劣っている」という古くからあるレイシズムと、「不当な特権を得ている」とする新しいレイシズムはどのような関係にあるのか。偏見を持つ人はもともと右翼的傾向にあるのか、それとも別の要因によるのか。インターネット利用との関係は? 偏見を理解するための社会心理学。
目次
はじめに
第1章 問題と目的
第2章 Twitterにおける言説の分析
2-1 研究1 コリアンについての言説:誰が、どのような投稿をしているのか?
2-2 研究1補足 レイシズム関連ツイートをさらに分析する
2-3 研究2 中国人についての言説を用いた比較
2-4 研究3 日本人についての言説:意識されるコリアン
2-5 第2章のまとめ
第3章 質問紙調査によるレイシズムの解明
3-1 研究4 レイシズムは2つに分けられるのか?
3-2 研究5 2つの“レイシズム”は“2つのレイシズム”か?
3-3 第3章のまとめ
第4章 インターネットの使用とレイシズムの強化
4-1 研究6 インターネットの使用と右翼傾向に関係はあるのか?
4-2 研究7 インターネットの何がレイシズムに関わるのか?
4-4 第4章のまとめ
第5章 集団間接触によるレイシズムの低減
5-1 研究8 友達、友達の友達の効果
第6章 全体考察
6-1 本書の構成と研究結果
6-2 在日コリアンに対するレイシズムの解明
6-3 本書の意義
6-4 本書の限界と今後の可能性
おわりに
あとがき
引用文献
索引

- SNSを超える「第4の居場所」
- 岡田尚起/佐藤大輔
- アンノーン
- ¥1540
- 2018年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
17歳の高校生からひきこもり、元暴走族の経営者、性同一性障がい者、70代の高齢者まで全561人の個性豊かなパーソナリティーが集うインターネットラジオ局「ゆめのたね」の全貌!

- インターネット新時代の法律実務Q&A第3版
- 田島正広/足木良太
- 日本加除出版
- ¥3850
- 2017年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
経験豊富な著者陣によるネット分野についての解説書。仮想通貨やIoT、改正個人情報保護法など最新情報を盛り込んだ分かりやすく丁寧な解説の125問!

- マーケティング・リサーチに従事する人のためのデータ分析・解析法
- 一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会/島崎 哲彦/中山 厚穂/大竹 延幸/鈴木 芳雄
- 学文社
- ¥3300
- 2020年04月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
実務経験4?5年程度で、基礎編となる『マーケティング・リサーチに従事する人のための
調査法・分析法─定量調査・実験調査・定性調査の調査法と基礎的分析法─』に記載した
調査法・分析法の基礎的知識を習得した人を対象に、
よく利用される調査データの高度な分析・解析法の習得を目標に編集。
また、読者の理解促進のために、事例を数多く用い、
これから多変量解析や時系列データの分析を学ぼう、
用いてみようとする方にも、よりわかりやすく、理解できるよう工夫した。
本書で分析・解析法を学ぼうとする人は、まず調査法・分析法の基礎的知識を
『マーケティング・リサーチに従事する人のための調査法・分析法─定量調査・実験調査・定性調査の調査法と基礎的分析法─』によって
整理・体系化した上で、本書にとりかかることをお勧めする。
この2冊を活用することで、マーケティング・リサーチ従事者が幅広いリサーチの知識を習得し、
リサーチの企画能力、リサーチの実施能力、リサーチ・データの分析能力を向上し、
多くのリサーチ課題を解決していくことが期待できる。
※(一財)統計質保証推進協会統計検定センターが実施する「統計調査士」,「専門統計調査士」
の資格試験出題の参照基準にも対応。

- ネットビジネス進化論第2版
- 中村忠之
- 中央経済社
- ¥2530
- 2015年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
急速に進化するネットビジネスと、それに関連するあらゆる基礎知識がこの一冊でわかる!

- 超初心者のためのWeb作成特別講座
- 永野 和男/学校インターネット教育推進協会
- 日本能率協会マネジメントセンター
- ¥1540
- 2020年12月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「全国中学高校Webコンテスト」は、制作物が誰かの役に立つ「教材」として構成・表現された内容であることが求められ、「伝える立場に立ち、何をどう表現するか、仲間とともに徹底的に考える」探究・協調学習として生徒たちに深い学びをもたらす点に大きな特徴があります。
本書は、本コンテストで要求されるレベルのWeb教材制作のための手引書であり、初めてWeb制作に取り組む人や、チームでのWeb制作プロジェクトに取り組む人に最適な入門書です。本書を通じ、プログラミングの前提となるHTML・CSSなどのWeb制作の基礎知識と、本コンテストで要求される構成力・表現力、および問題解決力・コミュニケーション力が身に付きます。
はじめに 指導にあたるコーチ・リーダーの方へ
基礎講座 Webページの基礎知識
第 1 章 自分のWebページを作成してみよう
個人学習をスタートする前に
1-1 HTML エディタの使い方を覚えよう
1-2 テンプレートを修正する
1-3 ページのデザインを変更しよう
1-4 表現を工夫してmyWeb ページを仕上げよう
第 2 章 あると便利な知識
2-1 テンプレートに書かれていることを知っておこう
資料 よく使うCSS プロパティ
2-2 写真・画像・動画などの表示を知っておこう
第 3 章 チームで分担・協力して1つの作品を作ろう
チーム学習をスタートする前に
3-1 テーマを決めて役割分担をしよう
3-2 Web ページを1 つにまとめよう
3-3 完成したWeb ページを発信しよう
第 4 章 あると便利な知識2
4-1 リストを使った装飾方法を知っておこう
4-2 ナビゲーションメニューのカスタマイズ方法を知っておこう
4-3 CSS の指定とCSS の有効性を知っておこう
4-4 Web ページ作成を支援するツールを知っておこう
参考1.リファレンス一覧
参考2.「チーム学習のためのHTML エディタ」のテンプレートのHTML
付録 Web コンテストにチャレンジしよう
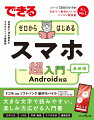
- できるゼロからはじめるスマホ超入門 Android対応 最新版
- 法林岳之/清水理史/できるシリーズ編集部
- インプレス
- ¥1408
- 2023年07月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
大きな文字で読みやすい、楽しみ方広がる入門書。文字入力、LINE、写真・動画、スマホ決済、機種変更。

- 論説体中国語 読解力養成講座
- 三瀦 正道
- 東方書店
- ¥2640
- 2010年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
新聞・雑誌は言うに及ばず、インターネット上にも中国の情報が溢れる昨今、ビジネスであれ研究であれ、中国とかかわりを持とうとするとき、中国語の文章を確実に正確に「読める力」が必要になってきます。中国語の「書き言葉」は、さまざまな文体を含みますが、その中でも代表的なのが、「論説体」です。本書は、新聞・雑誌、学術論文、インターネット上などで広く使われるこの「論説体」の読解力の養成のためにさまざまな試みを実践してきた著者の成果を余すところなくこの1冊に集約しています。「中国語が少し複雑になると正確に意味が取れない」「新聞や雑誌、インターネットなど生の中国語がうまく訳せない」そんな方にも絶好の参考書です。

- ICT×日本語教育
- 當作 靖彦/李 在鎬
- ひつじ書房
- ¥3300
- 2019年03月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ICTを利用した日本語教育の研究と実践の事例を紹介。研究編、実践編、ツール・コンテンツ編の3つの柱で構成。研究編ではウェブツールを利用した日本語教育の全体図を示す論考を収録。実践編では反転授業や仮想現実を取り入れた授業実践の具体例を紹介。ツール・コンテンツ編ではICTを利用した日本語テスト、学習支援アプリ、eラーニングの開発プロセスを紹介。理論と実践の両面から情報通信技術を利用した新しい日本語教育を提案する。
第1部 研究編
1 ネットワーク時代の言語教育・言語学習
當作靖彦
2 日本語文法認知診断Webテスト
島田めぐみ・孫媛・谷部弘子・豊田哲也
3 学習者作文の習熟度に関する自動判定とWebシステムの開発について
李在鎬・長谷部陽一郎・村田裕美子
4 CEFR読解指標に基づく日本語例文分類手法
宮崎佳典・平川遼汰・高田宏輝・谷誠司
5 Skypeによる遠隔セッションを取り入れた実践
Deep Active Learningの視点から
毛利貴美
6 AIチュータの実現に向けて
誤用例文コーパスデータの構築と誤用文修正知識の習得
相川孝子・高橋哲朗
第2部 実践編
7 反転授業を意識した教材開発のための実践授業
石崎俊子
8 インターネットを活用した異文化間コミュニケーション能力育成をめざした日本語学習活動
ショー出口香
9 デジタル・ストーリーテリング(DST)を用いた活動の可能性
多様な日本語教育の現場から
半沢千絵美・矢部まゆみ・樋口万喜子・加藤真帆子・池田恵子・須摩修一
10 To combine knowledge and the real world
拡張現実を利用した日本語学習の試み
米本和弘
第3部 ツール・コンテンツ編
11 行動中心アプローチにもとづいたヨーロッパにおける日本語オンラインテストの開発
東伴子・代田智恵子
12 漢字力診断テストによる日本語力の評価
加納千恵子・魏娜
13 メール作成タスクを用いた作文支援システム
金庭久美子・川村よし子・橋本直幸・小林秀和
14 継続的オーラルアセスメントの開発
「話せる」を実感する評価法をめざして
宮本真有・深田淳
15 漢越語データベースを活用した音声認識による漢語学習アプリの開発
クロス尚美・山崎恵
16 継続的な学習につなげる日本語学習サイト
「ひろがる もっといろんな日本と日本語」
伊藤秀明・石井容子・前田純子
17 まるごと日本語オンラインコースの開発と運用
自学自習を継続させるための工夫とは
武田素子・熊野七絵・千葉朋美・檜山治樹
18 気持ちを伝える音声のWeb教材
「つたえるはつおん」
木下直子・中川千恵子
19 Fluency Calculatorによる口頭流暢性客観指標の算出とそれを用いた流暢性の縦断的研究
松本一美・広谷真紀・深田淳
索引
執筆者紹介

- シモーヌ(Les Simones)VOL.6
- シモーヌ編集部
- 現代書館
- ¥1650
- 2022年06月08日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(2)
2021年9月、日本に誕生したデジタル庁のスローガンは「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」だが、オンライン空間ではヘイトスピーチ、ハラスメントがすさまじく、インターネットから距離をとる人が少なくない。白人男性中心の開発、高齢、貧困、障害など、さまざまな要因でアクセスすらままならない人もいる。
現在のインターネットは誰にでも優しいとは、決して言えない。これからのデジタル空間を生き抜くために、インターネットをフェミニズム視点で考えていく。

- ネット・コーチングで開業しよう!
- 杉本良明
- 同文舘出版
- ¥1540
- 2006年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.75(5)
「ネット・コーチング」とはネット上でコーチングを行なうビジネス。営業活動は、ホームページなどを活用して行ない、今の仕事を続けながら、週末のみ副業として「コーチ業」をすることも可能。だから、「ノーリスク」で開業できる!本書では、ネット・コーチング・ビジネスの魅力、コーチング技術の学び方、開業までの流れと、集客法までをわかりやすく解説する。

- モノづくり・発明家の仕事
- 中本繁実
- 日本地域社会研究所
- ¥1848
- 2023年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
これ一冊でわかる!特許出願書類の書き方。得意な分野の知識を深める!出来上がった作品の完成度をとことん高める!徹底的に情報を集めたら、いざ、勝負!

- ネットワークはなぜつながるのか第2版
- 戸根勤/日経network編集部
- 日経BP
- ¥2640
- 2007年04月
- 予約受付中
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.2(82)
ブラウザにURLを入力してからWebページが表示されるまでの道筋を探検。ネットワーク技術に関する説明内容を全面的に見直し、基礎的な解説を大幅に加筆した改訂版。

- セキュリティ技術の教科書 第3版
- 長嶋仁
- アイテック
- ¥4620
- 2023年03月17日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
この1冊で、セキュリティ技術の知識を深める!
◎情報セキュリティ分野の教育経験豊富な著者が執筆
情報処理安全確保支援士試験対策セミナーなどを担当し、受講生からも好評を得ている著者が執筆した信頼の一冊です。
◎技術分野ごとに知識事項を分かりやすく解説
重要用語は色付きで示し、イメージしづらい概念的な内容は図解しています。
◎知識確認用に「例題演習」問題を掲載
テキストを読んで終わりではなく、アウトプットして知識の確認ができるよう、例題演習問題138問を掲載しています。
第1章 情報セキュリティとサイバーセキュリティ
第2章 インターネット技術の基礎
第3章 セキュリティに対する脅威
第4章 暗号技術・認証技術,PKI
第5章 通信の制御とサイバー攻撃対策技術
第6章 Web システムのセキュリティ
第7章 メールシステムのセキュリティ
第8章 DNS システムのセキュリティ
第9章 セキュアプロトコルとVPN
第10章 システムセキュリティ
第11章 情報セキュリティの開発・運用マネジメント

- 楽しいことしか起きない! 福田ナオのわくわくインターネット生活
- 福田 ナオ
- KADOKAWA
- ¥1100
- 2022年05月26日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.75(4)
マンガ、アニメ、ゲーム、上手な承認欲求の満たしかた、気の合う友だちの見つけかた、逃げ込める場所のつくりかた。大切なことは全部インターネットから教わったーー。平成インターネットが生み出したモンスター福田ナオちゃんの、基本的には楽しいことしか起きない日常をお届けします!

- 現代広告全書
- 田中 洋/岸 志津江/嶋村 和恵
- 有斐閣
- ¥2750
- 2021年12月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
第一線の研究者と実務家による「全書」。理論と実践の両面からデジタル時代の広告の姿を示す。重要研究のレビューから事業展開に不可欠な視座を提供する,マーケター必読の1冊。「広告の理論」「マーケティング・コミュニケーションの新展開」の2部構成。
第1部 広告の理論
第1章 広告効果の理論──心理学の発展を中心に(岸志津江) 第2章 デジタル広告の効果(岸志津江) 第3章 広告効果の経験的一般化──広告はどのように効いているのか(田中洋) 第4章 メディアの近未来を予測する──メディア分化モデル(田中洋) 第5章 広告と社会倫理──インターネット時代にいっそう求められる広告倫理(嶋村和恵)
第2部 マーケティング・コミュニケーションの新展開
第6章 マーケティング・コミュニケーションの新手法群──新しい情報環境下における取り組み(丸岡吉人) 第7章 デジタル広告の歴史──デジタル・クリエイティブ,その四半世紀(大岩直人) 第8章 世界の広告クリエイティブ(佐藤達郎) 第9章 日本広告学会における研究動向──『広告科学』にみる2000〜2020年の動向(石崎徹) 第10章 デジタル広告研究の展開(広瀬盛一) 第11章 広告会社の歴史的変容(河島伸子) 第12章 SNSのブランドページを研究する(竹内淑恵) 第13章 中小・ベンチャー企業におけるデジタル・マーケティング戦略(荻原猛・北川共史・浅見剛)

- 仕事×ITの基本をひとつひとつわかりやすく。
- Gakken
- Gakken
- ¥1430
- 2024年02月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
★★★計発行部数980万部(※)の大ベストセラー参考書
「ひとつひとつわかりやすく。」から待望の仕事版が登場!★★★
※小学生・中学生・高校生向け全171点の合計発行部数(2024年1月現在)
『仕事×ITをひとつひとつわかりやすく。』は、エンジニア職ではない新入社員や入社を間近に控えた学生など、仕事に必要なITの知識を学びたい方のために、業務に役立つITの基礎知識やビジネスに活用されているITについて、ひとつひとつ解説しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼▼本シリーズの3つの特長▼▼
その1・見開き完結でわかりやすい!
本書では、1つのテーマが見開きにまとまっています。左ページではそのテーマのポイントをわかりやすく解説しています。右ページでは、「一目で理解!図解まとめ」があり、図や表を使って関連する情報をまとめています。
その2・ポイントが明白!
各テーマの冒頭には、「ここがポイント!」のコーナーを設けており、そのテーマで特に重要なポイントを紹介しています。解説を読む前にあらかじめポイントをおさえられるので、効率よく学習を進められます。
その3・新人からベテランまで幅広く役立つ仕事の参考書
社会人なら絶対に抑えておきた基礎知識はもちろんのこと、業務に直結するアドバイスや最新情報まで幅広く紹介。就活中の方や新入社員の方はもちろん、ステップアップを目指す社会人の方まで、幅広く役立つこと間違いなしの一冊です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼▼本書の主な内容▼▼
第1章 ITはどのように役に立つ?
第2章 パソコンの基本
第3章 パソコンとネットワーク
第4章 情報セキュリティ対策
第5章 ITの活用事例とトピック
知っておきたいIT用語集
よく使う! ショートカットキー

- SENSE インターネットの世界は「感覚」に働きかける
- 堀内 進之介/吉岡 直樹
- 日経BP
- ¥2420
- 2022年09月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(3)
人間はラクな方法に流れる。
そして、戻れない
★ネットの「勝ち組」は何をしているのか★
・なぜVTuber事務所の時価総額が、親会社のフジテレビを抜いたのか
・なぜClubHouseはメジャーにならなかったのか
・なぜYouTubeはライブへ移行しているのか
インターネットの世界の進歩は、今までの延長であると思っていませんか? しかし、現在決定的なことが起こっています。
それは、今、ネットはあの手この手で人の「感覚」を刺激しており、そこからは逃れられないということです。インターネットの技術の進歩もそれを可能にしています。
この本では、現在のユーザーの姿や、感覚を刺激するとはどういうことか、具体的にビジネスの現場でどう使われているのかを見ていきます。また、感覚を中心にしてインターネットで生まれている新しいものとは一体何かなどを、実際に人気のあるYouTubrやVTuberを例にして理解します。人間が感覚を刺激されることにいかに弱いのかがわかってくるはずです。
第1章 ユーザーにはもう、主体的な行動は期待できない
誰もがもうモノが欲しくない時代になった
「感覚」は無意識に働きかけ、もう人はコントロールされている
どうしてNetflixは「使っていない会員」を手放すサービスを始めたのか
アプリまんがの「新作無料モデル」はユーザーの負担を少し免除している
AKBのビジネスモデルはマドンナと同じ
人間には「人の音声に弱い」という特性がある
聴覚の強みは「親近感をわかせる」こと
VTuberは聴覚中心のメディアの最前線
第2章 ユーザーはネットが刺激する「感覚」に誘惑される
人間はどんどん楽な方に流れる
ヒカキンの動画はなぜ人気なのか
ゲームは、視覚だけでなく音声の設計もしっかりしているから優れている
YOASOBIのすごさは「音楽」と「アニメーション」の融合という新しいジャンルを作ったから
消費者からの要望で生まれてきた「新しいメディア」
第3章 「感覚」は想像以上に私たちを動かしている
「気づかせる」ためには視覚以外を使ったものが多い
スーパー業界で「呼び込み君」が大ヒットしているのはなぜか
ガギグゲゴを使うと、人は怪獣を連想しやすい
音を聞くと、人間は自動的にそれっぽいものを連想する
ドアの音で高級車かどうかを判断している
高周波数の音は魅力的に聞こえる
BGMには、意識させずに人間の行動を変える力がある
若者にきてほしくない場所にはクラシック音楽を流している
信用されたければ早く話せ
ギャル語は「仲間意識」のためにある
第4章 実践編 それではどう設計するか
いつまでも記憶される「サウンドロゴ」とは何か
イヤーキャッチで引きつける手法
スキップされなかったとして、どういう映像を作ればいいのか

- 奪われた在日コリアンの日本国籍
- 李 洙任
- 明石書店
- ¥4180
- 2021年03月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「〇〇人であること」は天与のものなのか。国籍とは、個人が置かれた状況、親子関係や生地などに基づいて人為的に与えられるものに過ぎない。グローバル化、多文化化が進むなかでどのような国籍制度が望ましいのか。日本国籍取得者の経験などを踏まえて考える。
はじめに
第I部 国籍という呪縛
第1章 日本の帰化行政ーー密室行政と悪しき慣例
第2章 情報弱者を支援する行政書士のインターネット情報
第3章 コリア系日本人として生きる
コラム1 就職差別という制度的差別と国籍の壁
第2部 日本社会を支えるのは誰か
第4章 日本最大のエスニック・マイノリティ・ビジネスーー在日コリアン系起業家についての新視座
第5章 日本経済を支えた朝鮮からの移住労働者たちーー伝統産業西陣の事例から
第6章 変化し始めた日本の外国人政策
コラム2 日本のために一生懸命働いたーー西陣に生きた在日朝鮮人女性
第3部 日本人とは誰を指すのか
第7章 植民地支配に対する未来責任と特別永住者への処遇
第8章 コリア系日本人としてのルーツの再認識
第9章 日本人と在日コリアンーー異文化理解の観点から
第10章 旧植民地出身者とその子孫、そしてコリア系日本人ーー日本の移民政策の幕開け
コラム3 日本人から信用を得る、それが差別に打ち勝つ最強の手段
おわりに 知られざる歴史から理解する人間の重層的アイデンティティ
索引