男装 の検索結果 標準 順 約 960 件中 341 から 360 件目(48 頁中 18 頁目) 

- 逆装ランデヴー 〜女装男子と男装女子の話〜(1)
- 次見 やをら
- 講談社
- ¥715
- 2020年04月09日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
かわいいは正義! 強気美少女の宝ちゃん(男)と
いつでも男前! さわやかイケメンの美鶴くん(女)。
共通の知人の紹介で、偶然出会ったあべこべなふたりだけど、考え方は妙に似ていて…?
Twitterで話題のハイテンションラブコメ、装いを新たにしてついに書籍化!
単行本限定の描き下ろしマンガも収録した待望の第1巻!

- 月刊TVガイド静岡版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- COSPLAY MODE (コスプレイモード) 2020年 03月号 [雑誌]
- シムサム・メディア
- ¥1320
- 2020年02月03日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
男装特集

- 月刊 TVガイド愛知三重岐阜版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- 月刊 TVガイド関東版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- Audition (オーディション) 2016年 11月号 [雑誌]
- 白夜書房
- ¥662
- 2016年10月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
芸能界に直結したオーディション情報誌【表紙】映画「闇金ウシジマくんPart3」ヒロイン
白石麻衣(乃木坂46)
【内容】
▼特集
★地方っ子が上京&日本各地で大あばれ!
シン・オーデ☆全国制覇大作戦
吉本実憂/長谷川里桃/秋本帆華&伊藤千由李(チームしゃちほこ)/
大場美奈(SKE48)/真広佳奈&杉本愛里/松風理咲/
鈴木絢音(乃木坂46)/AKB48チーム8/「美少女図鑑」
★秋ドラマ大収穫祭! 〜出演女優たちに聞く! キャラ立ちの大切さ〜
「べっぴんさん」土村芳/「仮面ライダーエグゼイド」松田るか/「彼岸島」柳ゆり菜
★インスタからデビュー☆結果発表!
▼オーディション情報
★旬のオーディションをお届け!
Pick UP!!Audition
★元・宝塚トップスター凰稀かなめ、ユナク(超新星)と共演!
ミュージカル「花・虞美人」オーディション
★華麗に! 優雅に!
この秋、男装デビューしてみない?/ルウト
★Auditionオリジナルコラボオーデ
橋本マナミ・永尾まりやが所属 アービング
▼編集部の推しオーデ
★一年間に渡り「宝くじ」の顔に!
平成29年度 宝くじ「幸運の女神」募集
★レース場の華☆イメージガールを今年も募集!
鈴鹿サーキットクイーン 第39期生募集
★日本一有名な観光バスのイメージガール☆
第6代 はとバスグループイメージガール募集
★活動20周年の劇団が若きキャストを募集!
「三月の5日間」リ・クリエーション 出演者オーディション
★渡辺いっけい主演映画に抜擢!
映画「いつくしみふかき(仮)」キャストオーディション
★あこがれのDJになってラジオデビュー♪
ZIP-FM ミュージック・ナビゲーター オーディション
その他、オーディション情報多数掲載!
▼インタビュー企画
★「CUTIE HONEY -TEARS-」主演
『Elements』File30 西内まりや
★special interview
「はじまり。」第33回 松浦雅
渡辺麻友(AKB48)
Happiness
近藤公園&平岩紙
内村光良
國島直希
田中道子
松本来夢
高橋優里花
倉野尾成美(AKB48)

- MdN (エムディーエヌ) 2017年 08月号 [雑誌]
- インプレスコミュニケーションズ
- ¥1518
- 2017年07月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
デジタルデザイン・DTPのパソコン情報誌【デザインとグラフィックに関する総合情報誌 MdN[エムディエヌ] 】
【特集】
『男装憧憬ー境界を超越するキャラクターのデザイン』
ミステリアスさや、出で立ちの凛々しさから
多くの女性の心を掴んでしまうような「男装」や、
ボーイッシュな装いの少女たち。
そうした装いを想像する時、どこか憧れや眩しさを
感じることはないでしょうか。
この特集では、時代や背景の異なる男装のキャラクターを取り上げ、
さらに芸能や文化、服飾などさまざまな側面から、
私たちがなぜ「男装」に惹かれるのかを読み解いていきます。
***表紙&誌面スペシャルフォトセッション***
「女王蜂のアヴちゃん、男装という概念をまとう」
自身も最高傑作というニューアルバム「Q」をリリースした
女王蜂のボーカル、アヴちゃんがビシッとキマったスリーピース姿で登場。
■『キラキラ☆プリキュアアラモード』プロデューサー・インタビュー
みんなを守る母性と少年性が結びついたキャラクター
剣城あきら(キュアショコラ)はどのように生まれたのか?
■少女マンガを彩る男装キャラクターの歴史
『リボンの騎士』サファイヤから、『ベルサイユのばら』のオスカル、
2000年以降の作品に至るまで、少女マンガを研究する押山美知子さんと辿る
男装の少女キャラクターたちの歴史!
■2次元世界の男装の少女たち、15キャラクターの造形
01. サファイア『リボンの騎士』
02. 天上ウテナ『少女革命ウテナ』
03. 彰子『パレス・メイヂ』
04. 芦屋瑞稀『花ざかりの君たちへ』
05. 藤岡ハルヒ『桜蘭高校ホスト部』
06. 更紗『BASARA』
07. 富永セイ『風光る』08. アラミス『アニメ三銃士』
08. アラミス『アニメ三銃士』
09. 長尾景虎(虎千代)『雪花の虎』
10. 藤波竜之介『うる星やつら』
11. ハトシェプスト『碧いホルスの瞳』
12. オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ『ベルサイユのばら』
13. ユリウス・レオンハルト・フォン・アーレンスマイヤ『オルフェウスの窓』
14. 朝霞れい『おにいさまへ…』
15. 折原 薫『おにいさまへ…』

- 月刊 少年シリウス 2020年 05月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥779
- 2020年03月26日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
☆「シリウス」5月号、3月26日(木)発売☆
★祝スピンオフ4コマ『転スラ日記』TVアニメ化決定!!★
【TVアニメ化記念★表紙&巻頭】
累計50万部突破!!
神クオリティの『転スラ』スピンオフ4コマ☆巻頭2本立て!!
[転スラ日記 転生したらスライムだった件]
原作:伏瀬
漫画:柴
キャラクター原案:みっつばー
【センターカラー★新連載】
夫婦同心★江戸の町で大活躍!!
大ヒット小説、初のコミカライズ!!
[うちの旦那が甘ちゃんで]
漫画:雷蔵
原作:神楽坂 淳(講談社文庫/刊)
【2話同時連載★スタート記念センターカラー】
最新単行本 第2巻 発売中!!
[ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話]
横田卓馬
(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』
『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
【新展開★センターカラー】
『シドニアの騎士』の作者が描く本格SFバトル!!
[人形の国]
弐瓶 勉
【マガポケより出張掲載!!】
『半沢直樹』公式スピンオフ★猫マンガ!!
[半沢ニャオ樹]
原作・企画:池井戸 潤
漫画:篠丸のどか
【W連載★W掲載!!】
異能力バトル×大人気長寿連載
[ブーツレグ]×[夜桜四重奏 ヨザクラカルテット]
ヤスダスズヒト
異世界攻略×ダークファンタジー
[時間停止勇者]×[怪物王女 ナイトメア]
光永康則
【ついに決着! 第一部、完結!】
大ヒット音楽原作キャラクターラッププロジェクト
公式コミカライズ
[ヒプノシスマイク
ーDivision Rap Battle- side B.B & M.T.C]
原作:EVIL LINE RECORDS
漫画:蟹江鉄史
シナリオ:百瀬祐一郎
【『転スラ』本編&スピンオフも大人気連載中】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件] 漫画:川上泰樹
ブラック企業スピンオフ4コマ!!
[転生しても社畜だった件] 漫画:明地 雫
幼児化スピンオフ4コマ!!
[転ちゅら!転生したらスライムだった件] 漫画:茶々
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!! こちらも2本立て!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜] 漫画:戸野タエ
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【早くも大人気★新連載 第2回】
爆裂の異世界活劇!!
[爆宴 BAKUEN]
原作:イダタツヒコ
漫画:士貴智志
『XBLADE(クロスブレイド)』のタッグ、再臨!!
大人気ハイ・ファンタジー!!
[ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人]
原作:加茂セイ(講談社レジェンドノベルス/刊)
漫画:刀坂アキラ
キャラクター原案:布施龍太
【大人気★連載陣】
最新単行本発売直前!!
叛逆ずべ公アクション★隔号連載
[べアゲルター]
沙村広明(『波よ聞いてくれ』『無限の住人』)
大人気 異世界ファンタジー
[異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。]
遠山えま(『わたしに××しなさい!』)
圧巻のスケールで描くSFロボット漫画
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
とにかくかわいい『はたらく細胞』スピンオフ
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子(TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
特別ショート掲載
[ライドンキング]
馬場康誌(『空手小公子』シリーズ)
男装の麗人☆スパイアクション
[川島芳子は男になりたい]
田中ほさな (『乱飛乱外』)
瞠目のエキゾチック・タクティクス
[将国のアルタイル]
カトウコトノ
驚愕の“悪魔憑き”バトル
[レイジング・ヘル]
荒木 光(『僕たちがやりました』)
『ゼロから始める魔法の書』新シリーズ
[魔法使い黎明期]
原作:虎走かける
漫画:タツヲ
キャラクター原案:いわさきたかし
連載100回を超えてますます人気!!
[妖怪アパートの幽雅な日常]
原作:香月日輪
漫画:深山和香
★第45回「シリウス新人賞」結果発表、掲載★
☆「シリウス」5月号、3月26日(木)発売☆★祝スピンオフ4コマ『転スラ日記』TVアニメ化決定!!★【TVアニメ化記念★表紙&巻頭】累計50万部突破!!神クオリティの『転スラ』スピンオフ4コマ☆巻頭2本立て!! [転スラ日記 転生したらスライムだった件] 原作:伏瀬 漫画:柴 キャラクター原案:みっつばー
【センターカラー★新連載】夫婦同心★江戸の町で大活躍!!大ヒット小説、初のコミカライズ!! [うちの旦那が甘ちゃんで] 漫画:雷蔵 原作:神楽坂 淳(講談社文庫/刊)
【2話同時連載★スタート記念センターカラー】最新単行本 第(2)巻 発売中!! [ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話] 横田卓馬(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
【新展開★センターカラー】『シドニアの騎士』の作者が描く本格SFバトル!! [人形の国] 弐瓶 勉
【マガポケより出張掲載!!】『半沢直樹』公式スピンオフ★猫マンガ!! [半沢ニャオ樹] 原作・企画:池井戸 潤 漫画:篠丸のどか
【W連載★W掲載!!】異能力バトル×大人気長寿連載 [ブーツレグ]×[夜桜四重奏 ヨザクラカルテット] ヤスダスズヒト 異世界攻略×ダークファンタジー [時間停止勇者]×[怪物王女 ナイトメア] 光永康則
【ついに決着! 第一部、完結!】大ヒット音楽原作キャラクターラッププロジェクト 公式コミカライズ [ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side B.B & M.T.C] 原作:EVIL LINE RECORDS 漫画:蟹江鉄史
シナリオ:百瀬祐一郎 ほか

- 月刊 少年シリウス 2020年 06月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥779
- 2020年04月25日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
☆「シリウス」6月号、4月25日(土)発売☆
★[ヒプノシスマイク]かけ替えカバー付録つき!!★
★光永康則W連載!! 最新巻がW発売!!★
【異世界×怪物★W単行本5月8日(金)発売!!】
待望の第2巻 発売直前!!
本格異世界ファンタジー
[時間停止勇者]
光永康則
最新 第6巻 発売直前!!
大人気ダークファンタジー
[怪物王女 ナイトメア]
光永康則
【ヤスダスズヒトもW連載中!!】
ご存知★大人気連載
[夜桜四重奏(ヨザクラカルテット)]
ヤスダスズヒト
NEO異能力バトル★シリーズ連載
[ブーツレグ]
ヤスダスズヒト
【コミックス第3巻発売記念★かけ替えカバー付録】
[ヒプノシスマイクーDivision Rap Battle- side B.B & M.T.C]
原作:EVIL LINE RECORDS
漫画:蟹江鉄史
シナリオ:百瀬祐一郎
【最新2巻★発売記念★センターカラー】
大人気 異世界ファンタジー
[異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。]
遠山えま(『わたしに××しなさい!』)
【最新巻ともに5月8日発売!!】
熱望の第2巻 発売直前!!
圧巻のスケールで描く近未来SFロボットバトル
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
待望の第6巻 発売直前!!
新・王道ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉 (『シドニアの騎士』『BLAME!』)
【『転スラ』本編&スピンオフも大人気連載中】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件] 漫画:川上泰樹
累計50万部突破!!
アニメ化決定のスピンオフ4コマ!!
[転スラ日記 転生したらスライムだった件]漫画:柴
ブラック企業スピンオフ4コマ★最終回!!
[転生しても社畜だった件]漫画:明地 雫
幼児化スピンオフ4コマ!!
[転ちゅら!転生したらスライムだった件]漫画:茶々
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜] 漫画:戸野タエ
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大ヒット小説コミカライズ★新連載 第2回】
夫婦同心★江戸の町で大活躍!!
[うちの旦那が甘ちゃんで]
漫画:雷蔵
原作:神楽坂 淳(講談社文庫/刊)
【大人気★連載陣】
単行本支持率ついに[60万部]突破!!
超格闘★異世界ドラマ
[ライドンキング]
馬場康誌(『空手小公子』シリーズ)
とにかくかわいい『はたらく細胞』スピンオフ
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子(TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
2話同時掲載の学園ラブコメ
[ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話]
横田卓馬
(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』
『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
大人気ハイ・ファンタジー
[ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人]
原作:加茂セイ(講談社レジェンドノベルス/刊)
漫画:刀坂アキラ
キャラクター原案:布施龍太
男装の麗人☆スパイアクション
[川島芳子は男になりたい]
田中ほさな (『乱飛乱外』)
瞠目のエキゾチック・タクティクス
[将国のアルタイル]
カトウコトノ
驚愕の“悪魔憑き”バトル
[レイジング・ヘル]
荒木 光(『僕たちがやりました』)
『ゼロから始める魔法の書』新シリーズ
[魔法使い黎明期]
原作:虎走かける
漫画:タツヲ
キャラクター原案:いわさきたかし
連載100回を超えてますます人気!!
[妖怪アパートの幽雅な日常]
原作:香月日輪
漫画:深山和香
★第45回「シリウス新人賞」大賞作品、[前編]掲載★
☆「シリウス」6月号、4月25日(土)発売☆★[ヒプノシスマイク]かけ替えカバー付録つき!!★
★光永康則W連載!! 最新巻がW発売!!★
【異世界×怪物★W単行本5月8日(金)発売!!】
待望の第(2)巻 発売直前!!
本格異世界ファンタジー
[時間停止勇者]
光永康則
最新 第(6)巻 発売直前!!
大人気ダークファンタジー
[怪物王女 ナイトメア]
光永康則
【ヤスダスズヒトもW連載中!!】
ご存知★大人気連載
[夜桜四重奏(ヨザクラカルテット)]
ヤスダスズヒト
NEO異能力バトル★シリーズ連載
[ブーツレグ]
ヤスダスズヒト
【コミックス第(3)巻発売記念★かけ替えカバー付録】
[ヒプノシスマイクーDivision Rap Battle- side B.B & M.T.C]
原作:EVIL LINE RECORDS
漫画:蟹江鉄史
シナリオ:百瀬祐一郎
【最新(2)巻★発売記念★センターカラー】
大人気 異世界ファンタジー
[異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。]
遠山えま(『わたしに××しなさい!』)
【最新巻ともに5月8日発売!!】
熱望の第(2)巻 発売直前!!
圧巻のスケールで描く近未来SFロボットバトル
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
待望の第(6)巻 発売直前!!
新・王道ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉 (『シドニアの騎士』『BLAME!』)
【『転スラ』本編&スピンオフも大人気連載中】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件] 漫画:川上泰樹
累計50万部突破!!
アニメ化決定のスピンオフ4コマ!!
[転スラ日記 転生したらスライムだった件]漫画:柴
ブラック企業スピンオフ4コマ★最終回!!
[転生しても社畜だった件]漫画:明地 雫
幼児化スピンオフ4コマ!!
[転ちゅら!転生したらスライムだった件]漫画:茶々
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜] 漫画:戸野タエ
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大ヒット小説コミカライズ★新連載 第2回】
夫婦同心★江戸の町で大活躍!!
[うちの旦那が甘ちゃんで]
漫画:雷蔵
原作

- 月刊 少年シリウス 2020年 07月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥779
- 2020年05月26日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
☆「シリウス」7月号、5月26日(火)発売☆
★創刊15周年記念号!!★
★[転スラ]ARリムル公開&プレゼント企画つき★
【最新第6巻 発売記念★巻頭カラー】
新・王道ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉 (『シドニアの騎士』『BLAME!』)
【シリウス創刊15周年Anniversary企画】
スマホをかざしてリムルを召喚(=ダウンロード)!
[転スラ]AR(=拡張現実)リムル、公開中!!
特製QUOカードを150名様にプレゼント!!!
【最新コミックス発売直前★2タイトル】
最新第3巻★発売直前★センターカラー
☆毎号2話掲載のショートラブコメ☆
[ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話]
横田卓馬
(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』
『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
最新第2巻★発売直前★センターカラー
☆血小板ちゃんのとにかくかわいい日常系ショート☆
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子(TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
【最新第2巻★発売ホヤホヤ★2タイトル】
最新第2巻 発売中!!
本格異世界ファンタジー
[時間停止勇者]
光永康則(『怪物王女』)
最新第2巻 発売中!!
近未来SFロボットバトル
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
【『転スラ』本編&スピンオフも大人気連載中】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件] 漫画:川上泰樹
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜] 漫画:戸野タエ
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大人気★連載陣】
最新第5巻 大人気発売中
叛逆ずべ公アクション★隔号連載
[べアゲルター]
沙村広明(『波よ聞いてくれ』『無限の住人』)
大人気 異世界ファンタジー
[異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。]
遠山えま(『わたしに××しなさい!』)
ご存知★大人気連載
[夜桜四重奏(ヨザクラカルテット)]
ヤスダスズヒト
超格闘★異世界ドラマ
[ライドンキング]
馬場康誌(『空手小公子』シリーズ)
爆裂★異世界活劇
[爆宴 BAKUEN]
原作:イダタツヒコ
漫画:士貴智志(『進撃の巨人 Before the fall』)
『XBLADE(クロスブレイド)』のタッグ、再臨!!
夫婦同心★江戸の町で大活躍
[うちの旦那が甘ちゃんで]
漫画:雷蔵
原作:神楽坂 淳(講談社文庫/刊)
大人気★ハイ・ファンタジー
[ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人]
原作:加茂セイ(講談社レジェンドノベルス/刊)
漫画:刀坂アキラ
キャラクター原案:布施龍太
男装の麗人★スパイアクション
[川島芳子は男になりたい]
田中ほさな (『乱飛乱外』)
可愛さ余って禁断領域★ハートフル転生コメディー
[小学生がママでもいいですか?]
ぢたま某(『kiss×sis』)
『ゼロから始める魔法の書』新シリーズ★
[魔法使い黎明期]
原作:虎走かける
漫画:タツヲ
キャラクター原案:いわさきたかし
連載100回を超えて★ますます人気
[妖怪アパートの幽雅な日常]
原作:香月日輪
漫画:深山和香
★第45回「シリウス新人賞」大賞作品、[後編]掲載★
☆「シリウス」7月号、5月26日(火)発売☆
ジン★創刊15周年記念号!!★
★[転スラ]ARリムル公開&プレゼント企画つき★
【最新第(6)巻 発売記念★巻頭カラー】
新・王道ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉 (『シドニアの騎士』『BLAME!』)
【シリウス創刊15周年Anniversary企画】
スマホをかざしてリムルを召喚(=ダウンロード)!
[転スラ]AR(=拡張現実)リムル、公開中!!
特製QUOカードを150名様にプレゼント!!!
【最新コミックス発売直前★2タイトル】
最新第(3)巻★発売直前★センターカラー
☆毎号2話掲載のショートラブコメ☆
[ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話]
横田卓馬
(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』
『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
最新第(2)巻★発売直前★センターカラー
☆血小板ちゃんのとにかくかわいい日常系ショート☆
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子(TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
【最新第(2)巻★発売ホヤホヤ★2タイトル】
最新第(2)巻 発売中!!
本格異世界ファンタジー
[時間停止勇者]
光永康則(『怪物王女』)
最新第(2)巻 発売中!!
近未来SFロボットバトル
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
【『転スラ』本編&スピンオフも大人気連載中】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件] 漫画:川上泰樹
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜] 漫画:戸野タエ
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大人気★連載陣】
最新第(5)巻 大人気発売中
叛逆ずべ公アクション★隔号連載
[べアゲルター]
沙村広明(『波よ聞いてくれ』『無限の住人』)
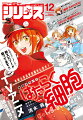
- 月刊 少年シリウス 2020年 12月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥779
- 2020年10月26日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
☆「シリウス」12月号、10月26日(月)発売☆
★㊗︎創刊15周年〜来年の16周年につづく!!!★
★本家☆本元=清水茜が描く『はたらく細胞』
超待望の新エピソードが・・・遂に!! 掲載★
【TVアニメ第2期2021年1月放送開始】
巻頭カラー!!
☆元祖・体内細胞 擬人化漫画☆
[はたらく細胞]
清水 茜
【新連載&スピンオフ★『細胞』ワールド】
センターカラー新連載!!
☆はたらく“白血球さん”スピンオフ☆
[はたらく細胞 WHITE]
漫画:蟹江鉄史
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
☆血小板ちゃんの とにかく かわいい日常系ショート☆
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子 (TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
☆赤芽球たちの うだうだ日常☆
[はたらかない細胞]
漫画:杉本 萌
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
【新章突入☆センターカラー】
爆裂の異世界★活劇!!
[爆宴 BAKUEN]
原作:イダ タツヒコ
漫画:士貴智志(『進撃の巨人Before the fall』)
【TVアニメ化情報も満載!!】
[転生したらスライムだった件] [転スラ日記]
[はたらく細胞] [怪病医ラムネ]
[異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術] etc...........
【禁断領域コメディ★感動の最終回】
最終巻は12/4『Kiss×sis』と同時発売!!
[小学生がママでもいいですか?]
ぢたま某
【シリーズ累計部数★2,000万部突破!!】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件]
原作:伏瀬
漫画:川上泰樹
キャラクター原案:みっつばー
【『転スラ』スピンオフも大人気連載中】
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜]
漫画:戸野タエ
幼児化スピンオフ4コマ!!
[転ちゅら! 転生したらスライムだった件]
漫画:茶々
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大人気★連載陣】
新・王道★ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉(『シドニアの騎士』『BLAME!』)
シリウス最長★看板連載!!
[夜桜四重奏(ヨザクラカルテット)]
ヤスダスズヒト
高校生活★ショートラブコメ
[ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話]
横田卓馬(『背すじをピン!と〜鹿高競技ダンス部へようこそ〜』
『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』)
本格★異世界ファンタジー
[時間停止勇者]
光永康則(『怪物王女』)
夫婦同心★江戸の町で大活躍
[うちの旦那が甘ちゃんで]
漫画:雷蔵
原作:神楽坂 淳(講談社文庫/刊)
超格闘★異世界ドラマ
[ライドンキング]
馬場康誌(『空手小公子』シリーズ)
近未来★SFロボットバトル
[無号のシュネルギア]
高田裕三(『3×3EYES(サザンアイズ)』)
驚愕の“悪魔憑き”★バトル
[レイジング・ヘル]
荒木 光(『僕たちがやりました』)
瞠目の★エキゾチック・タクティクス
[将国のアルタイル]
カトウコトノ
大人気★異世界ファンタジー
[異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。]
遠山えま(『わたしに××しなさい!』)
男装の麗人★スパイアクション
[川島芳子は男になりたい]
田中ほさな (『乱飛乱外』『聖骸の魔女』)
大人気★ハイ・ファンタジー
[ダンジョン・シェルパ 迷宮道先案内人]
原作:加茂セイ(講談社レジェンドノベルス/刊)
漫画:刀坂アキラ
キャラクター原案:布施龍太
『ゼロから始める魔法の書』★新シリーズ
[魔法使い黎明期]
原作:虎走かける (『ゼロから始める魔法の書』)
漫画:タツヲ (『マクロスΔ』)
キャラクター原案:いわさきたかし
連載100回を超えて★ますます人気
[妖怪アパートの幽雅な日常]
原作:香月日輪
漫画:深山和香
【“ツイシリ”より出張掲載★新人ショート読み切り】
[素直になれない猫は転校生と仲良くなりたい]
松もくば
[うちの生徒会長は完璧(?)だ ]
島 知宏
☆「シリウス」12月号、10月26日(月)発売☆★〓〓創刊15周年〜来年の16周年につづく!!!★
★本家☆本元=清水茜が描く『はたらく細胞』
超待望の新エピソードが・・・遂に!! 掲載★
【TVアニメ第2期2021年1月放送開始】
巻頭カラー!!
☆元祖・体内細胞 擬人化漫画☆
[はたらく細胞]
清水 茜
【新連載&スピンオフ★『細胞』ワールド】
センターカラー新連載!!
☆はたらく“白血球さん”スピンオフ☆
[はたらく細胞 WHITE]
漫画:蟹江鉄史
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
☆血小板ちゃんの とにかく かわいい日常系ショート☆
[はたらく血小板ちゃん]
原作:柿原優子 (TVアニメ『はたらく細胞』脚本)
漫画:ヤス (『とらドラ!』『じょしらく』)
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
☆赤芽球たちの うだうだ日常☆
[はたらかない細胞]
漫画:杉本 萌
監修:清水 茜 (『はたらく細胞』)
【新章突入☆センターカラー】
爆裂の異世界★活劇!!
[爆宴 BAKUEN]
原作:イダ タツヒコ
漫画:士貴智志(『進撃の巨人Before the fall』)
【TVアニメ化情報も満載!!】
[転生したらスライムだった件] [転スラ日記]
[はたらく細胞] [怪病医ラムネ]
[異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術] etc...........
【禁断領域コメディ★感動の最終回】
最終巻は12/4『Kiss×sis』と同時発売!!
[小学生がママでもいいですか?]
ぢたま某
【シリーズ累計部数★2,000万部突破!!】
メガヒット本編(メインストーリー)!!
[転生したらスライムだった件]
原作:伏瀬
漫画:川上泰樹
キャラクター原案:みっつばー
【『転スラ』スピンオフも大人気連載中】
ケモミミ娘の[転スラ]外伝!!
[転生したらスライムだった件 異聞 〜魔国暮らしのトリニティ〜]
漫画:戸野タエ
幼児化スピンオフ4コマ!!
[転ちゅら! 転生したらスライムだった件]
漫画:茶々
原作:伏瀬 キャラクター原案:みっつばー
【大人気★連載陣】
新・王道★ダークファンタジー
[人形の国]
弐瓶 勉(『シドニアの騎士』『BLAME!』)
シリウス最長★看板連載!!
[夜桜四重奏(ヨザクラカル

- なかよし 2023年 4月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥660
- 2023年03月03日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
なかよし4月号は、3月3日(金)発売!
表紙を飾る作品は『カードキャプターさくら クリアカード編』(CLAMP)。
4/1がお誕生日のさくらちゃんが登場!!
■ふろく:『カードキャプターさくら クリアカード編』
〜ずっといっしょだよ〜 メモリアルプレート2枚組
「なかよし」だけのプレミアムデザイン!
さくらちゃんと小狼君の名シーンに感動&胸きゅん。
二人が向かい合うカラーイラストもとってもステキ!
並べて飾りたくなっちゃう2枚組のプレート、ぜひお見逃しなく☆
■遠山えまスペシャル2本立て!
シーズン2も超大人気!!
男装女子と溺愛吸血鬼のキケンなラブ『ヴァンパイア男子寮』最新話掲載。
花嫁失格になってしまった美人は、吸血鬼の国から亜人の集まる男子校に転校!?
さらに、いま大注目の異世界ラブ『魔女メイドは女王の秘密を知っている。』も同時掲載!
どうぞおたのしみに♪
荒牧慶彦さんスペシャルインタビュー掲載+両面ピンナップふろくも☆
新学期に向けてハッピーチャージしていこう!!

- 婦人画報 2023年 12月号 [雑誌]
- ハースト婦人画報社
- ¥1300
- 2023年11月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
1
●冬の北海道へ
プレミアムな3泊4日
例年11月ごろになると、初雪の声が
聞かれるという、日本最北の地・北海道。
12月になるとほぼ全域に雪が降り、
心洗われる白銀の世界を見せてくれます。
そんな北海道で出合うことができる、
圧倒的な大自然の冬景色や土地の恵み、
そして、心も体も温まるおもてなし。
今回は、リゾートとして進化するニセコ・余市、
手つかずの自然が残されている道東、
冬季は雪まつりでひときわにぎわう札幌、
この3つのエリアを取り上げました。
3泊4日のとっておきのプランをご参考に、
忘れられない思い出をぜひ作ってみませんか?
2
●年末年始のパーティレシピ 手早くおいしく、おもてなし
今年の年末年始は久しぶりにパーティを
計画中という人も多いのではないでしょうか。
至れり尽くせりのおもてなしもさることながら、
思い立ったらすぐ集合、ホストもゲストも気負いなし、
という気軽な集いが近ごろのムードです。
手早くできるけれどきちんとおいしい。いまの
時代にフィットした“これからのもてなし料理”を、
人気料理家の皆さんに提案していただきました。
3
●ポーランド、祈りのクリスマス
ヨーロッパの中央に位置する
ポーランドは、ローマカトリック教徒が
人口の9割以上を占める
敬虔なキリスト教国です。
長い歴史のなかで多くの苦難を
経験しながらも、前向きに、たおやかに
生きる人々の強さの根底には、
常にローマカトリックの教えがありました。
しかしながら、プロテスタントや
ロシア正教、イスラム教、
ユダヤ教、仏教……
さまざまな少数の宗教もまた、
排除し合うことなく共存しています。
異なる信仰や民族に対する
この国の「寛容さ」は
いま全人類が倣うべき尊い精神。
そんなポーランドで毎年祝う伝統的な
クリスマスの習慣をご紹介します。
4
●婦人画報 Jewelry 宝飾遺産
「地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれ、
そして私たちが未来の世代に引き継いでいくべきかけがえのない宝物*1」。
「世界遺産」の定義は、果てしない時間が育んだ宝石と類いまれなる
クリエイティビティが融合した、ハイジュエリーの描写に最もふさわしいものでした。
きらびやかな輝きには、継承すべき歴史や技が秘められているのです。
この時代で私たちが享受すべき、その価値と物語をご紹介します。
*1公益社団法人日本ユネスコ協会連盟ウェブサイトより引用
5
●首と手、究極のお手入れ
読者の皆さまへの取材によると、年齢による首と手の
変化を気にしている人が多いことがわかりました。
しかもいずれかではなく、“年齢の表れやすい首と手”を
“ともにケアしたい”と感じている人が多いのです。
今月は“首と手”に年齢が表れやすい理由を繙きながら、
そのお手入れの方法をセットでご紹介します。
きものなど、年末年始の装いでも目立つところですから、
いまの時季から“究極のお手入れ”を始めましょう。
6
●いくつになっても、凛とした立ち姿で一生、美姿勢!
同じように歳を重ねていくのに
“しゃんと”背筋の伸びた人と
そうでない人がいる。
その違いはどこにあるのでしょうか。
その理由を知りたいと、現役の弓道家・
佐竹万里子さんを訪ねました。
歳を重ねても自分の「芯」を
しっかりと維持するために、
いまから私たちにできることとは──。
7
●柚希礼音×真風涼帆 新たな関係
ふたりの黒燕尾服姿のポスターが発表されたとき、宝塚歌劇ファンは誰しも
意表を突かれ、驚くと同時に、期待を大にしたのではないでしょうか。
『LUPIN 〜カリオストロ伯爵夫人の秘密〜』で、
男装の麗人・カリオストロ伯爵夫人役を宝塚歌劇団元星組トップ柚希礼音さん、
元宙組トップ真風涼帆さんがダブルキャストで務めます。
柚希さんの教えを糧に花開いていった真風さんの、退団後初の舞台。
師弟関係ともいえるふたりの特別な絆がこの舞台で見せる、華麗なる駆け引きとは?
8
●建築家の自邸を訪問 歴史を住み継ぐ
空間設計のプロフェッショナルが、自身と家族のために
デザインし、暮らす家。そこで重ねる時間は、
彼らの価値観に影響を与える、かけがえのないもの。
長く住み継ぐことで自身と向き合ってきた
3人の建築家の実例を紹介します。

- 月刊 TVガイド北海道版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- 月刊 TVガイド福岡佐賀大分版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- なかよし 2022年 05月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥650
- 2022年04月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
豪華付録つきでたのしめる小中学女子向まんがなかよし5月号は4月1日(金)発売!!
表紙は『カードキャプターさくら クリアカード編』(CLAMP)♪
発売日はさくらちゃんのバースデー♪
当日は単行本12巻で、さくらちゃん祭り!
ふろくは『カードキャプターさくら』連載25周年記念ふろく★第6弾
アニバーサリー・トートバッグ!
タテ340mm×ヨコ370mm×マチ100mmのうれしい超BIGサイズ♪
表面はさくらちゃんたちのイラストが華やかでとってもキュート!
裏面はグラデーションカラーで、封印の杖・星の杖・夢の杖が散りばめられたオシャレなデザイン♪
両面で使える2WAY☆
4月1日(金)『カードキャプターさくら クリアカード編』単行本12巻発売!
特装版は、BIGアートトランプ&ブック型ケース付き。
『カードキャプターさくら』『カードキャプターさくら クリアカード編』の美麗イラストが大きめトランプになって登場! あまりの豪華さに感動&見惚れてしまいます…!
しかもジョーカーのうち1点は、豪華描きおろし「ジョーカーさくらちゃん」♪
絶対手に入れたいスペシャルな特装版☆
『カードキャプターさくら』連載25周年記念
複製原画第2弾(さくらちゃん&小狼君)も4月1日より発売!!
(「さくら25周年特設サイト」http://ccsakura-official.com/25th/)
センターカラー
◆『どうせ、恋してしまうんだ。』満井春香
まぶしい青春に、ファン続出中! コミックス第4巻4月13日(水)発売
◆『ヴァンパイア男子寮』遠山えま
男装女子×溺愛吸血鬼のキケンなLOVE、盛り上がり最高潮! コミックス第9巻大好評発売中!
最終回
◆『かみつかないで、キスしてよ』夏園豪華
ついに最終回、二人の恋のゆくえはーー? コミックス第2巻4月13日(水)発売
注目記事
◆TVドラマ『金田一少年の事件簿』放送記念!
なにわ男子 道枝駿佑さんグラビア&インタビュー
(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社

- 月刊 TVガイド関西版 2019年 09月号 [雑誌]
- 東京ニュース通信社
- ¥397
- 2019年07月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
巻頭&巻末 嵐 PHOTO BOOK
嵐
●「24時間テレビ42 愛は地球を救う『人と人 〜ともに新たな時代へ〜』」SPグラビア&トーク
●「2020スタジアム」SPグラビア&トーク
●「嵐のワクワク学校〜」超リポート
●「24時間テレビ」完全ガイド
●嵐SP NEWS 「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」&「号泣甲子園」SPトーク、「VS嵐」、「嵐にしやがれ」、「ニノさん」密着リポート
センター BOOK in BOOK
ジャニーズJr.写真集
●関西ジャニーズJr.(西畑大吾&大西流星&西村拓哉&大西風雅&福本大晴&佐野晶哉)関西ジャニーズJr. 3ユニット奇跡のシャッフルグラビア
●山本亮太&原嘉孝 舞台「桃山ビート・トライブ〜」SPリポート
●岩本照&ラウール&渡辺翔太&目黒蓮 「簡単なお仕事です。に応募してみた」SPグラビア&トーク
●Travis Japan 「虎者ーNINJAPAN-」SPグラビア&トーク
特集1
20th Century(坂本昌行&長野博&井ノ原快彦)
●「舞台「〜カノトイハナサガモノラ」SPグラビア&トーク
特集2
高橋優斗&猪狩蒼弥&作間龍斗&岩崎大昇&佐藤龍我&中村嶺亜&織山尚大&正門良規&濱田崇裕
●「恋の病と野郎組」SPグラビア
特集3
岸優太&神宮寺勇太
●舞台「DREAM BOYS」SPグラビア&トーク
特集4
高山一実
●乃木坂46連載スタート!記念グラビア&インタビュー
特集5
夏ドラマ先どりストーリー〓
特集6
日付順番組ガイド 7.27→9.1
●「KinKi Kidsのブンブブーン」「炎の体育会TVSP」etc.
特集7
声優グラビア第40弾
●岡本信彦「奇跡の軌跡」
●内田雄馬「HORIZON」
特集8
CLOSE UP PEOPLE!
●植田圭輔 TVアニメ&舞台「pet」SPグラビア&インタビュー
特集9
祭nine.
●2ndフォトブック「祭男子2」発売記念 SPグラビア&トーク
特集10
ael-アエルー
●ロックな男装ユニットが誕生!SPグラビア&トーク
特集11
ザ少年倶楽部
●中島健人&A.B.C-Z&King & Prince etc.
特集12
山田涼介
●「セミオトコ」SPグラビア&インタビュー

- Audition (オーディション) 2016年 07月号 [雑誌]
- 白夜書房
- ¥662
- 2016年06月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
芸能界に直結したオーディション情報誌【表紙】第1回ミス美しい20代コンテスト開催中!
武井咲
【内容】
▼特集
★サイン入りポラプレほかプレゼント増量!
アイドルのお仕事の現場をのぞきました!
あこがれアイドル 大接近
ライブ●はちみつロケット(3B junior)/ラジオ●ももいろクローバーZ/
テレビバラエティ●欅坂46・乃木坂46/チーム4公演●AKB48/
原宿駅前パーティーズ公演●原駅ステージA/
秋葉原ディアステージ(ショップ)紹介●妄想キャリブレーション
★自分なりのやり方で“ワタシ”アピール!
オリジナルな方法で有名になる大作戦
山賀琴子/ゆうたろう/TAKASHI&ぎこちゃん/もえのあずき
★ガールズオーデ☆NEWS
けやき坂46(ひらがなけやき)の新メンバー決定!
▼オーディション情報
★旬のオーディションをお届け!
Pick UP!!Audition
★あのオスカーが特に「20代」を募集!
第1回ミス美しい20代コンテスト
★ソニー・ミュージックアーティスツがアニメ大好きな人大ぼしゅう!
アニストテレス
★スタダが“女優”に特化した初オーデ!
スターダストプロモーション 芸能1部第1回女優オーディション
★Auditionオリジナルコラボオーデ
斎藤工所属「ブルーベアハウス」
▼編集部の推しオーデ
★キャスターを目指す人必見! 第29期 圭三塾生 募集
★AbemaTV FRESH ! に出演 原宿FRESHガールズ募集
★芸能界唯一無二の男装ユニット 風男塾 新メンバーオーディション
★テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」で大人気★
Candy Boy新メンバー募集オーディション
★本格的・チアユニット!
原宿CHEERRIBBONS(チアリボンズ)メンバーオーディション
★生瀬勝久・古田新太が所属のリコモーションが主催!
NEXTEEN 第7期生オーディション
その他、オーディション情報多数掲載!
▼インタビュー企画
★舞台「Magician達のリファンタジ〜」主演
『Elements』File28 川口春奈
★special interview
「はじまり。」第29回 斎藤工
山本美月&玉城ティナ
BOYS AND MEN
村井良太
横山由依(AKB48)
藤原さくら
藤野涼子
花田優里音

- なかよし 2019年 04月号 [雑誌]
- 講談社
- ¥590
- 2019年03月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
豪華付録つきでたのしめる小中学女子向まんが4月号のふろくは「最強☆青春6大ふろく パシャっと!友活セット」!!
新学期に! クラスがえに! 卒業に!
友活のマストアイテムがこんなにおしゃれになった〜!
(1)春色カメラ〓ケース
プリクラ、お手紙…思い出ぜ〜んぶ持ちはこぼう!!
(2)SNS風☆フォトジェニックメモ
プリやチェキを貼って友情度UP☆
(3)わかメンフレームメモ
大人気れんさいコラボ♪
(4)わんころべえ黒板メモ
色えんぴつで黒板アート風!
(5)なかよし公式!仲良届
友だちとも〜っと“なかよし”になれちゃう☆
(6)おみくじシャープペン
きゃらマキ先生のスペシャルかきおろしイラスト!
表紙は、超盛り上がり! 男装女子×溺愛ヴァンパイア、キケンな同居生活★
『ヴァンパイア男子寮』遠山えま!!
新シリーズ、れんさいスタート! 読めばゼッタイ恋したくなる★共感度No.1よみきりシリーズ
『この恋、叶いますか? -君のためのコスモスー』雨宮うり
Twitterで大人気作家、なかよし初登場☆
巻頭カラーで登場☆ 圧倒的人気No.1!
『カードキャプターさくら クリアカード編』CLAMP
新展開も見逃せない!!!
サンリオコラボや、新学期モテデビュー記事、話題の人物のABC英会話連載などなど、
超トキメキ特集てんこもり〜!!
あなたの春はなかよしにお任せあれ★サクラ咲く新学期応援号!!
「なかよし」4月号は、3月1日(金)発売☆

- 男装したら数日でバレて、国王陛下に溺愛されています
- 若菜モモ
- スターツ出版
- ¥715
- 2018年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
密かに男装し、強国の若き国王クロードの侍従になった村娘ミシェル。バレないよう距離を置いて仕事に徹するつもりが、彼はなぜか毎朝彼女をベッドに引き込んだり、豪勢な食事を振る舞ったり、政務の合間に強く抱きしめたりと、過剰な寵愛ぶりで翻弄してくる。「お前に触れずにはいられない」と、クールな彼からは想像できないほど甘く囁かれ、ミシェルは戸惑うも恋心が深まってしまい…!?