インターネット の検索結果 標準 順 約 2000 件中 361 から 380 件目(100 頁中 19 頁目) 

- 日本型インダストリー4.0
- 長島聡
- 日経BPM(日本経済新聞出版本部)
- ¥1870
- 2015年10月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(4)

- インターネット的
- 糸井重里
- PHP研究所
- ¥792
- 2014年11月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(53)
どうやら、十年以上経って話題になっているらしい。じぶんで言うのもおかしいですが、読んだ方によれば「いまの時代が予見されている」そうです。「ぜんぶ、ここに書いてるじゃないか」なんていう声もいただきました。--糸井重里▼本書は、発刊から十年を経て、「まるで、予言の書!」と再評価の声が高まっている名著に、書き下ろしの「続・インターネット的」を加筆し、文庫化したものである。もとは、『ほぼ日刊イトイ新聞』を始めた当時の著者が、インターネット登場後の世界について考察したものだが、読む者は、ここ十年間に起きた変化の本質を、十年前のこの本によって知ることになるだろう。▼また本書で綴られる言葉は、パソコンすらいらない、「消費者」なんていない、自分を他人にするゲーム、寝返り理論、消費のクリエイティブ、妥協の素晴らしさ……など、普遍的価値を持つ。糸井重里の予言的、そして普遍的なメッセージが詰まった一冊である。

- インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式
- 神田知宏
- 日本加除出版
- ¥3300
- 2021年04月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
スムーズな削除請求・発信者情報開示請求のために。どのように行動すればよいか、端的に分かりやすい構成立て。どこに何が書かれているのか分かりやすい見開き完結スタイル。削除請求・発信者情報開示請求で使う書式や資料が充実。すぐに実務で使える!!資料にもログ保存期間一覧、接続先IPアドレス一覧など実務に役に立つ情報が多数収録!

- マネ-進化論
- 佐藤節也
- シグマベイスキヤピタル
- ¥2200
- 1999年11月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
電子マネーがグローバル・ネットワーク社会に何をもたらすか。次世代に課せられたテーマは、リアルな世界とデジタルな世界とをどうリンクするか、である。
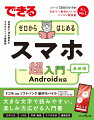
- できるゼロからはじめるスマホ超入門 Android対応 最新版
- 法林岳之/清水理史/できるシリーズ編集部
- インプレス
- ¥1408
- 2023年07月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
大きな文字で読みやすい、楽しみ方広がる入門書。文字入力、LINE、写真・動画、スマホ決済、機種変更。

- インターネットで文献探索 2019年版
- 伊藤 民雄
- 日本図書館協会
- ¥1980
- 2019年05月23日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2016年版から3年,インターネットの世界は日々変貌しています。そこで今回,本書では,2019年2月現在の文献・情報検索サイト情報を記録しました。
図書,雑誌,新聞,視聴覚資料とそれらの記事・論文等について,検索に有効なサイトとデータベースで,検索については無料のものを収録の原則としています。特に,スマートフォンによる文献探索についてコラムで紹介し,さらに利便性を高めています。
図書館での利用者支援のツールとしてはもちろん,インターネットの大海に漕ぎ出す一般の方々にも役立つ一冊です。

- インターネット社会を生きるための情報倫理 改訂版
- 情報教育学研究会・情報倫理教育研究グループ
- 実教出版
- ¥495
- 2018年03月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
情報社会のしくみや特徴、インターネットの利用に必要なルールやモラルについて解説。巻末には、重要用語の解説など、参考となる資料を掲載。

- RFワールド No.55 製作による無線・高周波の実践体験3
- トランジスタ技術編集部
- CQ出版
- ¥2200
- 2021年12月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ネット通販の普及により,高性能な量産部品やICなどを手軽に安価に入手できるようになりました.自作は趣味に留まりません.研究や実験/試作の治具などは,内製するほうが短時間で安価に目的を達成できます.便利な環境が整った今こそチャンスでしょう.
目次
● クローズアップRFワールド
★ 特集
◎ インターネットとPCを活用する少量製作/試作テクノウ公開
☆ 製作による無線・高周波の実践体験3
● イントロダクション 製作による無線・高周波の実践体験III
◎ 低価格RF製品の作り,SMDな電子部品,電子工作用工具,海外通販の利用
● 第1章 部品や工具とそれらの調達
◎ トラブル解決に関する一連の流れ
● Appendix 海外通販のトラブルについて
◎ スペアナ/ネットアナ,SG,アッテネータなど,tinySAやSDR受信機の実力チェック
● 第2章 揃えておきたいRF測定機器と今どきの測定機器
◎ 簡単な回路の組み立て配線法,手がきプリント基板,基板CADによるパターン設計
● 第3章 製作の流れと基板の作り方
◎ 面実装部品を半田ごてで実装する基本テクニック
● Appendix SMDを手で半田付けする方法
◎ 基板製造メーカの比較,オーダ方法,体験した不具合やトラブル
● 第4章 海外の基板メーカへ発注する
◎ 自分でプリント基板を複数枚作るときに役立つ
● 第5章 基板にパターンを転写する方法
◎ ヨルダン王国で指導したサバイバル的修理方法やプリント基板の手作り術
● Appendix 途上国で教えたプリント基板製作
◎ 加工の実際,銅張基板ケース,アクリル板利用,3Dプリンタ活用,ケースやパネル工作のアイデア集
● 第6章 ケース加工と製作
◎ 開発環境のセットアップとPLL発振器の試作
● 第7章 ArduinoとI 2Cを覚えよう
★ 特設記事
◎ RF応用の現場から:超高層ビル建設現場のICTを支える無線LANシステム
● ビル建設現場へ広がる 導波管の新応用
◎ 100GHzで0.5dB/km!
● Appendix 半世紀超えのRFヘリテージ「円形導波管」
★ 技術解説
◎ 0.1 MHz〜960 MHzのスペアナと信号発生器を内蔵したNanoVNA派生機
● 簡易スペアナ“tinySA”の試用&評価記
● 前編 動作のしくみとスペアナ性能の評価
◎ 図を使って手軽にLC値を求めよう
● インピーダンス整合設計の早見チャート
◎ 数十Gbpsを伝送する高解像ディスプレイのI/O
● ディスプレイ系高速シリアル・インターフェース
● 後編 ディスプレイ内部,放送機器,モバイル機器用
★ 一般解説
◎ ソレノイド・コイルからワンターン・コイルまで対応
● 長岡係数の近似計算式
◎ “Microwave Engineering”の分厚い翻訳書が登場!
● 「マイクロ波工学(第4版)」の翻訳者に聞く
★ 歴史読物
◎ 漁業用船舶無線と私設海岸局にまつわる栄枯盛衰
● 日本水産における漁業用無線通信の系譜
● 第3回 海岸局の短波化,戦中のトロール事業,そして戦後復興
● Appendix 電気技術史に関する論文とその要約
★ 折り込み付録
● 無線LANの周波数チャネル一覧チャート
● 無線と高周波の便利メモ

- ネットワークセキュリティ
- 高橋 修/関 良明/河辺 義信/西垣 正勝/岡崎 直宣/岡崎 美蘭
- 共立出版
- ¥3080
- 2017年09月21日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
我々がインターネットを利用する上で,守るべき資源(コンピュータ,ネットワーク,データ,等),これらの資源に対する脅威,脅威から資源を守る技術とその限界を含めたネットワークセキュリティを学ぶことは今後IoTを含む情報システムの研究・開発・実用化を行う上で必須になっている。
本書は,線形代数学,情報ネットワーク,アルゴリズムとデータ構造,オペレーティングシステムに関する基本的な知識を有する情報系学科/コースの3年生を想定して,ネットワークセキュリティを体系的に学習する事を前提に,技術要素,実システム,関係する法律などに関して具体的な事例を取り上げながら解説している入門書である。

- Windows 10セミナーテキスト 第3版
- 土岐 順子
- 日経BP
- ¥1870
- 2020年10月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
Windows 10を初めて使用される方が、起動と終了、文字の入力、ファイルとフォルダーの管理などの基本操作に加え、アプリケーションの使い方、ユーザーアカウントやパスワードの管理、インターネットや周辺機器を利用するための操作などを、実習しながら学習できるテキストです。「May 2020 Update」および新しいMicrosoft Edgeに対応しています。
ワードパッドやペイントなどの基本的なアプリケーションの使い方、インターネットの活用、写真の取り込みと編集など、パソコンを快適に使うためのさまざまな機能をわかりやすく説明しているので、楽しくパソコンが使えるようになります。
第1章 Windows 10の基本操作
Windows 10とはこんなソフト
Windows 10を起動するには
デスクトップ画面について
[スタート]メニューについて
アプリを起動するには
ウィンドウの各部の名称と役割について
ウィンドウを操作するには
Windows 10を終了するには
第2章 アプリの基本操作
文字を入力するには
ワードパッドで文書を作成するには
ペイントで絵を描くには
第3章 ファイルの管理
ファイルとフォルダーについて
エクスプローラーについて
コンピューターの構成について
フォルダーウィンドウの基本操作
ファイルやフォルダーの基本操作
ファイルやフォルダーを探すには
第4章 Windows 10の設定の変更
Windows 10の設定を変更するには
画面のデザインを変更するには
[スタート]メニューにアプリを登録するには
ユーザーアカウントを管理するには
第5章 インターネットの利用
インターネットとは
Webページを見るには
よく見るWebページを登録するには
Webページを印刷するには
安全にWebページを見るには
電子メールを利用するには
第6章 周辺機器の接続
USBメモリを利用するには
写真を取り込むには
総合問題
索引

- NTTコミュニケーションズインターネット検定.com Master ADVANC第3版
- NTTコミュニケーションズ
- NTTコミュニケーションズ
- ¥3740
- 2019年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 仮想通貨リップルの衝撃
- 四條寿彦
- 天夢人
- ¥896
- 2018年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)

- スピードマスター 1時間でわかる ネット広告 超入門
- AOI.コミュニケーションズ 古舘拡美
- 技術評論社
- ¥1100
- 2020年01月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
テレビや新聞といったマスメディアが圧倒的だった頃と比べ、最近ではインターネットで情報をチェックする人も増えてきました。そこで、活躍するのがインターネット上の広告です。ネット広告は、従来のマスメディアへの広告よりも、低予算から、かつ柔軟に広告を出すことが可能です。インターネットの仕組みを使えば、自社のターゲットとする顧客層にも、より効果的にリーチすることができます。本書では、「ネット広告を出してみたいけれどよくわからない!」という方を対象に、ネット広告の基礎知識や広告の種類、さらに効果的な出稿のポイントなどを解説しました。ネット広告に取り組む際のはじめの1冊として、おすすめです!
1章 ネット広告の基本
01 インターネットに広告を出すことのメリット
02 ネット広告が配信されるしくみ
03 ネットに広告を出すために必要なもの
04 広告を出す目的をはっきりさせる
05 ターゲット設定によって適切な広告は変わる
06 目的とターゲットから選ぶネット広告の例
コラム スマートフォンでの広告
2章 ネット広告の種類
07 ネット広告には様々な種類がある
08 購買意欲高めのターゲットに訴求するならリスティング広告
09 「見てもらいたい」ターゲットに確実に届くアドネットワーク広告
10 高精度なターゲティングと若年層への訴求も得意なSNS広告
11 多くの人に自然な形で見てもらえるネイティブ広告
12 抜群の視覚効果で低関心層にもリーチできる動画広告
13 口コミ効果を狙う商品にはアフィリエイト広告
14 関心の高いターゲットを取りこぼさず訴求するリターゲティング広告
15 効果は高いが価格も高い純広告
16 潜在層に効果が高いメール広告
コラム その他のネット広告
3章 ネット広告の出稿方法
17 ネット広告を出稿するまでの流れ
18 自社に合った広告代理店の選び方
19 無理のない範囲の予算から広告を出稿する
20 出稿にあたって作成するもの
21 広告のテキストと画像を用意する際のポイント
コラム ネット広告の最適な文字数
4章 ネット広告の運用ネット広告運用のサイクル
22 ネット広告運用のサイクル
23 どの広告がどのような効果に貢献しているか確認する
24 広告は2パターン以上用意してABテストを行う
25 広告だけでなくランディングページも改善する
26 複数の広告を併用する際のおすすめパターン
付録
ネット広告用語一覧

- 【改訂5版】図解でよくわかる ネットワークの重要用語解説
- きたみりゅうじ
- 技術評論社
- ¥2310
- 2020年04月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.91(12)
ネットワーク用語集の超定番書「図解でわかる ネットワークの重要用語解説」の改訂5版です。フルカラーとして5年ぶりの大改訂版となります。ネットワークの用語がすべてイラストで解説されているため、かんたんに仕組みからしっかり理解することができます。初級エンジニアや学生の学習用としてはもちろん、現場で活躍するSEやPMの「あんちょこ」としても利用することができると大変好評です。今回の版から、インタネット編は「基礎編」と「技術編」の2つにわかれ、また新たに「セキュリティ編」が追加されました。

- セはセキュリティのセ
- 桑田 喜隆/石坂 徹/中野 光義
- 学術図書出版社
- ¥1870
- 2023年04月10日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は情報セキュリティの入門書です.日常生活や仕事で情報機器を使いこなす人に向けて,理解の必要な項目を取り上げ,できるだけ平易な文章で説明しています.理解を助けるため,豊富なイラストを掲載しています.特に,これから学業や仕事にパソコンなどの情報機器を利用しインターネットを使う人に読んでもらうことを想定しています.
〈目次〉
第1章 日常のセキュリティ
1.1 アカウント管理とパスワード
1.2 パソコンのセキュリティ
1.3 スマホのセキュリティ
1.4 無線LANの利用
1.5 電子メールのセキュリティ
1.6 インターネットサービスの利用
演習問題
第2章 セキュリティの脅威と対策
2.1 情報セキュリティ
2.2 情報資産とリスクアセスメント
2.3 セキュリティ情報の収集
演習問題
第3章 具体的な攻撃手法
3.1 フィッシングによる個人情報の詐取
3.2 スマホ決済の不正利用
3.3 ランサムウェアによる被害
3.4 標的型攻撃による機密情報の窃取
演習問題
第4章 セキュリティ技術
4.1 インターネットの仕組み
4.2 ネットワークセキュリティ
4.3 ウイルス対策
4.4 暗号化
4.5 電子署名
演習問題
第5章 セキュリティに関する国際標準や法律,規則
5.1 ISMS
5.2 法律
5.3 規則
演習問題
付録A リスクアセスメント
A.4 情報資産の棚卸
A.5 想定されるリスク
A.6 リスク分析
A.7 対策
付録B Jupyter Notebookを使った暗号化
B.1 準備
B.2 ハッシュ値の計算
B.3 共通鍵暗号
B.4 公開鍵暗号
あとがきーー終わりのない物語のはじまりーー
演習問題解答例
参考文献
第1章 日常のセキュリティ
1.1 アカウント管理とパスワード
1.2 パソコンのセキュリティ
1.3 スマホのセキュリティ
1.4 無線LANの利用
1.5 電子メールのセキュリティ
1.6 インターネットサービスの利用
演習問題
第2章 セキュリティの脅威と対策
2.1 情報セキュリティ
2.2 情報資産とリスクアセスメント
2.3 セキュリティ情報の収集
演習問題
第3章 具体的な攻撃手法
3.1 フィッシングによる個人情報の詐取
3.2 スマホ決済の不正利用
3.3 ランサムウェアによる被害
3.4 標的型攻撃による機密情報の窃取
演習問題
第4章 セキュリティ技術
4.1 インターネットの仕組み
4.2 ネットワークセキュリティ
4.3 ウイルス対策
4.4 暗号化
4.5 電子署名
演習問題
第5章 セキュリティに関する国際標準や法律,規則
5.1 ISMS
5.2 法律
5.3 規則
演習問題
付録A リスクアセスメント
A.4 情報資産の棚卸
A.5 想定されるリスク
A.6 リスク分析
A.7 対策
付録B Jupyter Notebookを使った暗号化
B.1 準備
B.2 ハッシュ値の計算
B.3 共通鍵暗号
B.4 公開鍵暗号
あとがきーー終わりのない物語のはじまりーー
演習問題解答例
参考文献

- できるWindows 11 2025年 改訂4版 Copilot対応
- 法林岳之/一ヶ谷兼乃/清水理史/できるシリーズ編集部
- インプレス
- ¥1100
- 2024年12月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.83(6)
この一冊ですべてわかる、初心者にやさしい入門書。スマホで見られる!YouTube動画解説。生成AI活用・スマホ連携・メール・Copilot+PCなど、はじめての人にも乗り換えの人にも役立つ。

- 図解入門 よくわかる 最新センサ技術の基本と仕組み
- 松本光春
- 秀和システム
- ¥2200
- 2020年05月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(3)
IoT や 5G でもっとも重要な電子デバイスと言われるセンサについて、その基本から各センサの役割、物理センサ・情報処理センサ技術の仕組み、さらには生活や医療などでの活用事例などをわかりやすく図解します。
第1章 IoT(モノのインターネット)の基礎知識
1-1 IoTとM2M
1-2 IoTの基本構成
1-3 IoTに必要な技術
1-4 IoTを取り巻く現状
1-5 情報を蓄積する技術に関連する技術展望
1-6 情報を活用する技術に関連する技術展望
第2章 センサの基礎知識
2-1 センサとはなにか
2-2 IoTにおけるセンサの役割
2-3 センサの分類
第3章 センシング:物理センサとその仕組み
3-1 光センサ1(CdSセル)
3-2 光センサ2(フォトダイオード)
3-3 赤外線センサ
3-4 温度センサ(サーミスタ)
3-5 温度センサ(熱電対)
3-6 湿度センサ
3-7 静電容量型加速度センサ
3-8 圧電式加速度センサ
3-9 音圧センサ(コンデンサマイクロホン)
3-10 音圧センサ(ダイナミックマイクロホン)
3-11 振動式ジャイロスコープ(角速度センサ)
3-12 速度センサ(ドップラー式)
3-13 距離センサ(超音波)
3-14 距離センサ(光学式)
3-15 ひずみゲージ(金属ひずみゲージ)
3-16 圧力センサ
3-17 力覚センサ
3-18 磁気センサ(ホールセンサ)
3-19 CO2センサ
3-20 O2センサ
3-21 土壌水分量センサ
3-22 pHセンサ(ガラス電極法)
3-23 脈波センサ(光電脈波法)
3-24 カメラ
3-25 ステレオカメラ
第4章 リーディング:情報処理センサとその仕組み
4-1 押しボタンスイッチ(プッシュスイッチ)
4-2 トグルスイッチ
4-3 1次元バーコード
4-4 2次元コード
4-5 ARマーカー
4-6 RFID
4-7 GPS
第5章 IoTの活用事例とセンサ技術
5-1 医療分野のIoT -みまもりホットラインー
5-2 医療分野のIoT -G・U・M Play-
5-3 医療分野のIoT -活動量計(GARMIN、Fitbit、TANITAなど)-
5-4 生活分野のIoT -MAMORIO-
5-5 生活分野のIoT -GeoTrakR-
5-6 生活分野のIoT -スマートロックー
5-7 農業分野のIoT -PaddyWatch-
5-8 農業分野のIoT -foop-

- 日本におけるDTCマーケティングの歩みと未来
- 古川 隆
- 文眞堂
- ¥3080
- 2018年02月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
製薬企業と患者との間にコミュニケーションをもたらしたDTCマーケティングについて、過去から未来までを本書は丁寧にまとめている。これからますます発展していくであろうDTCマーケティングを知る上で、本書は最良の羅針盤である。
主要目次
第1部 対 談
対談1 DTCとの出会いと研究(対談者:大石芳裕)
対談2 判断に迷ったら患者さんの利益を優先する(対談者:高橋義宣)
対談3 製薬業界を取り巻く環境は,極めて大きな転換点にある(対談者:沼田佳之)
対談4 難病患者と専門医・研究者をつなぐプラットホームが目標(対談者:香取久之)
対談5 将来,患者さん一人一人に寄り添う形の情報提供へ(対談者:加藤和彦)
第2部 DTCマーケティングの基本
第1章 医療用薬品のマーケティング・コミュニケーションとDTCマーケティング
第2章 統合型マーケティング・コミュニケーションとDTCマーケティング
第3章 DTCマーケティングのコミュニケーションモデル
第4章 患者調査の手法とペイシェントジャーニーマップ
第5章 広告と広報の違いについて
第6章 疾患啓発Webサイトの構築とインターネットの活用法
第7章 効果検証の考え方
第3部 資 料
資料1 DTC・作品別CM放送回数TOP10とCM好感度(関東・2012-16年度)
資料2 ペイシェント・エクスペリエンスデータ
資料3 医療機関内における患者行動・意識調査
資料4 患者サポートの必要性と実際
資料5 医療関連記者クラブ・PR会社

- エロい副業
- 鳥胸インターネット
- コアマガジン
- ¥865
- 2016年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
ニートからたった一年で年収一億円を達成!!新時代のエロ系ビジネス最前線!!FC2はインターネットの歌舞伎町だ!
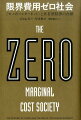
- 限界費用ゼロ社会
- ジェレミー・リフキン/柴田裕之
- NHK出版
- ¥2640
- 2015年10月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.79(59)
いま、経済パラダイムの大転換が進行しつつある。その原動力になっているのがIoT(モノのインターネット)だ。IoTはコミュニケーション、エネルギー、輸送の“インテリジェント・インフラ”を形成し、効率性や生産性を極限まで高める。それによりモノやサービスを1つ追加で生み出すコスト(限界費用)は限りなくゼロに近づき、将来モノやサービスは無料になり、企業の利益は消失して、資本主義は衰退を免れないという。代わりに台頭してくるのが、共有型経済だ。人々が協働でモノやサービスを生産し、共有し、管理する新しい社会が21世紀に実現する。世界的な文明評論家が、3Dプリンターや大規模オンライン講座MOOCなどの事例をもとにこの大変革のメカニズムを説き、確かな未来展望を描く。21世紀の経済と社会の潮流がわかる、大注目の書!