ジェンダー の検索結果 標準 順 約 2000 件中 361 から 380 件目(100 頁中 19 頁目) 

- スポーツとトランスジェンダー スポーツ医科学、倫理・インテグリティの見地から
- 貞升彩
- ブックハウス・エイチディ
- ¥2200
- 2024年11月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 正義・ジェンダー・家族
- スーザン・M.オーキン/山根 純佳/内藤 準/久保田 裕之
- 岩波書店
- ¥4840
- 2013年05月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
性別分業、女性の経済的依存、権力の格差…家族には男女間の不平等が折り重なっている。古代ギリシャ・ローマから現代に至るまで、公的領域における正義を追求した主流の政治理論・社会理論は、私的領域とみなされた家族のあり方をその射程に入れることはなかった。著者スーザン・モラー・オーキン(一九四六ー二〇〇四)は、本書でこれらの理論を根底から問い、正義に適った家族を実現する道を切り拓いた。フェミニズムがつねに立ち返るべき現代の古典。

- 【POD】高校生がトランスジェンダーから学んだこと
- 長井 華蓮/New Future of Transgender
- デザインエッグ株式会社
- ¥2013
- 2023年10月16日頃
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
この本は、LGBTQの啓発活動をしている浦狩知子さんの「小学校低学年の子どもたちにもトランスジェンダーというものを分かりやすく説明したい」という要望に応える形で、高校生が制作しました。この本には、1冊の中に2つの物語が書かれています。1つ目のお話は、女の子として生まれた「えみちゃんのお話」です。2つ目のお話は、男の人として生まれた「レイ先生のお話」です。どちらのお話も実話を元にしています。ぜひこの絵本を手に取っていただき、トランスジェンダーについて、たくさんの人に少しでも知って貰えると嬉しいです。

- 大衆の狂気
- ダグラス・マレー/山田美明
- 徳間書店
- ¥3080
- 2022年03月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.3(15)
世界26カ国で翻訳され、英語版だけで28万部超のベストセラー!
英国のAmazon評価6000件、レビュー800件以上の話題作!!
行き過ぎた「多様性尊重」は、社会をどのように破壊したのかーー
ダイバーシティ先進国で起きている「不都合な真実」。
LGBT、フェミニズム、反レイシズム運動などをめぐり、欧米社会で広がる偽善と矛盾、憎悪と対立。おかしいと思っても誰も声に出せない同調圧力の実態とは。
アイデンティティ・ポリティクス、インターセクショナリティ…新たなイデオロギーはいかにして生まれ、なぜ急速に広まったのか。
ツイッターやグーグルなど、シリコンバレーが進める機械学習が生み出す歪んだ歴史と新たな偏見。その基底に潜むマルクス主義。
……さまざまな事象から問題の本質を見抜き、その複雑な構造を読み解いていく驚きに満ちた快著。
世界的ベストセラー『西洋の自死』の著者が、圧倒的な知性と知識を武器に新たなタブーに挑む!
◎世界で相次ぐ本書への称賛
「マレーの最新刊は、すばらしいという言葉ではもの足りない。誰もが読むべきだし、誰もが読まなければならない。ウォーク(訳注/社会的不公正や差別に対する意識が高いこと)が流行するなかではびこっているあきれるほどあからさまな矛盾や偽善を、容赦なく暴き出してい
る」
──リチャード・ドーキンス(イギリスの動物行動学者)
「実にみごとだ。最後まで読んだ瞬間、数年ぶりに深呼吸をしたような気分になった。大衆が狂気に陥っているこの時代に、正気ほど気分をすっきりさせてくれるものはない。刺激的だ」
──サム・ハリス(アメリカの神経科学者)
「アイデンティティ・ポリティクスの狂気についてよくまとめられた、理路整然とした主張が展開されている。興味深い読みものだ」
──《タイムズ》紙
「マレーは、疑念の種をまき散らす社会的公正運動の矛盾に切り込み、大衆の九五パーセントがそう思いながらも怖くて口に出せないでいたことを雄弁に語っている。必読書だ」
──《ナショナル・ポスト》紙(カナダ)
「ばかばかしいエピソードから悲劇的な逸話まで、マレーはアイデンティティ主義者が陥ったさまざまな病理を、冷静さを失うことなく描写している。この本は、政治闘争を呼びかける鬨(とき)の声ではなく、構造的特徴が転々と変わり矛盾が絶えず噴き出すこの奇妙な世界を案内する地図である」
──《コメンタリー》誌

- ジェンダー
- 加藤秀一/石田仁
- ナツメ社
- ¥1430
- 2005年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.89(12)
「社会的に作り出された男女の違い」を意味するジェンダーという概念は、1970年頃から登場し、現在ではマスメディアや行政の場で広く使われている。しかしその概念を正確にとらえるためには、ふだん私たちが拠り所としている「常識」の中に潜む矛盾や思い込みに気づき、それらを打ち破っていく必要がある。本書は、客観的なデータと最新の科学的知見に基づき、個人の生き方、恋愛、結婚、家族、社会などのあらゆる場面と深く関わるジェンダーの意味、その周辺に存在する問題に迫る。
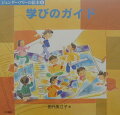
- ジェンダー・フリーの絵本(6)
- 橋本紀子/朴木佳緒留
- 大月書店
- ¥1980
- 2001年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
資料・用語解説から授業実践まで、調べ学習と活用のための手引き。小・中学生向き。

- 古代王権論
- 義江 明子
- 岩波書店
- ¥3410
- 2011年04月21日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
歴史を語るモノとしての系譜・神話を独自の視点から読み解き、古代における「歴史感覚」の特質を解明するとともに、ジェンダーと権力をめぐる普遍的な議論をふまえた斬新な女帝論を提示。古事記・日本書紀により垂直の時間軸をもつ王統譜として成型された「王権の歴史」の枠組みを超え出て、私たちの古代認識を根底から問いなおす、新しい日本古代王権論。

- トランスジェンダー生徒と学校
- 土肥いつき
- 生活書院
- ¥2970
- 2025年02月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
トランスジェンダー生徒が直面する困難は学校がつくりだしている!
教室の中で性別カテゴリーが構築される過程でトランスジェンダー生徒はどのような困難を抱えさせられるのか、その困難を軽減するためにどのような実践をおこなうのか。行為主体としてのトランスジェンダー生徒の姿を描く。
……
マイノリティが排除される過程と生徒たちの日常的実践を通して「学校文化」を問う必読の書!
はじめにーー本書を書くにいたった個人的な背景
序章 研究の背景と本書の目的
1 トランスジェンダー生徒をめぐる社会的背景
2 本書の目的
第1章 先行研究の検討と本書の分析視角
1 トランスジェンダー生徒はどのように語られてきたか
2 学校教育とジェンダー
3 本書の分析視角
第2章 調査の概要
1 私のポジショナリティ
2 研究の対象
3 調査協力者の5つの局面とその時代背景
第3章 トランスジェンダー生徒に対する学校の対応と当事者からの評価
1 何にもそんな言葉ないから「自分変なんや」みたいなーートランス男性のハルトさん
2 性別をおしつけるも何も、性別なかったですーートランス女性のツバサさん
3 「したい」っていう選択肢なんてないですよーートランス男性のススムさん
4 そういうちょっとしたことをやってもらうだけで自分はうれしかったなぁーートランス男性のユウヤさん
5 なんかもうすべてが「もうええわ」ってなりましたねーートランス男性のシュウトさん
6 直接聞いてきてくれたのが、すごいうれしかったーートランス男性のユウキさん
7 新しい前例としたらおかしくないでしょうーートランス女性のキョウコさん
8 あれがなかったらなかったで、こうならなかったーートランス男性をやめたアキさん
第4章 学校の性別分化とトランスジェンダー生徒のジェンダー葛藤
1 ジェンダー葛藤が強まる過程
2 「言語化」「カミングアウト」「出会い」「要求」
3 ジェンダー葛藤を弱める要素
4 「性別にもとづく扱いの差異」によって設定される性別カテゴリーの境界線とジェンダー葛藤
5 おわりに
第5章 トランスジェンダー生徒による性別移行をめぐる日常的実践
1 研究の対象と方法
2 ユイコさんの教室内の所属グループと他者からの性別の扱い
3 ユイコさんの語りから見た教室内に働くAGABの強制力と性別カテゴリーの境界線の変遷
4 おわりに
第6章 トランスジェンダー生徒による実践しない「実践」
1 研究の対象と方法
2 マコトさんの語りに見る女子グループへの参入過程
3 マコトさんによる実践しない「実践」
4 おわりに
終章 トランスジェンダー生徒の学校経験から見えてきたこと
1 性別カテゴリーへの「割り当て」に着目することの意義
2 AGABの強制力と性別カテゴリー内の多様な位置どり
3 トランスジェンダー生徒の実践が意味すること
4 トランスジェンダー生徒が包摂される学校であるために
あとがきーー「はじめに」のその後
文献

- 不平等の再検討
- アマルティア・セン/池本 幸生/野上 裕生/佐藤 仁
- 岩波書店
- ¥1892
- 2018年10月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.6(7)
人間の不平等の問題は、所得格差の面からだけでは解決できない。一九九八年にノーベル経済学賞を受賞した著者は、本書で、これらの問題を「人間は多様な存在である」という視点から再考察することを提案した。「潜在能力アプローチ」と呼ばれるその手法は、経済学にとどまらず、倫理学、法律学、哲学など関連の学問諸分野にも多大な影響を与えている。現代文庫版では、参考文献を改訂し、現代の日本における不平等に関する議論を本書の視点から考察した訳者による解説を新たに付した。

- SDGs先進都市フライブルク
- 中口 毅博/熊崎 実佳
- 学芸出版社
- ¥2860
- 2019年08月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
環境、エネルギー、技術革新、働きがい、人権、教育、健康……フライブルクではSDGsに関わる市民・企業活動が広がっている。本書では、それらがなぜ個々の活動をこえて地域全体の持続可能性につながっているのかを探り、SDGsを実現するために自治体や企業、市民が考えるべきこと、政策や計画立案、協働・連携のヒントを示す。

- ジェンダー入門
- 加藤秀一
- 朝日新聞出版
- ¥1430
- 2006年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.81(17)

- 多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理
- 小岩 広宣
- 日本実業出版社
- ¥2750
- 2024年11月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
「男らしさ」「女らしさ」をめぐる労務の課題と実務の最適解がよくわかる。人事労務担当者はもちろん、部下を持つ管理職のテキストとしても使える!

- 「声」とメディアの社会学
- 北出真紀恵
- 晃洋書房
- ¥3080
- 2019年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「声」を担ってきたアナウンサーたちは、「アナウンサーらしさとはなにか」、「なぜ女はアシスタントなのか」、「メディアの送り手は何をなすべきか」などの問題とどう向き合ってきたか。アナウンサーを生きる、彼女(彼)らのライフストーリーやインタビュー調査を通じて、更には、元フリーアナウンサーである著者が長年アシスタントをつとめたラジオ番組の事例から考える。

- 女性学・男性学(第3版)
- 伊藤 公雄/樹村 みのり/國信 潤子
- 有斐閣
- ¥2200
- 2019年04月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(8)
ジェンダーの視点から,自分たちの性とそのあり方を問い直していく入門テキストの第3版。恋愛,労働,育児など,さまざまな生活の場面に焦点を当てた本文と,マンガ,特別講義,コラムやエクササイズなど,工夫をこらした構成で日本の現状に鋭く迫る最新版。
第1章 女であることの損・得,男であることの損・得
第2章 作られる〈男らしさ〉〈女らしさ〉
特講1 女性学って何?
マンガ1 あなたとわたし
第3章 ジェンダーに敏感な教育のために
第4章 恋愛の女性学・男性学
特講2 男性学って何?
第5章 ジェンダーと労働
マンガ2 花子さんの見た未来?
第6章 多様な家族に向かって
第7章 育児はだれのもの
マンガ3 今日の一日の幸
第8章 国際化のなかの女性問題・男性問題
特講3 平和の思想と〈男らしさ〉
第9章 ジェンダー・フリー社会の見取り図

- データとモデルの実践ミクロ経済学
- 安達 貴教
- 慶應義塾大学出版会
- ¥2970
- 2022年06月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
▲データによる実証分析とモデルによる理論分析の協演!
▲ビジネス・テック・政治といった他分野を越境するミクロ経済学
▲入門書や教科書の「先」を知りたい人のための新しいスタイルの研究書
昨年のノーベル経済学賞授賞対象となった「因果推論」。そうした学問的進展を踏まえながらも、経済学の伝統である理論分析をどういかすか。「ジェンダー」「プラットフォーム」「自民党」といった現代日本における喫緊のテーマを対象にして著者自身が携わった研究成果をまとめる。ミクロ経済学の「実践」の新たなる可能性を示す。

- ジェンダーフリーってなんだろう?
- 稲葉 茂勝/赤木 かん子/こどもくらぶ
- 岩崎書店
- ¥3300
- 2023年02月02日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
男女格差、ジェンダー、LGBTなど様々な差別や人権や教育、社会的な問題を、日本と世界を比較して具体的に学ぶ。ジェンダー平等がSDGsに組みこまれた理由も解説。

- 日本社会の移民第二世代
- 清水 睦美/児島 明/角替 弘規/額賀 美紗子/三浦 綾希子/坪田 光平
- 明石書店
- ¥6490
- 2021年07月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
1990年代前後に来日した、移民第二世代の若者たち。その人生を振り返り紡いでくれた170名のひとりひとりの歴史、悩み、将来の夢から、直線的でも一様でもないホスト国日本への適応過程とその要因、世代間にまたがる文化変容の型がみえてくる。

- 現代日韓60年史
- 青柳 純一
- アジェンダ・プロジェクト
- ¥1320
- 2023年08月17日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、「植民地支配の歴史」を異なる立場から共有する隣国・韓国の歴史を併記して対比させ、国際情勢の変化にも留意しながら、現代日本社会の特徴や性格、変遷過程を歴史的に明らかにするものである。時期区分としては1960年前後を「現代日韓史」の起点と位置づけ、植民地期を含むそれ以前を「前史」、米ソ冷戦体制下を第1部、冷戦体制解体後を第2部としている。そして今日に至る「現代日韓60年史」の基軸として1953年の朝鮮戦争の停戦協定後に形成された「朝鮮停戦体制」という概念を新たに導入し、それが90年代以降は米ソ冷戦体制に代わって南北分断体制を補強する役割を担ってきたこと、これを「終戦・平和体制」へと向かわせることが現代の私たちの課題である。「補論」として「「安倍・改憲派と統一教会」20年史」、「ウクライナ戦争と朝鮮停戦体制」を収め、「安倍国葬」をめぐって噴出した問題の今日的重要性も強調している。
はじめに;前史1 近代日本と朝鮮・東アジア;前史2 現代日韓関係への移行過程;〔第1部〕米ソ冷戦体制下の日本と韓国;1.現代日本の確立;2.「市民自治体」の萌芽;3.自民党内の派閥抗争;4.冷戦激化から脱冷戦へ;5.米ソ冷戦体制の解体;〔第2部〕冷戦体制崩壊後の日本と韓国;1.「自社共存」体制の解体;2.「日韓パートナー」関係の萌芽;3.自公連立政権の確立;4.自民党の世襲政権;5.民主党中心の政権;6.安倍・改憲派政権の確立;7.安倍・改憲派政権の崩壊;補論1 「安倍・改憲派と統一教会」20年史;補論2 ウクライナ戦争と朝鮮停戦体制;むすびに;参考資料;

- ジェンダーの心理学改訂版
- 青野篤子/森永康子
- ミネルヴァ書房
- ¥2420
- 2004年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
女はやさしく、男は強い。このような男女差に対する意識はなぜ生まれ、どのようにして人びとの心のなかに定着するのか。人はいったん思いこむと、それに従って人を観察したり、ふさわしいようにふるまったりする。その思いこみーステレオタイプをキーワードに、法や制度を整えても、なぜ伝統的な性別分業社会は、人びとの意識の上からなくならないのかを、社会心理学の立場からときあかす。

- 新書版 性差の日本史
- 国立歴史民俗博物館/「性差の日本史」展示プロジェクト
- 集英社インターナショナル
- ¥924
- 2021年10月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.89(11)
話題の展覧会がコンパクトな1冊に!--ジェンダーの歴史1800年の旅
2020年秋、国立歴史民俗博物館で開催され、注目を集めた「性差(ジェンダー)の日本史」展の内容をダイジェスト。展示の見所を解説した、読みやすい新書にしました。
古代から現代までのジェンダーを示す貴重な資料130点の図版を掲載。
執筆は第一線で活躍する歴史研究者たちによるものです。
◇◇◇◇◇
無意識のうちに私たちを強く捉えているジェンダー。その歴史は驚きと発見に満ちています。
日本の歴史のなかで「男」と「女」という区分はいつ、どのようにして生まれたのか?
日本の社会のなかでジェンダーがどのような意味を持ち、どう変化してきたのか?
ジェンダーをめぐる悩み・葛藤ーー歴史のなかに自分をおいてみると、その先がみえてくる!
日本のジェンダー史を知るための必読書!
こんな方におすすめです。
◇最近よく耳にする「ジェンダー」とは何なのかを歴史的に知りたい
◇確かな資料をもとにジェンダーについて考えてみたい
◇なぜ、日本のジェンダー平等が進まないのかを考えてみたい
【本書の目次】
プロローグ 倭王卑弥呼
第1章 古代社会の男女
第2章 中世の政治と男女
第3章 中世の家と宗教
第4章 仕事とくらしのジェンダー -中世から近世へー
第5章 分離から排除へ 近世・近代の政治空間とジェンダーの変容
第6章 性の売買と社会
第7章 仕事とくらしのジェンダー -近代から現代へー
エピローグ ジェンダーを超えてー村木厚子さんに聞く
監修:国立歴史民俗博物館
千葉県佐倉市の佐倉城址にある、日本の歴史と文化について総合的に展示する博物館。通称、歴博(れきはく)。「大学共同利用機関」として、歴史学・考古学・民俗学と関連諸科学の連携による共同研究を行い、その成果を展示や出版物などで広く公開している。
2020年秋に開催された企画展示「性差(ジェンダー)の日本史」は、2016年から3年間かけて行われた共同研究の成果を発表したもの。