1~9を繰り返す の検索結果 レビュー多 順 約 100 件中 21 から 40 件目(5 頁中 2 頁目) 

- ネットニュースではわからない本当の日本経済入門
- 伊藤 元重
- 東洋経済新報社
- ¥1760
- 2021年08月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
日本経済の現状と見通しを、関連する経済理論とともに解説
ビジネスパーソン向けの経済学講義の決定版
「コロナ不況なのに、株価は異常に値上がりした」
「アメリカの景気がよくなって、円安に振れた」
「最近、ケインズが見直されている」
「日本には巨額の借金があるが、財政破綻を予想する人は少ない」・・・・
日々の経済ニュースは、実は全部つながっています。
ただし、ネットで短い記事を読んだり、日々の報道を断片的に見聞きしているだけでは、本質的な流れはわかりません。
本書は現実の生々しい経済現象を追いかけながら、それらを理解するのに必要なマクロ経済理論をやさしく解説しています。
経済学の知識を使うことでそれぞれのできごとのつながりが深く理解でき、グローバル経済や金融市場の見通しが抜群によくなることが実感できます。
序章 「戦後復興」政策と長期停滞の脱出策が議論にーーコロナ後の経済
第1章 コロナ危機からの回復はいつかーーGDPの理論
第2章 デジタルとグリーンがなぜ重要なのかーー総需要と総供給
第3章 見直されるケインズ経済学ーーインフレとデフレ
第4章 コロナ危機が働き方改革を加速ーー労働市場
第5章 ゼロ金利政策の”深掘り”とはーー金融
第6章 巨額の債務は何をもたらすかーー財政
第7章 先進国に共通する長期停滞と格差拡大ーー経済成長
第8章 貿易収支の背後にマクロ経済問題ーー国際金融
第9章 バブルも危機も繰り返すーー資産市場

- 企業に変革をもたらす DX成功への最強プロセス
- 小国 幸司
- 幻冬舎
- ¥1760
- 2023年08月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
目的の明確化、課題抽出、ワークフローの細分化……
泥臭い工程を踏んだフローと戦略策定で
DXを成功へと導く!
システムの導入だけではない
効果を最大化するDX実現のポイントを
ICT活用の提案・実行支援のプロフェッショナルが解説
今やDX(デジタルトランスフォーメーション)は企業経営者にとって最も大きな関心事の
一つといっても過言ではありません。2020年の新型コロナウイルス感染症の流行による
テレワークの普及などで急激に広がりを見せたDXは、今後企業が生き残るための
キーポイントといえます。
DXに取り組んでいる企業が急増する一方で、DXで大きな成果を残し、胸を張って
「わが社はDXを達成した」といえる企業は決して多くはないと著者は考えています。
こうした企業は、何を目標にDXをすべきか、どのような手段でDXを実行すべきか、
DXの成果をどう評価すべきかについて明確な方針と基準をもてていないのです。
著者は1990年代のIT黎明期といえる時代から、基幹系開発エンジニアや
外資スタートアップ企業の日本法人立ち上げを経験し、ビジネス開発支援や中小企業のIT化推進
などに携わってきました。そして2016年に会社を設立し、現在は企業への
ITコンサルティングやシステム開発、プラットフォームづくりなどを通じて
DXをはじめとする企業の課題解決に取り組んでいます。
DXはICTツールやシステムの導入を指すものではなく、ただ導入するだけで
どんな業務もあっという間に改善できるというものではありません。
著者は、経営陣やIT担当者の意識改革から、目的の明確化、課題の棚卸し、
ワークフローの細分化など、非常に泥臭く緻密な作業を繰り返し、
施策が社員に定着して初めてDXが成功したといえるのだと指摘しています。
本書は、著者がこれまでDXに取り組んだ企業の事例をベースに、
成功させるために必要な工程やその手法を詳しく解説したものです。業務の効率化、
生産性向上を期してDXを検討する経営者、担当者へ向けて、
後悔しないDXの手引きとなる一冊です。

- サムライたちのゼロ戦
- ロバ-ト・C.ミケシュ/立花薫
- 講談社
- ¥2136
- 1995年07月28日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
世界にその名を馳せた名機の雄姿を未公開写真多数で紹介。併せて、世界中の博物館に収蔵されたすべての日本軍機の所在と保存状態を網羅する歴史的な一冊。

- 写真でみる火山の自然史
- 町田洋/白尾元理
- 東京大学出版会
- ¥4950
- 1998年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)

- ここからはじめるC言語
- 高橋麻奈
- 日本実業出版社
- ¥1650
- 2000年08月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
本書では、C言語の基本的な考え方と知識について、図解を豊富に取り入れながら説明。言葉だけではわかりにくい事柄や概念も、図を見ながらやさしく理解できるように工夫してある。「市販の本を買って勉強してみたが、難しいコードばかりですぐ挫折した」という学生の方から、「C言語を勉強しなければいけない部署に配置されたが、どんなものなのかさっぱりわからない」というビジネスマンの方まで、本書は「入門の入門書」的な役割を果たすことだろう。

- 株勝ち続けている人たちの儲かるしくみ
- 中村光夫
- 日本実業出版社
- ¥1540
- 2004年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
資金も時間も限られる個人投資家が、どうしたら株で勝てるのか?そんなギモンに答える一番の方法は、実際に勝っている人に聞くこと。そこで、近年の下落相場でも勝ち続けてきた個人投資家10人に、実践している投資手法や実際の売買履歴を公開してもらった。元手は50万円から数千万円、年数回の売買しかしない人から短期回転売買を得意とする人までバラエティーも豊か。

- 研修が教えないビジネス能力の磨き方
- 落合敏明
- 日刊工業新聞社
- ¥1760
- 2006年01月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
大手企業に採用されるなど、ビジネス能力向上に実績を上げている注目のThinkingStyle(思考スタイル)強化のノウハウ本。

- 速効!図解Excel 2007(VBA編)
- 池谷京子
- マイナビ出版
- ¥1738
- 2007年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)

- 税理士要らず!個人事業者のための〈超簡単〉経理
- 吉田信康
- ぱる出版
- ¥1650
- 2010年12月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
領収書の束の前で途方に暮れているアナタに。すぐわかる逆引き勘定科目事典つき。

- こどものバイエル レパートリー ミッキーといっしょ 4
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- ¥1100
- 2012年01月27日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)

- 英国EU離脱の本当の理由!?いよいよドイツ発金融恐慌が始まる!
- 松藤民輔/中島孝志
- ゴマブックス
- ¥1320
- 2016年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(1)
英国はEU崩壊を知っていたから離脱した!ダウ最高値から大暴落!株価、ドル円為替、金価格、債券、国債はこれからこうなる!

- ツェルニー40番練習曲<新標準版>
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- ¥1210
- 2017年02月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)

- Pythonではじめるプログラミング
- 小波秀雄
- インプレス
- ¥2200
- 2019年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
本書は、プログラミングの初心者が、Pythonという言語の世界を通して、楽しくプログラミングの基礎を学べるように構成されています。セミナー形式でレクチャーを受けるスタイルなので、一歩ずつ着実に理解を深めることができます。このセミナーの目標は、プログラミングの初心者がPythonを使って実用的なデータ処理ができるレベルに到達することです。手を動かして、ステップごとに結果を確認しつつ、考えながら学ぶというスタイルで進めていきます。特に第1章から第3章までは、初心者目線でていねいなやり取りを展開しています。第4章〜第7章では、主にPythonプログラミングの基本を解説します。この範囲を押さえればプログラミングの基礎的なスキルは出来上がり、いろいろな処理のためのソースを書いていくことができるでしょう。第8章〜第10章では、Pythonの特徴を活かしたアルゴリズムの実装など、実践的なプログラミングを通してコーディングの力を養います。最後に数学ライブラリを使ったデータ処理、グラフィックスとデータ可視化の基本テクニックを身につけることになります。
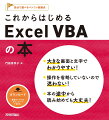
- これからはじめる Excel VBAの本
- 門脇香奈子
- 技術評論社
- ¥1848
- 2019年06月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
本書は、ゼロからExcelのVBAを学習する方を対象にした、いちばんやさしいVBAの入門書です。大きな画面と文字、わかりやすく楽しいイラストでVBAの書き方をていねいに図解しているので、初めての方でも迷うことはありません。また、章ごとに用意された練習問題で、学習の理解度をそのつど確認することもできます。本書を読むことで、Excel VBAの基本がしっかり身に付きます!

- あなうめ式Javaプログラミング超入門
- 大津真/田中賢一郎
- エムディエヌコーポレーション
- ¥1980
- 2019年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
あなうめ問題でJavaの基礎をしっかり身につける!!

- 解きながら学ぶ Pythonつみあげトレーニングブック
- リブロワークス/株式会社ビープラウド
- マイナビ出版
- ¥2728
- 2021年07月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
プログラミングの入門者とプロの違いには、どんな点があるでしょうか。
大きな違いの1つとして、「プログラムをすばやく理解する反射神経」があるかどうか、という点が挙げられるのではないでしょうか。
「プログラムはじっくり考えて作るもので、反射神経は関係ないんじゃないの?」と思われるかもしれません。確かに全体設計などじっくり考える部分もありますが、本書で説明するような基礎文法は、一瞬で把握できるのが理想です。「どこが変数でどこが関数・メソッドか」「式内の演算子が処理される順番」「行が実行される順番」などでいちいち考え込んでいたら、いつまで経ってもプログラムを理解できません。
本書では、そんな「大事なポイントや処理の流れがぱっとわかる」力を付けられるような内容を用意しました。
文法を解説する各セクションの後に「ミッション」を設け、ルールがわかっていれば簡単に解ける問題をいくつも出題し、反復訓練によってより速く解答できることを目指しました。
また、終盤の9、10章は、入門書のその先を目指した内容となっています。入門書を卒業して自分でプログラムを書くレベルに達するために、以下の2つのスキルが身に付けられるようにしました。
・公式ドキュメントの解説を読んで、自力で知識を増やせる
・エラーメッセージを読んで、解決方法を見つけられる
どちらも少し難しいですが、自分でプログラムを書くレベルに達するための必須スキルですので、ぜひ取り組んでみてください。
本書の解説は、Pythonが初めての方でも理解できるように、文法の基礎から解説しています。これからPythonを始める方にとっても、少しPythonがわかるけれど、細かいところに不安がある方、実践レベルに近づきたい方におすすめの1冊です。脱「Python入門」を目指して、本書でトレーニングを積みましょう!
※Python 3.x使用
※サンプルファイルおよびミッションのPDFをサポートサイトからダウンロードできます
1章 トレーニングを始める前に
2章 基本的なデータと計算
3章 命令と条件分岐
4章 データの集まり
5章 処理を繰り返す
6章 少し高度なデータ
7章 関数を作る
8章 クラスを作る
9章 ドキュメントとライブラリ
10章 エラーと例外処理
ミッションの解答・解説

- 解きながら学ぶ JavaScriptつみあげトレーニングブック
- リブロワークス/中川 幸哉
- マイナビ出版
- ¥2728
- 2021年12月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(1)
「いずれWebエンジニアとして仕事をするようになりたい」
「JavaScriptの入門書を1冊読んだけど、理解がぼんやりしている」
「現場に出て恥ずかしくないように勉強しておきたい」
本書は、そんな風に思っている人にぴったりな、JavaScriptのプログラミング力をぐっとアップする1冊です。
解説では、文法の基本はもちろん、エラーやドキュメントの読み方まで説明。
ミッションでは、「瞬間的に分からなければいけない問題」を解くことで理解力を深め、瞬発力をアップします。
プロに近づく確かな1冊が欲しい方に!
1章 トレーニングを始める前に
2章 基本的なデータと計算
3章 命令と条件分岐
4章 少し高度なデータ
5章 処理を繰り返す
6章 関数を作る
7章 オブジェクトをさらに理解する
8章 HTMLを操作する
9章 JavaScriptの新しい構文
10章 ドキュメントとエラーを読む
ミッションの解答・解説
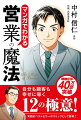
- マンガでわかる営業の魔法
- 中村信仁
- パンローリング
- ¥1760
- 2023年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
契約が一件も取れず挫折寸前の新人営業マン小笠原は、今日も日がな一日、伏魔殿のような喫茶店で時間をつぶしていた。そんな彼の目に飛び込んできたのは、自信と余裕に満ちた同じく営業マンらしき男性。まぶしいまでの輝きを放つ彼は顧客の話を聞き、質問を投げかけ、気づけば「魔法のように」契約を交わし、顧客と笑顔で店を後にした。そんな彼を追いかけ、懇願する。教えてくださいー営業を!プロ営業マン紙谷の実践ノウハウは、小笠原に気づきと勇気、そしてやる気と輝きを与えてくれ、まるで本物の魔法にかかったかのようにこれまでのダメ営業マンを脱し、成長していく。しかし12個の魔法を伝授すると言っていた紙谷は最後の魔法を伝えないまま忽然と姿を消してしまった。急に連絡が途絶えた紙谷の身に何が起こったのか。最後の魔法とは何だったのか。やりがいを見失っていた小笠原の苦悩と成長、そして営業の道程をリアルに描いたベストセラー本が、ついにマンガになって登場!

- 学校では教えてくれない 日本人のための英文法の授業
- 小川 直樹
- ナツメ社
- ¥1870
- 2025年05月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
ネイティブの文の作り方の感覚がわかると、
英語が聞き取りやすくなる!話せるようにもなる!!
学校で習う英文法はなぜわかりにくいのか?
それは、ネイティブにとっては当たり前の言語感覚や発想を知らないまま、英語を勉強しているから。
本書は、ネイティブにとって当たり前だけれど日本人が知らない「英語の根本の発想」を徹底解明。学校では教わらなかった「ネイティブの英語の文の作り方の感覚」がわかるようになります。
[ネイティブの感覚1] 一番伝えたいことを文末にもってくる
典型は能動態と受動態。能動態→受動態へ書き換えるとは、伝えたいことを変えるということ。
[ネイティブの感覚2] 複雑な文も出てきた語順で理解する
複雑な文も「主部・述部」「主部・述部」「主部・述部」…というセットが並んでできあがっている。この順番に理解すれば実はシンプル。
[ネイティブの感覚3] 現在時制と過去時制の違いが「時制の一致」を生む
現在時制は自分の目で今見ている主観的な世界。過去時制は変えようのない事実の客観的な世界。別だからこそ、しっかり分ける。だから、主節が過去形なら従属節まで全部過去形にする。
[ネイティブの感覚4] 現在完了は過去時制と現在時制をつなぐ唯一の手段
現在時制と過去時制は相いれない世界。両者をつなぐための唯一の手段が現在完了形。これが現在完了形の存在意義。
[ネイティブの感覚5] 現在進行形は“ストリートビュー”、単純現在形は“普通の地図”
現在進行形は「具体的」。現在の時間の一部を切り出してクローズアップで見る言い方。単純現在形は「抽象的」。線と文字だけでできた地図を見ているような感覚。
[ネイティブの感覚6] 情報の並べ方は「大枠」→「詳細」
英語の情報の並べ方の大原則。関係代名詞はその発想の典型。先行詞で大雑把に本質(=大枠)を示し、関係代名詞でそれを絞り込んでいく。
【目次】
PART1 英文法がわからないのにはワケがある/PART2 人称とは/PART3 文の構造/PART4 時制/PART5 続・文の構造/PART6 主述関係/PART7 不定詞/PART8 -ing形(現在分詞と動名詞)/PART9 分詞(現在分詞と過去分詞)/PART10 現在完了形/PART11 助動詞/PART12 仮定法/PART13 受身形と倒置/PART14 関係代名詞

- 文科系のFORTRAN入門
- 鈴木昇(1936生)
- オーム社
- ¥2883
- 1987年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
JISに準拠、どの機種にも対応できる!題材として事務処理を扱い、文科系用のFORTRANの最適入門テキストとなるよう編集したもので、数学が苦手な方にも無理なく理解できるよう、やさしく、ていねいに解説しました。