思春期 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 381 から 400 件目(100 頁中 20 頁目) 

- 父親のための家庭教育のヒント
- 林 道義
- 日本教文社
- ¥1361
- 2004年09月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
子供好きになることから躾やほめ方
まで、父親ならではの子供との接し方
を37話のなかで具体的に紹介。
子供と関わることが苦手なお父さんに
お勧めのわかりやすい子育てガイド。

- 自尊心を育てて「前向き」な子に
- 甲田繁則
- 文芸社
- ¥1100
- 2016年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ
- 小栗正幸
- ぎょうせい
- ¥2095
- 2010年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(6)
発達障害が原因でおこる失敗や挫折の繰り返しから、感情や行動にゆがみが生じ周囲を困らせる行動をとってしまう、それを二次障害と呼びます。その現れ方と非行化するプロセスとは驚くほど類似性があります。少年非行の現場で多くの発達障害児にも接してきた著者が、非行化のメカニズムの解説をもとに、二次障害の予防と対処を豊富な事例をあげて、わかりやすく紹介します。

- こどものこころのアセスメント
- マーガレット・ラスティン/エマニュエラ・カグリアータ
- 岩崎学術出版社
- ¥4070
- 2007年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●本書は,発達障害児,被虐待児,摂食障害児,乳幼児,思春期の家族,自殺に対するアセスメントが主なテーマとなっている。操作的な診断基準に従う診断のみではなく,個々のこどもの心的世界や家族との関係などの力動学的観点等,トータルな視点をもつことで,臨床の展望が開けるだろう。
* * * * * 本書の解説 * * * * *
本書は4部構成になっており,発達障害児,被虐待児,摂食障害児,乳幼児,それを取り巻く家族,思春期の家族,その精神分析的心理療法,自殺が主なテーマとなっている。生き生きとした臨床の息吹きを感じさせる諸論文で構成され,読者の関心に従ってどこの章から読んで頂いてもかまわない。各章の内容はこども・思春期の現代のトピック的なテーマであり,これらは精神分析の適応の拡大を意味し,ここには精神分析の挑戦的な試みが詳細に論じられている。タビストックでは自閉スペクトラム等の発達障害,虐待,摂食障害といった障害,疾患への精神分析的アプローチが伝統的に行われ,本書を読めば明らかなようにその成果を上げている。アセスメントは個々のこども,家族といった個別性や特異性についての理解を深めることであり,その延長線上,あるいはその結果の一部に診断がある。しかし,昨今,DSM,ICDなどの操作的な診断基準が汎化し,この診断基準に当て嵌めることがアセスメントであり,その診断がすべてであると誤解している専門家も時にいるようである。アスペルガー障害,ADHDという医学的用語が世間に周知されるにつれて,経験の浅い専門家からそうした診断名を宣告されている親子も時に見かける。DSM,ICDが初心者にとって有益であることは疑いないが,個々のこどもの心的世界や家族との関係などの力動学的視点を欠いたアセスメントは意味がないだけでなく,極めて危険な臨床行為である。(「監訳者まえがき」より)
●目次
監訳者まえがき
序 (ニコラス・テンプル,マーゴ・ワデル)
謝辞 (マーガレット・ラスティン,エマニュエラ・カグリアータ)
序章 (マーガレット・ラスティン)
◇重度の障害を持つこどものアセスメント
第1章 コミュニケーション障害のこどものアセスメント (マリア・ロード)
第2章 境界例児のアセスメント──混乱と欠損の鑑別 (アン・アルヴァレズ)
第3章 重度の摂食障害──生命への攻撃 (ジーン・マガーニャ)
◇心的外傷を負ったこどもとその家族
第4章 家庭崩壊の後には何が起きるのか──環境剥奪,トラウマそして複合的喪失を経験したこどもたちのアセスメント (マーガレット・ラスティン)
第5章 性的虐待児のアセスメント (ジュディス・トゥローウェル)
◇家族へのアプローチ
第6章 5歳児以下のこどもと親のカウンセリングとそのアセスメントの問題との関連 (リサ・ミラー)
第7章 家族の探索的アセスメント (ベータ・コプリー)
◇思春期
第8章 思春期のアセスメント──考える空間を探して (マーゴ・ワデル)
第9章 思春期における自傷リスクのアセスメント──精神分析学的見解 (ロビン・アンダーソン)
解説:タビストック・クリニック
─紹介から心理療法のためのアセスメントまでの流れ─ (脇谷順子)
あとがきにかえて─本書の視点─ (木部則雄)
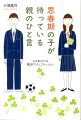
- 思春期の子が待っている親のひと言
- 大塚隆司
- 総合法令出版
- ¥1430
- 2009年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(15)
「急に勉強する気になったみたい!」「素直に話しをする子になった」「子どもにイライラしなくなった」-1000組の親子を導いたコーチング・メソッド。

- 自分から勉強する子の親がしていること
- 大塚隆司
- さくら舎
- ¥1540
- 2015年04月08日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(4)
子どもの勉強ぎらいは、実は周りの大人が原因だった!子どもに「勉強っておもしろい」という気づきを贈るために、親がしてあげられる具体的なアプローチ。

- 摂食障害
- 深井 善光
- ミネルヴァ書房
- ¥2420
- 2018年07月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.67(4)
「食べる・食べない」の問題ではない。「定常体重療法」の発案者が初めて語る、食べることを強要しない治し方
代表的な拒食症と過食症は、どちらも食を拒む病いだが、「拒食」が不安を内包するのに対し、「過食」は怒りや不安を相手にぶつけて暴力的になる傾向の違いがある。また、思春期に発症する食への異常行動は、実は乳幼児期に起因する場合もあり、ミルクの「イヤイヤ」や離乳食から始まる偏食を遡って見ていく。本書は「病は治せる」との観点より摂食障害の患者・家族に寄り添いつつ治療の経過と結果から「定常体重療法」をQ&A形式で紹介。

- 思春期未満お断り〔小学館文庫〕(1)
- 渡瀬 悠宇
- 小学館
- ¥680
- 2009年03月14日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
天涯孤独の16歳・樋口飛鳥(ひぐちあすか)が上京したのは、まだ見ぬ父に娘と名乗りをあげるためだった。亡き母に導かれるように出会った真斗(マナト)と和沙(かずさ)は、なんと飛鳥の異母弟妹。むりやり2人の家に居候を決めた飛鳥だったが、肝心の父は真斗と和沙にもいまだ姿を見せない謎のロクデナシであることが明らかに。
ひとつ屋根の下で暮らす3姉弟妹の前途に、思春期男女のあぶない予感が!?

- 思春期未満お断り〔小学館文庫〕(2)
- 渡瀬 悠宇
- 小学館
- ¥680
- 2009年04月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
飛鳥(あすか)、真斗(マナト)、和沙(かずさ)が通う清領学園。ケンカ上等の総番・速水(はやみ)やピーキーなお嬢様・神谷(かみや)、体操部に入った飛鳥の才能に惚れ込んだ能天気な体育教師・矢城(やしろ)らが入り乱れる学園生活はなかなかシビアだ。そんなハチャメチャな日々のなか、飛鳥と真斗の間に恋心が! 異母姉弟の禁断の愛に、超ブラコンの和沙が立ちはだかる。そしてついに姿を現した3人の父は、思いもよらない男だった!!

- やさしい思春期臨床
- 黒沢幸子
- 金剛出版
- ¥3520
- 2015年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
子どもと大人がみずから変わる!解決志向+未来志向の思春期臨床。不登校、ひきこもり、いじめ、友人関係、親子葛藤ー思春期の人々のもつれた“悪循環”を“希望”の流れに!悩める思春期の風向きを変える臨床実践のヒント。

- あおい先生は思春期(1)
- 凛田 百々
- 講談社
- ¥471
- 2017年01月13日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
高校生のひばりは、実は生物教師の青井先生とおつきあい中。教師と高校生の2人の恋は、絶対ナイショどころか、メールも電話もデートもキスだって…「恋人らしいことは一切禁止」! ウワサ一つでお別れのマジメな交際。--それは全て、“恋する気持ち”を守るためのものなんだけど……。でも先生、なんだか赤くない? 清く正しく限界すれすれ!? まじめ生物教師との毎日ぎゅんぎゅんラブ開幕です!
設問1. 空欄を埋めよ
設問2. 適当なものを選べ
設問3. 理由を述べよ
設問4. 解を求めよ
補習 実験せよ

- 思春期未満お断り〔小学館文庫〕(3)
- 渡瀬 悠宇
- 小学館
- ¥680
- 2009年04月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
血のつながりがないことがわかり、恋の障害が消えた飛鳥(あすか)と真斗(マナト)。だが、父・峻(たかし)が2人に告げたのは無情にも「H禁止令」。やりたい気持ちと秘密の恋を耐え忍ぶ2人だったが、キスシーンを隠し撮りされ、学園新聞に「禁断の恋」とスクープされてしまう。そのうえ、死んだはずの真斗の母まで現れて…!? 恋とHと友情と家族愛にあふれた「思春期未満お断り」、完結編も収録した完全版のフィナーレ!
シリーズ完結巻!

- 産婦人科の窓口から新装版
- 河野美代子
- 子どもの未来社
- ¥1650
- 2014年09月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
氾濫する危うい情報・知識=「ウソ」を本当と思い込んでしまう。これから先、長い人生を本当に豊かに生きるために、子ども・青年たちに生きる底力をつけてあげたい!人間は知ることで行動が慎重になる。

- 大家さんは思春期! 10
- 水瀬るるう
- 芳文社
- ¥680
- 2019年03月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 小児・思春期糖尿病コンセンサスガイドライン
- 日本糖尿病学会/日本小児内分泌学会
- 南江堂
- ¥4180
- 2015年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)

- 思春期ちゃんのしつけかた (4) 特装版
- 中田 ゆみ
- 一迅社
- ¥1155
- 2021年01月27日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 思春期を生きる発達障害
- 橋本和明/竹田契一
- 創元社
- ¥2530
- 2010年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
教育・非行・就労、やがて大人に…ゆれ動く“思春期”の子どものこころを丁寧に受けとる。生きにくい時代に生きる子どもにどのように寄り添うことができるか…。好評の1st Stageセミナー第2弾。

- 思春期ちゃんのしつけかた (2)
- 中田 ゆみ
- 一迅社
- ¥682
- 2020年01月27日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)

- 思春期ちゃんのしつけかた (4)
- 中田 ゆみ
- 一迅社
- ¥693
- 2021年01月27日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- おそい・はやい・ひくい・たかい(No.96)
- 岡崎勝
- ジャパンマシニスト社
- ¥1320
- 2017年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)