増税 の検索結果 標準 順 約 760 件中 401 から 420 件目(38 頁中 21 頁目) 

- ワンルームマンション投資の基本 秘訣は不動産会社選びだった
- 関野 大介
- 万来舎
- ¥1540
- 2020年04月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ワンルームマンション経営の教科書!!
最小リスクで安心をつかむ。家族を幸せにするための、資金ゼロから始めるワンルームマンション投資法。
本書は、不動産投資に少しでも興味のある方に、将来的に生活防衛の手段として有効な、安全で堅実な、ローリスク、ミドルリターンを目指すワンルームマンション投資法をご紹介。
リスクを低く抑え、将来の人生の支えとなる資産を、少しでも増やしたいと思う会社員の方や自営業の方、さらに学生の方にも読んでいただきたいと思っております。
資金ゼロで始めるワンルームマンション経営の教科書としてご活用ください。

- これからヤバイ世界経済
- 渡邉哲也/三橋貴明
- ビジネス社
- ¥1540
- 2015年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(4)
金融緩和の魔力から抜け出せない世界。3つのバブルが崩壊した中国。大難民が押し寄せるユーロ圏。周回遅れで、グローバリズムに門戸を開く日本。2016年は、大変動の年となる!

- 財政破綻の噓を暴く
- 高橋 洋一
- 平凡社
- ¥880
- 2019年04月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
財務省は、「このままでは、日本の財政は破綻する」と喧伝し、国債残高ばかりに目を向けさせ、増税や緊縮財政を声高に叫ぶ。だが当然のことながら、国には借金もあれば資産もある。企業財務を連結ベースでみるのと同様に、国家の財政状態も、日銀を政府の子会社とする「統合政府」として捉えなくてはならない。財政の実体を連結ベースのバランスシートで把握することで、いかに増税が悪影響を及ぼすかを指摘し、未来に向けた財政支出の必要性を説く。
序 章 消費税の増税は必要ない
財務省の話は鵜呑みにできない/八パーセント引き上げ時の現実/消費税は経済政策として得策ではない
第1章 「統合政府バランスシート」で捉えよ
財政状況を知る重要な指標とは/グロス債務残高にこだわると“過小投資”になる/「統合政府」という捉え方/雇用の確保は金融政策の一つ/株価が上がると半年先の雇用が増える/財政再建を進める新たな財源
第2章 財政危機の“ウソ”を検証する
財務省はなぜ、「日本は財政破綻する」と騒ぐのか/「国に借金はない」といえるカラクリ/増税にこだわる経済(財政)学者たちの間違い/国債が暴落すれば日銀は大損するか/財政再建のために増税は必要なのか/危険水準は国によって異なる/財政再建に必要なもの、不要なもの/増税と財政再建に因果性はない/名目成長率を高めれば増税はいらない/IMFの分析からも同じことがいえる
第3章 財政赤字はいかにして起きたか
一九九〇年を境にした経済成長の段差/いきなり低成長になった、その理由/バブル経済は悪いことか/資産価格の上昇でしかなかった/税制と証券の抜け穴がバブルを生んだ/バブルはまた起きるだろうか/財政赤字を深刻化させた日銀
第4章 国債は国の財政を揺るがす“悪者”か
戦費調達の手段としてはじまった国債/国債は国の経済には欠かせない/国の借金は「悪」ではない/日銀は国債と引き換えに紙幣を刷る/国債をめぐる日銀と政府の関係性/国債は最終的には政府の収入になる/日銀はさらに国債の直接引き受けをすべき/本当の意味での「公平な分かち合い」とは/国債は「投資」でもある/半径一メートルの思考でマクロをみるな/国債は決して「発行され過ぎ」てはいない
第5章 財政再建のポイントとは
財政再建のための五つの方法/必要なのは増税よりも経済成長/税制をいじるより徴収漏れをなくせ/増税の前に埋蔵金の発掘と行革こそ必要/埋蔵金を隠し合う財務省と日銀/埋蔵金の温床は特別会計/消費増税は日本経済をぶち壊している/消費税は社会保障税ではなく地方税とすべき
第6章 財政を悪化させないために
財政政策と金融政策に関する三つのモデル/「統合政府」の考え方で、財政再建はほぼ終わり/国債発行による未来投資を/教育国債は「将来への付け回し」ではない/なぜ天下りはなくならないのか/天下りをさせないために
あとがき

- 老後を救う投資術 投資信託と保険こそ、最高の金融商品
- 児玉 正浩
- 幻冬舎
- ¥990
- 2022年09月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 1.0(1)
老後を救う投資術 投資信託と保険こそ、最高の金融商品

- 日本経済 「円」の真実
- 榊原 英資
- KADOKAWA
- ¥1100
- 2012年10月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
世界同時恐慌を予測し、元大蔵官僚・金融局長として日本円の舞台裏を知っている「ミスター円」が、経済ニュースでは語られない「日本円」の真相をあばく。

- 魔法の生前贈与
- 柴田昇
- 実務出版
- ¥662
- 2015年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ここがポイント“生前贈与”。贈与から始める『相続税』大増税対策の第一歩。

- 小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本
- 高橋敏則
- ダイヤモンド社
- ¥1760
- 2014年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
税率アップで何がどう変わるのか?価格表示はどうする?税抜き表示にできる条件とは?「消費税還元」はダメでも「8%還元セール」はOK?消費税特別措置法の知っておくべきポイントは?知りたいことがすぐに探せる全125項目。

- 経済のしくみがわかる「数学の話」
- 高橋洋一
- PHP研究所
- ¥814
- 2014年07月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(3)
「ず〜っと疑問に思っていたことがあった。世の中の人は、なぜ、これほどたやすく官僚・政治家・マスコミ・御用学者の嘘に騙されるのだろう…」(本書より抜粋)▼そう、テレビや新聞をにぎわす、「日本は財政破綻寸前」、「消費税増税が必要」といったニュースは、実はウソが多い。そして、それを見抜くカギは、「数学」にある。「高校レベルの数学」さえできれば、誰にでも、それらの言説がいかに間違っているのかが分かるのだ。▼本書は、理論派で知られるエコノミストが、経済・ビジネスに役立ち、騙されないための「数学的思考」を徹底解説。抱腹絶倒の講義形式で、経済と数学の関係がおもしろいほどわかり、世の中の見方も変わる!▼『数学を知らずに経済を語るな!』を改題。▼[内容例]▼○復興財源は増税なしで確保できる▼○消費税増税は要らない▼○そもそも「財政破綻」キャンペーンが大嘘▼○定義に無頓着な人は騙される▼○中学・高校の数学を勉強し直そう▼○マクロ経済を勉強して財務省に対抗しよう

- 日本大沈没
- 藤巻健史
- 幻冬舎
- ¥1047
- 2012年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.82(34)
消費税10%は「焼け石に水」。財政破綻かハイパーインフレで社会的大混乱は必至。なぜ周知の事実を誰も言わないのか?お金は自分で守るしかない。
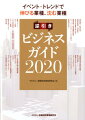
- 逆引きビジネスガイド(2020)
- 金融財政事情研究会
- 金融財政事情研究会
- ¥2750
- 2020年02月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ポスト2020における日本経済が直面する変化の波を26のテーマで徹底予測!どのようなビジネス(業種)が、どのような(ポジティブ/ネガティブ)インパクトを受けるのかを解説。半世紀を超えて活用される“業界情報の宝庫”。全面改訂した『第14次 業種別審査事典』と同時刊行!業種の知識をさらに深める1冊。

- ヘルスケア・レストラン(2019 2)
- 日本医療企画
- ¥1210
- 2019年01月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- デフレと闘う
- 原田 泰
- 中央公論新社
- ¥2970
- 2021年06月22日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(3)
量的・質的金融緩和(QQE)、マイナス金利、イールドカーブ・コントロール、そしてコロナショック……。2015年3月から2020年3月までの5年間、著者は黒田総裁下の日本銀行で、金融政策を決定する政策委員会審議委員を務めた。2%の物価目標とデフレ脱却に向け、日銀はいかに苦闘したのか。さまざまな批判に何を思い、反論したのか。アベノミクスと金融政策決定の舞台裏を明らかにする。

- ビルオーナーの相続対策
- 川合宏一
- 幻冬舎メディアコンサルティング
- ¥814
- 2013年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
知識の有無で納税額に数億円の差が出る。『生きているうちに相続税をゼロにする方法』第二弾。

- 相続税を減らす不動産相続の極意
- 森田義男
- 幻冬舎メディアコンサルティング
- ¥814
- 2014年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 今こそ消費税廃止+積極財政を!
- 原口一博/藤井聡
- かや書房
- ¥1760
- 2025年08月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
原口一博氏は「消費税は日本弱体化装置」と断言し、
藤井聡氏は「消費増税がアベノミクスを破壊」と分析。
そして両氏は、「緊縮財政から脱却し、積極財政を!」
と声を揃える。その声は、物価高と景気低迷に苦しむ
多くの国民の声であると言っても過言ではない。
日本の没落を招いた悪政から脱するための緊急提言!
第1章 消費税は「日本弱体化装置」だ!
第2章 トランプ大統領が導く日本の消費税廃止
第3章 なぜ財務省は増税したがるのか?
第4章 緊縮財政派VS積極財政派
第5章 財務省解体をどう実現するか
第6章 トランプ革命とグローバリズムの終焉

- プロの財産コンサルタントが教えるやってはいけない不動産相続対策
- 高田吉孝
- 実業之日本社
- ¥1760
- 2016年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
不動産現金化時代が再びやってきた!安易な土地活用、節税、借り入れに頼った相続対策に警鐘!建築会社、不動産会社などに言われるがままの「必要のない相続対策」「やりすぎ相続対策」に要注意!財産を減らさずに相続を乗り切る相続対策のための法人活用方法など、あなたに最適な相続対策と最適な財産ポートフォリオを教えます。

- 富裕層なら知っておきたいスイス・プライベートバンクを活用した資産保全
- 高島 一夫/高島 宏修/西村 善朗/森田 貴子
- 総合法令出版
- ¥1760
- 2024年03月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
現在、日本の資産運用環境は極めて悪い状況にある。円安による資産価値の目減り、高所得層をターゲットにした増税措置、そして突如として襲い掛かる地震や水害などの自然災害リスク。円安を背景に株価は一時的に高騰し、日銀の利上げ方針転換への期待はあるものの、少子高齢化が進む日本の先行きは明るいとは言えない。
そんな日本人にとって格好の資産運用先がスイスのプライベートバンクである。投機的な運用ではなく、資産を確実に保全することを目的に、長い歴史で培われた唯一無二の資産運用メソッドは、世界の富裕層のお金を惹きつけてやまない。
本書はそんなスイス・プライベートバンクの基礎情報から、実際の口座の開設、運用、税務までを1冊でまとめた入門書。プライベートバンクは基本的に富裕層向けであるが、その運用手法は一般投資家にも参考になるものである。また、将来富裕層を目指す人々にとっても役立つ情報が満載。
第1章: 日本の富裕層が迎える「大増税時代」への備え
第2章: 富裕層の危機回避手段としての海外投資
第3章: 富裕層を惹きつけるスイス・プライベートバンク
第4章: スイス・プライベートバンクの資産運用スタイル
第5章: スイス・プライベートバンクで資産を継承する
第6章: スイス・プライベートバンクに口座を開設する
第7章: 海外で資産運用する際の税金対策

- 世の中の見え方がガラッと変わる経済学入門
- 川本明/矢尾板俊平/小林慶一郎/中里透/野坂美穂
- PHP研究所
- ¥1650
- 2016年03月24日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
ついに18歳の選挙権が解禁。そこで「18歳でも選挙の争点がよくわかる」ようになる「経済学の本質をまとめた1冊」をお届けします!

- 相続税ゼロの不動産対策
- 重邦宜/鎌倉靖二
- 幻冬舎メディアコンサルティング
- ¥814
- 2013年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
まさに大増税時代と言える現在。先祖代々の土地を守り、そして子孫によりよい財産として引き継ぐためには、基本的な相続税や贈与税の知識だけでは足りない。必要となるのは不動産の知識と、その知識を積極的に活かす術を知ることだ。資産税のスペシャリストがタッグを組んでここに明かす次世代の相続対策。

- 社会保障亡国論
- 鈴木 亘
- 講談社
- ¥924
- 2014年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(12)
消費税が増税されると本当に社会保障は充実するのか。現在わが国の社会保障給付費は、GDPの約4分の1にあたる110兆円を超える規模に達しており、年間3〜4兆円というペースで急増している。消費税率の引き上げの効果は3〜4年で消失する計算となる。年金・医療・介護・子育て支援など、「少子高齢化」日本を暮らす人々の不安は拡がる一方だ。社会保障財源の現状を具体的に改善する議論と給付の抑制・効率化策も提言する。
消費税が増税されると本当に社会保障は充実するのか。
現在わが国の社会保障給付費は、GDPの約4分の1にあたる110兆円を超える規模に達しており、年間3〜4兆円というペースで急増している。消費税率の引き上げの効果は3兆〜4年で消失する計算となる。
年金・医療・介護・子育て支援など、「少子高齢化」日本に暮らす人々の不安は拡がる一方だ。社会保障財源の現状を具体的に改善する議論と給付の抑制・効率化策も提言する。
第一章 財政から語る社会保障
第二章 社会保障の暗黙の債務は一五〇〇兆円
第三章 社会保障と税の一体改革、社会保障制度改革国民会議
第四章 年金支給開始年齢は七〇歳以上に
第五章 高齢化社会の安定財源は消費税ではなく相続税
第六章 公費投入縮減から進める給付効率化
第七章 消費増税不要の待機児童対策
第八章 「貧困の罠」を防ぐ生活保護改革
第九章 改革のインフラ整備と仕組み作り