ダイバーシティ の検索結果 高価 順 約 620 件中 461 から 480 件目(31 頁中 24 頁目) 

- 会社員のためのCSR入門
- 大久保和孝
- 第一法規出版
- ¥1885
- 2008年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
CSRの第一線で活躍している著名な学者、専門家、企業実務家が勢ぞろい!CSRの基本的な枠組み、企業は社会とどう関わっていくべきか、社員一人ひとりはどう考えるべきかなどの観点からリレー講義する一冊。さまざまな異なる分野・立場の専門家がCSRをとらえることで、多面的なCSRの本質を探ります。

- 立教ビジネスレビュー(第8号)
- 立教大学/立教経営学会
- 立教経営学会
- ¥1885
- 2015年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 実践リーダーをめざすひとの仕事術
- F.メアリー・ウィリアムズ/キャロリン・J.エマーソン
- 新水社
- ¥1870
- 2005年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
キャリア設計に役立つスキルを手に入れる。セルフプロモーションからリアルプロモーションへ。「リーダーをめざす女性たちへ」赤松良子さんインタビュー収録。

- おいしいダイバーシティ
- 横山 真也
- ころから
- ¥1870
- 2021年01月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
驚異的に発展するアジアとイスラム圏に精通する気鋭のコンサルタントが、ポストコロナ時代の「美食ニッポン開国論」を提言。
ビジネス・ブレークスルー大学長の大前研一氏推薦!
おいしいダイバーシティをはじめよう
第1章 日本食の現在地
日本観光を楽しめないムスリムたち
ネギを取り分ける台湾人
買い物に2時間かかるムスリマ
引きこもる在住ムスリムたち
1人だけ弁当持参
飲み会に恐怖するムスリム
スキー旅行でインスタント食品
「キットカットはハラールですか?」
第2章 美食の国の不都合な真実
「ジャパン・アズ・ナンバー1」と機会の窓
「選ぶ側」ではないという認識はあるか?
ムスリムの市場規模は世界最大に
「勤勉さ」では計れない生産性
産業構造の変化に乗り遅れた日本
日本が小国から学ぶ点
多様性が生む競争力
各種調査から見える若者の姿
驚きの「留学したくない理由」
低下しつづける東大の世界ランキング
留学フェアのお粗末な実態
データから見える日本の閉鎖性
人生100年時代に学びは必須
難民認定に見る日本の非寛容さ
ムスリム社員の「生の声」
祈りのための”努力”
行政による排他性も
知られざるムスリム墓地問題
教育の問題ではないか
第3章 「食」からなら開国できる
日本食への意外な低評価
求められる「彼らもまた正しい」の姿勢
なぜ、日本のフードダイバーシティは遅れたのか
「食べられない」という多様性
文化・嗜好による「食べられない」
宗教上の理由での「食べられない」
ポリシー、思想に基づくもの
体質・体調による制限
「食べられない」にどう対応するか
おいしい対応法(個人編)
おいしい対応法(事業者編)
「正解はない」という基本
「ぶっちゃける」ことがおいしい
便利なビュッフェ
第4章 未来予想図
ポジティブシナリオ
ネガティブシナリオ
現在地はどこか
ハラール対応したラーメン店
クリケットタウンを目指す佐野市
ムスリムに大人気の大阪のソウルフード
東北の町がリードするSDGs
ハラールメニューを揃える学食
伝統を進化させた味噌煮込みうどん店
「いつまで拒むのですか?」
あとがき 食は世界の共通語
もっと知るためのコラム
1 ヒジャブは典型的?
2 進化するコンビニ、スーパー
3 もしイスラム教徒がハラームを食べたなら?
4 イメージの中のテロリスト
5 お祈りは歯磨きみたいなもの?
6 お清めの水とシャワートイレ
7 断食はつらいよ?
8 知っていると便利 ハラール認証
9 保育園を探して

- 図解!ダイバーシティの教科書
- 木下明子
- プレジデント社
- ¥1870
- 2023年01月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(3)
日本で唯一の女性向けビジネス誌編集長が、20万人データから語る女性活躍のリアル。

- xDiversityという可能性の挑戦
- 落合 陽一/菅野 裕介/本多 達也/遠藤 謙/島影 圭佑/設楽 明寿
- 講談社
- ¥1870
- 2023年01月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
AIに代表される計算機技術の成熟とともに訪れる、新しい自然。
デジタルデータと自然が融和し、そのどちらでもない自然に生まれ変わった自然・自然観を、落合陽一は「デジタルネイチャー」と名付けた。
計算機と自然の様々な中庸状態を探るなかで、人の身体が制約から解放され、新たな制約を楽しむこともできる、という気づきの先にあるのが、クロス・ダイバーシティのプロジェクトである。
菅野裕介(東京大学生産技術研究所准教授)、本多達也(富士通株式会社Ontennaプロジェクトリーダー)、遠藤謙(ソニー株式会社シリアリサーチャー)ら日本を代表する若手研究者・エンジニアが集結し、落合陽一を代表としてJSTクレストxDiversityを結成した。
メンバーは4つのチームに分かれ、それぞれのタスクに取り組んだ。
聴覚補助デバイス、ロボット義足、視覚障害者支援デバイスなどの製作と、それらのデバイスを実装するためのワークショップ、プロトタイピングなどである。
義足を着けた乙武洋匡氏は国立競技場でみごと117メートルを歩ききった。
ろう者・聴覚障害者のために開発された「Ontenna」は全国の8割以上のろう学校に採用され、新たな体験をもたらしているだけでなく、聴者の世界も広げつつある。
xDiversityは、技術(=どうやって解くか)の多様性と課題(=何を解くか)の多様性をクロスさせて新しい価値を生み出すことをコンセプトに挑戦を続けてきた。
本書は、4年半におよぶxDiversityプロジェクトの内容を、落合陽一氏をはじめとしたメンバーが報告するレポートである。
いま、たしかに姿を現わしつつある新しいデジタルネイチャーの実像がここにある。
序章 最強のチーム
第1章 Ontenna--AIでろう・難聴者の可能性を拓く
第2章 OTOTAKE義足プロジェクト
第3章 OTONGLASSからファブビオトープへ
第4章 当事者の視点によるxDiversityの未来
第5章 Maker movement の期待と失敗
第6章 ”現実”の自給自足展
第7章 インクルーシブワークショップの5年
第8章 技術の多様性と課題の多様性に挑む
終章 対談「斎藤幸平(東京大学大学院総合文化研究科准教授)×JSTクレストxDiversity」
xDiversityはGAFAの先のコモンをつくる

- 増補新版 女性管理職のためのしなやかマネジメント入門
- 細木聡子
- NTT出版
- ¥1870
- 2024年03月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
モデルが少なく孤立しがちな女性管理職を、NTTでのべ1000人の人材育成に携わってきた著者が〈6つの力〉と〈メソッド〉でサポートする「はじめての女性管理職の教科書」。生産力を2倍に、離職率を50%ダウンさせてきた著者の力の源は「信じる力」。部下を信頼し、可能性を引き出す支援型リーダーシップで、持続的な成果を導く、「しなやかマジメント」を2024年度版にバージョンアップ。巻末に元 東レ取締役の佐々木常夫氏とのダイバーシティ対談を収録した増補新版。

- SIGNAL 7
- (オムニバス)
- リバーシティミュージックエンタテインメント
- ¥1864
- 2008年02月22日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ネペンテス (初回盤B)
- MEJIBRAY
- (株)フォーラム
- ¥1782
- 2015年04月01日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 盈虧 (初回限定盤B)
- MEJIBRAY
- (株)フォーラム
- ¥1782
- 2015年05月06日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- EXIT TUNES PRESENTS Vocaloconnection feat.初音ミク
- (V.A.)
- エグジットチューンズ(株)
- ¥1780
- 2012年08月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)

- 女性のキャリア・マネ-ジメント
- 金谷千慧子
- 中央大学出版部
- ¥1760
- 2003年10月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
企業改革は女性のキャリアアップから。自分でできるキャリアワークシート付き。

- 選ばれる企業の条件
- 峰如之介
- すばる舎
- ¥1760
- 2006年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 女性力で強くなる!
- 前田典子
- 近代セールス社
- ¥1760
- 2007年12月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
価値観の枠組みを広げ、多様性を活かしたマネジメントが職場活性化のカギ。営業店で女性力を活かし営業店の力を強化するための考え方とコツをわかりやすく伝える。

- 世界の知で創る
- 野中郁次郎/徳岡晃一郎
- 東洋経済新報社
- ¥1760
- 2009年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.33(4)
日産開発部門がグローバル展開に成功したのはなぜか。日産のこの経験から日本企業は何を学べるか。日米欧での一〇〇人を超える関係者への取材を通じて「知の共創」という観点から二〇年間の軌跡を総括し、『日本流グローバル化の本質』を探る。

- ザ・ベロシティ
- ディー・ジェイコブ/スーザン・バーグランド
- ダイヤモンド社
- ¥1760
- 2010年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.64(53)
あえて「ムダ」は残せ。なぜ、ムダをそぎ落とし、バランスの取れたシステムが機能しないのか。なぜ、「過剰な」生産能力が重要なのか。本当に絞るべきムダとは何か。どこに集中して、何を変えて、そして何に変えればいいのか。21世紀版『ザ・ゴール』誕生。

- ビジネスコミュニケーションのためのケース学習(教材編)
- 近藤彩/金孝卿
- ココ出版
- ¥1760
- 2013年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 本当のホワイト企業の見つけ方
- 東洋経済新報社/岸本吉浩
- 東洋経済新報社
- ¥1760
- 2014年06月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
「ゆったり働ける」だけでは真のホワイト企業ではない。人材活用・環境・企業統治・社会性といったCSR(企業の社会的責任)の観点や財務状況から、本当の優秀企業を見る眼を養う徹底ガイド。282社採録!
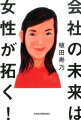
- 会社の未来は女性が拓く!
- 植田寿乃
- 日経BPM(日本経済新聞出版本部)
- ¥1760
- 2014年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(4)
働くママを部長にすれば、組織は変わるんです。カギを握るのは、男性管理職。

- 当たり前の経営
- 野田稔
- ダイヤモンド社
- ¥1760
- 2014年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.2(5)
有給休暇取得率95%、残業1日1時間。「働き方改革」でワークライフバランスを正したら生産性が上がり、増収増益になった!心に訴える経営で、ホワイト企業が生まれる。