ウェブ の検索結果 標準 順 約 2000 件中 541 から 560 件目(100 頁中 28 頁目) 

- Web制作会社年鑑2022
- Web Designing 編集部/合資会社小宮佳将(kudzilla.com)
- マイナビ出版
- ¥5280
- 2022年04月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
この1年間で話題となったWebサイト、Webマーケティング施策、スマートフォン/タブレット向けアプリ施策などを制作会社ごとにアーカイブ化したインタラクティブコンテンツ集。
時代の先端をいくインタラクティブな制作事例はもちろん、ビジネスの目的・課題の解決に成果を上げたWebサイト、アプリの事例、そして制作物だけでは伝わらない制作会社の魅力を伝える取材記事で、自社の課題を解決する最適な業務委託先の選定により役立つ情報を提供し、デジタル施策の企画・提案・制作会社の強みや得意施策などを一覧できます。

- Webサービス開発徹底攻略(vol.2)
- 技術評論社
- ¥2178
- 2016年02月16日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
徹底攻略シリーズでは、Webアプリケーション開発のためのプログラミング技術情報誌『WEB+DB PRESS』の掲載記事をテーマ別に厳選し再編集してお届けします。「最新技術を基本から学びたい」「実際の活用事例が知りたい」「定番の開発手法を身につけたい」など、一歩先行くWebエンジニアの意欲と好奇心を各分野の第一人者による解説できっと満足させます!

- PythonによるOpenCV4画像処理プログラミング+Webアプリ入門
- 北山直洋
- カットシステム
- ¥4400
- 2021年11月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)

- WEB+DB PRESS(Vol.107(2018))
- 技術評論社
- ¥1628
- 2018年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)

- ウェブ解析士
- MarkeZine Academy編集部/ウェブ解析士協会
- 翔泳社
- ¥2420
- 2012年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 1.0(1)
ビジネスとウェブをつなぐコンサルティング能力を証明する資格「ウェブ解析士」。仕事のようすから、初級試験の合格に直結する演習・解説まで、ぎゅぎゅっとコンパクトにまとめました。

- PT・OTのための臨床技能とOSCE 機能障害・能力低下への介入編 第2版[Web動画付き]
- 才藤 栄一/金田 嘉清/冨田 昌夫/大塚 圭/鈴木 由佳理/谷川広樹
- 金原出版
- ¥6050
- 2022年04月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「機能障害・能力低下への介入編」待望の改訂!視覚的な理解を促す豊富な写真、採点者・模擬患者の注意点などの特長はそのままに、内容の刷新を図った。
好評のweb動画もアップデートし、分析・介入のポイントをより理解しやすいものとなった。
指定規則改定により臨床実習前後の評価が必修化され、OSCEの重要性が増すなか、臨床家を目指す学生のみならず、養成校教員、臨床実習指導者まで必読の1冊となった。
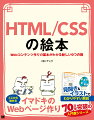
- HTML/CSSの絵本 Webコンテンツ作りの基本がわかる新しい9つの扉
- 株式会社アンク
- 翔泳社
- ¥2178
- 2023年03月22日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
Webコンテンツ作りには興味があるけれど、HTMLやCSSは複雑で難しそうだな、と感じている人も多いのではないでしょうか。本書はイラストも多く交えて解説しているので、HTML/CSSの仕組みや書き方などの基本を直感的にイメージでき、理解も進められます。さあ、HTML/CSSの扉を開き、Webコンテンツ作りの一歩を踏み出しましょう。

- デジタル時代の実践スキル Web分析&改善 マーケティングの成功率を高める戦略と戦術(MarkeZine BOOKS)
- 川田 曜士
- 翔泳社
- ¥1958
- 2019年08月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.33(3)
成果につながる基本を身につけて
ビジネスに好循環を生み出そう
【本書で身につくこと】
・Webにおけるビジネスモデルを理解できる
・業務に使えるフレームワークがわかる
・施策を運用し、改善を続ける方法がわかる
・指標を理解し、自ら設計できるようになる
【内容紹介】
Web分析・改善は、いまや
どんなビジネスでも欠かせません。
これからはいろいろな視点と
組み合わせたり、データから
アイディアを生み出す発想力も
求められることでしょう。
本書では、指標の読み方はもちろん、
データ分析のための考え方や
Webのビジネスモデル、さらには
戦略や戦術まで解説しています。
Web分析・改善をするための基本を
しっかり押さえられるので、
トレンドの技術やツールに
流されることのない“基礎体力”を
付けることができます。
【目次(抜粋)】
Introduction デジタル時代に不可欠な「Web分析・改善」
Chapter 1 Web分析・改善でできること
Chapter 2 Web戦略の基本
Chapter 3 Web分析・改善の第一歩「会社とユーザーを知る」
Chapter 4 いろいろな指標の意味と活用方法
Chapter 5 マーケティング視点で分析・改善計画を立てる
Chapter 6 測定方法を設計する
Chapter 7 意図を持って施策を運用する
Chapter 8 データから課題を発見する
Chapter 9 データの「見せ方」と「伝え方」

- ウェブはバカと暇人のもの
- 中川淳一郎
- 光文社
- ¥836
- 2009年04月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.7(242)
著者はニュースサイトの編集者をやっている関係で、ネット漬けの日々を送っているが、とにかくネットが気持ち悪い。そこで他人を「死ね」「ゴミ」「クズ」と罵倒しまくる人も気持ち悪いし、「通報しますた」と揚げ足取りばかりする人も気持ち悪いし、アイドルの他愛もないブログが「絶賛キャーキャーコメント」で埋まるのも気持ち悪いし、ミクシィの「今日のランチはカルボナーラ」みたいなどうでもいい書き込みも気持ち悪い。うんざりだ。-本書では、「頭の良い人」ではなく、「普通の人」「バカ」がインターネットをどう利用しているのか?リアルな現実を、現場の視点から描写する。

- Webエンジニアのための監視システム実装ガイド
- 馬場 俊彰
- マイナビ出版
- ¥2992
- 2020年03月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
システムは、何もしないと壊れます。
システムは、よくわからない状態になります。
どれだけ技術力の高いエンジニアが設計・構築しても、残念な事実として、システムを構築した後に何もしないと壊れます、よくわからない状態になります。
システムを「監視」あるいは「モニタリング」することで、
異常を検知し復旧させること
システムの価値を維持・向上させること
ができます。
本書では、監視テクノロジの動向から組織での実装まで、わかりやすく学ぶことができます。
最新ツールの説明、実装パターンの紹介だけでなく、組織での実装にあたっての態勢づくり、システムづくりについても現場目線で寄り添って解説しています。
これから監視を始める方にはもちろん、現状の監視システムに疑問を抱いている方にもおすすめの1冊です。
【章構成】
第1章 監視テクノロジの動向
第2章 監視テクノロジの概要
第3章 監視テクノロジの基礎
第4章 監視テクノロジの導⼊
第5章 監視テクノロジの実装
第6章 インシデント対応実践編
第7章 監視構成例
第1章 監視テクノロジの動向
1.1 システムにまつわる残念な事実
1.2 監視テクノロジの2 つの志向性
1.3 監視テクノロジの動向
1.4 Web システム運用の文化
第2章 監視テクノロジの概要
2.1 監視テクノロジで実現したいこと
2.2 可用性の測り方
2.3 監視システムの種類
2.4 監視システムの構成概要
2.5 自己修復機構と監視テクノロジ
2.6 自己修復システムの継続的運用を支えるChaos Engineering
第3章 監視テクノロジの基礎
3.1 監視テクノロジの基礎
3.2 観測部分の基礎技術
3.3 データ収集部分の基礎技術
3.4 データ利用部分の基礎技術
3.5 時系列データベースの基礎技術
3.6 ログの基礎技術
第4章 監視テクノロジの導⼊
4.1 「監視」に対する期待
4.2 監視を始める
4.3 監視ツールどれにしよう問題
第5章 監視テクノロジの実装
5.1 アラーティングする / しないの基準
5.2 アラーティング目的の観測項目を決める
5.3 定番の観測項目
第6章 インシデント対応実践編
6.1 インシデント対応の基礎知識
6.2 インシデント対応の心構え
6.3 インシデントがOpen ステータスのときにやること
6.4 インシデントがResolved ステータスのときにやること
6.5 恒久対応 / 改善対応
第7章 監視構成例
7.1 チェック、メトリクス、ログ、トレース、APM の構成例
7.2 通知、コミュニケーション、ドキュメント、チケットの構成例

- 副業でもOK! スキルゼロから3か月で月収10万円 いきなりWebデザイナー
- 濱口 まさみつ
- 日本実業出版社
- ¥1650
- 2023年04月28日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.8(5)
高度な技術は不要!スキマ時間に働ける!仕事に困らない!「自由に働き」「必要な額を」らくらく稼ぐ方法。スキルシェアサービスMENTAの人気ナンバーワン講師がノウハウを全公開!

- TypeScriptとReact/Next.jsでつくる実践Webアプリケーション開発
- 手島 拓也/吉田 健人/高林 佳稀
- 技術評論社
- ¥3498
- 2022年07月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.75(5)
新しいフロントエンドの入門書決定版!
本書はReact/Next.jsとTypeScriptを用いてWebアプリケーションを開発する入門書です。
WebアプリケーションフレームワークNext.jsはReactをベースに開発されています。
高速さに裏付けされた高いUXと、開発しやすさを両立しているのが特徴です。
本書では、Next.jsの開発をより快適・堅牢にするTypeScriptで開発を進めます。
Next.jsによるアプリケーション開発の基礎、最新のフロントエンドやWebアプリケーションの開発方法が学べます。

- Webデザイナーの仕事を楽にする!gulpではじめるWeb制作ワークフロー入門
- 中村勇希
- シーアンドアール研究所
- ¥3762
- 2018年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 救急画像診断のロジック
- 長谷智也
- 日本医事新報社
- ¥6380
- 2023年07月23日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
レジデント必読! 見逃し症例から学ぶER画像の読み方
研修医相手に開いている勉強会でみんながよく見逃す症例や、ERで誤診された症例などについて、どうやったら診断できたのか、あるいは診断できなかったのならdispositionはどうすべきか、などあれやこれやと考えてみました。(まえがきより)
第1章 外傷・ショック〈11症例〉
第2章 熱源検索〈17症例〉
第3章 頭痛・頚部痛・意識障害〈13症例〉
第4章 胸痛・呼吸苦〈11症例〉
第5章 腹痛・その他〈13症例〉
(B5判2色刷344ページ・電子版付き)
★CT・MRIの連続スライスを動画として収録。紙面のQRコードからアクセスできます。
★無料の電子版が付属。巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます。
第1章 外傷・ショック
Case 00 肝損傷
Case 01 大動脈損傷
Case 02 腸管損傷
Case 03 脾損傷後、仮性動脈瘤からの再出血
Case 04 横隔膜損傷、腸管および腸間膜損傷
Case 05 肝細胞癌破裂
Case 06 網嚢内出血
Case 07 頭部外傷+臀部血腫
Case 08 左卵管妊娠破裂
Case 09 特発性腸腰筋血腫
Case 10 無気肺+肝性胸水
第2章 熱源検索
Case 01-1 結石性腎盂腎炎
Case 01-2 腎外腎盂
Case 01-2' 傍腎盂嚢胞
Case 01-3 腎盂外尿溢流
Case 02 気腫性膀胱炎
Case 03 腸腰筋膿瘍
Case 04 肝膿瘍
Case 05 膿胸
Case 06 S状結腸穿孔
Case 07 特発性気腹症、腸管嚢胞様気腫症
Case 08 浣腸による直腸穿孔
Case 09 フルニエ壊疽
Case 10 放線菌症
Case 11 感染性心内膜炎
Case 12 子宮留膿腫
Case 13 前立腺膿瘍
Case 14 腸骨静脈圧迫症候群、深部静脈血栓症、肺塞栓
第3章 頭痛・頚部痛・意識障害
Case 01 脳動脈瘤破裂+脳実質内血腫
Case 02 単純ヘルペス脳炎
Case 03 脳静脈洞血栓症
Case 04 頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血
Case 05 RCVS(reversible cerebral vasoconstriction syndrome)
Case 06 両側椎骨動脈解離
Case 07 頚髄硬膜外血腫
Case 08 Crowned dens syndrome
Case 09 石灰化頚長筋腱炎
Case 10 脳脊髄液減少症
Case 11 鼻性眼窩内合併症
Case 12 脳室炎
Case 13 門脈大循環短絡路による猪瀬型脳症
第4章 胸痛・呼吸苦
Case 01 肋骨骨折
Case 02-1 特発性縦隔気腫
Case 02-2 食道破裂
Case 03 PTP誤飲
Case 04-1 大動脈解離
Case 04-2 大動脈解離(Stanford A型、偽腔開存)
Case 05 急性好酸球性肺炎
Case 06 左MCA閉塞による超急性期脳梗塞とそれに伴う神経原性肺水腫
Case 07 直腸癌に伴う癌性リンパ管症
Case 08 粟粒結核
Case 09 PTTM(pulmonary tumor thrombotic microangiopathy)
第5章 腹痛・その他
Case 01 腹部大動脈瘤切迫破裂
Case 02 大動脈解離
Case 03 総腸骨動脈閉塞
Case 04 S状結腸穿孔
Case 05 副腎静脈血栓症
Case 06-1 腎盂腎炎
Case 06-2 十二指腸穿通
Case 07 特発性腸間膜動脈瘤破裂
Case 08 虫垂炎穿孔
Case 09-1 内膜症性嚢胞破裂
Case 09-2 横隔膜損傷、脾損傷、腸間膜損傷
Case 10 鼡径ヘルニア自然整復後+Nuck管水腫
Case 11 大動脈解離(Stanford A型)、心タンポナーデ
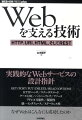
- Webを支える技術
- 山本陽平
- 技術評論社
- ¥2827
- 2010年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.95(95)
本書のテーマはWebサービスの実践的な設計。まず良いWebサービス設計の第一歩として、HTTPやURI、HTMLなどの仕様を歴史や設計思想を織り交ぜて解説。そしてWebサービスにおける設計課題、たとえば望ましいURI、HTTPメソッドの使い分け、クライアントとサーバの役割分担、設計プロセスなどについて、現時点でのベストプラクティスを紹介。

- 2023年度版 わかる!!わかる!!わかる!!SPI&WEBテスト
- 新星出版社編集部
- 新星出版社
- ¥715
- 2021年01月08日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
頻出「推論」問題を増やしパワーアップ!3色刷り、赤シートつきで見やすく、直前対策にも最適!様々なテスト形式が出ている中、今だ主流のSPI問題集をコンパクトにまとめた。苦手な人が多い非言語問題の分量を多く掲載。また、WEBテストについても解説した。ハンディータイプで試験直前の確認、携帯して空き時間に進めるのにも最適な一冊。

- 100%成果が出るウェブ集客の成功法則
- 神山有史
- セルバ出版
- ¥1760
- 2017年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、中小企業を対象に、ウェブを活用して理想的な見込客を継続的に獲得するための、成果に直結するノウハウを解説。

- 新・彼女は食いしん坊!(1)2訂新版
- 藤田裕二
- 朝日出版社
- ¥2640
- 2013年01月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 地理統計Plus-Web GIS付きー(2022年版)
- 帝国書院
- ¥699
- 2022年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
★ 帝国書院の『地理統計』に情報をPlus!さらに詳しく、便利にパワーアップした統計資料!
・デジタルコンテンツ「統計見えマップ」を使って、約600項目の統計データをWebGISで地図化し、統計データを視覚的に捉えることができます。
・複数の統計データの重ね合わせやベースマップの変更も可能で、情報活用能力の育成につながります。体験版はこちらから!
・後半の「国旗解説・国別資料編」では、197か国の国旗の由来や国別基礎資料を掲載し、前半の統計資料部分で気になった国について、地誌的な情報も併せて確認ができます。

- 【POD】Web技術速習テキスト 実践編
- 田中 賢一郎
- インプレスR&D
- ¥2420
- 2019年08月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は2019年7月インプレスR&Dより刊行した『Web技術速習テキスト』の続編で、実際にWebアプリを作成する「実践編」です。
Web関連技術の進歩は目覚ましいものがあります。クラウドファーストという言葉があるように、クラウド前提のシステム開発が一般的になってきました。
本書では前著『Web技術速習テキスト』を読み終えた方を対象に、Vue.js、Vuetifyなどのフレームワーク、Firebaseなどを使って、Webアプリを作って実際にクラウド上で動かしてみます。Webアプリの範囲は膨大なのですべての範囲を深くカバーすることはできませんが、慣れ親しむきっかけになればと思っています。