多様性 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 541 から 560 件目(100 頁中 28 頁目) 

- ナマコを歩く
- 赤嶺淳
- 新泉社
- ¥2860
- 2010年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
水産資源の減少と利用規制が議論されるなか、ナマコをめぐるエコ・ポリティクスを追う。グローバルな生産・流通・消費の現場を歩き、資源利用者が育んできた固有の文化をいかに守り、地球主体の資源管理を展望できるのかを考えた。

- ダイバーシティ・マネジメント入門
- 尾崎 俊哉
- ナカニシヤ出版
- ¥2420
- 2017年03月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
1 ダイバーシティ・マネジメント
--経営者の関心の高まり
2 歴史と現状、ダイバーシティ・マネジメントのルーツ(1)
--差別、異文化マネジメント
3 歴史と現状、ダイバーシティ・マネジメントのルーツ(2)
--競争力の再構築
4 人材の登用と企業の業績
5 「同一財」をめぐるダイバーシティ・マネジメントと企業業績
6 統計的差別
7 「多数財」をめぐるダイバーシティ・マネジメントと企業業績
8 組織能力ーーまとめにかえて
参考文献
あとがき
索引〔人名/事項〕

- 栽培植物の進化
- ギディアン・ラディジンスキー/藤巻宏
- 農山漁村文化協会
- ¥3666
- 2000年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、エルサレムのヘブライ大学農学部で行なわれた「作物の進化について」の講義を元にして書いたものである。近年は、作物と野生種の交配を意識的に行なうようになり、各種の遺伝資源が作出されている。栽培のもとでの進化の大きな要因の一つに遺伝的浮動があり、経済的に重要視されない形質、つまりDNAマーカーなどの多様性は、野生種に比較して栽培種には少ない。栽培のもとでの進化は、人と自然の成せる業であり、作物ごとに進化の特徴がみられる。ある作物は、植物学上の「科」の一員にすぎず、多くの作物がそれぞれの「科」に属し、それらが人類に豊かな食料資源を提供している。ある作物は、発祥の地域を中心とした小さな領域で、またある作物は広い地域で順化(栽培化)され広く拡散している。人とかかわる利用の面でも、ある作物は一つの目的のために、またある作物は多様な目的により開発され利用されている。進化・改良の過程では、あるものは形態的・生理的に激しい変化を受けたものもあれば、いまだに祖先種とあまり変わらないものもある。本書では、このような栽培に伴う植物進化の主要な側面を、7章に分け記述している。

- 日本の危機言語
- 呉人恵
- 北海道大学出版会
- ¥3520
- 2011年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 奄美群島の自然史学
- 水田拓
- 東海大学出版部
- ¥4950
- 2016年02月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
日本の「辺境」といってもよい亜熱帯島嶼域、奄美群島は、世界に誇るべき生物多様性を有する生物学者にとっての“約束の地”だ。「奄美・琉球」の名で世界自然遺産登録を目指すこの地から、最前線の自然史研究の成果を発信。

- アゲハチョウの世界
- 吉川 寛/海野 和男
- 平凡社
- ¥3740
- 2018年09月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
食草選択と擬態の謎にせまる。約150種の美しいアゲハチョウが見せる多様性ワールド。

- 生物多様性とは何か
- 井田 徹治
- 岩波書店
- ¥990
- 2010年06月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(24)
クロマグロの大量消費は何が問題なのか?人類を養う絶妙な生物ネットワークの破壊が進んでおり、生物多様性条約もその歯止めになっていない。今なすべきことは何なのか。世界で最も多様性に富み、脅威にさらされているホットスポットの現状と、保全のための新しい仕組みをレポートし、人間と自然との関係修復を訴える。

- どんぐりの生物学
- 原 正利
- 京都大学学術出版会
- ¥2200
- 2019年04月08日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
どんぐりは、ブナ科の植物が着ける果実である。ブナ科が作る森は、北半球の温帯から亜熱帯、熱帯まで様々な環境下に広がり、どんぐりの形や生態も多様性に富んでいる。本書は、古植物学や分類学、形態学、生態学など様々な側面から、どんぐりとは何か?を検証し、昆虫や動物、菌類など様々な生物と関係しながら進化してきた、その特性を明らかにする。どんぐりについて知ることは、森の生態系について知ることでもある。
口 絵
はじめに
第I章 ブナ科植物の誕生と分化
1 白亜紀後期ーブナ科植物の誕生
2 古第三紀ーブナ科植物の多様化と現生属の出現
3 新第三紀ー気候の寒冷化に伴う針葉樹・落葉樹混交林の拡大とブナ科フロラの変遷
4 化石から見たどんぐりと動物との共進化
コラム1 世界最大のどんぐりは?
第II章 ブナ科植物の多様性
1 ブナ科植物の分類
2 多様性の地理的パターン
3 日本列島における多様性の特徴
4 各属の分布と分類
コラム2 奇妙などんぐり
第III章 どんぐりの形態学
1 果皮とへその構造
2 種子の構造
3 花の形
4 奇妙な受精過程
5 複雑な花序
6 送粉様式
7 子房の成長ー果実へ
8 殻斗の起源
9 花序殻斗と花殻斗
10 ブナ科の系統と殻斗の進化
11 果実の散布
第IV章 ブナ科植物の芽生え
1 実生の多様性
2 地上子葉性と地下子葉性
3 実生の形態
4 発芽
5 地上茎の伸長
6 実生の初期成長戦略
コラム3 へそから根を出すどんぐり
第V章 どんぐりと昆虫
1 どんぐりと昆虫の密接な関係
2 虫えい形成昆虫
3 どんぐりを食べる鱗翅目昆虫ー蛾の仲間
4 どんぐりを食べる鞘翅目昆虫ーゾウムシとキクイムシ
5 ブナ科の属ごとに見た堅果食昆虫相の特徴
第VI章 どんぐりと哺乳類・鳥類
1 分散貯蔵散布
2 物理的防御
3 化学的防御
4 タンニン
5 タンニンの影響とげっ歯類の対抗戦略
6 物理的防御と化学的防御のトレードオフ
7 堅果の散布をめぐる植物と哺乳類の戦略的駆け引き
8 マスティングと昆虫・小型哺乳類
9 どんぐりと中・大型哺乳類
10 どんぐりと鳥類
11 哺乳類や鳥類による種子散布距離
コラム4 ところ変われば大きさも変わる -どんぐりのサイズの地理的クラインー
VII章 ブナ科植物と菌類
1 病原菌
2 菌根菌
3 外生菌根菌とブナ科植物の共生
4 菌根ネットワーク
5 樹木の実生再生と菌類
6 植生における“科の優占”と菌類
第VIII章 ブナ科植物の分布と植生
1 ブナ科植物と植生群系
2 南アジアの熱帯におけるブナ科植物の植物地理
3 タイ北部インタノン山における植生の垂直分布
4 タイ北部インタノン山におけるブナ科植物の垂直分布
5 ボルネオ島の植生
6 ボルネオ島におけるブナ科植物の垂直分布
コラム5 南西諸島の森とブナ科の植物
用語解説
引用文献
索 引

- カロテノイド
- 高市 真一/三室 守/富田 純史
- 裳華房
- ¥4400
- 2006年03月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
自然界を彩る色素の中でカロテノイドが占める割合は非常に多く、多種多様である。植物の光合成や動物の視覚に必要不可欠であるほか、活性酸素を消去したり、がん(腫瘍)を抑制したり、免疫の働きを高めたりするなど、さまざまな機能が注目されており、現在まで、天然から750種類以上のカロテノイドが単離され、構造決定されている。
本書は、動物、植物、微生物等におけるカロテノイドのさまざまな機能と生理活性を中心に、基礎的な反応機構や天然での分布、分離・分析方法までをわかりやすく記述したカロテノイド全般にわたる入門書である。
本書に出てくるカロテノイドにはすべて統一番号を記載し、巻末にその名称と構造式を一覧にすることで、読者の便宜を図った。また、命名法やおもなカロテノイドの吸収スペクトル、参考書籍や関連ホームページの紹介、市販品の一覧、各種の索引など、付録も充実させた。
本書の姉妹書に『クロロフィル -構造・反応・機能ー』(三室 守 編集)がある。
1.カロテノイド
2.植物における機能と生理活性
3.動物における機能と生理活性
4.生合成経路とその遺伝子
5.分離・分析方法

- 言語の多様性から複言語教育へ
- 欧州評議会/山本冴里
- くろしお出版
- ¥2420
- 2016年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)

- 生き物たちのつづれ織り(上)
- 井上敬/高井正成
- 京都大学学術出版会
- ¥2750
- 2012年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
脈々と連なる遺伝子の川を縦糸に、多様に枝分かれした生き物たちの関わり合いを横糸に、実験室とフィールドワークの出会いが織りなす知のタペストリー。動物学・植物学・生物物理学など、対象も手法も異なる多彩な研究の結びつきから浮かび上がってくる生物界の全体像を鮮やかに描き出す。

- 困っている子の育ちを支えるヒント
- 井澗 知美
- ミネルヴァ書房
- ¥2420
- 2018年09月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「困った子」といわれる子どもの大半は「困っている子」ともいえる。本書は、子どもにとって一番身近な存在であり、また「困っている」大人でもある親に対して、発達はそもそもどんな子どもであっても多様であることを優しく解説。そのなかで発達障害に凸凹のある子どもを理解し、支援する方法を、ペアレント・トレーニングを使って具体的に紹介。保護者と子が困り感を一人で抱え込まないためのスキルを紹介する。
はじめに
第1章 発達は多様である
1-1.「みんな違って みんないい」?
1-2.かけがえのない存在である「わたし」
1-3.社会に適応すること
1-4.うちの子,もんだい?
1-5.発達とそれをささえるもの
1-6.発達障害とは?
【コラム】 診断は何のために?
1-7.発達の多面性
1-8.発達をみていくための3つの軸
1-9.特性と脳の問題
1-10.障害か個性か
1-11.平等? 公平?
第2章 困っている子を支援するためのヒント
2-1.「困った子」ではなく「困っている子」
【コラム】 アセスメントとは?
2-2.私たちは同じものを見聞きしているのだろうか?
2-3.子どもの特性を理解する
【コラム】 前庭覚・固有覚
2-4.行動を観察する
2-5.行動の背後にある特性をつかもうーー氷山モデル
2-6.ペアレント・トレーニングって何だろう
【コラム】 氷山モデルとは
第3章 ペアレント・トレーニングで学ぶスキルを試してみよう 基礎編
3-1.行動を3つに分ける
3-2.ポジティブな注目をする
【コラム】 ほめることと文化
3-3.ポジティブな注目をしようーーほめ方のコツ
3-4.注目のつかい分けをする
3-5.「スペシャルタイム」というスペシャルな技
3-6.指示の工夫をする
「ほめる」をめぐるQ&A
これまでの復習
第4章 ペアレント・トレーニングで学ぶスキルを試してみよう 応用編
4-1.ペナルティの考え方
【コラム】 ルールのカテゴリー
【コラム】 機能分析をしよう
4-2.ペナルティの上手なつかい方
【コラム】 間違えること≠悪いこと
4-3.「行動チャート」を活用する
4-4.支援の目的は何か?
第5章 社会のなかで育つ子どもーー「孤育て」にならないために
5-1.人と人の間で育つ子どもの心
5-2.「こころ」の在りようはそれぞれの関係のなかに
【コラム】 社会化の土台としての信頼感
5-3.育てにくい子どもを育てる親の困難さ
5-4.子育てに必要な3つのゆとり
5-5.孤立感の分析ーー保護者へのインタビューから
【コラム】 ライフスキルを身につけよう
5-6.多様性のなかで学ぶーー映画『みんなの学校』から
【コラム】 人に迷惑をかけてはいけない?
5-7.学校と家庭の連携
5-8.いろいろな人がいるのが普通の社会
参考文献
おわりに

- 進化38億年の偶然と必然
- 長谷川政美
- 国書刊行会
- ¥4180
- 2020年10月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
強いものが勝つとは限らない。運も重要であるーー
世界的な分子系統学者が着目する「進化」の最重要トピックス。
文系と理系の枠を超えて「進化」を読み解く!
今世紀に入って、科学分野は比べものにならないほどの精度と分析能力で発展してきた。日進月歩に新知見が登場し、それらを結びつけた、深く広い「進化の歴史」が語られようとしている。それが本書である。
アリストテレスの「生命の階段」からはじまり、ダーウィンの『種の起源』が革命を起こした、進化にまつわる仮説の数々。
分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを、探求の道をともに歩んだ研究者たちとのエピソードを交え、生物学的な空間、大陸移動など地球科学的な時間軸の絡みあいのなかにつむぐ、38億年の壮大な「進化」のストーリー! カラー口絵8頁添。
◎漂流する大陸と生物の進化
◎進化発生生物学「エボデボ」
◎エピジェネティックス ほか
はじめに
第1章進化論の歴史
1・1「自然の階段」から「生命の樹」へ
1・2リンネの階層分類
1・3キュヴィエの新しい分類
1・4共通祖先からの進化
1・5偶然性の重視
1・6自然選択の現場
1・7なぜ多様な種が進化したか?
1・8分子系統学の登場
第2章進化と地理的分布
2・1ウォーレスの進化論
2・2ウォーレスのマレー諸島探検
2・3ペンギンはなぜ北極にいないのか
2・4ホッキョクグマの分布
2・5漂流する大陸と生物の進化
2・6大陸移動説の拒絶と受容
2・7大陸分断による種分化
2・8海を超えた移住
2・9古顎類の進化
第3章進化と発生
3・1発生と進化
3・2繰り返し要素の個性化と多様な形態の進化
3・3表現型の可塑性
3・4ジャンクDNA
3・5少ない遺伝子
3・6ヘモグロビンにおける調節
3・7エピジェネティックス
3・8獲得形質は遺伝するか
3・9美しいオス
3・10性選択はどのように働くか
第4章すべての生き物の共通祖先
4・1生命の誕生
4・2すべての生き物の共通祖先LUCA
4・3古細菌と真核生物を結ぶ失われた鎖
4・4真核生物の起源についての「水素仮説」
4・5地球生物の2大分類群
4・6細胞核の起源
第5章絶滅と進化
5・1絶滅
5・2凍りついた地球
5・3全球凍結後の生物進化
5・4カンブリア爆発
5・5生命の陸上への進出
5・6哺乳類型爬虫類の絶滅と恐竜の台頭
5・7多様な菌類の進化
5・8分解者を食べる変形菌の進化
第6章恐竜の世界から哺乳類、ヒトの世界へ
6・1中生代の世界とその終焉
6・2非鳥恐竜の衰退
6・3哺乳類の台頭
6・4小さな生物が担う多様性
6・5鳥類の台頭と翼竜の衰退
6・6大量絶滅からの再出発
6・7ホモ・サピエンスの進化
6・8脳の進化
6・9ヒトの多様な脳
おわりに

- ゲイの可視化を読む
- 黒岩裕市
- 晃洋書房
- ¥1980
- 2016年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 「無理しない」観光
- 福井 一喜
- ミネルヴァ書房
- ¥3080
- 2022年02月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(3)
これから私たちは、どんな観光をめざせばよいのだろうか。無理な町おこしやオーバーツーリズム、いきすぎた観光投資……。観光の問題は、現代社会そのものの矛盾と結びついている。本書は社会を広くとらえる視点から、「無理しない」をテーマに、地域を守る新しい観光のあり方を提言する。
はじめに
序 章 なぜ「みんな幸せ」になれなかったのかーー観光をめぐる理想と現実
1 「観光で日本と地域を再生しよう」
2 観光で経済を活性化させる方法
3 観光へのいらだちとみんなの「自助努力」
4 「無理しない」観光論
第1部 観光で稼ぐのは難しいーー観光による経済成長の限界
第一章 高級ホテルの従業員は高級ホテルに泊まれる?--観光する人/される人に生じる格差
1 買う者と買われる者の格差
2 「観光立国」とはなんなのか
3 観光で経済が活性化したのはどこのだれか?
4 観光による格差の再生産
第二章 今日の空室は明日売れないーー観光が格差を悪化させるのはなぜか?
1 「腹が空いているのは現在である。明日の馳走では間に合わない」
2 「今日の空室」は明日売れないし、「人間にしかできない仕事」は、儲からない
3 「人気の地域」がみんな持っていく
4 観光で得をするのはどこのだれか?
第三章 予約サイトに一割持っていかれるーープラットフォームビジネスの限界
1 観光のデジタル化とプラットフォームビジネス
2 デジタル化は観光地になにをもたらす?
3 「フローの空間」の支配構造
4 必然としてのプラットフォーム化とデジタル化の限界
第2部 観光と地域の多様性と自由を生かすーー「無理しない」観光のかたち
第四章 すべての地域が「観光地」をめざすべきなのか?--地域をめぐる政治と自由を再考する
1 観光で自治体の財政難は解決できるか?
2 観光政策論の「自助努力」という精神
3 数によるガバナンス
4 すべての地域が「観光地」をめざすべきなのか?
第五章 無理な町おこしはしなくていいーーローカルな限定性を生かす
1 観光地の「もともと」を考えてみる
2 あらためて、観光とはなにか?
3 むしろ観光がITビジネスを支える
4 「ローカルな限定性」を生かす
第六章 暮らしやすさを保つ、国土を守るーー消費されない観光をめざして
1 観光は「暮らしやすい地域」を作る
2 観光は文化を守るーー暮らしやすさとオーセンティシティ、価値観の多様化
3 観光は国土を守るーー災害、水資源、安全保障
4 消費されない観光をめざす
終 章 これからめざす「無理しない」観光のかたちーー価値と多様性を再考する
1 パンデミックが暴いてしまったこと
2 地域と観光をめぐる「構造的不正義」
3 地域の責任と自由を考える
4 「無理しない観光」から、「無理しない社会」へ
おわりに
参考文献

- チームのことだけ、考えた。
- 青野慶久
- ダイヤモンド社
- ¥1650
- 2015年12月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.28(80)
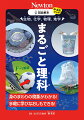
- 超絵解本 生物、化学、物理、地学 まるごと理科
- 縣秀彦
- ニュートンプレス
- ¥1479
- 2024年02月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
自然科学系の学科のことを「理科」といいます。多くの人は,中学校や高校で,「生物」「化学」「物理」「地学」の,四つの分野を学んだのではないでしょうか。
中学校や高校で理科を学ぶのには,理由があります。それは,理科の知識を「教養」として身につけることで,自然界のさまざまなしくみやルールがわかるようになるからです。そして,単に知識がふえるだけではなく,物事を科学的に考えられるようになります。SNSやインターネット上の情報を簡単に信じこまず,疑問に感じたことをきちんと調べ,検証するくせを早いうちにつけておくと,その後の人生にきっと役立つでしょう。
さらに,理科は最先端の科学の基礎にもなります。中高で学習する理科の知識を正しく身につけることで,世の中の見え方が変わってくることでしょう。
この本は,中学校と高校で学ぶ理科の重要項目を,1冊に凝縮したものです。1章で「生物」,2章で「化学」,3章で「物理」,4章で「地学」を紹介していますが,どの章から読んでも大丈夫! 好きなところから読み進め,大いに楽しんでください。

- 未来につなごう身近ないのち
- 中山れいこ/中井克樹
- くろしお出版
- ¥2090
- 2010年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
写真をしのぐ迫力のイラスト。自然な環境写真により生息環境をリアルに表現した画期的図鑑。命の歴史からビオトープの試み、自然の保護、外来生物問題まで、小学生も大人も楽しみながら学べる。

- 基礎から学ぶ遺伝看護学
- 中込 さと子/西垣 昌和/渡邉 淳
- 羊土社
- ¥2640
- 2019年01月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
遺伝学を基礎から学べ,周産期・母性・小児・成人・がん…と様々な領域での看護実践にダイレクトにつながる,卒前・卒後教育用の教科書.遺伝医療/ゲノム医療の普及が進むこれからの時代の看護に必携の一冊.

- よくわかる観光社会学
- 安村克己/堀野正人
- ミネルヴァ書房
- ¥2860
- 2011年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)