性感染症 の検索結果 ベストセラー 順 約 1720 件中 41 から 60 件目(86 頁中 3 頁目) 

- 臨床微生物検査ハンドブック第5版
- 小栗豊子
- 三輪書店
- ¥5500
- 2017年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
新項目として寄生虫検査を追加!検査材料別検査法を見直し、検出菌の表を充実!薬剤耐性菌のメカニズムおよびその検査法のUpdate!抗菌薬の体内動態についてわかりやすく解説!微生物検査の基本操作、アウトブレイクの定義を追加!学生さんにも臨床家にも使いやすい、必携の1冊。

- 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック第2版
- 落合慈之/渋谷祐子/志賀淑之
- 学研メディカル秀潤社
- ¥4180
- 2017年09月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
好評シリーズの大改訂版.写真・イラスト・図表をさらに充実させ,最新の医療現場に即して疾患の概念や検査・治療などの記載をアップデートした.医師,看護師ほかのメディカルスタッフ,またそれを目指す人のための決定版ビジュアルテキスト.

- 慢性期医療のすべて
- 武久 洋三/武久 敬洋/北河 宏之
- メジカルビュー社
- ¥7700
- 2017年10月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
超高齢社会を迎えているわが国では,慢性期医療のニーズは高まるばかりである。しかしながら,実際はほとんどの医師が急性期病院で卒後研修を行うため,慢性期医療に詳しい医師は非常に少ない。この状況を打破するべく,慢性期病院として全国に27病院を傘下にもつ平成医療福祉グループのノウハウを詰め込み,慢性期医療のすべてを網羅した教科書として刊行するのが本書である。
急性期病院では完治を目指して検査や治療を行うが,慢性期病院では高齢患者に対する栄養管理,QOLの保持,合併症の対応などが行われる。また,高齢者特有の感染症や認知症などについての知識も要求される。実際の慢性期医療現場で要求されるのは,既存の教科書にあるような老年医療の理論ではなく,より実践的なノウハウである。
「診療」「リハビリテーション」「看護,介護」「薬剤」「栄養」まで,慢性期医療のすべてをこの1冊でマスターしてほしい。

- 股関節・骨盤の画像診断
- 川原康弘
- メディカル・サイエンス・インターナショナ
- ¥8580
- 2017年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- あめいろぐ 予防医学
- 反田 篤志/青柳 有紀
- 丸善出版
- ¥3850
- 2018年01月26日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
日本とアメリカの臨床を経験した若きエキスパートの猛者が「米国のここがスゴイ」「日本のここがいただけない」「米国のここはどうか…」「日本のここは際立っている」比較文化論的な視野から、あなたの臨床に役立つ本音ベースのノウハウを語ります。

- ジェネラリストのための性感染症入門
- 谷崎隆太郎
- 文光堂
- ¥3300
- 2018年04月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 胸部のCT
- 村田 喜代史/上甲 剛/村山 貞之/酒井 文和
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- ¥16500
- 2018年04月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
胸部CT診断の基準となる包括的テキストのベスト&ロングセラー、7年ぶりの改訂。
胸部領域の新しい疾患概念や、肺癌のTMN分類、組織分類、癌取り扱い規約の改訂などを踏まえ、画像、記述内容ともに全面的にアップデート。臨床の現場で役立つ教科書を目指し、より疾患の解説に重点を置く構成となった。放射線科のみならず、呼吸器内科・外科、一般内科の医師にとっての必読・必備書。
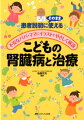
- こどもの腎臓病と治療
- 後藤 芳充
- メディカ出版
- ¥2640
- 2018年07月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
腎臓病と診断されたこどもや家族の不安を少しでも和らげるために、病気について理解できるように、イラストを中心にやさしく解説した本。いろいろな種類の腎臓病があることや、最新の治療法について、ていねいに解説。患者説明にそのまま使うこともできる。

- 糖尿病療養指導士に知ってほしい歯科のこと
- 西田亙
- 医歯薬出版
- ¥3080
- 2018年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
歯の本数が命に関わる!?日本糖尿病学会が患者に歯周治療を勧めるワケから話題の医科歯科連携まで全国講演に引っ張りだこの内科医がやさしく教えます!「目からうろこ」の糖尿病と歯科のこと。

- 極論で語る消化器内科
- 小林 健二/香坂 俊
- 丸善出版
- ¥3850
- 2018年10月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
消化器内科といえば 研修医の鉄板中の鉄板ともいえる。
すぐに内視鏡を依頼あるいは胃薬の処方でその場をしのいでいないだろうか。
できる内科医になるために、内科系疾患で最も頻度の高い消化管や肝胆膵疾患を診る必要がある。
本書では便秘、下痢にはじまり、消化性潰瘍、胃食道逆流症、機能性ディスペプシアの対処法や各種検査の捉え方もわかりやすく解説。

- 病気がみえる(vol.6)
- 医療情報科学研究所
- メディック メディア
- ¥3850
- 2018年09月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(6)
免疫・膠原病・感染症すべてを1冊に凝縮!
分かりやすいイラスト・画像で基礎から徹底的に解説。
『病気がみえるvol.6免疫・膠原病・感染症』に待望の第2版が登場!
主な改訂ポイントは以下の通りです。
●約20疾患を加えて88ページの増量!
初版では記載がなかった「自己炎症性疾患」や「IgG4関連疾患」、「劇症型A群レンサ球菌感染症」など約20疾患を追加しました。
●初版収録の総論・疾患も大幅に改訂!
「感染症」、「抗菌薬」、「アレルギー」などの総論を全面的に刷新。
「SLE」、「結核」、「HIV感染症」などの疾患も、病態生理から検査・治療まで記載をさらに充実させました。
●最新の診療ガイドライン・指針を反映!
初版発行(2009年11月)以降に公開・改訂された診療ガイドライン・指針をはじめ、免疫疾患・膠原病・感染症領域の進歩を反映し、内容を最新化しました。

- これならわかる! 整形外科の看護ケア
- 松本守雄/瀬戸美奈子
- ナツメ社
- ¥3300
- 2019年03月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
整形外科看護の基礎となる必須疾患・病態を部位別に網羅。原因とメカニズム、症状、検査・診断、治療法まで流れにそって、わかりやすく解説しました。写真やイラストも豊富に掲載しています。患者への対処のポイントや説明方法、医師からのアドバイスなど、役立つ情報も満載です。
巻頭口絵 ナースが知っておきたい運動器の機能解剖
第1章 整形外科疾患の診断とケア
第2章 外傷性疾患とケア
第3章 脊椎・脊髄疾患とケア
第4章 肩甲帯・肩疾患とケア
第5章 肘疾患とケア
第6章 手関節・手疾患とケア
第7章 骨盤・股関節疾患とケア
第8章 膝疾患とケア
第9章 足関節・即疾患とケア
第10章 神経・筋疾患とケア
第11章 循環障害・脈管疾患とケア
第12章 退行性・代謝性疾患とケア
第13章 整形外科的感染症とケア
第14章 リウマチ性疾患・類縁疾患とケア
第15章 骨・軟部腫瘍、腫瘍類似疾患とケア
第16章 小児の整形外科疾患とケア
第17章 周術期のケア
第18章 整形外科特有のケア

- 小児感染症のトリセツREMAKE
- 笠井 正志/伊藤 健太
- 金原出版
- ¥5940
- 2019年04月24日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
圧倒的な情報量で感染症を完全攻略!原典“Origin”。必要な情報を即検索!携帯に便利な要約版“Essence”。2冊セット。

- 新版 骨関節のX線診断
- 江原 茂
- 金原出版
- ¥13200
- 2019年09月27日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
骨軟部における単純X線撮影は,従来より簡便で有効な診断手段であり,画像診断において揺るがない地位を保っている。
さらに近年,コンピュータ断層撮影の知見のフィードバックにより,従来を越える深い病態の理解が可能になった。
本書では骨関節疾患の単純X線読影を,CT・MRIを交え,分かりやすく解説している。
また本書は,放射線科のみならず,整形外科,リウマチ科,小児科など幅広い読者を対象としている。

- 同種造血細胞移植後フォローアップ看護(改訂第2版)
- 日本造血細胞移植学会
- 南江堂
- ¥4620
- 2019年09月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
日本造血細胞移植学会編集による看護師向け公式テキストの改訂版.同種造血細胞移植をめぐる現状,移植後合併症の基礎知識,移植後の外来フォローアップにおいて必要な知識・技術を各分野のエキスパートが詳細かつわかりやすく解説.今改訂ではがん対策推進基本計画(第3期)への対応といった情報更新に加え,合併症重症例の写真を充実させた.
【はじめに】
1980年代の近代的移植の幕開けから、骨髄・さい帯血バンクの整備、移植法やその支持療法の目覚ましい進歩に支えられ、同種造血細胞移植は多くの難治性造血器疾患の根治療法として盛んに施行されてきた。そして、移植件数増加とともに多くの移植患者がより長期に生存するようになった。しかし、長期生存者が着実に増加する一方で、移植対象疾患の根治が得られても、社会復帰までには移植後後期合併症に伴う生活の質の低下、不妊、二次がん、復職・復学の問題など多くの課題が残されていることが明らかとなってきた。そして、移植後の治癒の可能性を拡大するだけでなく、その質をしっかりと担保するフォローアップ体制を構築することが不可欠であると広く認識されるようになった。
これを受けて2012年度の診療報酬の改定で、看護師を含むさまざまな職種の専門家による同種造血幹細胞移植患者の外来フォローアップ体制が「造血幹細胞移植後患者指導管理料」として算定されるようになった。この造血幹細胞移植後患者指導管理料の施設基準では、造血幹細胞移植に従事した経験を有し「移植医療にかかわる適切な研修」を修了した専任の常勤看護師の配置が求められ、日本造血細胞移植学会は、これまでの看護部会で行われた研修の質をさらに高めた「造血細胞移植後患者の外来におけるフォローアップにかかわる看護師」を対象とした研修会を開始した。この研修会は、単に施設要件を満たすための看護師研修ではなく、造血細胞移植後患者の外来でのフォローアップに継続的に加わり、そのさまざまな病態・問題に対して適切に指導・介入し、フォローアップの充実を図るとともに、医師の負担軽減にも貢献できる看護師を育成することを目的としたものである。
本書籍は、この研修会の教科書として、2014年3月に初版が発刊された。そして、2014年以降のわが国における移植後合併症、生活の質、社会復帰に関するエビデンスを盛り込み、その内容をより充実させたのがこの改訂版である。少子高齢化が進むわが国においては、完璧な社会復帰を目標とした移植医療体制を構築することが切に求められている。是非、各施設での移植後外来フォローアップの看護に本書を役立てていただければ幸いである。
2019年8月
岡本真一郎
高坂久美子
森文子
山花令子

- オーソモレキュラー医学入門
- エイブラム・ホッファー/アンドリュー・W・ソウル/中村篤史
- 論創社
- ¥5280
- 2019年10月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.57(7)
家庭の医学とメガビタミン療法
ノーベル賞受賞者の生化学者ライナス・ポーリング博士が唱えた「オーソモレキュラー〔=分子整合〕医学」。この革命的な新医学を牽引してきた2人の大家、A・ホッファーとA・W・ソウル両博士が、医師だけでなく一般読者に向けて書き上げた、栄養療法/メガビタミン療法の決定版!
〈本書で紹介する主な疾患/症例〉
消化器系障害、心血管系疾患(動脈硬化・静脈瘤、血管炎・脳卒中・糖尿病・心不全)、関節炎、各種の“がん”、精神・行動障害(アルツハイマー症、てんかん、統合失調症、うつ病、ADHD)、アレルギー、風邪その他の感染症、皮膚障害や老化……etc.

- 女性生殖器
- 苛原 稔/渡邊 浩子
- メディカ出版
- ¥2860
- 2019年12月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●女性生殖器の疾患の基本的な知識と看護を学ぶテキスト。
●女性のライフサイクルの変化に関連する疾患の予防など、女性の生涯の健康を守る視点を盛り込んでいる。
●最新の知見も踏まえ、臨床現場がリアルに感じられる。

- 見てわかる皮膚疾患 診察室におきたいアトラス
- 川田暁/佐藤貴浩
- 中外医学社
- ¥13200
- 2019年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
豊富で質の高い臨床写真による、最新かつ最良のアトラス。現場で見る皮膚疾患を幅広く網羅・解説!鮮明な写真は患者への説明にも便利。

- 点眼薬の選び方【電子版付】
- 石岡 みさき
- 日本医事新報社
- ¥3960
- 2020年02月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
鑑別診断上重要となる,全身投与薬の副作用が眼に出た場合について新規章を設けました。眼科の基本中の基本、点眼薬の選び方・使い方を懇切丁寧に解説。市販薬から,調剤が必要となるような処方薬までカバー。点眼アドヒアランスの上手な確認の仕方など,明日からの診療で真似してみたくなる具体的な診療のコツや工夫を紹介しています。
第1章 点眼薬の基礎
第2章 アレルギー性結膜疾患
第3章 結膜炎(感染性)
第4章 ものもらい
第5章 ドライアイ
第6章 角膜上皮疾患
第7章 眼瞼縁炎,眼瞼炎
第8章 緑内障
第9章 非感染性の眼表面の炎症
第10章 角膜感染症
第11章 白内障
第12章 周術期
第13章 眼精疲労
第14章 ぶどう膜炎
第15章 眼内炎(感染性)
第16章 点眼麻酔
第17章 散瞳薬・調節麻痺薬
第18章 ステロイド剤と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
第19章 全身投与薬の眼に出る副作用
COLUMN 「眼脂をディフ・クイック®で染色する方法」

- 薬名[語源]事典
- 阿部和穂
- 武蔵野大学出版会
- ¥7480
- 2020年03月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
その医薬品はなぜその名前になったのか?日本の医薬品1321点を網羅し、誕生した背景や特徴、エピソードなどから、その医薬品名の由来を解説しました。医療従事者にはもちろん、薬剤師国家試験対策にも活用できる事典です。
A・自律神経系に作用する薬
B・体性神経系に作用する薬
C・中枢神経系に作用する薬
D・抗炎症薬・抗アレルギー薬
E・循環器系に作用する薬
F・血液・造血器系に作用する薬
G・泌尿器系・生殖器系に作用する薬
H・呼吸器系に作用する薬
I・消化器系に作用する薬
J・感覚器系・皮膚に作用する薬
K・代謝系に作用する薬
L・内分泌系に作用する薬
M・抗悪性腫瘍薬・免疫抑制薬
N・感染症治療薬