性感染症 の検索結果 標準 順 約 1780 件中 581 から 600 件目(89 頁中 30 頁目) 

- プラネタリーヘルス
- Samuel Myers/Howard Frumkin/長崎大学/河野 茂
- 丸善出版
- ¥3520
- 2022年03月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
SDGsの先へ 地球規模の課題解決に向けて
地球上の環境変化は、時空間的に離れたところへ波及し、思いがけない影響を及ぼし合う。そこで、地球規模の課題をシステム全体にわたって捉えるために用いる概念がプラネタリーヘルスである。プラネタリーヘルスは、環境破壊が私たちの健康や幸福に及ぼす影響を理解し、数値化して、人間と自然とが将来にわたり継続できるよう解決策を生み出すことを目指す。本書では、気候変動、災害、汚染、生態系の現状と、それに起因する人間の感染症や様々な疾患、メンタルヘルス、さらには移民、紛争、人口、食料、公平性の問題、エネルギー、都市化、経済、幸福、倫理などの幅広い視点から、事例のつながりを浮き彫りにする。新型コロナウイルス感染症もまさにプラネタリーヘルスの課題といえ、エピローグで取り上げている。今と将来に生きる、人類とすべての生き物を含む地球全体の未来のため、分野を超えた考え方を学べる。

- 微生物学・感染症学(第3版)
- 塩田 澄子/黒田 照夫
- 化学同人
- ¥5940
- 2024年05月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は,薬学生に必要な微生物学・感染症学の基礎知識をわかりやすく簡潔に記述されている.微生物やウイルスの分類などはもちろん,感染症の特徴,感染経路,感染症の予防,薬物の作用機序などを解説する.新たに追加された感染症治療学には処方例が取りあげられており,学習に役立つ.また,将来学ぶ免疫学,ゲノム薬学,薬物治療学などの基礎としての役割も視野に入れてまとめられている.薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠.用語解説,コラム,章末問題付き.

- 中枢神経 (非腫瘍性疾患病理アトラス)
- 新井 信隆
- 文光堂
- ¥18700
- 2024年03月06日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
【神経病理診断に役立つ標準的かつ最新の情報と写真が満載.神経病理の決定版アトラス!】
病変の強弱や経時的な変化など,多彩な組織形態を見せる神経病理像は,捉えかたが難しく,診断に苦慮することも多い.
本書では精選された肉眼像や組織像を多数提示して,判断に役立つ所見や標準的な診断法をわかりやすく解説.
病理医をはじめ,法医や脳神経外科医等にとっての神経病理診断の道標となることを目指す.
変性疾患や感染症,外傷,てんかん,プリオン病等々,多様な神経疾患を網羅した,診断実務にも知識の整理にも役立つ決定版アトラス.
≪主要目次≫
第1部 総 論
1.大脳の切り出し・肉眼所見
2.脳幹・小脳の切り出し・肉眼所見
3.脊髄の切り出し・肉眼所見
4.神経染色法
5.神経病理実務の紹介
6.パラフィンブロックの研究活用
第2部 各 論
1.循環障害・血管病変
2.頭部外傷
3.感染症
4.変性疾患
5.脱髄疾患・髄鞘障害性疾患
6.脳形成異常
7.神経皮膚症候群
8.てんかん
9.プリオン病
10.中毒・代謝異常など
索 引

- ジェネラリストのための高齢者画像診断
- 小橋由紋子
- メディカル・サイエンス・インターナショナ
- ¥6050
- 2015年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 子どもの病気栄養管理・栄養指導ハンドブック
- 伊藤善也/武田英二
- 化学同人
- ¥8800
- 2012年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
子どもの病気、栄養指導、栄養管理について、臨床医学、栄養学の視点から捉えた本。各分野の精鋭である小児科専門医、看護師、管理栄養士たちによる執筆。

- 最新主要文献とガイドラインからみる 小児科学レビュー 2023
- 長谷川 奉延/加藤 元博
- 総合医学社
- ¥13200
- 2023年08月28日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
雑誌「小児科臨床」75巻4号〜76巻3号に掲載されたものをまとめた一冊。主に2021〜2022年に国内外で発表された論文・ガイドラインから、小児科学分野のエキスパートが主要文献をピックアップし、レビューしています。小児科領域全般の最新の研究成果や動向を把握するのに役立ちます。
1.救急医療 -特に,小児の緊急気管挿管についてー
2.感染症
(1) 細菌感染症
(2) ウイルス感染症
(3) 予防接種
3.循環器疾患
(1) 先天性心疾患
(2) 不整脈 -特に,カテコラミン誘発多形性心室頻拍(CPVT)の診断と治療ー
(3) 心筋症
4.消化器疾患
(1) 消化管疾患 -特に,潰瘍性大腸炎の診断・治療・ワクチン接種についてー
(2) 肝胆道疾患 -Fontan associated liver disease(FALD)の診断と管理ー
5.神経疾患
(1) てんかん
(2) 脳炎・脳症
6.神経筋疾患
7.血液疾患
(1) 貧血・骨髄不全
(2) 造血器腫瘍
(3) 血液凝固異常
8.固形腫瘍
9.腎尿路疾患
(1) ネフローゼ症候群
(2) 腎 炎
(3) 先天性腎尿路異常
(4) 尿細管機能異常症
10.水電解質異常
11.内分泌疾患
(1) 成長障害
(2) 性分化疾患
(3) 肥満・やせ
(4) 糖尿病
12.先天代謝異常
13.原発性免疫不全症
14.アレルギー疾患
(1) 消化管アレルギー
(2) 気管支喘息
(3) アトピー性皮膚炎
(4) アナフィラキシー
15.膠原病と類縁疾患
(1) 自己免疫疾患(膠原病)・リウマチ性疾患
(2) 川崎病
16.先天異常症候群
17.精神疾患・こころの問題
(1) 小児精神疾患
(2) 心身症
(3) 発達障害
18.新生児疾患
(1) 新生児感染症
(2) 慢性肺疾患
(3) 脳室周囲白質軟化症
(4) 新生児蘇生
19.児童虐待

- 医療スタッフのための 微生物検査のススメ
- 柳原克紀
- ヴァン メディカル
- ¥2530
- 2017年01月23日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●はじめに
1 感染症と微生物の関係
1 感染症の捉え方
2 微生物とその特徴
3 感染症と微生物を取り巻く環境
2 微生物検査の基本
1 微生物検査の重要性
2 微生物検査の対象者ー感染症を疑う時
3 微生物検査の種類ー検査の特徴とメリット・デメリット
3 微生物検査の臨床応用
1 臨床応用のための検査プロセス
1 検査のオーダーー検査内容の組み立て方
2 検査のタイミングー検査結果への影響
3 検査前や検査途中の情報収集ー結果が出る前でも得られる情報
4 臨床応用のためのコツ・工夫ー現場活用に備えた事前措置
5 検体の取り扱い方ー正しい採取・正しい保管
6 検査室の動きー検体の受け取りから結果報告まで
7 検査結果の報告ー結果の示され方
8 検査のフィードバックー検査結果はどう伝え、どう共有するか
9 検査過程における注意事項
10 外部委託による検査とその注意点
2 診断・治療への応用
1 原因微生物の推定ー検査結果の治療への影響
2 感染巣の判定
3 感受性検査結果の読み解き方ー耐性菌を見逃さないための注目ポイント
4 抗菌薬選択への活用ー『抗菌薬の適正使用』に向けて
5 2回目以降の微生物検査の活用ー経過観察における検査実施
3 感染対策への応用
1 検査結果の共有ーサーベイランスの活用
2 感染対策への応用と考え方
3 微生物検査の患者対応への活用と実際
4 感染源の特定と感染伝播遮断への活用ーアウトブレイクに際して
4 臨床応用の実際
1 薬剤感受性検査による診断確定例
2 抗体検査による診断確定例
3 遺伝子検査による診断確定例
4 抗菌薬選択への活用例1(de-escalationの実際)
5 抗菌薬選択への活用例2(系統変更)
5 微生物検査のこれから
● 感染症診療・院内感染対策における微生物検査のこれから

- 社会政策 第14巻第2号(通巻第42号)
- 社会政策学会
- ミネルヴァ書房
- ¥2750
- 2022年11月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本号では対人支援サービスの現場に着目した2つの小特集を収録する。小特集1では、従来対面的・非対面的コミュニケーションの機会を提供してきた社会福祉のサービスやツールがコロナ禍においてどのような機能を担ったかを検証する。小特集2は地方自治体が提供する相談支援サービスを取り上げ、その利用者たちの実態や、彼らがサービスをいかに評価しているかについて、具体的な把握を試みる。その他意欲的な研究論文を多数収録。
【巻頭言】「社会政策研究」の多義性とその軸(松丸和夫)
【小特集1】コロナ禍における社会福祉と「つながり」の諸相
〈小特集1趣旨〉小特集に寄せて(山田篤裕・菅野道生・原田玄機)
地域の生活支援体制における民生委員・児童委員の機能と役割:コロナ前後の活動変化に注目して(西村幸満 )
新型コロナウイルス感染症拡大下における障害者就労継続支援事業:事業所へのインタビューに見る生産活動および利用者の社会とのつながりへの影響(榊原賢二郎)
高齢者の社会的つながりとコロナ感染症の拡大:孤立の二層性(泉田信行)
【小特集2】自立相談支援窓口への来談者から見た豊中市の相談等サービス
〈小特集2趣旨〉小特集に寄せて:「断らない相談支援」の前線から見えてくること(櫻井純理)
「豊中市来談者調査」の狙いと分析枠組み(筒井美紀)
豊中市・自立相談支援窓口への来談者の特徴と支援サービスへの評価(長松奈美江・中越みずき)
行政サービスへの信頼感は何によってもたらされるのか?:後期近代における制度・政策評価の陥穽(阿部真大)
【投稿論文】
危機下における大量失業を防ぐ政策の展開:ドイツでの操業短縮手当の拡張(松本尚子)
地方自治体幹部職員のキャリアパスにおける男女格差:政令指定都市A市の事例から(佐藤直子)
スウェーデンにおけるLSS改革:政府と障害者団体の関係に焦点を当てて(福地潮人)
シングルマザーの公的年金制度加入に関する分析:関東圏A市における実態調査から(吉中季子)
【書評】
堺恵著『児童扶養手当制度の形成と展開:制度の推移と支給金額の決定過程』(評者:北 明美)
岩月真也著『教員の報酬制度と労使関係:労働力取引の日米比較』(評者:鷲谷 徹)
永野仁著『日本の高齢者就業:人材の定着と移動の実証分析』(評者:田口和雄)
宮本太郎著『貧困・介護・育児の政治:ベーシックアセットの福祉国家へ』(評者:金 成垣)
阿部誠著『地域で暮らせる雇用:地方圏の若者のキャリアを考える』(評者:吉村臨兵)
SUMMARY
学会関連資料

- 感染症999の謎
- 岩田健太郎
- メディカル・サイエンス・インターナショナ
- ¥5500
- 2010年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(4)

- 〜臨床・画像・病理を通して理解できる!〜呼吸器疾患:Clinical-Radiological-Pathologicalアプローチ
- 藤田 次郎/大朏 祐治
- 南江堂
- ¥11000
- 2017年04月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
呼吸器疾患の臨床所見(Clinical),画像所見(Radiological),病理所見(Pathological)の三者の統合(カンファレンス)を切り口としたテキスト.疾患の病態から鑑別診断の考え方,「どんな画像が見られ,病理から何がわかるか,CRPカンファレンスを通した総合的な診断と病態把握まで,実臨床における診断過程に沿った構成でまとめ,知っておくと役立つ治療戦略の考え方も随所に盛り込んだ.X線・CTの画像所見と病理所見を多数供覧しながら総合的な呼吸器診断が学べる若手医師に特におすすめの1冊.

- 小児神経学
- 加我牧子/稲垣真澄
- 診断と治療社
- ¥13200
- 2008年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- グローバル時代のウイルス感染症
- 西條政幸
- 日本医事新報社
- ¥6820
- 2019年01月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
エボラウイルス病、MERS、SFTS、狂犬病、ジカウイルス感染症、風疹、etc…国立感染症研究所ウイルス第一部・部長の西條政幸先生全面編集の下、グローバル時代に注意すべきウイルス感染症の知識をこの1冊にまとめました。

- サクセス管理栄養士・栄養士養成講座 食品衛生学 第8版
- 一般社団法人 全国栄養士養成施設協会/公益社団法人 日本栄養士会/植木幸英/阿部尚樹
- 第一出版
- ¥2090
- 2021年03月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●管理栄養士国家試験出題基準に沿って目次を立て、要点を簡潔に解説。
●大学・短大・専門学校など、管理栄養士・栄養士養成施設のテキストに最適です。
●管理栄養士を目指す方の参考書として、毎日の学習をサポート。
●図表を多数活用。視覚を通じて本文の流れがわかります。
●直近5回の管理栄養士国家試験で出題された語句や内容について、出題番号を併記。
●重要なキーワードを色つきで表記。解説を同ページ内に掲載し、スムーズな理解を助けます。
●コラムでは、知っておきたい知識について解説。
●各章末には、その章に関する復習問題を掲載しました。

- コメディカルのための専門基礎分野テキスト 内科学 改訂8版
- 北村 諭/坂東 政司
- 中外医学社
- ¥4180
- 2024年02月29日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
本書は著者らがコメディカルの教育に携わった経験をもとにこれらの学生・卒業者のために必要にして十分な内科学の知識を箇条書きと図表を中心にコンパクトにまとめたものである.ミニマムでありながら分かりやすい解説はそのままに,近年の変化やトピックスを加えた.基本を補強するとともに,最新の知識を学べる改訂8版.コメディカルスタッフ
の教育が重視されるなか,教育の現場で活用できる最適なテキストである.

- 新版 骨関節のX線診断
- 江原 茂
- 金原出版
- ¥13200
- 2019年09月27日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
骨軟部における単純X線撮影は,従来より簡便で有効な診断手段であり,画像診断において揺るがない地位を保っている。
さらに近年,コンピュータ断層撮影の知見のフィードバックにより,従来を越える深い病態の理解が可能になった。
本書では骨関節疾患の単純X線読影を,CT・MRIを交え,分かりやすく解説している。
また本書は,放射線科のみならず,整形外科,リウマチ科,小児科など幅広い読者を対象としている。

- わかる!できる!急変時ケア 第3版
- 中村美鈴
- 学研メディカル秀潤社
- ¥3080
- 2012年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
病棟で起こりやすい急変時の一連の流れをフローチャートで展開.援助内容の根拠を記載した.主な内容は,呼吸停止,心停止,心原性ショック,感染性ショック,急性胸痛,呼吸困難,急性腹症,急性頭痛,悪心・嘔吐,痙攣など20の急変事例を解説.

- 現場で役立つ小児救急アトラス
- 内山聖/安次嶺馨
- 西村書店(新潟)
- ¥4180
- 2009年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- アトラスさくま 小児咽頭所見 第2版
- 佐久間 孝久
- 丸善出版
- ¥16500
- 2025年11月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
高い知名度と評価を誇るアトラスを復刊!
著者の20年にわたる「小児咽頭所見に関する研究」の集大成。小児感染症診断の貴重なノウハウを鮮明なオリジナルオールカラーによる症例写真284点とともに収載。第15回日本外来小児科学会総会において「リサーチ賞」受賞など高い評価を受ける。
日々の診察の中からこれだけの事例が集められた書籍は他になく、貴重な資料であるとともに、日々の診断の助けとなるアトラスとなっている。
小児科医・内科医・耳鼻咽喉科医・研修医・指導医必携!
本書は,2005年8月に(株)メディカル情報センターより発行したものに,一部写真等の修正を加えて2008年3月に丸善プラネット(株)より発行された同名書籍を再出版したものです.
目次
1.アデノウイルス
2.エンテロウイルス
a. エコーウイルス/b. コクサッキーウイルスA群/c. エンテロウイルス71/d. コクサッキーウイルスB群/e. ポリオウイルス
3.単純ヘルペスウイルス1
4.インフルエンザウイルス
5.その他(咽頭に特徴のあるその他の疾患)
a. Epstein-Barr virus/b. 突発性発疹症
6.種々の発疹性疾患
a. 多形滲出性紅斑(1エコーウイルス/➁ヘルペスウイルス/3インフルエンザ)/b.川崎病/c.Gianotti-Crosti syndrome
7.麻疹
a. 麻疹/b. 麻疹ワクチン接種後の麻疹
8.古典的疾患
a. 流行性耳下腺炎 水痘/b. 風疹/c. 伝染性紅斑
9.マイコプラズマ
10.細菌感染症
a. A群レンサ球菌/b. インフルエンザ菌/c. 黄色ブドウ球菌/d. ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)
Ⅺ.腸管感染症
a. ロタウイルス/b. Small round structured virus
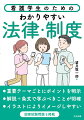
- 看護学生のためのわかりやすい法律・制度
- 望月聡一郎
- 中央法規出版
- ¥2860
- 2023年02月16日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
看護学生にとって苦手分野である法律・制度をとことんわかりやすく解説!
医療法から労働法規まで、看護教育で学ぶ関係法規を豊富なイラストと平易な文章で整理しました。
あわせて条文、過去の国家試験問題も収載し、入門書、サブテキストとして最適。国試対策にも活用できます!
「看護師に法律・制度は必要?」
医療や福祉といった社会保障は、さまざまな法律や制度に基づいています。
患者や利用者が治療や看護、介護を受けられるのも、そうした法律・制度があるからです。
また、看護師という国家資格自体も、法律によって決められているもの。
看護師として働き、看護ケアを提供することには、多くの法律がかかわっているのです。
「国家試験にも出題」
ある年の看護師国家試験で、なんらかの形で法律・制度が関係する出題が、240問中40問程度ありました。
医療や福祉には多くの法律が関係しているため、看護師になるためには幅広く法律・制度を押さえておく必要があります。
「キーワードを解説、関連条文、過去問題も掲載」
法律や制度を成り立ちからひも解くと長く複雑でわかりにくくなります。
本書では、今知りたい事柄やキーワードを取り上げて、ワンテーマでコンパクトに解説しているので、知りたい情報にすぐにアクセスできます。
しかも、関連する条文(法律の文章)は必要最低限にしているので、読むのも苦になりません。また、最近の看護師国家試験に出された問題も掲載し、受験勉強の参考になります。
【主な目次】
第1章 看護と法律・制度
第2章 看護師の資格や働き方に関する法律・制度
第3章 医療提供の原則に関する法律・制度
第4章 医薬品や医療機器の安全に関する法律・制度
第5章 国民の健康・保健の向上に関する法律・制度
第6章 感染症の予防、まん延防止に関する法律・制度
第7章 公的医療保険と公費負担医療に関する法律・制度
第8章 介護保険に関する法律・制度
第9章 障害者や子ども、高齢者、生活困窮者の支援に関する法律・制度
第10章 精神障害者の保健・医療・福祉に関する法律・制度
第11章 地域の健康と母子の健康に関する法律・制度
【著者情報】
望月聡一郎(もちづき・そういちろう)
湘南医療大学保健医療学部看護学科教授
東京大学医学部健康科学・看護学科卒業、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士課程単位取得退学。国家公務員共済組合連合会虎の門病院に勤務後、厚生労働省健康局総務課保健指導室、医政局看護課、医政局総務課、東日本大震災現地復興対策本部、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課などで勤務ののち、国際医療福祉大学成田看護学部教授に就任。2020年より現職。

- 日本のクマ
- 坪田敏男/山崎晃司
- 東京大学出版会
- ¥6380
- 2011年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)