性感染症 の検索結果 標準 順 約 1780 件中 601 から 620 件目(89 頁中 31 頁目) 

- 微生物学・感染症学(第3版)
- 塩田 澄子/黒田 照夫
- 化学同人
- ¥5940
- 2024年05月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は,薬学生に必要な微生物学・感染症学の基礎知識をわかりやすく簡潔に記述されている.微生物やウイルスの分類などはもちろん,感染症の特徴,感染経路,感染症の予防,薬物の作用機序などを解説する.新たに追加された感染症治療学には処方例が取りあげられており,学習に役立つ.また,将来学ぶ免疫学,ゲノム薬学,薬物治療学などの基礎としての役割も視野に入れてまとめられている.薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠.用語解説,コラム,章末問題付き.

- 敗血症ー感染症と臓器障害への対応
- 松田直之
- 中山書店
- ¥13200
- 2023年01月07日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
敗血症の原因となるさまざまな細菌やウイルスなどによる感染症の管理と,敗血症によって引き起こされる敗血症性ショックなどの臓器障害の管理について解説.抗菌薬のTDM,血液浄化法などの敗血症を管理するための工夫を取り上げ,「日本版敗血症診療ガイドライン」やCOVID-19についても盛り込んだ.敗血症をより深く理解して,どのような病態にも対応できる,これからの敗血症診療を見据える一冊.

- 神経疾患
- 石橋賢一
- 医学書院
- ¥3520
- 2013年05月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
思考し、感じ、駆動させる司令塔。神経疾患は実に多彩な症状を呈する。それは取りも直さず、脳と神経が身体の感覚と運動、そして高次脳機能をつかさどる“源”であることを意味している。眼前で起きている事象と神経学的知識との見事な一致をみたとき、あなたはきっとこの学問に魅了される。内科学を学ぶすべての人に贈る。“1周目”のテキスト!

- 現場で役立つ小児救急アトラス
- 内山聖/安次嶺馨
- 西村書店(新潟)
- ¥4180
- 2009年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 歯科衛生学シリーズ 疾病の成り立ち及び回復過程の促進2 微生物学
- 一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会/木村 重信/栗原 英見/前田 健康
- 医歯薬出版
- ¥3300
- 2023年01月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
歯科衛生士養成校のための新しい教科書、「歯科衛生学シリーズ」
【目次】
1章 疾病と微生物
(1)─疾病と微生物,免疫学
(2)─感染と感染症
2章 微生物の病原性
(1)─微生物の位置づけ
(2)─細菌
(3)─マイコプラズマ属(Mycoplasma)
(4)─スピロヘータ
(5)─リケッチア
(6)─クラミジア
(7)─ウイルス
(8)─その他の微生物(真菌・原虫)
3章 宿主防御機構と免疫
(1)─宿主防御機構
(2)─免疫機構
(3)─液性免疫
(4)─細胞性免疫
(5)─アレルギー(過敏症)
4章 口腔微生物学
(1)─口腔細菌叢
(2)─デンタルプラーク
5章 口腔感染症
(1)─う蝕
(2)─歯内感染症
(3)─歯周病
(4)─その他の口腔感染症
6章 化学療法
(1)─化学療法と化学療法薬
(2)─主な化学療法薬の種類と特徴
(3)─抗菌スペクトル
(4)─生体内動態
(5)─薬剤感受性試験
(6)─薬剤耐性
(7)─有害作用(副作用)
7章 院内感染対策と滅菌・消毒
(1)─口腔外感染症と院内感染対策
(2)─滅菌・消毒
(3)─滅菌・消毒の方法
8章 細菌培養・顕微鏡観察
(1)─培養法
(2)─培地
(3)─顕微鏡観察
(4)─微生物を観察するための方法(実習)

- 医科細菌学改訂第4版
- 笹川千尋/林哲也(細菌学)
- 南江堂
- ¥7480
- 2008年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- コメディカルのための専門基礎分野テキスト 内科学 改訂8版
- 北村 諭/坂東 政司
- 中外医学社
- ¥4180
- 2024年02月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
本書は著者らがコメディカルの教育に携わった経験をもとにこれらの学生・卒業者のために必要にして十分な内科学の知識を箇条書きと図表を中心にコンパクトにまとめたものである.ミニマムでありながら分かりやすい解説はそのままに,近年の変化やトピックスを加えた.基本を補強するとともに,最新の知識を学べる改訂8版.コメディカルスタッフ
の教育が重視されるなか,教育の現場で活用できる最適なテキストである.

- 感染症疫学 新版
- ヨハン・ギセック/山本太郎
- 昭和堂
- ¥3850
- 2020年07月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
1994年の初版以来、長きにわたり世界的に読まれてきたテキストの最新版。新型コロナの第二波・第三波に備えて現在もっとも読まれるべき一冊。著者はスウェーデンの「集団免疫戦略」をリードする専門家会議のメンバー。
第1部 感染症疫学への序
第1章 感染症の疫学ーーがんの疫学や循環器の疫学と何が違うのか
第2章 感染症疫学を学ぶための第一歩ーー定義
第2部 疫学の基礎
第3章 記述疫学ーー全ての疫学の始まり
第4章 リスクと相対リスクおよび発症率
第5章 ケース・コントロール研究ーー交絡について
第6章 コホート研究ーー偏りについて
第7章 感染症の臨床疫学ーー感度・特異度・分類間違い
第8章 多変量解析と交互作用
第9章 生存解析
第10章 感染症の数学モデル
第3部 感染症疫学への応用
第11章 アウトブレイクの発見と解析
第12章 感染症監視システム
第13章 「感染する」ということを計測する
第14章 感染症の自然史について
第15章 血清疫学
第16章 感染症と人々の暮らし、行動
第17章 ある疾病が感染症か否か、どうすればわかるのだろう
第18章 ワクチンの疫学
第19章 サブタイピングの使用

- かんテキ 脳神経 第2版
- 岡崎 貴仁/青木 志郎
- メディカ出版
- ¥3850
- 2025年07月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
全体に「ナースのギモン」、重要な症状項目として「嚥下障害」「運動麻痺」を新設!脳神経看護はモニターなどの機器ではわからない脳内の変化に気づく必要があり、観察・アセスメントが非常に重要。本書では、領域別疾患患者対応のポイントを徹底的に見える化。症例とチャートで、脳神経疾患患者の発症から退院後までの流れが、ストーリーで理解できる。患者さんの症状も多数イラスト化。注意したいサインがイメージできる!

- 新版すぐ身につく胸部CT
- 酒井文和
- 学研メディカル秀潤社
- ¥4840
- 2002年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.67(3)
新しいCTの技術的進歩と、びまん性肺疾患や早期肺癌を中心とする現在の最新知識はすべて網羅。初版から6年を経て、パワーアップした新版が登場。
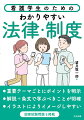
- 看護学生のためのわかりやすい法律・制度
- 望月聡一郎
- 中央法規出版
- ¥2860
- 2023年02月16日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
看護学生にとって苦手分野である法律・制度をとことんわかりやすく解説!
医療法から労働法規まで、看護教育で学ぶ関係法規を豊富なイラストと平易な文章で整理しました。
あわせて条文、過去の国家試験問題も収載し、入門書、サブテキストとして最適。国試対策にも活用できます!
「看護師に法律・制度は必要?」
医療や福祉といった社会保障は、さまざまな法律や制度に基づいています。
患者や利用者が治療や看護、介護を受けられるのも、そうした法律・制度があるからです。
また、看護師という国家資格自体も、法律によって決められているもの。
看護師として働き、看護ケアを提供することには、多くの法律がかかわっているのです。
「国家試験にも出題」
ある年の看護師国家試験で、なんらかの形で法律・制度が関係する出題が、240問中40問程度ありました。
医療や福祉には多くの法律が関係しているため、看護師になるためには幅広く法律・制度を押さえておく必要があります。
「キーワードを解説、関連条文、過去問題も掲載」
法律や制度を成り立ちからひも解くと長く複雑でわかりにくくなります。
本書では、今知りたい事柄やキーワードを取り上げて、ワンテーマでコンパクトに解説しているので、知りたい情報にすぐにアクセスできます。
しかも、関連する条文(法律の文章)は必要最低限にしているので、読むのも苦になりません。また、最近の看護師国家試験に出された問題も掲載し、受験勉強の参考になります。
【主な目次】
第1章 看護と法律・制度
第2章 看護師の資格や働き方に関する法律・制度
第3章 医療提供の原則に関する法律・制度
第4章 医薬品や医療機器の安全に関する法律・制度
第5章 国民の健康・保健の向上に関する法律・制度
第6章 感染症の予防、まん延防止に関する法律・制度
第7章 公的医療保険と公費負担医療に関する法律・制度
第8章 介護保険に関する法律・制度
第9章 障害者や子ども、高齢者、生活困窮者の支援に関する法律・制度
第10章 精神障害者の保健・医療・福祉に関する法律・制度
第11章 地域の健康と母子の健康に関する法律・制度
【著者情報】
望月聡一郎(もちづき・そういちろう)
湘南医療大学保健医療学部看護学科教授
東京大学医学部健康科学・看護学科卒業、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士課程単位取得退学。国家公務員共済組合連合会虎の門病院に勤務後、厚生労働省健康局総務課保健指導室、医政局看護課、医政局総務課、東日本大震災現地復興対策本部、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課などで勤務ののち、国際医療福祉大学成田看護学部教授に就任。2020年より現職。

- ドクターこばどんの感染症道場
- 小林美和子/西原崇創
- 三輪書店
- ¥4620
- 2014年02月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
感染症の事始めからトラベルメディシン、HIVまで充実の内容。

- 泌尿器科薬剤の考え方,使い方 改訂3版
- 後藤 百万/西山 博之/山本 新吾
- 中外医学社
- ¥5280
- 2025年11月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
泌尿器科の薬はこの1冊で!
ガイドラインの改訂と腫瘍領域の薬剤情報を反映して大幅にアップデート!
数あるガイドラインの薬剤の部分をかみ砕いてまとめ,フローチャートと表で適応,用法・用量,処方の注意点や評価項目,推奨グレードや薬剤選択の順序がひと目でわかる便利さで人気を得ているハンドブックの最新版.

- 生命科学の基礎
- 野島 博
- 東京化学同人
- ¥2640
- 2008年03月31日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
主要目次:
1章 人類はどうやって生まれたか
2章 細胞の成り立ちと遺伝の仕組み
3章 進化の理論
4章 細胞が増える仕組み
5章 性と生殖の不思議
6章 老化と病
7章 なぜ,がんになるのか?
8章 生体防御と感染
9章 遺伝子医療と感染症
10章 先端バイオ技術の応用
11章 ナノテクが拓くバイオの未来
12章 人類はどこへゆくのか?

- コメディカルのための 薬理学 第3版
- 渡邊 泰秀/安西 尚彦/櫻田 香
- 朝倉書店
- ¥4070
- 2018年04月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
薬剤師や看護師をめざす学生向けのテキスト。図表・イラストを多用して,初学者にもわかりやすい 2 色刷レイアウトで構成。演習問題と解説を充実させ,さらにエイジング,漢方薬,毒物,医薬品開発など最新の動向を盛り込んだ全面改訂版。

- 臨床心エコー図学第3版
- 吉川純一
- 文光堂
- ¥38500
- 2008年04月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
最新第3版では、読者の理解が容易なように「方法編」と「疾患編」に分けて記載。基本から最新知見まで心エコー図学を完全網羅。

- 中枢神経 (非腫瘍性疾患病理アトラス)
- 新井 信隆
- 文光堂
- ¥18700
- 2024年03月06日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
【神経病理診断に役立つ標準的かつ最新の情報と写真が満載.神経病理の決定版アトラス!】
病変の強弱や経時的な変化など,多彩な組織形態を見せる神経病理像は,捉えかたが難しく,診断に苦慮することも多い.
本書では精選された肉眼像や組織像を多数提示して,判断に役立つ所見や標準的な診断法をわかりやすく解説.
病理医をはじめ,法医や脳神経外科医等にとっての神経病理診断の道標となることを目指す.
変性疾患や感染症,外傷,てんかん,プリオン病等々,多様な神経疾患を網羅した,診断実務にも知識の整理にも役立つ決定版アトラス.
≪主要目次≫
第1部 総 論
1.大脳の切り出し・肉眼所見
2.脳幹・小脳の切り出し・肉眼所見
3.脊髄の切り出し・肉眼所見
4.神経染色法
5.神経病理実務の紹介
6.パラフィンブロックの研究活用
第2部 各 論
1.循環障害・血管病変
2.頭部外傷
3.感染症
4.変性疾患
5.脱髄疾患・髄鞘障害性疾患
6.脳形成異常
7.神経皮膚症候群
8.てんかん
9.プリオン病
10.中毒・代謝異常など
索 引

- 自閉症と広汎性発達障害の生物学的治療法
- ウィリアム・ショー
- コスモトゥーワン
- ¥4180
- 2011年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
自閉症や発達障害に関する効果的な最新治療法についてのわかりやすいガイド。

- 糖尿病療養指導士に知ってほしい歯科のこと
- 西田亙
- 医歯薬出版
- ¥3080
- 2018年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
歯の本数が命に関わる!?日本糖尿病学会が患者に歯周治療を勧めるワケから話題の医科歯科連携まで全国講演に引っ張りだこの内科医がやさしく教えます!「目からうろこ」の糖尿病と歯科のこと。

- 栄養士・管理栄養士のための食品衛生学
- 川合清洋
- 静風社
- ¥2200
- 2015年11月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)