多様性 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 681 から 700 件目(100 頁中 35 頁目) 

- 僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回
- 森田 真生
- 集英社
- ¥1760
- 2021年09月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.23(13)
未来はすでに僕を侵食し始めている。
未曾有のパンデミック、加速する気候変動……人類の自己破壊的な営みとともに、「日常」は崩壊しつつある。それでも流れを止めない「生命」とその多様な賑わいを、いかに受け容れ、次世代へと繋ごうか。
史上最年少で小林秀雄賞を受賞した若き知性が2020年春からの「混沌」と「生まれ変わり」を記録した、四季折々のドキュメント・エッセイ!
【目次】
はじめに
春 / STILL
夏 / Unheimlich
秋 / Pleasure
冬 / Alive
再び、春 /Play
おわりに
森田真生(もりた・まさお)
1985年生まれ。独立研究者。2020年、学び・教育・研究・遊びを融合する実験の場として京都に立ち上げた「鹿谷庵」を拠点に、「エコロジカルな転回」以後の言葉と生命の可能性を追究している。著書に『数学する身体』(2016年に小林秀雄賞を受賞)、『計算する生命』、絵本『アリになった数学者』、随筆集『数学の贈り物』、編著に岡潔著『数学する人生』がある。

- 【楽天ブックス限定特典】あの写真集 あの在処(フィルム風しおり1枚)
- あの/川島 小鳥
- 小学館
- ¥3520
- 2024年09月04日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.38(8)
「いま」の空気を体現するアーティストとして、若者世代だけでなく現代のポップアイコンとして認知度を拡大し続けている“あのちゃん”。
そんな彼女の「いま」を見つめる、5年ぶりとなる写真集「あの在処」を、2024年9月4日に小学館より刊行いたします。
本作の撮影を担当したのは、写真界の芥川賞と言われる『木村伊兵衛賞』を2015年に受賞し、あのちゃんとは公私共に交流のある川島小鳥氏。
撮影地は新潟県佐渡島。佐渡島ならではの自然の中で見せる”あのちゃん”の表情・姿を収めた1冊です。
ロケは2泊3日で行われ、衣装は全19着と、“あのちゃん”のイメージを体現する衣装から、意外性のある衣装まで大ボリュームな内容になっています。
■撮影中のあのさんの手記よりコメント抜粋
たらい舟でフグやクロダイみれた。
5年前、小鳥さんとの撮影で花火をした。それも写真集。
あれから5年が経ち、最後、花火をした。
別に何も変わらないけど、
あの日、髪の毛が燃えた。
今日は、フードで燃えなかった。少し成長した。
「YOU&愛Heaven」を海辺で弾き語りした。
波の音にかき消されまいと歌をうたった。
僕の声はどでかい海とその波の音に吸い込まれてった。
まだまだでっかくなる。
でっかくなれるんだ、と少し嬉しくなった。
■プロフィール
あの/9月4日生まれ。身長166cm。TOY'S FACTORY所属。若い世代の女性を中心に人気を誇る「あの」。2020年9月より「ano」名義でのソロ音楽活動を開始。2022年4月 TOY'S FACTORYよりメジャーデビュー。同年10月TVアニメ『チェンソーマン』エンディング・テーマに「ちゅ、多様性。」が抜擢。2023年末には日本レコード大賞特別賞を受賞。NHK紅白歌合戦にも出場。2024年3月映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」 主演声優と主題歌を担当。音楽活動だけに留まらずタレント、女優、声優、モデルと多岐に渡りに活動。

- インターセックス
- 帚木蓬生
- 集英社
- ¥2090
- 2008年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.83(90)
生殖と移植では「神の手を持つ名医」と評判の岸川卓也院長が率いる、贅沢な施設と高度な医療を誇るサンビーチ病院。泌尿婦人科医の秋野翔子は岸川に請われてこの病院に勤務することになった。そこでは性同一性障害やインターセックスの患者たちへの性転換手術やさまざまな治療が行われていた。翔子は「人は男女である前に人間だ」と主張し、人知れず悩み、絶望の淵にいた患者達のために奔走する。やがて翔子は、彼女に理解を示す岸川の周辺に不可解な変死が続いていることに気づく…。神が創り出した少数派の人間たちの魂の叫び、身体と魂の尊厳。医学の錯誤を見据える世界初テーマに挑む、衝撃と感動のサスペンス大作。

- 知的食生活のすすめ
- 榊原英資
- 東洋経済新報社
- ¥1650
- 2009年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(3)
食通や大食漢ではない、これからの食生活とは。世界の食文化とその歴史をたどり、食をめぐる楽しい話を満載。

- 「この人なら!」と部下がついてくる話し方の極意
- 福田健
- 東洋経済新報社
- ¥1540
- 2010年01月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
迷うな!ブレるな!これからのリーダーはコレで行け!「話が通じない」「部下の気持ちが読めない」など、コミュニケーションの悩みを抱える上司必読の書。

- 一橋ビジネスレビュー(61巻2号(2013 AUT.)
- 一橋大学イノベーション研究センター
- 東洋経済新報社
- ¥2200
- 2013年09月09日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
少子高齢化の進展、総人口の減少、経済のグルーバル化の浸透領域の拡大、多文化共生などの課題に直面するわが国は、これからどのような経済社会をつくって人々の幸福を追求すべきだろうか。本特集では、「地域創造マネジメントと大学教育」「人的多様性を活用して地域の未来を創造する」「地域文化創造を支える市民組織のマネジメント」「(求められる)人材をめぐる混迷」「社会経済を創造するまちづくりの論理」など、求められる未来社会を創造するイノベーション・マネジメントについて論じる。特集編者は、学生による「まちづくり」の研究に詳しい林大樹(一橋大学教授)。主な執筆者は、石川公彦(明治大学助教)、田中弥生(大学評価・学位授与機構教授)、福嶋路(東北大学教授)、結城恵(群馬大学教授)。ビジネス・ケースでは海外拠点の自律化に取り組むブラザー工業、研究と事業の戦略転換を図った住友電気工業を取り上げる。インタビュー・コーナーにはアイリスオーヤマの大山健太郎社長が登場。
[特集第1論文]地域創造マネジメントと大学教育
林 大樹 一橋大学大学院社会学研究科教授
[特集第2論文]人的多様性(ダイバーシティー)を活用して地域の未来を創造する
結城 恵 群馬大学教育基盤センター教授
[特集第3論文]人材をめぐる混迷
田中弥生 大学評価・学位授与機構教授/日本NPO学会会長
浅野 茂 神戸大学企画評価室准教授
[特集第4論文]経済社会を創造する「まちづくりの論理」
石川公彦 明治大学経営学部助教
[特集第5論文]地域文化創造を支える市民組織のマネジメント
福嶋 路 東北大学大学院経済学研究科教授
[経営を読み解くキーワード]退職給付会計基準のコンバージェンス
[技術経営のリーダーたち]職人的なものづくりからスポーツ工学によるものづくりへの道程で得たもの
西脇剛史 株式会社アシックス スポーツ工学研究所所長/フェロー
[ビジネス・ケース]
ブラザー工業ーーグローバル経営の進化と人事部門の役割
住友電気工業ーー研究開発と事業化戦略の転換
[コラム]日本経営学のイノベーション
小川 進 神戸大学大学院経営学研究科教授
[マネジメント・フォーラム]
ユーザーインの思想で消費者に快適さを提供するメーカーベンダーをめざす
大山健太郎 アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役社長
[投稿論文]ライベートブランドのサプライチェーン・マネジメント
秋川卓也 日本大学商学部専任講師
戸田裕美子 日本大学商学部専任講師

- 東洋経済ACADEMIC 龍谷大学
- 東洋経済新報社
- ¥880
- 2015年05月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
無限の可能性を解き放て
社会構造が変化し、価値観が多様化する中でさまざまな問題が複雑に絡み合う現代社会。
日本国内はもとより、国境を越えたスケールで解決すべきグローバルイシューが無数に横たわっている。
このような問題に対し、知の拠点として何ができるのか。
大学は今、改めてその存在意義を問いただされている。
そんな新しいフェーズを迎え、龍谷大学は大きく舵を切った。
「何が本質か」を見出し、自ら未来を切り拓く人材を育成することで、社会的要請に応えていこうというのだ。
“You、Unlimited” すべての学生に、無限の可能性を。
これは学生へのメッセージであるとともに、「龍谷大学の可能性」を模索し、
変化を恐れず挑戦し続ける大学としての強固な決意表明でもある。
未来に向けて、新たな一歩が踏み出された。
[赤松徹眞学長インタビュー]
積み重ねてきた歴史を礎に新たな龍谷大学の創造へ
[第1特集] 龍谷大学農学部の誕生
今、「食」と「農」に何が起こっているのか?
[第2特集] 龍谷大学国際学部の挑戦
来るべき「他文化共生」の時代に向けて
他

- 心の多様性
- 中村哲之/渡辺茂
- 大学出版部協会
- ¥1100
- 2014年06月05日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
トリ,ヒト,それぞれが視る世界は同じものではない.赤ちゃんはいつごろから自分を自分と認識するのか.心の働きの多様性を比較認知科学・発達認知科学の視点からわかりやすく解き明かす.大学出版部協会創立50周年記念出版.
第一章 トリの「視る」世界ー動物の錯視と心(中村哲之)
私が視ている世界が絶対ではないーー視ることは主観的体験/錯視研究から「視る」を見る/トリとヒトの錯視を比べる/トリとヒトはどのように世界を視ているか/ハトとニワトリの実験部屋/心の相対性から見えてくるもの
第二章 ヒト型脳とハト型脳(渡辺 茂)
いろいろな動物の脳/ヒトの脳はなぜ大きくなったのか/見る能ーーピカソとモネを見分けるハト/ヒトとハトの脳の違い/鏡の中の自分がわかる?/細胞レベルからの脳理解へーー動物の脳研究の可能性
第三章 脳は世界をいかに捉えているか(開 一夫)
意識とはなんだろうか/赤ちゃんの意識/自己映像と脳の活動
第四章 討論ーー心の多様性と現代(藤田和生×中村哲之・渡辺 茂・開 一夫)
ヒトの視覚システムがもし急にハト型になったら/「自己認知できる」とは/
質問?-自然界で錯視は起こる?/質問?-錯視は学習か進化か?/質問?-「使われていない」脳の役割は?/質問?-ヒトの脳は特別?/質問?-研究で人間の本質がわかる?/質問?-動物の権利とは?/心の多様性を人間社会に活かすー比較認知科学の役割
あとがき(藤田和生)

- コンフリクト・マネジメントの教科書
- ピーター・T・コールマン/ロバート・ファーガソン/鈴木 有香/八代 京子/鈴木 桂子
- 東洋経済新報社
- ¥3080
- 2020年08月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
ダイバーシティ、複雑化する働き方の時代、異なる立場や意見の人々に配慮し、どのようにうまくやっていくべきか?
状況をいかに読み解き、「権力」「感情」「変化」を理解して、自分や組織を活性化していくべきか?
昨今注目されるビジネス現場の必須スキルとマインドセットを世界の第一人者が解き明かす。7つの戦略と70の戦術、チェックリストなど、すぐに使えるメソッドが充実。
「今日の職場は多様性に満ちています。正社員、派遣社員、契約社員、嘱託など雇用契約が異なる人々がいます。世代格差、ジェンダー、身体障がいの有無などさまざまです。
経済のグローバル化で労働力の移動は頻繁になり、外国人を雇用しているのは、もはや大企業ばかりでなく、外国人労働者抜きでは稼働できない工場も少なくはありません。オープンイノベーションや付加価値のある商品開発では、社内外の人々との協働プロジェクトも一般化しました。
さらに、ワークを支えているのはライフです。ライフスタイルも多様化しています。独身、共働き、子育て中、介護しなければならない人とそれぞれの家庭事情を抱えた人々が職場に期待することは一様ではありません。
さまざまな人がいるからこそ、意見が違うのです。つまり、コンフリクトは不可避なものであり、日常なのです。ならば、面倒だと避けるのではなく、意見の対立を効果的にマネジメントする力を持ちましょう。立場や意見の相違を克服し、危機をチャンスに変え、目的を達成していくリーダーシップを時代が求めています。
コンフリクト・マネジメントは、グローバル化するビジネス環境に身を置くすべての人にとって必須の理論であり、実践なのです」(本文より)
Introduction コンフリクトとパワーの関連性
Part I 理論編
Chapter 1 コンフリクトとパワーの本質
Chapter 2 コンフリクトの罠ーー感情とパワーの問題
Chapter 3 コンフリクト・インテリジェンス
Part II 実践編
Chapter 4 現実的仁愛
Chapter 5 賢明なサポート
Chapter 6 建設的支配
Chapter 7 戦略的譲歩
Chapter 8 選択的自立
Chapter 9 効果的な状況対応
Chapter 10 道義的反乱
本書のまとめ
コンフリクト・インテリジェンス 事前準備ワークシート

- 小論文これだけ!法・政治 超基礎編
- 樋口 裕一
- 東洋経済新報社
- ¥1100
- 2022年08月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
★累計40万部突破!受験生から圧倒的支持!
★今一番売れている「小論文の参考書」シリーズ!
★法・政治系の志望者は全員必読!一番やさしい「超入門書」!
法・政治系の小論文に必要な「基礎知識」が
たった1冊で全部わかる!一番やさしく解説!
【民主主義についての基礎知識】
民主主義、日本の選挙の問題点、シルバー・デモクラシー、一票の格差 etc.
【日本が抱える難問についての基礎知識】
国際関係、歴史問題、少子高齢化、年金制度、格差拡大、非正規労働者の増加 etc.
【日本が今後進むべき道についての基礎知識】
持続可能な社会、SDGs、地球温暖化、ごみ問題、生物多様性の尊重 etc.
【都市と地方の問題についての基礎知識】
都市と地方の格差、外国人との共存、地方衰退3つの問題点、地方活性化4つの方法 etc.
【災害・感染症についての基礎知識】
災害対策3つのポイント、ワクチン・新薬開発、情報公開、法の整備 etc.
【ジェンダーにまつわる問題の基礎知識】
ジェンダーフリー、クオーター制、夫婦別姓 etc.
【日本社会の人権問題についての基礎知識】
日本人の集団主義、外国人労働者、移民問題、難民受け入れ問題、外国人参政権、死刑廃止論、DV・子どもの虐待、いじめ、ひきこもり、ハラスメント etc.
【報道のあり方についての基礎知識】
報道機関の役割、匿名報道 etc.
【ネット社会についての基礎知識】
フェイクニュース、ネット依存、ネットでの中傷、実名での発信 etc.
この1冊で、知識がしっかり身につく!
課題文が読める!書くべきこともわかる!
「こんな入門書が欲しかった!」
法・政治系の学部学科をめざす全受験生、必読の1冊!
第1部 小論文の書き方
1作文と小論文との違いとは?
2小論文の「型」ってなに?
3小論文を書くときの7つのポイント
4小論文を書くときに守るべき7つの基本的なルール
5課題文がつくタイプの小論文問題の書き方
6要約問題がつく小論文問題の書き方
7説明問題がつく小論文問題の書き方
第2部 法・政治系の小論文とは
1法・政治系の学部って何を学ぶところ?
2どんな人がこれらの学部に向いている?
3法・政治系の小論文を書くときに気をつけること
第3部 法・政治系の小論文に出る基礎知識
民主主義についての基礎知識
日本が抱える難問についての基礎知識
日本が今後進むべき道についての基礎知識
都市と地方の問題についての基礎知識
災害・感染症についての基礎知識
ジェンダーにまつわる問題の基礎知識
日本社会の人権問題についての基礎知識
報道のあり方についての基礎知識
ネット社会についての基礎知識

- となりのきょうだい 理科でミラクル 地球にやさしく編
- となりのきょうだい/アン・チヒョン/ユ・ナニ/イ・ジョンモ/となりのきょうだいカンパニー/となりのしまい
- 東洋経済新報社
- ¥1320
- 2025年07月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(3)
☆☆☆気になりすぎて死んじゃううう〜〜〜!!!☆☆☆
☆☆☆小学校の理科が大好きになる! 超爆笑まんが☆☆☆
トムとエイミのきょうだいが
日常のふしぎを探究していくよ!
ゲラゲラ笑って頭がよくなりたい子、集まれ〜〜〜!!
●海に捨てられたゴミはどうなるの?
●家庭ゴミはどうやって処理されるの?
●人間のせいで海の生き物が困ってるって本当? ……
みんなのまわりで起こるふしぎな現象のほか、
気になりすぎて眠れない身近な18のナゾをスッキリ解決!
オモシロすぎて、勉強している感覚はゼロ。
なのに「科学の基本」が楽しく身につく、と
累計700万部突破!!
☆☆☆総ルビで読みやすい☆☆☆
☆☆☆小学校就学前から小学校1〜6年生まで対象☆☆☆
1 お小づかいかせぎならトムにお任せ!
空きビンはどうやって再使用されるの?
2 捨てちゃいけない大事なゴミ
家庭ゴミはどうやって処理されるの?
3 トムのしめっぽい1日
ヘアドライヤーは、どうやって熱い風をつくるの?
4 はてしない階段
エレベーターはどうやって動くの?
5 ドキドキ映画館デート
3D映画はどうして立体的に見えるの?
6 風よ、とまれー!
台風はどうして起こるの?
7 砂ばくでサバイバル1
砂ばくはどうしてできるの?
8 砂ばくでサバイバル2
ラクダはどうして砂ばくでも生活できるの?
9 砂ばくでサバイバル3
砂ばくのオアシスはどうやってできるの?
10 願いをかなえて! お月様
月はどうして形が変わるの?
11 ねても覚めても雨に注意!
どうして夏は夕立がよく起こるの?
12 ガタゴトゆられて電車の旅
電車はどうやって動くの?
13 水族館のとなりのきょうだい!?
オットセイはどうして陸の上でも暮らせるの?
14 魚と友だちになるには?
魚はどうして水の中でも素早く動けるの?
15 トムのおかしな飛行機エチケット
飛行機はどうやって空を飛ぶの?
16 ようこそ、火山島へ!
火山島はどうやってつくられるの?
17 波がさらったプレゼント
げん武岩にはどうして穴があいているの?
18 ウミガメの恩返し
海に捨てられたゴミはどうなるの?

- ぼくの世界博物誌
- 日髙 敏隆
- 集英社
- ¥858
- 2023年07月21日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
動物にも人間にも個々の文化と戦略がある。動物行動学者が世界で出会った不思議、暮らしの風景、人と自然との関係を綴るエッセイ集。

- マラッカ海峡物語 ペナン島に見る多民族共生の歴史
- 重松 伸司
- 集英社
- ¥1012
- 2019年03月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.33(4)
マラッカ海域北端に浮かぶペナン島。淡路島の半分ほどのこの小島では、
実に30以上の民族集団同士が絶妙なバランスで共生し続けてきた。
南アジア研究の第一人者による、本格的な「マラッカ海峡」史。

- 英語のこころ
- マーク・ピーターセン
- 集英社インターナショナル
- ¥770
- 2018年04月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.83(7)
『日本人の英語』の著者が、「多様性」「性と愛」「資本主義」「原子力問題」「津波」「死」などのキーワードを縦横無尽に論じる。日英米の社会・文化の魅力と本質を英語から浮かび上がらせる画期的な1冊。

- 完訳ファーブル昆虫記第2期(全10巻セット)
- 集英社
- ¥42020
- 2017年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
自然に親しむ手引書として大人から子供まで楽しめる待望の完訳版の第2期(6~10巻 各巻上・下 全10冊)セットです。

- 一橋ビジネスレビュー 2024年AUT.72巻2号
- 一橋大学イノベーション研究センター
- 東洋経済新報社
- ¥2420
- 2024年09月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
昨今、社会的なグローバル課題や価値観の変化は、新しい規範の形成を促している。これにより、企業活動の法的順守だけでなく、法の領域を超えた社会的責任や持続可能な発展にかかわる取り組みをどうビジネスに反映させ、統合していくかが戦略的課題となる。本特集では、変化するビジネス規範と環境の展望を念頭に、課題に焦点をあわせ、革新的なアプローチを検討し、持続可能な未来に向けた多様な側面からの洞察を提供する。主な執筆者:村嶋美穂(立教大学)、芳賀和恵(早稲田大学)、齋藤紀子(千葉商科大学)、ロバント・サヴ(一橋大学)、赤石枝実子(ZOZO)。インタビューは、国谷裕子(ジャーナリスト)、尾形優子(メロディ・インターナショナル)、ビジネスケースは、不二製油とユニファ。
[特集]ビジネス倫理の展望:
持続可能な価値観を考える
変化する価値観(村嶋美穂)
地域の社会的課題を解決する共創の手法としてのリビングラボ(芳賀和恵)
有償ボランティアにおける謝礼金が生み出す会計的なジレンマ(齋藤紀子)
スローイングの観点から見た日本の循環型経済(ロバント・サヴ)
持続可能性とウェルビーイングの包含(赤石枝実子)
[特別寄稿]
忙しいリーダーのパラドクス(鈴木竜太/砂口文兵)
[連載]
理解のマネジメント 第3回(佐藤大輔)
[産業変革の起業家たち]
モバイル分娩監視装置がかなえる
周産期医療格差のない世界
尾形優子(メロディ・インターナショナル代表取締役CEO)
[ビジネス・ケース]
不二製油:食品業界における「両利きの経営」
ユニファ:TOPPAN CVCとの価値共創
[マネジメント・フォーラム]
サステナビリティの実現に向けて
アートやメディアに何ができるのか
国谷裕子(ジャーナリスト)
[投稿論文]
経営トップの特性はCSRに影響するのか(中尾悠利子/國部克彦/奥田真也/喜田昌樹)

- 新・ムラ論TOKYO
- 隈研吾/清野由美
- 集英社
- ¥836
- 2011年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.48(24)
ムラとは何か?それは行政上の「村」ではない。人が安心して生きていける共同体のありかであり、多様な生き方と選択肢のよりどころとなる「場所」を、本書では「ムラ」と呼ぶ。したがって、都会にも「ムラ」は存在するし、むしろ存在するべきなのだ。前者『新・都市論TOKYO』で大規模再開発の現場を歩いた二人が、高層ビルから雑多なストリートに視点を移し、「ムラ」の可能性を探る。東京におけるムラ的な場所ー下北沢、高円寺、秋葉原。そして、地方から都市を逆照射する新しいムラー小布施。そこに見えてきた希望とは?-。
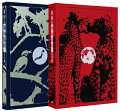
- 世界の動物遺産
- 自然環境研究センター
- 集英社
- ¥27500
- 2015年12月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
地球は今、猛烈な勢いで貴重な住人を失っている。開発や戦争で追いつめられ、絶滅を危惧される野生動物の“決定的瞬間”を収めた大型愛蔵版写真集。研究者の詳細解説付き、至高のドキュメンタリー!

- ライオンはとてつもなく不味い ヴィジュアル版
- 山形 豪
- 集英社
- ¥1430
- 2016年08月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.4(5)
弱肉強食の頂点に立つライオンは「とてつもなくマズい」。大自然を貫く掟や、生きることの本質とは? 幼少期より人生の多くをアフリカで過ごした写真家が、動物たちが織り成す究極の生き様に迫る。

- GEO5地球環境概観第5次報告書(上)
- 国際連合環境計画
- 環境報告研
- ¥2750
- 2015年10月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
GEO地球環境概観は、地球温暖化だけでなく、それ以外の全ての地球環境の問題を取り上げており、国際連合環境計画(UNEP)が1997年に第1次報告書を発表して以来、何千人もの科学者と何百もの組織が関与して構築されてきた、地球環境に関する世界で最も権威ある報告書である。
本書はその第5次報告書の上巻で、地球が温暖化をはじめとしたいくつかの臨界閾値(限界点)に接近していること、また大気、陸、水、生物多様性、廃棄物、といった分野別、および地球システム全体としての現状と傾向、ならびに多くの環境条約や協定名と共にそれらのうちの重要な90の国際目標とその進捗状況について述べている。
<第1部の主な課題>
第1章 「駆動要因」: 人口、経済発展、輸送、都市化、グローバル化、臨界閾値
第2章 「大気」: 温暖化、粒子状物質(PM2.5)、窒素化合物、オゾン、メタン、黒色炭素
第3章 「陸」: 森林、REDD+、乾燥地の劣化、食糧安全保障、食肉生産、バイオ燃料
第4章 「水」: 水不足、海面上昇、海洋酸性化、栄養塩汚染、水ガバナンス
第5章 「生物多様性」: 愛知ターゲット、生物多様性への圧力、からの恩恵、脅威への対応
第6章 「化学物質と廃棄物」: POP、金属汚染、海洋汚染、海ゴミ (マイクロプラスチック)、環境中のプラスチック、放射性物質
第7章 「地球システムの全体像」: 極地域、オーバーシュート、惑星限界、遷移管理
後付け: GEO-5の制作工程、関与した600名の一覧、用語解説、索引