性感染症 の検索結果 標準 順 約 1780 件中 701 から 720 件目(89 頁中 36 頁目) 

- 医師と薬剤師が考える処方箋のつくり方
- 矢吹 拓/青島 周一
- 丸善出版
- ¥4180
- 2024年09月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
薬の効果とは「無意味」と「嘘」の間にある。患者にとって、本当に望ましい処方箋とは何か。11の処方箋をめぐり医師と薬剤師が「対話」から導く本当の「解」

- 関節リウマチの鑑別診断
- 竹内勤
- 先端医学社
- ¥1980
- 2022年05月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 性のトリセツ
- 津曲茂久
- 緑書房(中央区)
- ¥2860
- 2018年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
獣医繁殖学者が科学と想像力で読み解く人と動物の性の真実と不思議。老いも若きも呼び覚ませ!人間本来の「性活力」。

- 内科医のための処方集改訂6版
- 北村諭/池口邦彦
- 中外医学社
- ¥2530
- 2016年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 糖尿病学2022
- 門脇 孝/山内 敏正
- 診断と治療社
- ¥11000
- 2022年05月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
糖尿病学のなかでも特にわが国発の研究に重点を置いて重要な課題を取り上げ,専門的に解説したイヤーブック.今年もこの1年の基礎的研究,臨床・展開研究の成果等が18編の論文に凝集されている.糖尿病研究者のみならず,一般臨床医にとっても必読の書.

- 眼手術学(8)
- 大鹿哲郎
- 文光堂
- ¥22000
- 2012年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 看護師・看護学生のためのなぜ?どうして? 2018-2019 5
- 医療情報科学研究所
- メディックメディア
- ¥1650
- 2017年04月11日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
『レビューブック』と『クエスチョン・バンク』に対応。呼吸器の解剖生理からCOPDを理解できる!関節リウマチやSLEの大事なポイントがわかる。国試によく出る内容や必修問題として出題されるテーマを中心にストーリーを構成。

- 助産師基礎教育テキスト 2024年版 第2巻 ウィメンズヘルスケア
- 吉沢豊予子
- 日本看護協会出版会
- ¥5060
- 2023年10月11日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
女性のライフサイクル各期の健康問題、性と生殖のケアの基礎知識を詳述
●【2024年版改訂】「助産師国家試験出題基準 令和5年版」を踏まえて全面改訂。遺伝、ゲノム、性の多様性、プレコンセプションケアの内容を刷新し、国家試験を見据えた学習をサポート。
●女性のライフサイクル各期の基礎知識、そこで生じる健康問題とケアについて図解しながら解説。高度生殖医療など性と生殖をめぐる今日的課題、女性の生き方の変化について、幅広い知識が得られる内容。

- 肺移植の臨床
- 平間 崇
- ぱーそん書房
- ¥6600
- 2025年10月09日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
肺移植診療のための実践書がついに刊行‼
過渡期から新たな時代に向けてブラッシュアップ↑
肺移植の基礎知識と診療のノウハウを詳細に解説‼
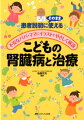
- こどもの腎臓病と治療
- 後藤 芳充
- メディカ出版
- ¥2640
- 2018年07月04日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
腎臓病と診断されたこどもや家族の不安を少しでも和らげるために、病気について理解できるように、イラストを中心にやさしく解説した本。いろいろな種類の腎臓病があることや、最新の治療法について、ていねいに解説。患者説明にそのまま使うこともできる。

- 鑑別診断ネモニクス
- 徳田安春
- メディカル・サイエンス・インターナショナ
- ¥4180
- 2017年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 歯科医のための皮膚科学第2版
- 山崎双次/山本浩嗣
- 医歯薬出版
- ¥6820
- 2004年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 呼吸器内科実践NAVI
- 林 清二/杉本 親寿/安宅 信二/井上 義一/橘 和延/鈴木 克洋
- 南江堂
- ¥4950
- 2018年05月07日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
若手呼吸器医,非専門医が習得すべき知識と技術を,近畿中央呼吸器センターが総力を挙げて執筆.実臨床に即し,検査・治療手技,肺癌,間質性肺炎・希少難病,閉塞性肺疾患,呼吸器感染症,その他の重要な呼吸器疾患,呼吸器集中治療について実践的に解説.医局からベッドサイドや外来診察室,検査室に向かう際の診療ポイントの整理に役立つ一冊.現場で役立つ知恵と極意がここに!

- 越境者との共存にむけて
- 村田 和代
- ひつじ書房
- ¥4620
- 2022年03月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
日本社会における喫緊の課題である多文化共生をめぐり、ナラティブ分析というミクロアプローチから、言語教育政策や公共政策への提言といったマクロアプローチまで、分野を超えて多層的に考察する。ポストコロナの日本社会において、何を変えるべきなのか、誰が変わるべきなのか、越境者との共存や多様性をあらためて問い直す。
執筆者:岩田一成、大石尚子、岡本能里子、片岡邦好、木村護郎クリストフ、Astha TULADHAR、村田和代、山口征孝、吉田悦子、Julian CHAPPLE、Magda BOLZONI
はじめに
第1章 ネパール人が選ぶ留学先としての日本ー渡日前後の質問紙調査から探る
吉田悦子・Astha TULADHAR
第2章 移動する子どもの「語り」から見る受け入れ側の課題ー多文化に拓かれた「選ばれる国ニッポン」を目指して
岡本能里子
第3章 長期在留カナダ人から見た日本社会ー高度人材移民とのインタビューからの考察
山口征孝
第4章 マルチチュードとしての多文化共生社会ーイタリアに暮らす日本人女性たちのライフストーリーを通じて
大石尚子
第5章 職場談話研究から人材育成への貢献ーニュージーランドにおける実践紹介
村田和代
第6章 教育現場における「やさしい日本語」の可能性ー子どもたちにとって難しい科目は何か
岩田一成
第7章 日本社会を開く妨げとしての英語偏重
木村護郎クリストフ
第8章 共生と「スケール」-新型コロナ感染症と「ばい菌」言説
片岡邦好
第9章 日本語概要 境界を越える、別々に暮らす?-日本の都市における多様性と多文化主義
マグダ・ボルゾーニ
Chapter 9 Crossing the Border, Living Apart?: Diversity and Multiculturalism in Japanese Cities
Magda BOLZONI
第10章 日本語概要 多様性とインクルージョンか、多様性の排除かー日本が進むべき方向とは
ジュリアン・チャプル
Chapter 10 Diversity and Inclusion or Excluding Diversity: Which Way Forward for Japan?
Julian CHAPPLE
索引
執筆者紹介

- 脳MRI 3.血管障害・腫瘍・感染症・他
- 高橋昭喜
- 学研メディカル秀潤社
- ¥13200
- 2010年09月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
大好評の「1.正常解剖」「2.代謝・脱髄・変性・外傷・他」に続いて、血管障害・腫瘍・感染症・全身性疾患・頭蓋骨の異常を収載した待望の1冊が登場!豊富な画像ととても詳しい解説で、日常臨床や読影をする際に必ず役立つ1冊。

- 魚病学概論改訂 第2版
- 小川和夫/室賀清邦
- 恒星社厚生閣
- ¥4180
- 2012年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 感染症はこう叩け!
- 前崎 繁文
- 中山書店
- ¥3300
- 2013年04月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
抗菌薬の使い方は若手ドクターが頭を悩ます共通のテーマです.本書では抗菌薬の基本的知識から,診療科/感染症別に抗菌薬使用のポイントを,ワンテーマ見開き2頁で解説します.どこから読んでもOK.前著『抗菌薬はこう使え!』と併せて読めば,あなたも抗菌薬使用のプロになれます.

- 患者さんの信頼を勝ちえる 自然療法活用ハンドブック
- ジョゼフ・E・ピゾルノ・Jr/マイケル・T・マレイ/ハーブ・ジョイナーーベイ/帯津 良一/岩本 さなえ
- ガイアブックス
- ¥3960
- 2015年07月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
自然療法とは、対症療法としてハーブや栄養素を使用するのみならず、患者と向き合い病気の真の原因を理解し、それらを患者の正常な機能回復のサポートに統合・補完的に活用する療法のことである。本書は自然療法が有効な36の疾患について、それに対応した自然療法の活用方法を示す実践的手引書。本書の前身となる『自然療法』では取り上げなかった、がん、子宮筋腫、子宮内膜症、女性の抜け毛、線維筋痛症候群、パーキンソン病など17の疾患を追加。臨床現場でのさらなる活用が期待される19の疾患を厳選し、全章を最新のエビデンスに基づいて再検証。最も信頼性の高い診断法、最も新しい治療法を収載した。疾患ごとに、診断のポイント、病気の概要、独自のフローチャート、治療上の留意ポイント、自然療法の治療アプローチの5つのパートで構成。特に症例管理の概念図となる3段階のフローチャートは、自然療法の活用要旨が明確に分かり、症例に応じた治療手順と方法を効率よく見出すことができる。自然療法を臨床に取り入れたいと願う医師や薬剤師、就学者をはじめ、在宅でのケアに関心の高い一般読者まで幅広く活用できる。
◎3段階のフローチャート
・通常医療の必要性を判断する。
・治癒を妨げる要因を特定してできる限り除去する。
・患者に合わせた治療プランを策定する。
監修者序文/著者序文/自然療法における治療優先順位
アトピー性皮膚炎(湿疹)
アフタ性口内炎(アフタ性潰瘍/鵞瘡/潰瘍性口内炎)
アルコール依存症
アルツハイマー病
過換気症候群/呼吸パターン異常
過多月経
関節リウマチ
乾癬
感染性下痢症
がんー自然療法による総合的支援
原虫腸管感染
更年期障害
肛門科疾患
骨粗鬆症
子宮筋腫
子宮内膜症
歯周病
情動障害
女性の抜け毛
じんま疹
セルライト
線維筋痛症候群
喘息
単純ヘルペス
中耳炎
つわり
パーキンソン病
肥満症
不眠症
片頭痛
扁平苔癬
膀胱炎
ポルフィリン症
慢性カンジダ症
慢性疲労症候群
免疫力強化
付録
資料1 健康的な献立作りに役立つ食品リスト
資料2 塩酸サプリメントの使用法(患者用)
資料3 ローテーション式食事療法:基本プランIおよびII
索引

- リウマチ・膠原病になったら最初に読む本 -外来通院学2.0-
- 前島 圭佑
- 日本医学出版
- ¥1650
- 2024年10月04日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
リウマチ・膠原病患者さんのための外来通院ガイドブックです。
2019年に発行した前版『リウマチ・膠原病患者さんとそのご家族のための 外来通院学』から大幅改訂しました。
前半は,医師からの説明を理解する手助けとなるよう、医学的言語をかみ砕いて,分かりやすく説明し,外来通院に際して必要な知識を独自の視点でまとめています。
後半は,患者さんがリウマチ・膠原病と上手に付き合うための知識やテクニックを中心に紹介し,どのように病気と付き合うべきかを学べる内容となっています。
本書は読者の方々のリウマチ・膠原病に伴う心身の負担を軽減させることを目指した1冊です。
【対象】リウマチ・膠原病の患者さん、そのご家族など

- 気管支拡張症Up to Date
- 長谷川直樹/森本耕三
- 南江堂
- ¥6600
- 2022年05月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
一時は「消えゆく疾患概念」と考えられていた気管支拡張症だが.欧米において嚢胞性肺線維症と関連しない症例の増加から大規模な患者レジストリへと進展し,近年目覚ましい研究成果をもたらしている.いまや呼吸器領域の一大カテゴリーとなった気管支拡張症について,欧米の最新知見を踏まえ,臨床像から病態,疫学,診断や重症度分類,治療と管理までを体系的にまとめた.