ウェブ の検索結果 標準 順 約 2000 件中 821 から 840 件目(100 頁中 42 頁目) 

- ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑
- 菅原 大介
- マイナビ出版
- ¥2629
- 2019年06月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「ユーザーのニーズがわからない…」とお悩みのあなたも、
「ユーザー対応が社内でバラバラ…」とお嘆きのあなたも、
これ一冊でサイトユーザーの攻略法がまとまる!
サイトリニューアル、新サービスのインキュベーション、マーケティング施策、広告プロモーション、他社サイトとの提携コラボレーション、などなど、ウェブサービスの現場では、「共通のユーザーイメージ」を持って臨まなければならないプロジェクトが多数あります。
プロジェクト内で統一したイメージを持つために、ここ数年増えてきている手法が、「ペルソナ」・「カスタマージャーニー」です。しかし、それらを作成するにあたり、高いハードルとなっているのが、ファーストステップであるユーザーデータを集める工程です。
ここできちんとデータを集め、分析することができないと、データが「使えない」ものになってしまい、結果「ユーザーイメージ」も現実とブレた、使えないものになってしまいます。
そこでカギになってくるのが、「代表的なユーザーイメージ」と「理想的なサイトの体験シナリオ」なのです。
本書は、ネットリサーチ国内最大手の「マクロミル」でアンケート調査によりデータを作成する技術を学び、その後、ウェブサービスの事業会社でリサーチの仕事に10年間携わってきた著者が、「代表的なユーザーイメージ」と「理想的なサイトの体験シナリオ」作りのノウハウを解説するものです。
次のような内容になっています。
・カテゴリ別サイトユーザー図鑑
・ユーザーイメージづくりのセルフワークショップ
・ユーザーイメージの失敗例
・ユーザーイメージのつくり方
・サイトの体験シナリオの失敗例
・サイトの体験シナリオのつくり方
・ユーザーレポートの作成法
・ユーザー勉強会のやり方
・公開リサーチデータの紹介
ぜひ本書を使って、あなたのウェブサイトのユーザーの攻略法を見つけてください。

- ウェブ社会の思想
- 鈴木謙介
- 日本放送出版協会
- ¥1177
- 2007年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.73(24)
「ユビキタス」「ウェブ2・0」「ネットビジネス」…華々しい流行語の陰で何が起きているのか。蓄積された個人情報をもとに、各人の選ぶべき未来が宿命的に提示される。カスタマイズされた情報が氾濫する中で、人は自らの狭い関心に篭もり、他者との連帯も潰えていく。共同性なき未来に、民主主義はどのような形で可能なのか。情報社会の生のゆくえに鋭く迫り、宿命に彩られた時代の希望を探る、著者渾身の一冊。

- スタンダード検査血液学第4版
- 日本検査血液学会
- 医歯薬出版
- ¥8800
- 2021年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ウェブに夢見るバカ
- ニコラス・G.カー/増子久美
- 青土社
- ¥2640
- 2016年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
Facebook、Googleなどが描くバラ色の未来に異を唱え、ネット時代に失われつつある人間性を取り戻すために何ができるかを問う。

- 看護師・臨床工学技士のための 透析シャントエコー入門
- 春口 洋昭
- メディカ出版
- ¥4400
- 2018年07月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
血液透析治療ではシャントが不可欠であり、安定して治療を行うためにはシャントの機能維持が欠かせない。透析室において、日々のシャント管理や穿刺にエコーをどう活用するか、シャントエコーの基礎とポイントを透析室スタッフ向けにやさしく解説。

- Angular Webアプリ開発スタートブック
- 大澤文孝
- ソーテック社
- ¥3025
- 2018年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(3)

- 眼科スゴ技 白内障手術
- 大鹿 哲郎/須藤 史子
- メディカ出版
- ¥16500
- 2018年09月26日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
第一線で活躍するサージャン独自の手術手技や、最新デバイスの知識・使い方 を「スゴ技」として厳選紹介。さらに、核片やIOLが落下した場合の処理など、本書でしか読めない新たな項目も追加。

- 女性のファンが生まれる!「伝わるウェブ」のブランド戦略
- こぼりあきこ
- 同文舘出版
- ¥1870
- 2020年09月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
もう女性客を逃さない!
“消費から体験”時代の小さなお店・会社のウェブ・コミュニケーション
・「自店らしさ」
・「理想のお客様像」
・「市場での立ち位置」
これらを分析し、お客様の居心地がよいホームページをつくりましょう。
女性は雰囲気・世界観で購入を決めます!
あまたのお店・商品とウェブの雰囲気、“ちぐはぐ”になっていませんか?
小さいお店・会社ほどブランディングに取り組みやすいです。
価格や機能では「人の心」が動かない時代だからこそ、「自店らしさ」を正しく伝えるホームページが重要です!
第1章 女性の心を動かすホームページとは
1 最初の「出会い」が分かれ道 -好きになる? or 不信感を持つ?
2 居心地がよい場所かどうか
3 お客様はウェブ上で「接客姿勢」を見ている
4 「誰から買うか」で背中を押す
5 購入後も「買ってよかった」と思ってもらう
第2章 「ホームページブランディング」であなたのお店のファンをつくる
1 ホームページでブランディングすべき3つの理由
2 「ブランディング」と「マーケティング」の違い
第3章 「自店らしさ」「お客様像」「市場での立ち位置」を知って戦略を立てよう
1 「らしさ」=「強み」を探す【自己分析】
2 お客様が、どんな人かをとことん把握する【顧客分析】
3 「ペルソナシート」の本当の活用法
4 市場の中での「立ち位置」を考える【競合分析】
第4章 事例解説! お客様との関係を築くホームページブランディングのプロセス
1 あなたのお店のコンセプトシートをつくる
2 ケーススタディ1 ひとりの時間をゆっくり過ごしてもらうための静かなカフェ fuzkue(東京・初台/下北沢)
3 ケーススタディ2 小さい子どもがいるお母さんのための鍼灸院 しらき鍼灸治療院(東京・小平市)
4 効果的にデザイナーの力を借りよう
第5章 求人・採用にもホームページブランディングは活用できる
1 「採用」もブランディングの時代 --採用難の時代にホームページブランディングが必須である理由
2 「求職者=ペルソナ」という視点
3 採用サイトで職場の魅力を伝える

- フツウのWebデザイナーから卒業して食えるWebクリエイターになるためのWORD
- 吉岡豊
- 秀和システム新社
- ¥1870
- 2018年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
Web業界で食べていく。なぜ今WordPressなのか。アクセス解析/SEO対策/セキュリティ/ユーザーエクスペリエンス/コストカット/トレンドデザイン/などWordPressを「使える」か「使えない」かが、クリエイターの大きな収入差につながっています。

- 伊藤病院ではこう診る!甲状腺疾患超音波アトラス
- 伊藤公一(医学)/北川亘
- 全日本病院出版会
- ¥5280
- 2018年02月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)

- 達人に学ぶGoogleアナリティクス実践講座
- 小川卓(ウェブ解析士)/野口竜司
- 翔泳社
- ¥2860
- 2015年06月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
目標・KPIの設計方法がわからない。用語やメニュー操作が難しそう。顧客タイプ別の分析ってどうやるの?新バージョンへの移行方法が知りたい。分析結果をわかりやすく伝えるレポート作成のコツは?ゼロから学ぶ人でも安心。頼りになる1冊です。

- PythonフレームワークFlaskで学ぶWebアプリケーションのしくみとつくり
- 掌田津耶乃
- ソシム
- ¥3520
- 2019年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
(1)http.serverを使ったアプリ開発。(2)Flaskを使ったアプリ開発。(3)Bootstrapでスタイリング。(4)Vue.jsでSPA開発。(5)データベースとの連携。PythonでWebアプリ開発をゼロから、じっくりと学ぼう。

- Webシステムの開発技術と活用方法
- 速水 治夫/服部 哲/大部 由香/加藤 智也/松本 早野香
- 共立出版
- ¥3080
- 2013年03月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
わたしたちの生活になくてはならなくなったWebをプラットフォームとして,目的地までのルートを検索したりショッピングしたりするなどさまざまなアプリケーション(Webシステム)が数多く動作している。必要に応じてWebサービスやツールを適切に取り入れてWebシステムを開発するためには,Webサーバとクライアント(Webブラウザ)がどのようにメッセージをやり取りしているのか,現在のWebシステムには欠くことのできないデータベース,Webサービスの基礎となっているXMLなど幅広い技術を身につけることが不可欠である。さらに,このような幅広い技術とともに,それらが社会や生活の中でどのように活用されているのか,またそのときのポイントは何かを理解することWebシステムを開発するためには非常に重要である。
そこで,本書は,Webシステムの開発に不可欠な技術的な側面と社会的な側面の両方を体系的に理解できるように解説する。技術的な側面の解説では,具体的なプログラムコードも取り上げ,Webシステムを開発するために必要な知識と技術を詳細に説明する。社会的な側面の解説では,地域コミュニティでの応用を中心に,Webシステムの開発・実践例をシステムの目的や工夫なども含めて紹介し,身近な現場で重要な技術を説明されている。
さらに,大学の学部レベルの情報系学生向けの教科書として利用されることも想定しており,これからWebシステムの開発や実践に取り組みたい人の入門書・参考書として利用されることを期待している。
第1章 Webシステムの概要
1.1 Webシステムとは
1.2 インターネット
1.3 Webシステムの歴史
1.4 HTMLとURIとHTTP
1.5 Webシステムの構成
第2章 HTTP
2.1 HTTPとは
2.2 HTTPリクエストとレスポンス
2.3 リクエストメッセージの詳細
2.4 レスポンスメッセージの詳細
2.5 TCP/IPの基礎知識
第3章 クライアントサイド技術
3.1 クライアントサイド技術とは
3.2 HTML
3.3 クライアントサイドの動的処理技術
第4章 サーバサイド技術
4.1 サーバサイド技術とは
4.2 フォーム処理
4.3 サーバサイドの動的処理技術
4.4 データベース
第5章 Webサービス技術
5.1 Webサービス技術とは
5.2 XML
5.3 XMLWebサービス技術
5.4 REST方式のWebサービス
第6章 Webプログラミング技法
6.1 Webプログラミング技法とは
6.2 マッシュアップ
6.3 セッション管理
6.4 Webシステムのセキュリティ
第7章 Webシステムの事例
7.1 ソーシャルメディア
7.2 地域情報システム

- 高校生WEB作家のモテ生活「あんたが神作家なわけないでしょ」と僕を振った幼馴染が後悔してるけどもう遅い(2)
- 茨木野(GA文庫/SBクリエイティブ刊)/さとうゆう/一乃ゆゆ
- スクウェア・エニックス
- ¥730
- 2023年01月25日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
熱くなる少女達の「想い」「神作家」無双ラブコメ、沸騰中ッ!!!!
神作家と称される天才高校生・上松勇太。才能とは裏腹に性格は純心そのもの。その魅力に惹かれた美少女、アイドル歌手・アリッサとJK声優・由梨恵は勇太をそれぞれデートに誘い…!?一方、勇太=神作家だという事を信じられない幼馴染・みちるはある作戦を実行するのであった。超絶可愛い娘ばかり登場「神作家」争奪ラブコメ、第2幕。

- Web ブラウザセキュリティ Web アプリケーションの安全性を支える仕組みを整理する
- 米内貴志
- ラムダノート
- ¥3080
- 2021年01月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(3)
本書は、「現代のWebブラウザが備えていてアプリケーション開発者にも理解が求められる多様なセキュリティ機構」について、一つひとつ丁寧に整理して解説するものです。 そもそもどんな脅威に対抗するためのセキュリティ機構なのか、現在の形でWebブラウザに導入されているのはなぜか、攻撃者がさらに対抗してくる可能性はないのか、リファレンスなどを通じて使い方を調べるだけでは理解しにくい背景まで掘り下げて説明しています。
攻撃者とWebブラウザ開発者たちとのせめぎ合いの歴史から、Webセキュリティについての理解を深める一冊です。
序文
本書を読み進める前に
本書を読むにあたって
サンプルコードと動作環境を手に入れる
開発者ツールに慣れ親しむ
第1章 WebとWebセキュリティ
1.1 Webを構成する基本の3つのコンポーネント
1.2 プラットフォームとしてのWeb
1.3 Webセキュリティ
1.4 サーバーサイドWebシステムのセキュリティ
1.5 クライアントサイドWebシステムのセキュリティ
1.6 まとめ
第2章 Origin を境界とした基本的な機構
2.1 Webリソース間の論理的な隔離にむけて
2.2 OriginとSame-Origin Policy(SOP)
2.3 CORS(Cross-Origin Resource Sharing)
2.4 CORSを用いないSOPの緩和方法
2.5 SOPの天敵、XSS(Cross-Site Scripting)
2.6 CSP(Content Security Policy)
2.7 Trusted Types
2.8 まとめ
第3章 Webブラウザのプロセス分離によるセキュリティ
3.1 Webブラウザが単一のプロセスで動作することの問題
3.2 プロセスを分離した場合の問題
3.3 Process-per-Browsing-Instanceモデルに対する攻撃
3.4 Process-per-Site-Instanceモデルとその補助機能
3.5 まとめ
第4章 Cookie に関連した機構
4.1 Cookieの導入の動機
4.2 属性によるCookieの保護
4.3 Cookieの性質が引き起こす問題とCookieの今後
4.4 まとめ
第5章 リソースの完全性と機密性に関連する機構
5.1 問題と脅威の整理
5.2 HTTPSとHSTS
5.3 Mixed Contentと安全でないリクエストのアップグレード
5.4 Webブラウザが受け取るデータの完全性とSRI
5.5 Secure Context
5.6 まとめ
第6章 攻撃手法の発展
6.1 3種類の攻撃手法
6.2 CSP下でのXSS
6.3 Scriptless Attack
6.4 サイドチャネル攻撃
6.5 まとめ
あとがき
参考文献
索引

- 応用Web技術 改訂2版
- 松下 温/市村 哲/宇田隆哉
- 株式会社オーム社
- ¥2750
- 2017年02月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
Webサービス構築の技術が実践的に学習できる教科書
Webシステムを利用したビジネスが急速に展開している今日、大学でも実践的なWeb技術の教育が求められるようになりました。
本書は、HTMLなどを解説した「IT Text 基礎Web技術(改訂2版)」の姉妹編として、動的Webページの作成から携帯端末Webサイトの構築、データ管理、セキュリティ技術まで学べる教科書です。
第1章 Webアプリケーション概要
第2章 サーバサイドで作る動的Webページ
第3章 データ管理とWebサービス
第4章 セキュリティと安全
第5章 マルチメディアストリーミング
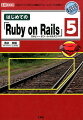
- はじめての「Ruby on Rails」5
- 清水美樹
- 工学社
- ¥2530
- 2016年11月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
これまで「Ruby on Rails」を使ったことがない人や、これから「バージョン5」に乗り換えようと考えている人を対象に、「Ruby on Rails5」の環境導入、簡単なWebアプリの作り方、「バージョン5」の新機能である「Action Cable」を使った「簡単チャットアプリ」の作り方ーなどを解説します。

- 2022年版出る順中小企業診断士FOCUSテキスト&WEB問題 3 企業経営理論
- 東京リーガルマインドLEC総合研究所 中小企業診断士試験部
- 東京リーガルマインド
- ¥2200
- 2021年08月24日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
<3STEPで""試験に出る論点""を効率的に攻略!>
忙しい社会人に人気の中小企業診断士だからこそ生まれた超効率的テキスト。
「要点をとらえる」→「過去問に挑戦する」→「基礎知識を学習する」の3STEPで、ピックアップされた重要テーマのインプットとアウトプットが同時にできる!
<WEB連動により、あなたの学習を充実サポート!>
【1】全テーマの詳細解説つきWEB問題をダウンロード!
テーマごとに掲載している過去問と、その類題の問題・回答・解説がスマートフォンやパソコンで閲覧できます。
この1冊で多くの問題にチャレンジでき、また通勤中や外出先のスキマ時間にも学習できるので、お得&効率的です。
【2】テーマ別ポイント解説動画!
LEC専任講師による本書収録の全テーマの解説動画が無料で視聴できます。
講師が簡潔に解説をしますので、書籍で学習したことがより理解が深まり知識が定着します。
※ご利用には登録が必要です
【3】門外不出!LEC診断士講座の使用教材、応用編テキスト・過去問集を無料進呈!
本書の応用編テキストと、5年分の問題を収録した1次試験過去問題集を購入者特典としてWEB上で無料提供します。
【4】令和3年度1次試験解説動画!
LEC専任講師による令和3年度中小企業診断士1次試験の解説動画が無料で視聴できます。
※WEBページの閲覧期限は2022年11月23日までですので、ご購入の際はご注意ください。

- ずーっと売れるWEBの仕組みのつくりかた
- 伊藤勘司/菅智晃
- 厚有出版
- ¥1980
- 2017年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(2)
WEB集客とセールスが苦手なすべての人に贈る。なぜ集客とセールスの自動化は、いつも失敗するのか?ゼロから始めて仕組みを育てる、王道のWEB集客術。

- 作家の読書道(3)
- Web本の雑誌編集部/本の雑誌編集部
- 本の雑誌社
- ¥1650
- 2010年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.58(14)
人気作家18人の読書ライフ。インタビュアーはTBSテレビ「王様のブランチ」BOOKコーナーでも活躍中の瀧井朝世。