図書館 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 841 から 860 件目(100 頁中 43 頁目) 

- 情報革命の世界史と図書館
- 山口 広文
- 樹村房
- ¥3740
- 2019年07月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
人類は,文明の誕生までさかのぼれば,これまでに文字の創造,紙の普及,印刷術の革新,電信の発明,そしてインターネットを核としたICT技術の浸透と,幾度も情報革命を経験して来ている。
本書では,それらの情報革命をキーワードに世界の歴史と現代社会の構図を改めて整理し、それらに伴う図書館の形成・変貌を視野に入れながら、組織としての役割の変容について考察する。
序 章 粘土板からインターネットへ
第1部 文字と紙が創った世界
第1章 文字革命:情報の保存と文明の形成
第2章 紙の長い旅:東から西へ
第3章 文書庫から図書館への道
第2部 活字とケーブルが拡げた世界
第4章 印刷革命:情報の複製と国民的な情報圏の形成
第5章 電信網の構築と情報のグローバル化
第6章 欧米における図書館の発達
第7章 日本列島の情報革命
第3部 電子情報が渦巻く世界
第8章 ICT革命:情報電子化の激流
第9章 ICT革命と図書館

- SDGsクイズブック楽しく学ぼう!17の目標(全4巻セット)
- 古沢広祐
- 金の星社
- ¥11440
- 2023年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 子グマのジョニー(図書館版)
- アーネスト・T・シートン/今泉 吉晴
- 童心社
- ¥1980
- 2010年07月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
国立公園で食べ物に不自由なく育てられたジョニーは、クマ王国の王子のようにわがままであまえんぼう。ある日、母グマから見捨てられ、体調をくずして……。野生動物と人間とのあり方を問う物語。

- 図書館だよりを作りませんか?
- 太田和順子
- 少年写真新聞社
- ¥2200
- 2017年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 児童図書館サービス(2)
- 日本図書館協会
- 日本図書館協会
- ¥2090
- 2011年11月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 怪談レストランナビ 妖[図書館版]
- 松谷みよ子/たかいよしかず
- 童心社
- ¥1320
- 2009年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ようこそ「怪談レストラン」へ。本日は、数ある「怪談レストラン」の中から、妖怪、妖しいもの、不思議な存在…など妖の世界のお料理をとりそろえました。

- 図書館年鑑 2019
- 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会
- 日本図書館協会
- ¥18700
- 2019年08月09日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2018年1年間の図書館にかかわる事象を記録し,あわせて関連資料を収録しています。
構成は,図書館界の動向を,都道府県・館種・問題別に概観した「図書館概況」,図書館関係統計と資料・書誌を収録した「図書館統計・資料」の2章です。
資料編では,「公立社会教育施設の所管の在り方」,「文部科学省の組織再編」,「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」,「地方交付税制度」,「学校教育法等の一部改正」,「高等学校学習指導要領」,「統合イノベーション戦略」,「指定管理者制度」,「デジタルネットワーク環境における図書館利用のプライバシー保護ガイドライン(案)」,「マラケシュ条約と読書バリアフリー法」,「著作権法の改正」,「出版物への消費税率軽減」などに関する資料や図書館関係法規,そのほか図書館や図書館関係の団体・関連機関・住民運動団体などが発表した要望,声明,決議,答申,報告などの文書で重要なものが収録されています。
また,「図書館関係図書・資料目録」と,『図書館雑誌』2018年1〜12月号の「資料室欄」に掲載された「図書館関係雑誌記事索引」も掲載。

- おはなしのろうそく(10)愛蔵版
- 東京子ども図書館
- 東京子ども図書館
- ¥1760
- 2010年10月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
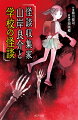
- (図書館版)怪談収集家 山岸良介と学校の怪談
- 緑川 聖司/竹岡 美穂
- ポプラ社
- ¥1320
- 2020年04月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
強烈な霊媒体質の浩介がいよいよ学校へ! 通い始めた小学校には思いもかけない怪談の黒幕がいたーー。
閉じられた空間で、語りつがれることでますます力をつける「学校の怪談」。クラスメイトの園田さんにも危機が迫る!? 浩介は、彼女を救えるのか!?

- 図書館政策資料(14)
- 日本図書館協会
- 日本図書館協会
- ¥1100
- 2015年07月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 図書館版 あの時こうしていれば…… 本当に危ないスマホの話
- 遠藤 美季
- 金の星社
- ¥4180
- 2021年01月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
漫画でスマホの危険・トラブルを回避!
スマートフォンにまつわるトラブルや事件を全9話の漫画で紹介。ストーリーごとにターニングポイントを設け、そこでどんな行動をとれば危険を回避できるのかを徹底解説。スマホやネットを賢く使うための必読書!

- 明治大学図書館所蔵 高句麗広開土王碑拓本
- 明治大学広開土王碑拓本刊行委員会/吉村武彦/加藤友康/徐建新/吉田悦志
- 八木書店
- ¥16500
- 2019年03月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
拓本画像による釈文の再検証ができる!
新たに見つかった明大本2種を含む重要な拓本7種を厳選し、全拓本画像と釈文を一覧に。
明治大学図書館所蔵の拓本2種の全文写真と翻刻を、さらには高句麗広開土王碑と並ぶ重要資料「集安高句麗碑」の解説・全文翻刻を併載。
論考編には、日本と中国の専門家が、最新の知見を書き下ろした論考7本を収録。
第一部 史料編
第一章 整紙本〔写真版〕
第二章 剪装本〔写真版〕
第三章 校訂本文(吉村武彦・加藤友康・矢越葉子・石黒ひさ子)
附 関係史料「集安高句麗碑」翻刻本文・解説(徐建新原著/石黒ひさ子翻訳)
第二部 論考編
第一章 明治大学本の書誌と採拓年代(矢越葉子)
第二章 解 説(吉村武彦)
第三章 広開土王碑拓本の残存数と保存方法(徐建新原著/石黒ひさ子翻訳)
第四章 東アジア学界の広開土王碑研究史(徐建新原著/石黒ひさ子翻訳)
第五章 三・四世紀高句麗都城と中原王朝都城(朱岩石原著/石黒ひさ子翻訳)
第六章 唐代陵戸の再検討(黄正建原著/波多野由美子翻訳)
第七章 集安の遺跡と東アジアの積石塚(河野正訓)
【執筆者】矢越葉子(明治大学研究推進員・日本古代史)/石黒ひさ子(明治大学兼任講師・中国史)/朱岩石(中国社会科学院・中国考古学)/黄正建(中国社会科学院・中国古代史)/河野正訓(東京国立博物館・日本考古学)/波多野由美子(日本中国考古学会会員・日中交流史)

- 怪談オウマガドキ学園【図書館版】(2)
- 怪談オウマガドキ学園編集委員会/常光徹
- 童心社
- ¥1320
- 2013年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識第3版
- 黒澤節男
- 太田出版
- ¥3080
- 2011年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)

- (図書館版)花里小吹奏楽部(4) キミとボクの輪舞曲
- 夕貴 そら/和泉 みお
- ポプラ社
- ¥1540
- 2019年04月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
吹奏楽部を舞台にした青春ストーリー第4弾。全国大会出場に向け予選が始まった。都大会を危なげなく通過し、支部大会を目前に毎日、練習の日々が続いていた。そんな合い間、怜奈は真央たちと夏祭りに。省吾と光真も合流して、ほんの束の間、楽しい時間を満喫する。そして、いよいよ支部大会。ところが、当日、省吾が大会に出られない事態が起きる。急遽、怜奈がクラのパートリーダーになることに……。
01 それぞれの”好き” 02 目指せ支部大会 03 人気者はつらいよ 04 正しい夏休みの過ごし方 05 大橋先生怒る 06 これってヤキモチ? 07 お祭りの夜に 08 かき氷とアンズ飴 09 また明日ね 10 吹部最大のピンチ 11 キミがいないと 12 想いをひとつに 13 ぼくらの未来

- 数ってどこまでかぞえられる?
- ロバート・E.ウェルズ/せなあいこ
- 評論社
- ¥1540
- 2016年03月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.17(6)

- 図書館・まち育て・デモクラシー
- 嶋田 学
- 青弓社
- ¥2860
- 2019年09月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(4)
人々の興味・関心を「持ち寄り」、利用者は世界中の本から自身の気づきを「見つけ」、わかる喜びをほかの人と「分け合う」。図書館は市民の〈知りたい〉を支え、情報のナビゲートを通じて主体性の確立を促す。まちの活性化の鍵は図書館にあると提言する。
はじめに
第1章 図書館を知っていますか?
1 図書館があるということ
2 「わかる」ということ
3 知りたい、学びたいに応える仕事
4 図書館という「場所」と「機能」
コラム 「図書館屋の小さな窓」
第2章 文化としての図書館
1 文化という「物語」
2 子どもの文化と図書館
3 文化格差は埋められるか
4 文化の自己決定能力
コラム 「生活文化」と図書館
第3章 持ち寄り・見つけ・分け合う広場を作るーー瀬戸内市の図書館づくり
1 図書館整備とサービスの現前化
2 正面突破としての「としょかん未来ミーティング」
3 事業承継策としての人材育成
4 「もみわ広場」というコミュニティー
コラム 寄付金に込められた思い
第4章 図書館とまち育て
1 地方分権から市民自治へ
2 地域活性化と図書館
3 社会関係資本(ルビ:ソーシャル・キャピタル)という緩やかなネットワーク
4 図書館が醸し出すエートス
コラム 「お客様」という呼称と「消費者民主主義」
第5章 図書館と蔵書づくり
1 図書館ではどのようにして本が選ばれているか
2 選書をめぐる論争
3 地域政策としての蔵書構築
4 蔵書づくりのあれこれ
コラム 『ぼくは、図書館がすき』--写真家・漆原宏の流儀
第6章 図書館とデモクラシー
1 デモクラシーを支える「死者の声」
2 リベラルアーツと図書館
3 これからの図書館員の仕事
4 図書館・まち育て・デモクラシー
初出一覧
おわりに

- 学校図書館で役立つレファレンス・テクニック
- 齊藤誠一
- 少年写真新聞社
- ¥1760
- 2018年06月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(5)
レファレンスの基本的な心構え、利用者とのコミュニケーション、レファレンスブックの使い方など、豊富な事例をもとに学校図書館で役立つテクニックを紹介します。学校図書館職員のレファレンス力のアップとともに、調べる楽しさ・面白さを生徒に伝えられます。

- 道徳図書館みんなといのちの章(3巻セット)
- 文渓堂
- ¥10560
- 2019年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ローズの小さな図書館
- キンバリー・ウィリス・ホルト/谷口由美子
- 徳間書店
- ¥1760
- 2013年07月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.33(3)
一九三九年、農場は干ばつにみまわれ、水をくむ風車がこわれ、パパも家を出ていってしまった。ママは、私と弟と妹をつれてふるさとルイジアナの川辺の町に移ることに決めた…。十四歳のローズは、家族のために年をごまかし、図書館バスのドライバーとして働きはじめる。でもその後も、作家になる夢はずっと忘れなかったー。戦前のローズから始まり、その息子、孫、ひ孫、と四世代にわたる十代の少年少女を生き生きと描きます。時代ごとに、『大地』、『怒りの蔔萄』、「ハリー・ポッター」など話題の本が登場。本への愛がつなぐ家族の姿を描く、心に残る物語。