ジェンダー の検索結果 標準 順 約 2000 件中 921 から 940 件目(100 頁中 47 頁目) 

- 張扇一筋ジェンダー講談
- 宝井琴桜
- 悠飛社
- ¥1540
- 2002年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
ジェンダー(社会的性差)問題を、肩肘はらない噺『山下さんちの物語シリーズ』に仕立て、女性として初の真打となった著者が、その痛快でユーモアに満ちた人生を語る。

- 変容するジェンダー
- 勉誠社
- ¥1980
- 2002年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 高校生のジェンダーとセクシュアリティ
- 須藤廣
- 明石書店
- ¥1650
- 2002年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)

- ジェンダーとアメリカ文学
- 原恵理子
- 勁草書房
- ¥2860
- 2002年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ジェンダーと人種を分析概念に、歴史認識と文学作品を読み解く。多文化社会アメリカの表象を問い、有色人の女性たちの語られなかった声を聴く。

- ジェンダ-の社会学改訂新版
- 江原由美子/山田昌弘
- 放送大学教育振興会
- ¥2530
- 2003年03月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 心理学とジェンダー
- 柏木恵子/高橋恵子(発達心理学)
- 有斐閣
- ¥2640
- 2003年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
ジェンダー・フリーを支援できるような、あるいは既存の理論、制度、常識の中のジェンダー・バイアスを的確に掘り起こすような、心理学の研究とはいかなるものであろうか。それを具体的な研究で示したのが本書である。本書はジェンダーの視点を取り入れた心理学研究とはいかなるものかを、家族関係、教育・学校生活、社会生活、臨床・実践の4分野の中から、32編の優れた研究を選んで、具体的な実証研究を通して明らかにしたわが国初の研究案内の手引き書である。ジェンダー研究に関心をもつ学生、大学院生、研究者の必読書。

- ジェンダー医学
- 芦田みどり
- 金芳堂
- ¥4620
- 2003年03月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ジェンダーで学ぶ教育
- 天野正子/木村涼子
- 世界思想社
- ¥2090
- 2003年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
女なら、あたりまえ。男だから、当然。そんな「常識」にクサビを打ち込めば、何が見かてくるだろう。ライフコースに沿って、ジェンダーの視点から教育を問い直す、新たなテクストの誕生。

- ジェンダー・フリーってなあに?(1)
- 草谷桂子/鈴木まもる
- 大月書店
- ¥1760
- 2003年05月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(1)
一人ひとりの個性を大切に育みあうことの大切さを、ジェンダー・フリーの視点で描く絵本。幼児・低学年向き。

- ジェンダーがわかる。
- 朝日新聞出版
- ¥1430
- 2002年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(6)

- ジェンダ-・組織・制度
- 数家鉄治
- 白桃書房
- ¥3960
- 2003年06月06日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ジェンダーと教育の歴史
- 橋本紀子/逸見勝亮
- 川島書店
- ¥3300
- 2003年05月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
近年、教育史研究においても、男性中心の事件史、政権交代史ではなく、女性を含めた視点にたつ民衆史、生活史として、また社会史としてとらえ直そうとする試みがすすんでいる。本書は、それらの動向、とりわけフェミニズムの視点からの先行研究をふまえながらも、さらに越えて、両性の関係性を射程に入れたジェンダーの視点をとることによって、各時代がかかえていた教育史的課題を明らかにしようとした最新の研究成果である。女性と男性という性差をもつ人間が、歴史的にどのように形成され、どのような関係を築いてきたのかを、誕生から死にいたる人間発達のいとなみの側面から具体的に描き出そうとする意欲的な論考によって構成されており、これまで見えなかった歴史の諸相にあらたな光を投げかけている。

- 身体、ジェンダー、エスニシティ
- 鴨川卓博/伊藤貞基
- 英宝社
- ¥4180
- 2003年09月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
急速な情報の増大と断片化が、重要なパラダイム転換を迫っている。ポスト・ポストモダンの現在、アメリカ文学は人間をどう扱い表象しているか。身体は?ジェンダーは?エスニシティは。

- 日本近代国家の成立とジェンダー
- 氏家幹人
- 柏書房
- ¥4620
- 2003年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
近代日本の「性差」「性」の領域へ切り込む、歴史学の空白を生める「知」の議論。歴史・経済・思想・文学などの多様な視線から、学際的・国際的視野に立ってジェンダー・アプローチした、気鋭の研究者11人による共同研究の成果。

- 短歌のジェンダー
- 阿木津英
- 本阿弥書店
- ¥1980
- 2003年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書の第一章では、古くから女性が活躍し、女の言葉が蓄積された“短歌”に、異分野から光をあてる。第2章では、ジェンダーの観点から、日本文化を見直す。

- 知っていますか?ジェンダ-と人権一問一答
- 船橋邦子
- 解放出版社
- ¥1100
- 2003年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
この本ではまず第一に、「ジェンダーとは何か」の問いに対して、可能なかぎり、わかりやすい言葉で説明する努力をしました。性差別をなくすことを目的とするフェミニズムとの関係、女性差別という表現とどう違うのかについてもふれました。第二に、ジェンダーというメガネをとおして、学校、スポーツ、家族、労働、絵画、途上国での開発、戦争など、総合的(ホリスティック)に現代社会をとらえることを試みました。第三には、政策課題として男女共同参画を推進することの意味を確認することです。

- 女性・人間関係・ジェンダー
- 四之宮玲子
- 八千代出版
- ¥1980
- 2003年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書では、「女性」というジェンダーに絞り、まず女性特有の職業であるとされる秘書の業務と意識の関連とその実態を調査し、論述している。次に秘書業務だけでなく、表面化された男女ジェンダー間のトラブルについて職場と家庭双方を取り上げている。これらの動向を見ることにより、ジェンダー・トラブルの変化を捉え、いかなる要因がジェンダー意識を変化させ、新たな現象を構築していくのか分析を試みた。
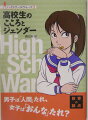
- 高校生のこころとジェンダ-
- 鍋島祥郎
- 解放出版社
- ¥1320
- 2003年12月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ジェンダーと人口問題
- 阿藤誠/早瀬保子
- 原書房
- ¥3520
- 2004年01月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、発展途上国ならびに先進国(主として日本)における人口動態ならびに人口構造のいくつかの側面をとりあげ、それらを性差、性比、ジェンダーの視点から再検討し、日本の人口研究に新しい視点を定着させると同時に、ジェンダー的視点をもった他の研究分野の実証研究の発展に寄与することを目指したものである。

- 都市空間とジェンダー
- 影山穂波
- 古今書院
- ¥5500
- 2004年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)