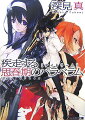思春期 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1081 から 1100 件目(100 頁中 55 頁目) 

- 「ああ、そうか」と気づく「子育てQ&A」(思春期・青年期50例集)
- 2009年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「中学生の外孫が不登校、母はうつ症」「深夜帰りの中学息子、父親は母親任せ」「反抗的に母を避け食欲不振の女子高生」「やる気のない高二の息子の思いがつかめない」「試験日が近づくと体調を崩し、大学受験が心配」「引きこもり過食や嘔吐する女子大生」など、思春期・青年期のさまざまな悩みに、ベテランの臨床心理士が答える。

- 思春期のこころ
- 1996年07月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
思春期は子どもから大人に向かう不安定な年頃。この時期、生じやすいこころの揺れや病い-不登校、拒食、非行、対人恐怖、うつ、精神分裂病、いじめ等々。その原因や背景はなにか。家族や学校、今日の風潮についてはどこに問題があるのか。親や教師、医師の対応の原則とはなにか。子どもとの適切な距離を保てない親や大人になれない若ものの急増、個別生徒に目の届かない学校の問題を含め、思春期精神医療の第一人者が、30年にわたる臨床体験から、広い視野と深い洞察をもって考える。

- 思春期臨床の考え方・すすめ方
- 2007年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
本書は、思春期という特殊な時期について、また思春期に見られる個々の病理について、最新研究や報告を踏まえて、現在どのような視点から考えられ、どのような治療的アプローチがなされるようになったかを16人の経験豊かな臨床家が論じたものである。まず、従来から思春期臨床の中心テーマでありつづける境界性パーソナリティ障害・摂食障害をはじめ、わが国の思春期に特徴的な不登校・ひきこもり、そして社会不安障害(social anxiety disorder:SAD)の視点から捉え直されつつある対人恐怖症などの現在的な問題を取り上げる。つづいて、近年注目を集めている思春期のうつ病、発達障害、身体醜形恐怖、解離性障害などの新たな問題に触れ、最終部ではますます深刻化する自傷、自殺、性的非行など、行動化の問題にも考察を加えた。それらの疾患に対する、認知行動療法、心理教育などの近年登場した新たな治療的アプローチを、豊富な臨床例を通して解説している。

- あの頃マンガは思春期だった
- 2000年09月06日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
妄想癖の強かった少年時代に読んだ「サイボーグ009」。性に目覚める頃、強い印象を受けた「サスケ」の中の入浴シーン。「フーテン」に憧れた高校時代。漫研で活躍し、恋とジャズ修業に励む、大学生に影響を与えた真崎守、宮谷一彦、川本コオ、エモリ・I、佐々木マキ、山上たつひこ…恥多き青春の思い出を語りつつ、戦後マンガの歴史を新たな角度から描く。

- 自分らしく思春期
- 1997年12月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
子どもたちの不安やいらだちを「輝き」に変える。いま、親と教師が子どもといっしょにできること。

- 小児救急医が診る思春期の子どもたち
- 2010年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
若年妊娠、不登校、自傷行為、自殺未遂、薬物乱用、摂食障害、適応障害、起立性調節障害、過敏性腸症候群など。小児救急で遭遇した思春期の子どもたち11症例を紹介。

- 思春期のからだとこころ
- 2007年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
大人になるとはどういうことなのか。性についての正しい知識を求める10代の子どもたちへ、子どもの疑問に適切に答えたいと願う親・教師・心理臨床に携わる人たちへ。

- 思春期精神科症例集
- 若林慎一郎教授退官記念行事委員会
- 金剛出版
- ¥4400
- 1993年03月13日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 思春期のこころが壊れるとき
- 1998年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
思春期のさまざまな事件や現象は、子どもからのSOS。命がけのメッセージを親はどう受けとめ、どうかかわる?心理臨床家であり、3人の子どもを持つ著者が、自らの体験と豊富な事例をもとに解き明かす。

- LOVE
- 2020年01月15日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
K-POP最強の音源女王!!
アン・ジヨン(Vocal)とウ・ジユン(Guitar)からなる、韓国発2人組女性デュオ「赤頬思春期」(英:BOL4)は「思春期の記憶・残像」をテーマに自ら作詞・作曲・演奏を行う。その独特な感性とジヨンの透明感溢れる歌声で生み出される楽
曲は“唯一無二”の存在感を放ち、聴く者の心を癒し魅了する。2016年に韓国でデビューすると、その類い希な才能は瞬く間に開花。
1stAlbum「RED PLANET」に収録されたリード曲「Galaxy(宇宙をあげる)」は韓国内の多数の音楽ランキングで1位を獲得。以降も立て続けにヒ
ットを重ね、多くの主要アワードで受賞を果たすなど名実ともにスターダムに登り詰めた。
2019年6月に待望の日本デビューを果たし、サマーソニック2019にも出演。今後の日本活動に大きな注目が集まっている。