PHP の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1101 から 1120 件目(100 頁中 56 頁目) 

- 仕事の思想
- 田坂 広志
- PHP研究所
- ¥836
- 2003年09月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.02(94)
なぜ、我々は働くのか。この深い問いに対しては、あくまでも、私たち自身が、その人生と思索を通じて、答えを見つけていかなければなりません。本書は、その思索を深めるために、仕事の真の報酬とは何か、を始めとする様々なテーマについて、著者の体験的なエピソードを交え、語っていきます。仕事を通じていかに成長していくか。成長のために夢や目標はいかなる意味を持つのか。なぜ顧客は成長の鏡となるのか。顧客との共感ということの本当の意味は何か。人間学を学び、人間力を身につけていくための唯一の方法は何か。なぜ、人間との格闘が大切なのか。働く人間にとって地位とは何か。生涯、会うことのない友人が、なぜ、我々の支えとなるのか。仕事の本当の作品とは何か。職場の仲間とは何か。仕事において、未来とは何か。そして、なぜ、仕事に思想が求められるのか。それらのテーマを深く考えることを通じ、読者一人ひとりに、生き方と働き方を問う本です。
●第1話 思想/現実に流されないための錨 ●第2話 成長/決して失われることのない報酬 ●第3話 目標/成長していくための最高の方法 ●第4話 顧客/こころの姿勢を映し出す鏡 ●第5話 共感/相手の真実を感じとる力量 ●第6話 格闘/人間力を磨くための唯一の道 ●第7話 地位/部下の人生に責任を持つ覚悟 ●第8話 友人/頂上での再会を約束した人々 ●第9話 仲間/仕事が残すもうひとつの作品 ●第10話 未来/後生を待ちて今日の務めを果たすとき

- 青鬼 異形(いぎょう)編
- noprops/黒田研二/鈴羅木かりん
- PHP研究所
- ¥1100
- 2014年08月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(4)
累計30万部突破の『青鬼』公式ノベル第3弾がついに発売! 青鬼との鬼ごっこが、3度、繰り広げられます。今作では原作ゲームの完成版とされるver6.23をベースに小説化。物語は大きな展開を迎え、更に加速していきます!▼特典:早期購入者を対象に『青鬼 闇蘇露編』との連動購入キャンペーンを実施!▼【あらすじ】▼前回の惨劇から2週間。ひろしたちは日常を取り戻しつつあった。しかし、ジェイルハウスの権利を持つ卓郎の父親が、卓郎の説得を拒み、屋敷の内部調査に向かうことが判明。シュンは、これ以上の犠牲を阻止すべく、自作ゲームのヴァージョンアップに奮戦する。ひろしたちが日常を取り戻したのとは逆に、青い怪物に襲われる悪夢にうなされ、眠れぬ日々を過ごすたけし。彼は悪夢の原因を、ジェイルハウスに住む怪物だと考え始め……。

- 仙石秀久、戦国を駆ける
- 志木沢郁
- PHP研究所
- ¥968
- 2015年12月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
戦場逃亡という戦国史屈指の汚名を残した武将は、かくも涼やかないい男だった! 仙石秀久の波乱の生涯を新解釈で活写した本格歴史小説。

- 日本人だけが知らない「本当の世界史」中世編
- 倉山 満
- PHP研究所
- ¥1056
- 2022年06月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(6)
客観的に正しい歴史など存在しない。日本人が信じる「世界史」を疑え!
ギリシャもローマも、常にオリエントの世界に屈服し続けた。アレキサンダー大王や五賢帝は、例外にすぎない。その例外を特筆大書し、さも「常に西洋は人類の中心だった」と描いているのが、日本人が信じる「世界史」だ。別に西洋人を噓つきと糾弾する必要はない。どこの国でも、歴史の記述とはそういうものだ。
人によって「世界史」とは何なのかの定義は違って良い。むしろ歴史家が千人いれば千の「世界史」の定義がなければおかしい。本書をおのおのが「世界史」とは何なのかを考える材料としてほしい。 (「文庫版 はじめに」より抜粋)
(目次)
●第一章 世界史の正体と日本
●第二章 十字軍の爪痕
●第三章 世界史を語る視点としての鎌倉幕府
●第四章 暗黒の中世の終焉と室町幕府
●第五章 中世と近代のはざまで
『真実の世界史講義 中世編』を改題の上、文庫化。

- 京都祇園もも吉庵のあまから帖4
- 志賀内 泰弘
- PHP研究所
- ¥825
- 2021年09月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(7)
京都・祇園の片隅にひっそりと佇む甘味処「もも吉庵」。
店を営む元芸妓のもも吉の、趣向を凝らした麩もちぜんざいと人柄に惹かれ、お客が今日も訪れるーー。
楽しいはずの修学旅行で、終始沈んだ表情の女の子が抱える事情とは。
病のため職を失った男が起こした、思いもよらぬ行動。
声を失った舞妓と、駆け出しの料理人の淡い恋。
ーー古都の風情と、花街に集う人々のひたむきに生きる姿を描いた人情物語。
朝日新聞、読売新聞、中日新聞、夕刊フジ、MBSラジオ、雑誌「ダ・ヴィンチ」……、各メディアで話題の人気シリーズ第四弾。
文庫オリジナル。

- 健康の9割は腸内環境で決まる
- 松生 恒夫
- PHP研究所
- ¥968
- 2021年11月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
2019年「国民生活基礎調査」によると、便秘を感じている人の数は 431.5万人。また、大腸がんの罹患者の数も1975年と比較すると8倍以上増え、15万人を突破した。
これまで5万件以上の大腸内視鏡検査をおこない、日本人の腸を見続けてきた著者は、これら疾患の原因は現代の日本人の食物繊維不足にあると警鐘を鳴らす。
大腸がんの罹患者が少なかった1960年代頃まで多くの日本人は、大麦を使った麦ご飯で食物繊維を摂取していた。
そのメリットは、ご飯として毎食、手軽に摂れること、さらに大麦には水溶性食物繊維が多く含まれていることだ。水溶性食物繊維は、私たちの健康に不可欠な「酪酸」を多く産生するための原料になる。
近年、酪酸には、整腸作用のほか、潰瘍性大腸炎などの腸疾患の改善、自己免疫疾患の抑制、肥満細胞の抑制、血糖値のコントロールなどの効果が判明してきた。
腸内環境を整えることで疾患の多くが改善する可能性がある!

- 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54字の物語13
- 氏田 雄介/武田 侑大
- PHP研究所
- ¥1320
- 2025年05月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(4)
現役小中学生、大絶賛! 累計90万部突破の人気シリーズ第13巻は、「学校生活」をテーマにしたちょっと不思議な90話を収録。
【あなたはこの物語の意味、わかりますかーー?】
●変化のない学校生活に飽き、通学路で寄り道をしてみた。目の前に「この先はマップがありません」と表示が浮かんだ。
●入試問題のデータを事前に入手できたので、合格は余裕だった。私は模範的な生徒としてスパイ養成学校に迎えられた。
●真面目な所が好きで付き合った彼。借りたノートも字が綺麗。でも気づいたの。丁寧なのは最初の数ページだけだって。
物語の解説&他の物語は、ぜひ本書でお楽しみください!
【小中学生の声】
●初めて小説が好きになりました。(小6/つぐみさん)
●読み始めたら止まらない。(中1/箕面のまるさん)
●「?」が「!」に変わる瞬間、いつも頭がゾワッとします。(中2/一葉さん)
●長編小説を読んだときみたいな満足感。(中2/嘉城さん)
●本をあまり読まない私でも、楽しく読めた。(小5/衣織さん)
【目次】
●一時間目:不穏な日常……歓迎/先手/ウソデミック/衝撃的な出会い/抜き撃ちテスト/睡眠具/判定/大規模/ほうかご/暗闇/模擬人生/模擬生徒/閉鎖作戦/狼人/スキップ不可/おつかい/◯(まる)/数を楽しむ/見るな
●二時間目:巧みな授業……検証不能/落書き/神頼み/元号/安眠装置/こだわり/完成度/苦手科目/跳び箱/正確な答え/効率的な学び
●三時間目:明るい教室……王の席替え/青木さんの悩み/点呼/消失/授業は中断/カーテン裏の声/自白/いきもの/当番/ロボット掃除/延期/複雑な時間割
●四時間目:眩しい青春……完璧な作戦/見分け方/身体が資本/期待の星/スクール・オブ・フィッシュ/文化部の戦略/借り物の恋人/衝動/サヨナラ/最短距離/初心/お前のことが/不器用な彼女/成就率/ずっと友達
●五時間目:日々の生活……トウコウ/予備/見逃せない/永い朝礼/スカウト/未実装/貴重な夏休み/顔/野心/夏休み最後の日/天使の秘密/第三者面談/第三の選択肢/実技/間違った努力/一年越しの告知
●六時間目:楽しい学校……部活の幽霊/ないの/全員校長/本の住人/月面宙返り/早弁/均衡/ほけん室/自動車の学校/絶滅校/進路/係の飼育/老化/図書館の怪物/即完/長髪禁止/交代

- 「どうせ無理」と思っている君へ
- 植松努
- PHP研究所
- ¥1650
- 2017年03月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.2(40)
「どうせ無理」に負けないで。北海道の町工場で、ロケット開発をしている植松努さんが、本当の自信を取り戻す方法を教えてくれる本。

- 「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける
- 関 裕二
- PHP研究所
- ¥814
- 2021年09月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(4)
祝 2021年 「北海道・北東北の縄文遺跡群」 世界文化遺産登録!
渡来人の影響は限定的だった!
DNA分析からわかる驚きの結果
これまで、縄文の文化は渡来人の文化によって
一掃されたと考えられてきたが、大きな誤りだった。
縄文人たちの暮らしは決して原始的ではなかったのだ。
現代日本に通じる信仰と習俗、生活がすでに縄文時代に完成されていたのである!
◎縄文観を塗り替えた三内丸山遺跡
◎縄文時代に階級の差が生まれていた
◎日本人はどこからやってきたのか
◎世界的にも珍しい日本列島の遺伝子の多様性
◎弥生時代に伝えられた縄文の第二の道具
◎縄文人が水田稲作を始めていた証拠
◎戦争は農耕とともに始まった
◎ヤマト建国は縄文への揺り戻しだった?
◎平和な時代に戻りたいと願った日本人
日本は縄文時代からガラパゴスだった!
世界を驚かせた縄文文明とは?
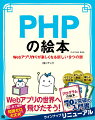
- PHPの絵本 第2版 Webアプリ作りが楽しくなる新しい9つの扉
- 株式会社アンク
- 翔泳社
- ¥1848
- 2017年04月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
PHPは、さまざまなWebアプリケーションが簡単に作れそうなので、興味のある人は多いのではないでしょうか。本書は、イラストで解説しているので、難しい概念も直観的にイメージができ、理解が進みます。さぁ、PHPの扉を開き、できるプログラマへの道を進んでみましょう!

- 原爆の落ちた日[決定版]
- 半藤一利/湯川豊
- PHP研究所
- ¥1320
- 2015年07月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
原爆はなぜ落とされたのか、そしてそれが今日問いかけるものとは……。日米独それぞれの視点を交えた迫真のドキュメントの決定版。

- 【謝恩価格本】なぜか金運を呼び込む人の「すごい!お金の法則」
- PHP研究所
- PHP研究所
- ¥880
- 2018年07月09日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ワタナベ薫氏、本田健氏など、引き寄せのスペシャリスト21人が、金運を呼び込む驚きの方法を一挙公開! 読むだけで、お金のめぐりがよくなる充実の1冊です。
FUMITO氏による「幸運が舞い込む不思議な写真」が特別付録!
◎ワタナベ薫ーー人生がガラリと変わるお金の「使い方」
◎本田 健ーー才能をお金にかえてワクワクした人生を!
◎田宮陽子ーー「お金持ち」にならう一生お金に困らない習慣
◎ゲッターズ飯田ーー自分の欲望を知って、運気の変化を乗り切ろう!
◎FUMITO--見たい景色、してみたい経験。お金はそのためのツール
◎中井耀香ーー敬意を払って接すれば、お金と相思相愛になれる
◎心屋仁之助ーーがんばるのをやめると、どんどんお金が回る
◎かずみんーー妄想パワーで、幸せもお金も恋も引き寄せる
◎羽賀ヒカルーー神さまに上手にお願いすれば、お金持ちも夢じゃない
◎MACO--ネガティブでもうまくいく! MACO式引き寄せメソッド
◎ボルサリーノ 関 好江ーー食材パワーの開運飯で、運気がグンとアップする
◎宮本佳実ーー好きなことを好きな時間に! 可愛く楽しく年収1000万円
◎タマオキアヤーーワクワクのために出したお金は戻ってくる
◎浅野美佐子ーーあなたの財布を「開運財布」にする秘訣
◎キャメレオン竹田ーー神さまからのゴーサイン! 波動でいいこと連発ライフ
◎まさよーーエネルギーの魔法で夢を叶え、人生を輝かせる
◎斎藤芳乃ーー貧乏の箱から抜け出せば、愛もお金も手に入る!
◎藤本さきこーー神さまに愛されるように願いを3行に書くだけ
◎碇のりこーー「結界」をはることで、「いいこと」だけ引き寄せる
◎小野寺S一貴ーー龍神ガガが教えてくれた正しいお金の使い方
◎伊藤勇司ーー貧乏神を追い払って、座敷わらしを呼ぶ部屋づくり

- 文蔵 2020.5
- 「文蔵」編集部
- PHP研究所
- ¥770
- 2020年04月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
新学期に新生活、そして新入社。「春の出会い」は、ただの1秒を永遠にするーー。思わず胸がときめく瞬間を掬い取った小説を特集。

- 文蔵2023.1・2
- 「文蔵」編集部
- PHP研究所
- ¥825
- 2022年12月19日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
こんなミステリー、今まで読んだことない! 奇抜な特殊設定、奇想天外なトリック。新たな挑戦を続ける注目の若手作家の作品を紹介。

- [愛蔵版]松下幸之助一日一話
- PHP総合研究所
- PHP研究所
- ¥1100
- 2007年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.43(16)
現在でも経営者をはじめ、多くの人々からの支持を集める松下幸之助。松下電器グループの創設者として著名であるが、いまだ人気を集める理由はその「哲学」にある。▼9歳で単身奉公に出た松下幸之助は、病弱な身体を抱えながらも、一歩ずつ着実に歩みを進め、さまざまな苦難を乗り越えた末に、日本を代表する経営者となる。困難な時代を乗り越えた人生経験と、また経営者としてのさまざまな体験から得た考えは示唆に富み、今を生きる私たちに、前向きな気持ちを与えてくれるのである。▼本書は、これまで多くの人々に勇気をあたえ、成功への指針を示した松下幸之助の言葉365編を収録。経験と洞察から生まれた松下哲学を伝える書である。▼「新年は偉大なことを成し遂げる」「熱意は磁石」「ほんとうの勇気」など、壁につきあたったとき、あきらめの心が頭をもたげてきたときにも、新しい発見と喜びを与えてくれる珠玉の一冊。
●1月 ●2月 ●3月 ●4月 ●5月 ●6月 ●7月 ●8月 ●9月 ●10月 ●11月 ●12月 ●出典一覧 ●内容索引

- PHPフレームワークSymfony 4入門
- 掌田津耶乃
- 秀和システム
- ¥3300
- 2018年12月14日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
PHPでWebアプリケーションを開発するフレームワークには種々ありますが、常に高い評価を得ているのがSymfony(シンフォニー)。実績も安定感も抜群です。そのSymfonyが2017年末にバージョン4になり、2018年5月には4.1がリリースされて高速化・軽量化が図られています。本書は、そんな新しいSymfonyのわかりやすい入門書です。
もし、あなたが「PHPのスタンダードといえて、この先、もっとも安定して使い続けられるもの」を選びたいと思ったなら、学ぶべきはSymfonyでしょう。Symfonyは、MVCアーキテクチャーに基づいて設計されており、およそWebアプリケーション開発に必要となる諸機能をほとんど網羅しています。非常に堅牢であり、大規模開発に多くの実績を持っています。また、現在のバージョン4ではマイクロサービスを導入するなど、王道を歩みながらも常に最新の技術を取り入れています。あらゆる機能をカスタマイズし、開発者がすべてを制御できるように設計されているのも特徴です。
しかも、現在人気急上昇中であるLaravelや、日本で人気の高いCakePHP、アジアや東欧などで広く使われるYiiなど、多くのフレームワークが、実は内部でSymfonyを使っています。そういった意味でも、SymfonyはPHPの「スタンダード」といえます。PHPフレームワークの中央にSymfonyがあり、それを中心にあらゆるフレームワークが構築されている、といってもよいでしょう。
Chapter 1 Symfony を準備する
1-1 インストールとセットアップ
1-2 プロジェクトの作成と実行
Chapter 2 コントローラーとルーティング
2-1 コントローラーの基本
2-2 コントローラーに関する諸機能
Chapter 3 テンプレートとビューの基本
3-1 Twig テンプレートの利用
3-2 フォームの利用
3-3 Twig テンプレートを使いこなす
Chapter 4 データベースとDoctrine ORM
4-1 データベース利用の準備
4-2 エンティティとリポジトリの基本
4-3 CRUD の基本
Chapter 5 データベースを使いこなす
5-1 検索とリポジトリの拡張
5-2 検索を更に探求する
5-3 DQL/SQL の実行
5-4 バリデーション
5-5 複数テーブルの連携
Chapter 6 ページネーション、ファイルアクセス、フラッシュメッセージ、ユーザー認証
6-1 ページネーション
6-2 ファイルアクセス
6-3 フラッシュメッセージ
6-4 ユーザー認証
Chapter 7 Symfony の拡張
7-1 サービスの作成
7-2 バリデーターの作成
7-3 Twig の拡張

- ラストで君は「まさか!」と言う 冬の物語
- PHP研究所
- PHP研究所
- ¥1100
- 2019年09月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
人気シリーズ第9弾!
誰にも予測できない3分間。冬に読みたいショートストーリー!
【本書の特徴】
★3分間ショートストーリー×25話! 朝読にもぴったり!
★雪の日のお話、クリスマス、お正月、節分、バレンタインなど、冬ならではのお話を収録。
★ラストには「まさか!」のエンディングをお約束! ひんやり冷たい「冬」のお話をあなたに。
【もくじ】
プロローグ/消えないで雪だるま/鍋神/猫の手/てぶくろ かたっぽ/凍れる星の論争/冬の気配/氷のジジイ/裏サンタとユメ/冬のポケット/花を抱いた人/抜け道/葉っぱの地図/雪女を待ってる/コタツ天使/お助け地蔵/初雪コーヒー倶楽部/書き初め/大罪/餅姫/ぼくの青いコート/雪の下には何かが埋まっている/ふきだしの森/ドキドキバレンタイン/さよなら、ユキコ

- 特攻隊員と大刀洗飛行場
- 安部 龍太郎
- PHP研究所
- ¥968
- 2021年07月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
昭和20年(1945)3月、重要拠点ゆえにB29に爆撃され、壊滅的被害を受けた大刀洗飛行場(福岡県)。
大正8年(1919)に完成したこの飛行場は、その後、陸軍飛行学校や技能者養成所が置かれ、東洋一と謳われた。
国民学校を卒業したばかりの15歳の少年たちは、この地で速成され、ある者は整備兵として、そしてある者は特攻兵として戦場へと送り出されていったのである。
当時を知る者が数少なくなる中、大刀洗飛行場で若き日を送った4人に、直木賞作家・安部龍太郎が取材。
古代から近代まで、数多くの歴史小説を上梓してきた著者が、満を持して初めて「太平洋戦争」に取り組んだ。
【目次】●序章 大刀洗飛行場を訪ねて●第一章 松隈嵩氏への取材ーー技術者たちの苦闘●第二章 信国常実氏への取材ーー生き地獄を味わった整備士●第三章 河野孝弘氏への取材ーー陸軍の迷走と「さくら弾機事件」●第四章 末吉初男氏への取材ーー特攻兵の届かなかった手紙

- なぜ皮膚はかゆくなるのか
- 菊池新
- PHP研究所
- ¥836
- 2014年10月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.56(11)
「掻いちゃだめ」といわれても、脳は「掻いて」という……▼(1)原因を突き止めて取り除く (2)「かゆみスパイラル」を止めるーーどちらか一方だけでは解決しない。これを同時並行してしか、かゆみは消えません。▼どうして皮膚はかゆくなるのか? なぜ掻くと快感を得られるのか? 最近になって解明されつつあるそのメカニズムをわかりやすく説明。▼体の中で掻けるところしかかゆくならない、「かゆかった」記憶からかゆみが復活する、ストレスが悪化させるといった特性のほか、これまでは「かゆみは軽い痛み」と考えられていたがそれが完全な誤解であることなど一般化していた間違いも解説する。▼皮膚が無性にかゆくなるのは、イッチ・スクラッチサイクルによるものだ。その負のスパイラルを止める方法、原因の探し方、取り除く例など、著者が長年みてきた実際の治療エピソードを交えて紹介していく。

- 稲盛和夫の哲学
- 稲盛和夫
- PHP研究所
- ¥814
- 2003年07月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.41(49)
「人は何のために生きるのか」。この根本的な問いに、本書で真正面から対峙し答えているのが、一代で京セラを世界的企業に育てた稲盛和夫である。▼戦後、私たちは物質的に豊かな社会を実現するべく懸命に働き、そして、荒廃した日本を見事再建に導いた。▼にもかかわらず、今、多くの人の心は満たされることなく、毎日不安を抱きながら過ごしいる。なぜなのだろうか?▼本書で稲盛はこう答えている。「人間の生き方や考え方について真剣に考えることなく、また足ることも、人を思いやることも忘れ、ただ利己的に生きているからではないか」。▼現代のように自由な社会では、確かに私たちはどのような考えをもって生きようと自由であり、、誰からの制約を受けるわけではない。▼しかし、人生に対する考え方により、その結果が大きく変わることを私たちは知っておかなければならない。「自分は何のために生きるのか」。本書は自分の人生を考える契機になるだろう。
●第1章 人間の存在と生きる価値について ●第2章 宇宙について ●第3章 意識について ●第4章 創造主について ●第5章 欲望について ●第6章 意識体と魂について ●第7章 科学について ●第8章 人間の本性について ●第9章 自由について ●第10章 若者の犯罪について ●第11章 人生の目的について ●第12章 運命と因果応報の法則について ●第13章 人生の試練について ●第14章 苦悩と憎しみについて ●第15章 逆境について ●第16章 情と理について ●第17章 勤勉さについて ●第18章 宗教と死について ●第19章 共生と競争について ●第20章 「足るを知る」ことについて ●第21章 私の歩んできた道