健康 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1261 から 1280 件目(100 頁中 64 頁目) 

- 血管を強くする歩き方
- 木津直昭/稲島司
- 東洋経済新報社
- ¥1540
- 2014年07月25日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
ゆっくり歩く人は、速く歩く人より心臓血管の病気で死亡する確率が約3倍!正しい姿勢をマスターするだけで速く歩ける!腰痛、膝痛、肩こりもよくなる!

- 世界一簡単な驚きの健康法 マウステーピング
- あいうべ協会/今井 一彰/中島 潤子
- 幻冬舎
- ¥1320
- 2021年08月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
貼って寝るだけ、体の不調が消える。
あなたが長年悩んでいる病気は「マウステーピング」が解決する⁉
寝ているときに口が開いていると喉が乾燥し、免疫力が下がります。たとえマスクをしていたとしても口が開いていれば乾燥を防ぐことはできず、口腔内の環境は悪化します。それを防ぐのがマウステープ。寝る前に口にテープを貼るという簡単な習慣です。まずは、睡眠の質がガラリと変わります。そして、口や鼻の疾病はもちろん花粉症やアトピー性皮膚炎、さらには糖尿病、不整脈、血圧、うつ病、過敏性腸症候群などの改善にも期待が。まして今の時代、朝起きたときに喉がヒリヒリしたり、熱っぽかったりすると、「しまった、コロナか‼」と、ひやひやしたりするもの。元気に健やかに新型コロナ時代を生き抜くための知恵が詰まった待望の一冊!

- 不整脈 知って解消 不安と疑問
- 副島 京子/NHK出版
- NHK出版
- ¥1320
- 2023年08月18日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
不整脈は種類もいろいろ、対処法もさまざま。正しい向き合い方をわかりやすく紹介
ひと口に「不整脈」といってもいろいろな種類があり、危険性もさまざまです。健康な人にも日常的に起こる怖くない不整脈もあれば、突然死につながるものもあるため、やみくもに怖がるのではなく、自分の不整脈の種類と危険性を正しく知ることが大切なのです。本書では、心房細動、期外収縮、房室ブロック、期外収縮、心房細動、房室ブロック、右脚/左脚ブロック、洞不全症候群、発作性上室性頻拍、心室細動など、さまざまな種類の不整脈について症状や特徴、医療機関での治療法などを詳しく解説しています。また、日常生活のなかで心臓をいたわるために心がけておきたいポイントや、AED(自動体外式除細動器)の使い方も詳しく解説します。
第1章 脳梗塞の原因になることもある「心房細動」
第2章 「頻脈性不整脈」は突然死の原因になることも
第3章 息切れやだるさを感じる「徐脈性不整脈」
第4章 日常生活で気をつけたいこと
コラム 期外収縮は健康な人にもみられる不整脈です/人が倒れていたらためらわずAEDを使いましょう
第1章 脳梗塞の原因になることもある「心房細動」
第2章 「頻脈性不整脈」は突然死の原因になることも
第3章 息切れやだるさを感じる「徐脈性不整脈」
第4章 日常生活で気をつけたいこと
コラム 期外収縮は健康な人にもみられる不整脈です/人が倒れていたらためらわずAEDを使いましょう

- 和食と健康
- 一般社団法人 和食文化国民会議/渡邊 智子/都築 毅
- 思文閣出版
- ¥990
- 2016年09月21日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
世界的にみて、日本人は寿命が長いが、その理由は食生活(特に食事)にあると言われている。
和食はなぜ健康によいのか?
本書では、その秘密を探り、和食と健康について考え、和食を取り入れた健康的な食生活を提案する。
はじめに
一 今日につながる養生の思想
(一)健康とは
(二)古代中国の食事と健康の考え方
(三)養生訓の世界
二 栄養学を取り入れた近代の健康と食
(一)日本の栄養学の発展
(二)日本型食生活の特徴
(三)和食給食と健康
三 現在とこれからの健康と食ー日本型食生活を継承するために
(一)日本の食文化を反映する食品成分表
(二)食事を科学的に考えてみましょう
(三)健康に過ごすための食育の事例
四 日本人の食事の健康度を検証する
(一)健康と食品の機能性研究について
(二)日本人と米国人の食事のちがいー「米+魚食」 VS「 パン+肉食」-
(三)さまざまな有益性がみられた1975年の食事ー欧米化の善し悪しー
(四)1975年の食事にみられた長寿効果
(五)1975年の食事とPFCバランス
(六)まとめ

- 21世紀の健康・福祉・環境
- ブルース・アレン
- 成美堂
- ¥1980
- 2005年01月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 行列のできる子ども健康相談室 0〜10歳児の病気とケガのおうちケア
- 竹綱 庸仁
- KADOKAWA
- ¥1650
- 2023年05月11日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.75(4)
子どもの病気やケガは、突然やってきます。
「どうしよう!」
すぐ救急? 夜間・休日診療へ? かかりつけ医でOK?
この本は、そんな「困った!」に役立ちます。
年間約3万人の子どもを診るクリニックのほか、
「病児保育室」や「児童発達支援施設」も手掛ける
小児科医が書いた
「ママ・パパ向け 家庭の医学」。
・「病気かも?」フローチャート
・緊急性チェックリスト
・おうちでのケア方法や薬の使い方
・予防接種のスケジュール
・発育や発達の心配ごと
など、子育ての不安を解消するアドバイスが満載です。
【目次】
第1章 症状別「病気かも?」チェック&おうちケア
第2章 子ども特有の病気&おうちケア
第3章 注意したいケガと事故&おうちケア
第4章 子どもの「発育・発達のお悩み」Q&A
第5章 病気の子どもに寄り添うときの3つのルール
第1章 症状別「病気かも?」チェック&おうちケア
第2章 子ども特有の病気&おうちケア
第3章 注意したいケガと事故&おうちケア
第4章 子どもの「発育・発達のお悩み」Q&A
第5章 病気の子どもに寄り添うときの3つのルール

- Dr中路が語るあおもり県民の健康改訂版
- 中路重之/東奥日報社
- 東奥日報社
- ¥1540
- 2015年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
“短命県返上”の青森から伝えたい!平均寿命から読み解く健やか力。

- シニアのための大笑いクイズと大笑い健康体操
- 今井弘雄
- 黎明書房
- ¥1760
- 2013年03月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
誰もが願う「元気で楽しい生活」を送るために、大笑いできるクイズやなぞなぞ、健康体操を紹介。また、施設でのレクリエーションに最適な、みんなで楽しめるゲームや「はとぽっぽ」「炭坑節」などのよく知っている歌に合わせて楽しく踊る歌レク体操を収録しました。

- 60歳からのお金と健康の裏ワザ
- ホームライフ取材班
- 青春出版社
- ¥1100
- 2022年07月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
「ちょい我慢」の積み重ねで、膀胱が柔らかくなって頻尿が改善する!ラクなのに効果倍増! 足腰鍛えるなら上り階段より「下り階段」。年金は70歳から受け取ると42%もアップする! などなど、60歳から得する裏ワザが満載!

- 「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべて左右する
- 石黒 源之
- 東洋経済新報社
- ¥1540
- 2017年02月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
【お金も努力もいっさい不要! 知るだけで、驚くほど健康になる!】
【ありそうでなかった! 最高の「時間を変えるだけ」健康法!】
★なぜ事故や自殺は「月曜日」に多いのか?
★同じ薬でも「飲む時間」を変えると、なぜ効果が変わるのか?
★なぜ「月曜の仕事」は失敗しやすいのか?
★大事な予定を「木曜」に入れたほうがいい理由は?
■まずは、あなたの健康を左右する「4大リズム」を紹介
■次に、最も怖い「3つの魔の時間」の過ごし方をやさしく説明
■「曜日ごと」「季節ごと」「持病ごと」のポイントを、わかりやすく具体的に解説
「まさかの事故や病気」から、あなたと家族を守る方法は?
人生の「ブラックタイム」をどう上手に避ければいいのか?
知るだけで長生きできて、体調まで良くなる!
臨床医だから書けた「37年間の研究と経験」の集大成!
こんな健康書が欲しかった!
誰も書かなかった「時間と健康」驚きの真実が、いま明らかに!
はじめに
第1章 あなたの健康を左右する「4つのリズム」を知ろう
第2章 最も怖い「3つの魔の時間」をどうやり過ごせばいいか
第3章 ブラックタイムを知れば、持病と上手に付き合える
第4章 ブラックタイムを知れば、心まで健康になる
第5章 日常に潜むブラックタイムから命を守れ!
第6章 ブラックタイムを知れば、季節の変わり目にも強くなる
第7章 高齢者・子ども特有のブラックタイムにも気をつけよう!
特別付録 健康寿命が驚くほど延びる50のコツを総まとめ!

- トリマーのためのベーシック獣医学
- 竹内和義
- ペットライフ社
- ¥4180
- 2009年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.67(3)
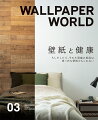
- WALLPAPER WORLD VOL.3
- Fill Publishing
- フィル
- ¥990
- 2021年09月08日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
その頭痛、もしかするとあなたの過ごす部屋が原因かもしれない。これまであまり知られてこなかった「インテリア」と「健康」の関係を、日本インテリア健康学協会の尾田恵さんが提唱する「アクティブ・ケア」を基に紐解きます。壁紙の色や柄、照明環境を今一度見直そうというのが、今回のメインテーマ「壁紙と健康」です。「明るくて、広く見えて、落ち着く」と言われる白い壁の真実、そもそもなぜ日本に白い壁がここまで広く普及したのか。そんな謎にも迫ります。
また、おそらく日本一壁紙にハマっている壁紙オタクのご自宅訪問インタビューに、海外デザイナーとタイアップしたMade in JAPANアイテム、ホテルの一室を京都水族館のいきものが占拠したとんでもないコンセプトルームなど、盛りだくさん。壁紙を変えると世界が変わる。この事実を一人でも多くの人に知ってほしい、そして変えてみたいと思わせる1冊です。
壁紙と健康
もしかしたら、その片頭痛の原因は
真っ白な壁紙かもしれない
壁紙オタクのご自宅インタビュー
水族館のいきものと一緒に泊まる夢の部屋
京都水族館 × クロスホテル京都
YOSHIDAKE × 壁紙屋本舗
正方形からつくる壁
コラボレーションインタビュー
・ 《Louise Body》
・ 《Catherine Rowe》
・ Coordinate Image Board
2021年上半期壁紙売れ筋ランキング
壁紙で世界旅行

- 【バーゲン本】安心して飲みたい人のための健康食品ガイド
- 田中 平三
- (株)同文書院
- ¥825
- 通常3~9日程度で発送
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、1999年に米国ではじめて刊行された、健康食品・サプリメントの世界的なデータベースである『ナチュラルメディシン・データベース』(日本語版:『健康食品・サプリメント(成分)のすべて』、日本医師会・日本薬剤師会・日本歯科医師会 監修)をもとに、よく摂取されている素材・成分項目を厳選し、素材、成分の「安全性」や「効き目」などをコンパクトにまとめた待望の書です。

- 【バーゲン本】糖尿病ーあなたに合った治療
- 別冊NHKきょうの健康
- NHK出版
- ¥632
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
血糖値が高い、糖尿病と診断されたあなたに。「糖尿病とは」「血糖値・HbA1cとは」などの基本知識から、治療チャート・食事・運動・合併症・低血糖・自己管理・教育入院など、あなたに合った治療を選ぶための情報を紹介。特に、新しく登場した薬も含め、薬物療法について詳しく解説する。

- 和田秀樹医師ら老年医学の専門家が伝授 70歳からの健康長寿 新常識
- マキノ出版
- ¥990
- 2022年12月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
現在、70代の女性の6〜7人に1人は
100歳まで生きると推定されています。
まさに「人生100年時代」の到来です。
とはいえ、元気で自立して暮らせる
「健康寿命」は、男性が72.14歳、
女性が74.79歳と、意外に短いのが現状です。
晩年を生き生きと元気に、
素敵に過ごせるかどうか。
そのカギを握るのは、意欲と免疫力、
筋力をいかに高く維持していけるか。
そして、ポイントの一つが、
「高齢者には動脈硬化がある」ことを
前提に考え、血圧、血糖値、
コレステロール値を薬で無理に
「正常値」まで下げ過ぎないようにすることだと、
和田秀樹医師は語ります。
70代は、老化と闘える最後のチャンス。
現役世代と大きく変わる70歳からの生き方しだいで、
その後の30年の暮らしが変わります。
1年でも2年でも長く
「元気で幸せな人生」を過ごすために、
私たちが今日からできる
「健康寿命の延ばし方」を詳しくご紹介します。

- 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい
- 槇孝子/鬼木豊
- アスコム
- ¥1210
- 2013年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.14(210)
血液の70%が集まる下半身の血流を上げれば病気にならない!もむだけで、体が温まって免疫力がアップする最強の健康法!

- 自律神経を整える「わがまま」健康法
- 小林 弘幸
- KADOKAWA
- ¥902
- 2018年10月06日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
本書では、たとえ忙しくても自分だけの時間をしっかりと楽しみ、心身を整えながら健康になれる、誰にでも簡単にできるテクニックや思考法を伝えていきます。
それをひと言で表すと、わたしは本書のタイトルである「わがまま」に生きることに尽きると思います。
「わがまま」と聞くと、ちょっと悪いイメージを感じる人もいるかもしれませんね。でも、ここでの「わがまま」とは、単に好き放題の言動をしたり、ルールやマナーを守らなかったりする、ただの「わがまま」ではないのです。むしろ、あなたの譲れない一線や信念のようなもの、あなたの生き方の根幹にかかわる姿勢を指していると考えてください。
わかりやすく言えば、あるがままの自分を指す「我がまま」というニュアンスを込めた「わがまま」です。
(【はじめにーー「わがまま」とはあなたらしく生きること】より引用)
はじめにーー「わがまま」とはあなたらしく生きること
第1章 もっと「わがまま」に生きる
第2章 人間関係のストレスを「わがまま」になくす
第3章 「わがまま」なゆとりを手に入れる
第4章 健康的に「わがまま」にこだわる
第5章 毎日を「わがまま」に暮らす
第6章 人生は「わがまま」と「無駄」との戦い
第7章 「わがまま」な自分を自らが助ける
おわりにーーいま、ここから「わがまま」に生きる

- 糖質制限の健康おつまみ
- 江部康二/検見崎聡美
- 東洋経済新報社
- ¥1540
- 2013年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
糖質制限食ではNGのはずの肉じゃが、羽根つき餃子、鶏のから揚げ、焼きうどん、ポテサラ、ナポリタンから、アジア風おつまみ、バル風タパスまで、人気のおつまみメニュー満載!!締めの麺&ご飯ひんやりスイーツのレシピ付き。「ポテトサラダ」はじゃがいもの代替食材として「おから」を、「焼きうどん」はうどんに「大根」を、「スパゲティ」は「しらたき」を使用して本物そっくりの味と食感を再現。

- 私の歯の健康ノート
- 医歯薬出版
- ¥1210
- 2000年01月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、患者とご家族と歯科医院が協力して、あなたの歯をムシ歯から守っていくための大切な記録です。

- アパレルと健康
- 日本家政学会被服衛生学部会
- 井上書院
- ¥2640
- 2012年04月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)