PHP の検索結果 新刊 順 約 2000 件中 1261 から 1280 件目(100 頁中 64 頁目) 

- 秘密に満ちた魔石館4
- 廣嶋 玲子/佐竹 美保
- PHP研究所
- ¥1100
- 2022年12月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.4(5)
学校でファンが急増中! 「銭天堂」の作者・廣嶋玲子が描く宝石好きに贈るシリーズ、第4弾!
石とはふしぎなものでございますね。あるものはきらめき、あるものはしっとりと艶をおび、またあるものは秘密をいだいている……魔石館の石たちはそうしたものばかり。どうか、彼らの物語をお聞きください。
★ブラッドストーンーードラゴンの卵
大好きなおじいちゃんから、ドラゴンの卵を託されたマックスは……
★ラリマーーーカリブ海の宝石
仕事につかれきったマーサは、水色の石のネックレスにひきつけられ……
★ガーデンクオーツーー魂の宿り木
空想世界が好きなヨハンナは、叔父から水晶を贈られて……
★アレキサンドライトーー色変わりの道化師
ロシアの青年・ビクトルは、大金持ちに借金のお願いをするのだが……
★インカローズーー盗まれたインディオの石
インディオに傲慢にふるまうスペイン人・ペドロは、村に宝石があると知り……
★サファイアーー青の魔性
「呪われたサファイア」と呼ばれるようになったのは……
美しく、神秘的で、魅力と秘密にあふれた石たちの知られざる物語を6話収録。

- 家康の海
- 植松 三十里
- PHP研究所
- ¥2090
- 2022年12月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.33(3)
戦国を勝ち抜いた男の卓越した外交戦略が、この国を平和に導いたーー。
今川家での苦難の人質時代、太原雪斎から天下国家のあり方、外交論を教わった竹千代。長じてのち、天下分け目の決戦を制した徳川家康が、雪斎の教えを胸に目指したものこそが、諸外国との対等な外交であった。豊臣秀吉によって途絶えた朝鮮との国交回復、さまざまな思惑をもって来日する西欧諸国との交渉、そしてメキシコへの野心……。知られざる家康の後半生を、その外交戦略を支えたイギリス人航海士のウィリアム・アダムス、家康の庇護を受けながらもキリスト教徒としての信仰を貫いた朝鮮貴族の娘・おたあの視点を交えて描き切った、感動の歴史ロマン。

- PHP (ピーエイチピー) スペシャル 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥420
- 2022年12月09日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)

- PHP(ピーエイチピー)からだスマイル 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥495
- 2022年12月09日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ユア・プレゼント
- 青山 美智子/U-ku
- PHP研究所
- ¥1760
- 2022年12月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.54(75)
頑張るあなたに、大切なあの人にーー「癒し」と「元気」をプレゼント。
2022年本屋大賞第2位『赤と青とエスキース』の著者と装画家が贈る、大好評アート×ショート・ショート第2弾!華やかな赤い水彩画と心動かす物語を48篇、オールカラーで収録。
本書は、新進気鋭の水彩作家・U-ku(ゆーく)氏のアートから受けるインスピレーションを手掛かりに、ハートフル小説の旗手・青山美智子氏が短い物語を綴った特別な作品集。
美しい絵画と優しい言葉のコラボレーションが、あなたの心にそっと寄り添ってくれるはず。
日々を懸命に生きる自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも最適な一冊です。
【目次】
●ソフトランディング
●切って貼って
●脈々と
●晴れの日に

- 1日1篇「人生を成功に導く」365人の言葉
- 『PHP』編集部
- PHP研究所
- ¥2585
- 2022年12月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.75(5)
創刊75周年を迎えた月刊誌「PHP」に寄せられた著名人の記事から、人生の道しるべとなる文章を1日1篇形式で365日分集めた本。

- 7つのポイントで、今すぐできる 「コミュ障」でもしっかり伝わる話し方
- 桐生 稔
- PHP研究所
- ¥1650
- 2022年12月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
「もしかして、自分ってコミュ障なの?」と悩む人も、ビジネスの世界で通用する、「しっかり伝わる」話し方を身につけられる一冊。

- 魔女のなみだのクッキー
- 草野 あきこ/ひがし ちから
- PHP研究所
- ¥1320
- 2022年12月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
ある日曜日のこと。道のはしっこに、小さな屋台がひとつ出ていました。屋根には「クッキー屋」と書かれています。屋台をやっていたのは、「この町の人間たちを、なみだのクッキーで不幸にしよう」とたくらんでる魔女でした。そこへ、文句を言いながら女の子がやってきました。
女の子はリコという名前で、「おばあちゃんはおかし屋さんを始めてから忙しくなって、リコの話を聞いてくれなくなった」と怒っています。そこで魔女は、「なみだのクッキー」を作るよう、リコにすすめました。「なみだのクッキー」は、クッキーにカラフルな粒をまぶして、怒りや悲しみなどの不幸な気持ちをこめて振るとできるクッキーです。そして、そのなみだのクッキーを食べると不幸な気持ちになり、なみだが出るというのです。
おばあちゃんのことが嫌いなわけではないリコは、少しためらいますが、なみだのクッキーを作り、おばあちゃんに渡すためおかし屋さんに向かいました。

- パンダのがらをなんにする?
- おおの こうへい
- PHP研究所
- ¥1540
- 2022年12月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
きみなら、どんなパンダのがらにする? 想像を広げるって面白い!
大人気妄想絵本『ショートケーキになにのせる?』に続く第2弾!
もしも動物園にいるパンダが全然ちがう「しろくろがら」だったら……?
ぼくと妹は動物園が大好き。なかでも、いちばんは「しろくろがら」がかわいいパンダ!……でも、まてよ? これが、ちがう動物がらだったら、もっとかわいくなるのかな?
たとえば……シマウマがらのパンダ! う〜ん、想像してみたけど、シマウマというより、ふとった白いトラだなぁ。 じゃあ、ウシがらのパンダ! う〜ん、ウシとちがって牛乳でないし……。次は、スカンクがらのパンダ! ブゥゥゥゥ〜おなら、くっさぁ〜〜!
なんだか、おもしろい! よーし! もう動物がらじゃなくてもいいから、色々なしろくろがらにしてみよう! みずたまがらのパンダ! うずまきがらのパンダ! めいろがらのパンダ……⁉

- 働く君に贈る25の言葉
- 佐々木 常夫
- PHP研究所
- ¥814
- 2022年12月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.38(8)
43万人に読まれた名著、待望の文庫化!
自閉症の長男、病に倒れた妻……。過酷な運命を引き受けながら、数々の大事業を成功させ、社長まで上りつめた佐々木常夫氏。ビジネスマンの逆風をしなやかに生き抜くための「仕事力」と「人間力」とはーー。
本書は、「リーダーとは、周りを元気にする人」「逆風の場こそ、君を鍛えてくれる」など、仕事や人生に悩んだとき、心の支えになってくれる珠玉の言葉集。
部下力、リーダーシップからタイムマネジメント、ワークライフバランスまで、あらゆる仕事に通じる働き方のエッセンスを25の金言に集約しました。
若手からベテランまで役立つ、“何度でも読み返したい″心揺さぶる本。
文庫版だけの書き下ろし「エピローグ13年後」を収録。
(主な内容)
●強くなければ仕事はできない。優しくなければ幸せにはなれない。
●君は人生の主人公だ。何ものにもその座を譲ってはならない。
●仕事で大切なことは、すべて幼い時に学んでいる。
●すぐに走り出してはいけない。まず、考えなさい。
●人を愛しなさい。それが、自分を大切にすることです。 etc.
「仕事をするうえでは強さが必要です。困難な仕事を成し遂げるための「粘り強さ」、失敗しても叩かれても立ち上がる「芯の強さ」、ときには自説を押し通す「気の強さ」も必要でしょう。ただ、強さだけでは幸せになることはできません。強さの根底に優しさがなければ、幸せになることはできないのです」(本書より抜粋)

- [新版]「がまん」するから老化する
- 和田 秀樹
- PHP研究所
- ¥891
- 2022年12月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
本書は、30年以上にわたって6000人以上の高齢者を診てきた著者が、老化予防、アンチエイジングにまつわる考え方や具体策をまとめたものである。著者によれば、いまの多くの医者が推奨している、予防医学的、節制的健康法は老化を逆に進めてしまうという。メタボ対策もダイエットも、間違いだらけ。太めの人のほうがやせ型の人より6〜8年も長生きすることが明らかになっていることなど、国内外の興味深いデータに基づいて「新常識」を説いている。
●日本人はもっと肉を食べたほうがいい
●ダイエットすると飢餓レベルに近づく
●快体験は免疫力を上げる
●人は感情から老化する
●血圧も血糖値も下げすぎのほうが怖い
●骨だけは老け込んでいる日本人、ほか。
『「がまん」するから老化する』(2011年刊)の内容を新版としてアップデートした文庫版。老化予防、アンチエイジングに関する著者の原点と言える一冊。

- 江戸はスゴイ
- 堀口 茉純
- PHP研究所
- ¥880
- 2022年12月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
文庫化に際し、番外編で「徳川家康」を加筆してバージョンアップ!
2023年大河でも話題の家康公が、その礎を築いたお江戸の町。「武士が主役」だった時代だと思われる方も多いはずですが、実際にはそうでない面が多々あったことをご存じでしょうか。
その様子は、版本(木版で印刷された本)や浮世絵などの当時の絵画史料によく描かれており、江戸で生きる「庶民が主役」としてイキイキと暮らしていた姿をイメージすることができるのです。
本書にはそうした史料が厳選収録され、ヴィジュアル満載で「えっ!?」と驚く逸話もたくさん紹介されています。
庶民が、裕福でなくても、生きがいや幸せを感じて、毎日を過ごしていた時代だからこそ、歌舞伎や浮世絵、寿司や蕎麦などの食文化も大いに発達したのです。しかもそれらの風俗・文化は、現代の私たち日本人にとって、世界に誇ることのできる貴重な財産になっているのです。
著者・堀口茉純は、自らが運営するユーチューブ「ほーりーとお江戸、いいね!」で、今もその江戸の素晴らしさを伝え続けています。歴史好きの方々に好評のこのユーチューブでは、「江戸への愛だけは誰にも負けないわよ!」という情熱が静かに伝わってきます。
ページを開けば、楽しく明るいお江戸の世界。本書をぜひ手にとって、その不思議な魅力を味わってください。
<目次構成>
◆其の一◆実はこんなにスゴかった! 世界が驚く江戸城下町のヒミツ
◇番外編◇「まさか私が将軍に(確信犯)?!」江戸にやって来た徳川家康の勝算
◆其の二◆城下町探検隊ーーようこそ! 大江戸観光ツアーへ
◆其の三◆アレ、けっこう楽しそう(笑)! 江戸町人の暮らし
◆其の四◆役者・アイドル・スポーツ選手……憧れのスターたち
◆其の五◆異常発達☆食文化
◆其の六◆毎日がスペシャル?! とにかくイベント大好き

- 弟子・藤井聡太が教えてくれた99のこと
- 杉本 昌隆
- PHP研究所
- ¥880
- 2022年12月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
藤井聡太氏は棋聖、王位、叡王、竜王、王将と立て続けに五冠を制覇し、五回の防衛戦を含めてタイトル戦十連勝という前人未 到の記録を打ち立てた。
公式戦で六連敗していた豊島九段にも圧勝を重ねて苦手意識を完全に払いのけた。
もちろん、それまでも盤石の安定感だったが、変化といえば、以前に比べて持ち時間に対する意識が変わったことだろう。それまでは時間不足によって追い込まれることが多かった勝負が、一分将棋に入る前に一、二分時間を残すようになったのだ。わずかな時間ですが、読みの速度が尋常ではない藤井氏の場合、その一、二分が勝敗を左右する。さらに、どんな戦法に対しても逃げずに受け入れる姿勢が、弱点を作らず地力をつけることにつながっている。修正能力が高いため、同じ相手に一回は負けても、二回、三回と負けることはない。番勝負で圧倒的な強さを見せる所 以だ。
大勝負で次々に強豪を倒して実績を積み上げてきた経験によって、精神的にも落ち着きと風格が備わってきた。わずか二年間で人はこれほど成長できるのか、と驚くばかりだ。
五冠という肩書だけではなく、高校生から将棋一筋の社会人となり、第一人者としての自覚が芽生えてきた、と著者は語る。
人はいくつになっても成長できる。成長の機会は師匠や周囲の人間が用意できるものではなく、本人の意志と不断の努力によってもたらされる。藤井氏の場合、その意志と努力は「この上なく将棋が好き」「もっと強くなりたい」という気持ちに支えられている。
単行本刊行時に無冠の七段だった藤井が五冠に成長する、その源泉の思考法に触れられる一冊。
●何気ないことでもこだわれば勝機はある
●人生には勝ちしかない
●弟子たちの存在そのものが「師」である
●練習は本番のように、本番は練習のように
●非効率的な勉強法が成長のヒトになる
●一流ほど負けて悔しい勝負を数多く経験している

- 生物に学ぶ敗者の進化論
- 稲垣 栄洋
- PHP研究所
- ¥858
- 2022年12月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.25(5)
弱肉強食の自然界で、なぜ弱者が生き残れたのか?
人気の生物学者が教える「生物に学ぶ画期的な生き残り戦略」。
生命の歴史で滅び去っていったのは不思議なことに強者である勝者だった。人間は敗者の中の敗者だから生き残れたのだ。ミトコンドリアとの共生から人類誕生までを弱者の生き残り戦略から学ぶ生物学。
生命がエラーをする存在だったから進化が起こり命のリレーは38億年つながった!
生物の歴史を振り返れば、生き延びてきたのは、弱きものたちであった。そして、常に新しい時代を作ってきたのは、時代の敗者であった。そして、敗者たちが逆境を乗り越え、雌伏の時を耐え抜いて、大逆転劇を演じ続けてきたのである。まさに、「捲土重来」である。逃げ回りながら、追いやられながら、私たちの祖先は生き延びた。そして、どんなに細くとも命をつないできた。私たちはそんなたくましい敗者たちの子孫なのである。(「あとがき」より)
【目次より】
●「食べて共生する」という驚異の進化
●共通の祖先から生まれた動物と植物
●大腸菌にもオスとメスがある
●根も葉もない植物
●植物は「食べられること」を巧みに利用
●酸素という猛毒
●オスの誕生
●植物の上陸
●六回目の大量絶滅
●恐竜を滅ぼした花
『敗者の生命史38億年』を加筆・修正し改題。

- THE 21 (ザ ニジュウイチ) 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥760
- 2022年12月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- Voice (ボイス) 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥840
- 2022年12月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 歴史街道 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥789
- 2022年12月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
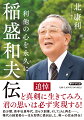
- 稲盛和夫伝
- 北 康利
- PHP研究所
- ¥1650
- 2022年12月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
<ど真剣に生きてみろ。君の思いは必ず実現する!
日本が世界に誇る名経営者・稲盛和夫。本書は、幼少期、若手社員時代から京セラ創業、JAL再生まで、稲盛氏本人へのロングインタビューと膨大な資料の綿密な考証を元に、その稀有な生涯を丁寧に綴った傑作評伝です。
京セラの経営思想が生まれた背景やエピソードを、日本経済が活況を呈していた時代の風景とともに、迫真の臨場感をもって描き出します。「フィロソフィ」「アメーバ経営」の原点はここにある!
『思い邪なし 京セラ創業者 稲盛和夫』を改題して文庫化。
(本書の構成)
序 章 誓いの血判状
第一章 勝ちに見放されたガキ大将
第二章 ファインセラミックスとの出会い
第三章 世界の京セラへ
第四章 第二電電への挑戦
第五章 奇跡のJAL再生
第六章 利他の心を永久に
「この社会で、中小企業のオーナーほど“ど真剣”に経営と向き合っている人たちもいないだろう。彼らは本物を見抜く。彼らに一時の流行の経営指南書など無用である。稲盛の経営哲学に普遍性と実用性があり、実体験に基づいた説得力があるからこそ、彼らは心惹かれるのだ」(本書「あとがき」より)

- 精神科医に、ご用心!
- 西城 有朋
- PHP研究所
- ¥935
- 2022年12月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
精神科医の自殺率は一般人の数倍という。死のうとする人を食い止める仕事であるはずの精神科医がなぜ、そのようなことになってしまうのか。みずからが薬漬けになっている医師、女性患者と肉体関係に進んでしまった医師、不正な事件にかかわり、当局のご厄介になった医師……。本書冒頭には、こうした残念な精神科医、ダメな精神科医が次々と登場する。私たちは、安心して精神科の門をたたくことができないのだろうか……。
本書は、現役の精神科医が、日本の精神医療界の闇を冷静に分析して解説し、患者が心の問題と向き合う時に知っておくべきこと、信頼できる医師に出会うための心得を説いたものである。
●世界でも1位、2位を争う膨大な外来患者数
●100人の精神科医がいれば、診断も100通りある
●精神科薬の成功確率は誰も証明できない
●費用対効果の高い読書療法
●瞑想は大きな効果が期待できる
●万人にとっていい精神科医は存在しない、ほか。
『精神科医はなぜ心を病むのか』(2008年刊)を改題、大幅に加筆、修正して文庫化。

- PHPスペシャル増刊 2023年前半 あなたの運勢 2023年 1月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥579
- 2022年12月06日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)