更新 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1281 から 1300 件目(100 頁中 65 頁目) 

- 科学という名の信仰 新型コロナ「ワクチン」政策を問う
- 福島 雅典
- 岩波書店
- ¥2970
- 2024年10月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
新型コロナ政策のワクチン国内総接種回数は4億36193341回(24年4月)。接種後副反応や死亡例が多発しているが国・メディアは沈黙している。本書は今回のワクチン政策を科学的に検証し、科学立国としての政策の在り方を提言するものである。内容は全て科学論拠・学術論文に基づいており、「反ワク」論とは別物である。
はじめに
序 章 日本の「ワクチン」政策を問う
科学・技術立国とは相容れない現実
温故知新
「ワクチン」政策の実態
検証のポイント
第一章 「ワクチン」接種後死亡の現実
私が意見書を書いた3人のケース
ケース1:2回目接種5日後、心不全で死亡
予防接種健康被害救済制度適用認定
ケース2:2回目接種翌日、大動脈解離
Kさんの家族の思い
ケース3:3回目接種翌朝、大動脈解離で死亡
ケース4:3回目接種後、ヤコブ病の後死亡
モンタニエ博士報告のヤコブ病か?
ケース5:2回目接種後、脳出血・心筋梗塞で死亡
第二章 全世界で広がる「ワクチン」の健康被害
知らされない未曽有の健康被害
健康被害者と向き合う医師たち
科学のメスを入れよ
スパイクタンパク質症(Spikeopathy)
全国民に「ワクチン」接種手帳を!
私の身近な人々の場合
身近な経験から臨床科学へ
一筋の光明と韻を踏む医学史
第三章 繰り返される薬害
薬害を生む構造的背景
イレッサの薬害はなぜおこったのか
薬害イレッサ裁判での証人証言記録に添えて
第四章 薬の有効性と安全性のバランス
医療者としての責任の自覚
規制の科学としての薬剤疫学
薬物療法と因果関係
くすりのリスク/ベネフィット
薬剤疫学と臨床医学
医療における意思決定
ベネフィットの理解
ベネフィットの正しい評価
リスクの正しい評価
リスク/ベネフィットのバランス
リスクーー有害反応
ベネフィットーー治療効果
疾患のリスク、治療効果の算出
漢方薬の問題
薬剤疫学上の根本課題
医薬品適正使用の問題点
規制の意思決定
それぞれの自律性(オートノミー)
補遺 ワクチンの「利益がリスクに勝る」は妄言
副作用のない薬はない
終 章 健康とは何か?--健康を守るための科学する心
「ワクチン」でパンデミック解決は不可能
「病気は薬で治す」という思い込み
医学のパラダイム変換
幹細胞療法とは?
組織工学的治療法とは?
細胞社会の原理を知って治療をデザインする
これからの医療は変わる
新しい医学・医療建設に向けて
資料編
資料1:薬害イレッサ裁判において、大阪地裁に原告側から証拠として提出された、筆者による厚生労働大臣宛意見書
資料2:MCIフォーラム講演録〔2023年10月6日〕
おわりに
謝辞

- 不等式
- 梁取弘
- 科学新興新社
- ¥796
- 1990年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- PassLine突破シリーズ5 「中学校新学習指導要領パスライン 2025年度版」
- 時事通信出版局
- 時事通信出版局
- ¥1210
- 2023年09月01日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
新学習指導要領のキーワードを「書き込んで覚える」問題集です。
学年,分野ごとのキーワードが比較できるよう構成しています。
何を覚えればいいのかがひと目で分かるので,効率よく学習することができます。
また,トピック別に各教科からの関連事項をピックアップした特別資料付き!
本試験で必出の新学習指導要領対策は,この1冊でOK!

- ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第9番・第10番・第11番≪大ソナタ≫ 第12番≪葬送行進曲≫
- ヴィルヘルム・バックハウス/ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン/ヴィルヘルム・バックハウス
- ユニバーサルミュージック クラシック
- ¥3080
- 2020年11月18日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 小池百合子氏は流行神だったのか
- 加瀬英明
- 勉誠出版
- ¥1100
- 2017年11月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
日本の「良識」とは何か?
アメリカ、中国、南北朝鮮の正体を暴く。
まず、わが手に日本を取り戻そう!
加瀬英明が日本の現状にモノ申す!
1 小池百合子氏は流行神か
1 小池百合子氏は流行神か
2 ドングリころころどんぶりこ
3 豊田真由子議員の罵詈雑言はかわいらしい
4 史上最初の二十九連勝 十四歳の快挙
5 トランプ大統領のアメリカを、見誤ってはならない
6 非核三原則を取り上げた石破発言を、歓迎したい
2 「安らかに眠って下さい」
7 「安らかに眠って下さい」
8 日本における左翼運動は風俗でしかない
9 これで日本を守れるのか
10 いったい「良識」は、良識なのだろうか
11 スーパーの野菜のように、没個性に陥った日本人
12 白頭鷲と中国龍
13 百四十一年も変わらない日韓関係
3 軍艦行進曲、瓦解と侠気
14 軍艦行進曲、瓦解と侠気
15 東京五輪で、もっとも大切な国と、どう接するか
16 大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終わらなかった
17 快男子!! 秦野章・法務大臣
18 流しのギター弾きになりたかった
19 船出の和船には、女夫釘
4 スカイツリーは、今の日本にとっての大伽藍
20 スカイツリーは、今の日本にとっての大伽藍
21 粋な女将、十月の青空と松茸
22 鰻なんて食い物はな……
23 佳人に心がときめくのは、若さの証し
24 秋来 タダ一人ノタメニ長シ
25 失われた男らしさ、女らしさ
5 男は独立していることが生命
26 男は独立していることが生命
27 日本は女性的な国
28 李白、兼好法師、佐藤一斎に学ぶ
29 国と社会に幸せを運びたい
30 六十年前の“夏めく”
31 熟年世代が立ち上がって国を立て直す秋
6 小鳥と分けあう、春の豊かな饗食
32 小鳥と分けあう、春の豊かな饗食
33 金盃とマッカーサー
34 二人は「公人」
35 父のラブレター
36 わが偉大なる従姉 小野洋子
37 時代精神の代表選手
あとがき
出典一覧

- エルガー:交響曲第1番 行進曲≪威風堂々≫第1番・第4番
- ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団/エドワード・エルガー/ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団
- ユニバーサルミュージック クラシック
- ¥1410
- 2022年10月05日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 光明皇后
- 瀧浪 貞子
- 中央公論新社
- ¥968
- 2017年10月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(8)
藤原不比等の子として生まれ、同い年の首(おびと)皇子(後の聖武天皇)と一緒に育った光明子。多くの期待を背負った彼女は、やがて皇后となり、大仏建立等の政策を補佐していく。華やかな天平時代はしかし、長屋王事件、相次ぐ遷都など動乱の時代でもあった。皇太子の死、藤原四兄弟の急死などもあり、光明皇后の生活は愁いに満ちたものとなってゆく。時代史のなかに光明皇后の生涯を位置づけ、新たな人間像に光を当てる。

- 【バーゲン本】外国人は日本文化の何を知りたがっているのか そのエッセンスは茶道の中にー淡交新書
- 山崎 武也
- (株)淡交社
- ¥660
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
豊富な海外ビジネス経験を持ち、裏千家茶英会の指導責任者を長年務める著者を招き、外国人(=異文化の人)に、茶道とそれにまつわる日本文化をより的確に伝えるには、どのような心がまえ・方法が必要・有効かをわかりやすく説く書です。単に英語の言い回しを教える「教科書」ではなく、著者の実体験に基づく「血の通った」一話読み切りのエッセイで、外国人とのコミュニケートの際に私たちがとるべき姿勢を、根本から問い直します。

- 学校心理学の理論から創る生徒指導と進路指導・キャリア教育
- 山口 豊一
- 学文社
- ¥1980
- 2022年02月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
現場に関わる担任教師、教育相談担当、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事、
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどが、学校心理学的視点から、
子ども一人ひとりに対する援助サービスを充実させ、心身の成長発達をより促進し、
学校生活の質(QOSL)を高めるための理論と方法を論じる。
【執筆者】
山口豊一、永作 稔、小菅清香、都丸けい子、藤枝静暁、高橋 誠、原田恵理子、水野雅之
序 章 学校心理学の理論から創る生徒指導と進路指導・キャリア教育
第1部 生徒指導の理論と方法
第1章 生徒指導の意義と原理
第2章 生徒指導の現代的課題
第3章 学校心理学と生徒指導
第4章 児童生徒理解と発達・教育課題
第5章 生徒指導体制と心理職の活用
第6章 生徒指導と授業
第7章 教育相談の意義と特質
第8章 教育相談の限界と他機関との連携
第2部 進路指導・キャリア教育の理論と方法
第9章 進路指導とキャリア教育
第10章 進路指導・キャリア教育の理論
第11章 就学前から始まる系統的・体系的取り組みとしてのキャリア教育
第12章 小学校における進路指導・キャリア教育の実践と現状
第13章 中学校における進路指導・キャリア教育の実践と現状
第14章 高等学校における進路指導・キャリア教育の実践と現状
第15章 進路指導・キャリア教育における心理的支援
第16章 大学における進路指導・キャリア教育とキャリア・カウンセリング

- ドイツ行進曲集
- ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー・ブラスオルケスター
- ユニバーサルミュージック クラシック
- ¥1609
- 2023年09月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- モーツァルト ピアノソナタ イ長調 KV331[トルコ行進曲付き]
- 渡邊順生
- 全音楽譜出版社
- ¥1210
- 2016年05月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2014年9月に発見された自筆譜に基づく原典版。この発見により、これまで短調で演奏されてきた一部が、自筆譜には長調で書かれていたことが判明。本書は従来の誤りを正し、自筆譜・初版の一次資料の忠実な再現を目指し編纂。

- CAMS 自殺の危険のマネジメント
- デイヴィッド・A・ジョブズ/高橋祥友
- 金剛出版
- ¥4620
- 2018年08月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
世界中で起きている,患者の自殺という最も重大な問題の予防に向き合うには何が重要か。
自殺の危険の高い患者に対する治療にとって,本書で紹介するCAMS(Collaborative Assessment and Management of Suicidality)の治療的アプローチは革新的な枠組みとなる。
CAMSでは治療者と患者の「協働」が鍵となる。治療者は患者自身も積極的に診断や治療に関与していくよう働きかけることで,治療の効果を最大限に引き出そうとする。著者は,初回セッションでの危険評価,治療計画の立案,その後の評価,終了の決定,終了後の計画といった治療経過で一貫して患者の関与を強調する。
また,CAMSの治療においては自殺状態評価票(SSF: Suicide Status Form)が欠かせず,危険評価用紙としてだけでなく,治療を通して応用的に使用する臨床ツールとなっている。巻末付録にはSSF本体と記入例,記入における各マニュアルを収録しており,実際の臨床での使用を見据えたつくりとなっている。
SSFには,万が一患者の自殺が起きてしまった場合の医療過誤訴訟から臨床家を守る治療の記録としての役割もあり,この問題に関する章も一読の価値がある。
本書は自殺予防に携わる臨床家にとって新たな道標となる治療の哲学と実践的アプローチの書である。
序文
はじめに
謝辞
第1章 自殺の危険の協働的評価と管理ー現代の治療領域における自殺に焦点を当てた臨床的介入
第2章 SSFとCAMSの発展
第3章 臨床的ケアの体制とCAMSの最適な実施法
第4章 CAMS危険評価ーSSFの協働的使用
第5章 CAMS治療計画ー患者と協力して自殺に焦点を当てた治療計画を立てる
第6章 CAMS中間セッションー自殺の危険評価のモニターと治療計画の更新
第7章 CAMS臨床結果と治療後計画ー人生からの教訓と自殺の危機後の人生
第8章 医療過誤訴訟の危険を減らす手段としてのCAMS
第9章 CAMSの適用の拡大と将来の発展
おわりに
附録A 自殺状態評価票(Suicide Status Form: SSF)第4版(SSF-4)
附録B SSF主要評価尺度ー評点マニュアル
附録C SSF生きる理由と死ぬ理由ーコード・マニュアル
附録D SSFたったひとつのこと反応ーコード・マニュアル
附録E 治療ワークシート
附録F CAMS評価尺度(CRS.3)
附録G CAMSについてしばしば尋ねられる質問
附録H ビルに対して実施したCAMSの実例
訳者あとがき

- 人形浄瑠璃文楽名演集 紙子仕立両面鑑 心中宵庚申
- 豊竹小松太夫/野澤勝平/竹本越路太夫/野澤喜左衛門[二代]/吉田玉男[初代]/桐竹勘十郎[二代目]/吉田簑助/豊松清十郎[4代]
- (株)NHKエンタープライズ
- ¥3344
- 2018年01月26日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 日本画の歴史 近代篇
- 草薙奈津子
- 中央公論新社
- ¥1012
- 2018年11月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(5)
大和絵、狩野派、浮世絵など日本伝統の絵画は、開国後、西洋絵画と出会った。日本美術はフェノロサによって評価され「日本画」が成立、岡倉天心らの努力により発展した。
近代篇では、幕末に盛んになった横浜浮世絵・南画から説き起こす。そして、富国強兵の空気の中、国家主導で堂々たる作品が数多く制作された国家形成期の明治、人文主義を背景にのびやかな画風が完成した大正を描く。主要な日本画を多数収載。

- 茶の湯のトリビア
- 中村 幸
- 淡交社
- ¥1320
- 2021年03月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
〈茶席にうるおいを与える蘊蓄集〉
〈茶の湯の疑問?に答えます〉
茶の湯の蘊蓄や雑学のなかでも、「へぇ」「うそっ!」「プッ!」と思わず漏れてしまいそうな意外な茶の湯のトリビア99話を集め、お稽古やお茶会がさらに楽しくなる知恵が授かる内容とします。
話題は堅苦しいものではなく、こんなことに疑問を抱くのか? といったばかばかしくも斬新な視点で、初心者だけでなくベテランの方もあらためて考えもしなかった疑問や話題も取り上げます。
文章は、短めの問い、そして簡潔な文章の回答で展開します。

- 句集 盆太鼓
- 五井昌久
- 白光真宏会出版本部
- ¥1068
- 1990年01月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
著者は晩年の昭和50年より俳句をつくりはじめ、亡くなる昭和55年夏までに145句つくった。 著者ならではの味わい深い全作品を収録。

- 図解ポケット フリーランス法がよくわかる本
- 山入端翔
- 秀和システム
- ¥1210
- 2024年12月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2024年11月1日から施行されたフリーランスのための新しい法律「フリーランス法」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について、図解でコンパクトに解説します。受注者・発注者共に押さえるべき新常識がよくわかります! 新しい「7つの義務」がよくわかる! 取引適正化のポイントがよくわかる! 義務違反した時の対処法がよくわかる! 従来の下請法との違いがよくわかる!
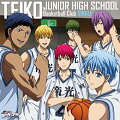
- TVアニメ『黒子のバスケ』第3期 第2クール 帝光編 キャラクターソング
- (アニメーション)
- (株)ランティス
- ¥1075
- 2015年04月29日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
往年の名曲をスーパープライスで!

- 仏像と日本人
- 碧海寿広
- 中央公論新社
- ¥946
- 2018年07月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.8(7)
寺や仏像と日本人はどのように関わってきたのか。岡倉天心、和辻哲郎、高村光太郎、土門拳、白洲正子、みうらじゅんなどを通して、この国の宗教と美のかたちを浮き彫りにする。

- 今宵も猫は交信中
- 水庭 れん
- 講談社
- ¥1980
- 2024年08月08日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.74(22)
第17回小説現代長編新人賞受賞後第一作!
猫がごろごろと喉を鳴らす理由を、皆さんはご存じですか?
実は、テレパシーで他の猫と交信している真っ最中なのですーー
宵、きせき、シュトレン、めい子の4匹は別々の家に引き取られた四姉妹。今日も元気にごろごろ喉を鳴らし、テレパシーで会話中。しかし、いつも明るいめい子の様子がおかしい。飼い主夫婦が離婚の危機にあるようだ。猫の自分には引き留めることができないと途方に暮れるめい子の元に現れたのはなんと宵だった! なぜならお姉ちゃんだから!
猫と猫、猫と人の絆を描く、猫視点ハートフルドラマ!