PHP の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1381 から 1400 件目(100 頁中 70 頁目) 

- 現代活学講話選集2 十八史略(下)
- 安岡正篤
- PHP研究所
- ¥836
- 2005年03月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.89(9)
混迷の時代こそリーダーの資質が問われる! 本書は、秦の始皇帝、項羽と劉邦に始まり、三国時代の曹操、劉備、孫権、宋の哲人宰相・耶律楚材まで、戦国乱世に光芒を放った英雄たちの優れた戦略と巧みな人心掌握術について語り明かした講話録である。▼「剣は一人の敵なり。学ぶに足らず。万人の敵を学ばん」(項羽)、「背水の陣」(韓信)、「太学を起こし礼楽を修明す」(後漢の光武帝)、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」(班超)、「不可ならば、君自ら取るべし」(劉備)、「死せる諸葛、生ける仲達を走らす」(諸葛亮)、「刮目して相待つ」(呂蒙)、「至誠を以て天下を治めん」(唐の太宗)……など、知略をめぐらし、死力を尽くして成功を収めた者、悲劇を辿った者の言行は、時を超えて我々にリーダーの行動規範を指し示す。▼わが国の指導者に多大な影響を与えた著者の確かな視座からの解説が心に響く好著である。ビジネスリーダー必読の一冊。
●第5章 天下統一への興亡 ●第6章 『三国志』の主役たち ●第7章 長い戦乱と内乱の後

- PHP増刊 60代からの老けない習慣 2024年 5月号 [雑誌]
- PHP研究所
- ¥550
- 2024年03月18日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 生きていてもいいかしら日記
- 北大路公子
- PHP研究所
- ¥607
- 2012年05月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.08(68)
40代、独身。好きなもの、昼酒。座右の銘は「好奇心は身を滅ぼす」。“いいとこなし”に見えるけれど、なぜかおかしいキミコの日々。「結婚しないの?」と聞かれた時の答え方、圧力鍋との15年戦争、父のゴミ分別の不可解なルール、朝はなぜ眠いのかについての考察など、日常の出来事に無駄な妄想で切り込んでいく。読んでも何の役にも立たないけれど、思わず笑いがこみあげて、不思議と元気が出てくるエッセイ集。解説の恩田陸さんも「この人に一生ついていくと決めました」と絶賛。

- 白村江
- 荒山 徹
- PHP研究所
- ¥1034
- 2020年01月10日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.17(25)
歴史・時代小説ベスト10(週刊朝日/2017年)第1位
歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞
本屋が選ぶ時代小説大賞2位
白村江の戦いの“真の勝者”とはーー
東アジアを舞台にした歴史大河小説がついに文庫化!
六六〇年、唐・新羅連合軍によって百済は滅亡、王とその一族は長安に送られた。
遺された王族は倭国へ亡命していた豊璋ただ一人ーー。
新羅の金春秋、高句麗の泉蓋蘇文、倭の蘇我入鹿、葛城皇子(のちの天智天皇)……各国の思惑は入り乱れ、東アジアは激動の時代を迎える。
大化の改新、朝鮮半島の動乱、そして白村江の戦いへと連なる歴史の裏でうごめいていた陰謀とは。
圧倒的スケールで描かれた感動必至の長編小説。

- 松下幸之助発言集ベストセレクション 社員は社員稼業の社長
- 松下幸之助
- PHP研究所
- ¥639
- 1996年04月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
『松下幸之助発言集』全45巻より厳選。 松下電器(現パナソニック)の主に若い社員に対する講話から、「プロとして立つ責任」など昭和33〜43年のものを話し言葉のまま収録。

- 文蔵2021.11
- 「文蔵」編集部
- PHP研究所
- ¥825
- 2021年10月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
【ブックガイド】小さな物語に広がる、大きな世界
再発見! 「短篇小説」の魅力●ミステリーおすすめ5篇…西上
心太●歴史時代小説おすすめ5篇…細谷正充●エンターテインメントおすすめ5篇…大矢博子
【待望の新連載】●坂井希久子 セクシャル・ルールズ1
男女逆転した役割を持つ夫婦が織りなす新時代エンターテインメント小説。【連載小説】●あさのあつこ おいち不思議がたり 【夢路篇】6 おいちは「浦之屋」の一件で動いている松庵の様子が気になっていた。●諸田玲子 麻阿と豪7 秀吉の没後、武将たちは一触即発の状態に。その時、前田家の姫たちは。●下村敦史 ガウディの遺言7 志穂の恋人の父・カザルスが語った、ガウディに関する衝撃の事実とは。●中山七里 越境刑事11 中国公安に拘束された冴子。趙の苛烈な拷問は彼女の精神を追い詰める。●朝井まかて 朝星夜星21 錦と結婚した米三郎の不行状が発覚する。怒る丈吉に対し、ゆきは……。●宮部みゆき おでこの中身 その四 きたきた捕物帖33 北一は、銀杏の葉の彫り物のある女が現場を見詰めていることに気づく。
【話題の著者に聞く】●西澤保彦『スリーピング事故物件』
女子大生たちが事故物件で
ルームシェアする物語です
【涙の最終回】●村山早紀 灯台守(後編) 桜風堂夢ものがたり(終)
「会いたい人に会える」奇跡の噂がある峠。そこにまつわる秘密とは。

- 満洲事変
- 宮田 昌明
- PHP研究所
- ¥1210
- 2019年12月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.25(4)
満洲事変とは何だったのか。事変に先立つ一九二〇年代を民族自決の理念が登場した時代とするなら、当時の中国は、満洲族やモンゴル族、ウイグル族などの民族自決を明らかに否定していた。満洲事変から支那事変を経て大東亜戦争に至る日本近代史について、帝国主義と民族主義の対立を絶対化する革命思想からではなく、長期的な歴史的文脈の中で、かつ、様々な制約下の行動の中にも新たな理念の影響を読み取る多面的、複合的な視点から再評価すべきである。「侵略」論を超えて世界的視野から当時の状況を知り、歴史認識の客観性を求める新たな試み。日米中や西欧諸国、ロシアという大国のみならず、満洲やモンゴル、東トルキスタン(新疆)やチベット、東南アジアなど周辺地域の研究成果を取り入れることは「日本を加害者、中国を被害者とする定型的な、あるいは結果から過程を演繹するような歴史を克服することにもつながるであろう」(本書「はじめに」より)。

- ラストで君は「まさか!」と言う 恋の手紙
- PHP研究所
- PHP研究所
- ¥1100
- 2018年12月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.67(4)
人気シリーズ第7弾!
トキメキが止まらない3分間。恋にまつわるショートストーリー!
【本書の特徴】●キュンとする恋、切ない恋、泣ける恋……たっぷり24話収録! ●3分で読めるショートストーリーだから、朝読にもぴったり。 ●ラストは「まさか!」なエンディングをお約束!
【もくじ】プロローグ/黒板/朝が来る前に/最後のキス/恋の結末/彼は霧の向こうへ/私の告白/秘めた恋/会長選挙じゃん!/初恋なんだ/ホィッポー/秋が降る公園/彼の好みは/世界の終わり、きみとのはじまり/恋妖奇譚/拝啓 わたし/マジカルナイト/通学電車/友だち想い/最初で最後の恋/きみとぼくとラーメンと/サンタクロースの悩み/ただいま/ホームラン日和

- 経営者になるためのノート
- 柳井正
- PHP研究所
- ¥1324
- 2015年08月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.58(92)
柳井正が語る仕事に必要な4つの力とは?
ユニクロ幹部社員が使う門外不出のノート。
欄外に気づきを書き込めば、自分だけの一冊に。
「自分で完成させていくノート」
このノートのコンセプトです。
このノートは、これから経営者になる人のために、ぜひ知っておいてほしいことを書き記したものです。
しかし、完成させていくのは、読者である、あなたです。
ビジネスをする人にとっての勉強というのは、勉強したことを実践してはじめて意味があります。単に知識量を増やすだけの「お勉強」には意味がありません。(中略)
欄外に空白を贅沢に取ったのは、あなたのこの本との対話を書き記しやすいようにするためです。
どんどん線を引き、どんどん書き込み、たくさん汚して下さい。(中略)
このノートを踏み台にして、あなたに柳井正を超えていってもらうこと、それが私の心からの願いです。(「本ノートの使い方ーーまえがきに代えてーー」より)

- 5分でできる「プチ・ストレス」解消術
- 保坂隆
- PHP研究所
- ¥726
- 2017年03月01日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
何となく気が散る、少しの音が気になる……。そんなプチ・ストレスも放っておくと大変なことに! 人気精神科医が早めのケア方法を解説。

- 松籟邸の隣人(一)
- 宮本 昌孝
- PHP研究所
- ¥2310
- 2023年11月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.67(6)
明治時代の湘南といえば、大磯だった!
この地には、明治20年代後半から、伊藤博文、大隈重信、陸奥宗などの大物政治家や、岩崎弥之助など経済人が別荘を建て、そこを目指して多くの人が集まるようになった。
また大磯は、日本初の海水浴場として、老若男女が集う一大リゾート地だったのである。
本書は、この地をこよなく愛し、後に宰相となる少年・吉田茂と、謎の隣人・天人(あまと)の二人が、別荘地で起きる様々な事件を解決していく連作活劇ミステリー。
茂が少年時代を過ごした吉田家の別荘は、父・健三によって「松籟邸」と名付けられていた。一方、隣人・天人が住んでいたのは、瀟洒な洋館。アメリカ帰りとも思えるこの若者は、一体何者なのか。そんな天人によって人間性を育まれた茂は……。
『天離(あまさか)り果つる国』で注目を集めたエンタメ作家が、虚と実を巧みに織り交ぜて紡ぎ出した「明治浪漫」。

- 看護師僧侶が説く 悩みの底を聴く力
- 玉置 妙憂
- PHP研究所
- ¥1320
- 2023年01月25日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
本書は、終末期医療、精神科医療に携わる著者が、悩みや不安を抱えている人の話の聴き方についてまとめたもの。
著者はもともと看護師、看護教員であるが、夫の死をきっかけに開眼し出家。人間の根源的な苦しみをケアする、スピリチュアル・ケアの活動を行い、日々、人生のさまざまな問題に直面している人たちと向き合い、話を聴いている。そこで気づいた、「聴く」ことの意味や大切さ、そして相手と自分、双方の幸せにつながる聴き方について説く。
悩みや不安を抱えている人の話を聴くことは、相手のために答えを出してあげることではなく、相手自身が答えを出すのを手伝うことだと、著者は言う。
相手の話に、ただ丁寧に耳を傾ける。それは、一般に「傾聴」と呼ばれるが、この本では傾聴のテキストに載っているようなことではなく、著者自身がケアの現場で実践して気づき、獲得してきたことを、「こうしてみたら」と、一つの提案として紹介している。

- 「営業」で勝つ! ランチェスター戦略
- 福永雅文
- PHP研究所
- ¥1045
- 2011年01月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.71(17)
小が大に勝つ戦いのバイブル「ランチェスター戦略」の第一人者が、御社の営業戦略を変える!!▼◆1時間で基本の理論を習得できる ◆経営から営業部課レベルまでの“実務”に有効 ◆多くの企業で成果を実証済み▼営業パーソンの商談スキルやモチベーションなど「戦術」レベルの対策で、過当競争時代を生き抜くことはできない。▼目標達成のためのシナリオをつくり、資源を最適配分する「戦略」を立ててこそ、真の営業改革は達成されるのである。▼既存客セールスと新規開拓の両方について実務的に解説した本書で、ライバル会社に圧倒的な差をつける!

- 限りなくシンプルに、豊かに暮らす
- 枡野俊明
- PHP研究所
- ¥1100
- 2015年09月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.96(29)
自分にとって本当に必要なものを見極め、いらないものを最大限削ぎ落とすーー禅の精神に裏付けされた、清々しく心豊かな生活のすすめ。

- す〜べりだい
- 鈴木のりたけ
- PHP研究所
- ¥1320
- 2015年02月16日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.49(63)
「しごとば」シリーズや、『ぼくのトイレ』などで人気の鈴木のりたけがおくる、小さい子から楽しめることばあそび絵本。
公園のすべりだいが、変な形になっちゃった! すーーーーべりだいに、すべりだいーーーーーに、するするべりべりだい〜ん! すべりパイや、なが〜いすべりだい、さらには、空からすべりだいがふってきて……? こんなすべりだい、あったらいいな!
声色を変えたり、抑揚をつけたり、読み方次第で楽しみ方が何倍にも広がります。読み聞かせにぴったりの一冊です。

- 雑談力
- 百田 尚樹
- PHP研究所
- ¥814
- 2022年11月04日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
多くの人は雑談について「相手が興味を持ちそうな話をすればいい」と思っているが、それは大きな勘違い。実は本当に面白い話題とは、「話し手が一番興味がある話題」である。その話の構成を工夫しさえすれば、誰もが引き付けられる雑談になるのだ。
本書では稀代のベストセラー作家が、面白い話を構成する技術を開陳。「地球上には、自然界で生きていけない動物が一種類だけいる」「毎日同じ服を着て同じメニューの粗食を食べた『ドケチ』の超お金持ち」「若き出光佐三にとことん資金援助した日田重太郎のぐっとくる一言」など、「ウケるネタの具体例」も満載。21万部ベストセラーとなった前著(PHP新書)に、「『藩』という言葉はほとんど使われていなかった」など、江戸時代のエピソードを加えて文庫化。
【目次より】
●数字が重要ーーシャチの体重は10トン
●失敗談ほど面白いものはない
●「面白さ」の7割以上が話術
●零戦の話ーー機体に直線がほとんどない奇跡の戦闘機
●雑談に使える古典の物語
●個人的な思い出話でも、普遍性を持たせればOK
●ヨーロッパ人を驚かせた幕末の日本人
●親友とする真面目な話
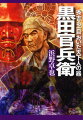
- 黒田官兵衛
- 浜野卓也
- PHP研究所
- ¥869
- 1996年06月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(6)
累計10万部突破のロングセラー!
軍略の才と仁徳を併せもった戦国一の器量人。
官兵衛が荒木村重のいる有岡城に入ったまま出てこない、と聞いた信長は、裏切られたと思い、 直ちに 「官兵衛の子、松寿丸を殺せ」と秀吉に命令した。
しかし、官兵衛を信じる秀吉は竹中半兵衛と謀り、秘密裏に松寿丸をかくまうのだったーー。
秀吉の信任厚く、天下統一に向かって縦横無尽の活躍をした黒田官兵衛。
敵将からもその人徳を称えられた名軍師の生涯を描く長編人物小説。
信長は時代が生んだ天才である。そして天才に相応しく、古いこの国の慣習を根こそぎ改めていった。だが信長には、覇道はあっても王道はない。王道を歩もうとしない王は、いつかこの世から拒まれ、不慮の死を遂げる、と官兵衛は思った。
すると、官兵衛の心中に不逞の野望が芽生えた。
これから天下はどうなる、と思った時、官兵衛は秀吉の耳もとで囁いた。
「との! 天の時が訪れてござる。天下をお取りなされ!」
(本書より)
文庫書き下ろし。

- がんになったら悲しんでいる時間はありません!
- 鈴木 みちる/遠藤 陽一/田中 聡/廣田 毅
- PHP研究所
- ¥1760
- 2024年01月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.0(1)
夫が「ファイナルステージ」のがんと告知され、呆然とし、何を頼りにしていいかわからない状態から、約8カ月で腫瘍マーカーの数値を、医師も驚くような低い値に安定させ、がんを克服した体験談。
幸いにも信頼できる医師や遺伝子治療と出会い、食事を「砂糖・塩・醤油」を使わない内容にすることで、夫のがんを「やっつけた」著者の「夫を助けるために一体何をしたのか?」をまとめた1冊。
「がんが棲みにくい体」をつくるため、「制限はありつつも、食べるのが楽しみになる美味しい食事」を心がけてサポート。専門家監修の「がんの最新情報」や著者が実践してきた「がんをやっつけるレシピ」を多数紹介している。
「後悔のないよう、できることから始めること」を促す、「自分や家族が、がんになってしまった人、がんに関心がある人」が知りたい情報を集結させた内容。

- 中学時代にガンバれる40の言葉
- 中谷彰宏
- PHP研究所
- ¥1210
- 2015年07月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
壁は越えるもの破るものだけど、夢を掲げる場にもなる! 夢をかなえるために自分を励まし戒める、壁に貼る中谷さん流の言葉を紹介。

- ディベートをやろう!
- 特定非営利活動法人 全国教室ディベート連盟
- PHP研究所
- ¥3300
- 2017年11月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
対話的で深い学びに効果的で、客観的・批判的・多角的な視点を身につけられるディベートの進め方を、具体的な論題を示しながら紹介。