更新 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1401 から 1420 件目(100 頁中 71 頁目) 

- 小学校新学習指導要領図画工作科題材&授業プラン
- 岡田京子
- 明治図書出版
- ¥2420
- 2020年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
子供の資質・能力を育成するために、本書では、指導計画作成から題材設定、評価まで、図工授業づくりの基礎をしっかり盛り込みました。また、各題材の紹介では、子供の様子を丁寧に語ることで、授業展開がバッチリ理解できるようにしています。目の前で活動を楽しんでいる子供には何が起こっているのか。それに気が付けば、楽しい活動のその先が見えてきます。

- 経済後進性の史的展望
- ガーシェンクロン/池田 美智子
- 日本経済評論社
- ¥6050
- 2016年09月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
後進国の工業化に関して半世紀以上にわたり影響力を持ち続けてきた基本的文献。中国など新興国の動向への示唆にも富み今日的意義もきわめて大きい。
第1章 歴史的観点から見た経済後進性
第2章 近代工業化の「前提諸条件」という概念に関する考察
第3章 社会体制、企業者活動と経済発展
第4章 イタリアの工業成長率に関する覚書(1881-1913年)
第5章 ロザリオ・ロメオと資本の本源的蓄積
第6章 ロシアの経済発展のパターンとその諸問題 1861-1958年
第7章 19世紀のロシア思想史に現れた経済発展
第8章 ブルガリアの工業化の若干の様相:1878-1939
第9章 ソヴィエト重工業:1927-1937年間のドル表示生産指数
第10章 ソヴィエト・ロシアの工業成長率に関する覚書
第11章 ソヴィエト・ロシアの工業企業
第12章 ソヴィエト・ロシアの経済情報に関して見落とされていた資料
第13章 ソヴィエト小説への反映
第14章 『ドクター・ジバゴ』に関するノート
補稿1 イタリアの工業発展指数の記述 1881-1913年
補稿2 ブルガリアの工業化基礎資料および計算
補稿3 所得と富の長期的成長測定上の諸問題

- 歌集 冬の海
- 五井昌久
- 白光真宏会出版本部
- ¥1980
- 1987年01月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
心を練って言葉を練れ、言葉を練って心を練れ、歌は心であると透徹した心がうたう世界平和、信仰、神、人生など363首の短歌を収める。

- 茶の湯の銘 禅のことば
- 淡交社編集局
- 淡交社
- ¥1320
- 2020年12月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
〈禅味あふれることばを銘に〉
〈銘から禅語も覚えましょう〉
茶道具の銘には禅語や禅の歴史にまつわるエピソードなどに取材したものも少なくありません。
本書は、既刊の淡交新書・茶の湯の銘シリーズ(季節のことば・和歌のことば・物語のことば)に加える新たな一冊として、禅語や禅に関わる銘や、禅味あふれることばの銘を簡単な解説とともに掲載、関連する禅語も併記して紹介します。
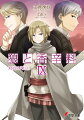
- 狼と香辛料IX対立の町(下)
- 支倉 凍砂/文倉 十
- KADOKAWA
- ¥748
- 2008年09月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.19(53)
「狼の足の骨」の情報を得るため、ロレンスたちが訪れた町ケルーベは、土地を巡って北と南が対立していた。そんな訳有りの町に、生肉を喰らえば長寿を得るという伝説を持つ海獣、イッカクが陸揚げされる。町の力関係をひっくり返しかねない価値を持ったイッカクの登場で、町は俄かに騒がしくなる。
そんな中、イッカクの横取りを狙う女商人エーブは、ローエン商業組合を抜けて自分のところへ来るようロレンスを誘う。狼狽するロレンスのもとには、さらにローエン商業組合から協力要請の手紙が送られてきて……!?
ロレンスの出した答えとは? そして、その時ホロは……。 『対立の町』編、いよいよ完結!!

- もっと知りたくなる 最適化数学の基礎
- 田中 環
- 培風館
- ¥2530
- 2025年10月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は,最適化(線形計画と非線形計画)の数理について,基本的な線形代数の1次形式の考え方からはじめ,連立1次方程式の様々な表現方法,シンプレックス法,双対定理,二者択一の定理,および多変数関数の極値と最適性条件の関係などを初心者向けに解説するものである。高等学校の数学の内容からの接続を意識して,やさしい例を取り上げて,図も用いながら,論理的厳密性にはあまりこだわらず,直感的理解が身につけられるよう配慮している.
1. 線形数学の基礎と1次形式
2. 線形計画
3.線形計画の双対性
4.非線形計画
参考文献
問題解答

- 最新テレビまんが大行進〜女の子【カセット】
- アニメサントラ
- ¥2349
- 1993年12月21日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 最大と最小3訂版
- 春日正文
- 科学新興新社
- ¥880
- 1988年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 列車大行進 大手私鉄コレクション 関東編 大都会を支える車両バリエーション
- (鉄道)
- ビコム(株)
- ¥2662
- 2017年10月21日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- スギと広葉樹の混交林 蘇る生態系サービス
- 清和 研二
- 農山漁村文化協会
- ¥2750
- 2022年09月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
戦後の拡大造林によって全国隅々まで広がったスギ人工林は水質浄化や洪水防止、持続的生産といった生態系サービスを著しく損なっている。それでは生態系サービスを向上させる森林とはどのようなものか。東北大学の試験地のスギ林での無間伐区、弱度間伐区、強度間伐区の比較研究によって、通常の林業経営で行われるような弱度間伐ではなく、広葉樹との混交化がすすむような強度間伐でこそ生態系サービスが改善することをメカニズムを含めて示す。あわせてスギ天然林のような本来の生態系を取り戻す植栽や制御、間伐のあり方を提案する。
【目次】
序章 スギの林冠に近づく広葉樹 --尚武沢試験地の今
1部 蘇る生態系サービス
1章 水質の浄化 --きれいな水が飲める
2章 生産力の向上ーー林冠に転流する大量の窒素
い
3章 持続する生産力ーー窒素は巡る
4章 洪水や渇水を防ぐ
5章 クマを山に留めるーー足ることを知らしめる
2部 スギと広葉樹の混交林をつくるーー自分の山でやってみる
6章 目標は地域のスギ天然林
7章 天然更新で混交林を目指すーー尚武沢間伐強度試験の20年
8章 人工植栽で混交林をつくる
9章 広葉樹の良質材をつくる --曲がりや太枝を抑制する方法
10章 巨木林を目指す全層間伐ーー間伐木を利用しながら
11章 制度を練り直すーー進歩する科学に依拠して
序章 スギの林冠に近づく広葉樹 --尚武沢試験地の今
1部 蘇る生態系サービス
1章 水質の浄化 --きれいな水が飲める
2章 生産力の向上ーー林冠に転流する大量の窒素
い
3章 持続する生産力ーー窒素は巡る
4章 洪水や渇水を防ぐ
5章 クマを山に留めるーー足ることを知らしめる
2部 スギと広葉樹の混交林をつくるーー自分の山でやってみる
6章 目標は地域のスギ天然林
7章 天然更新で混交林を目指すーー尚武沢間伐強度試験の20年
8章 人工植栽で混交林をつくる
9章 広葉樹の良質材をつくる --曲がりや太枝を抑制する方法
10章 巨木林を目指す全層間伐ーー間伐木を利用しながら
11章 制度を練り直すーー進歩する科学に依拠して

- 【謝恩価格本】魚の自然誌ー光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説
- ヘレン・スケールズ/林裕美子
- 築地書館
- ¥3190
- 2020年01月28日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
体の模様・色はなんのためにあるのか、
浮袋が先か肺が先か、
ナマズはハトの捕まえ方をどのように学ぶのか、
群れの中で魚どうしぶつからないのはなぜか、
大きな口で丸呑みする捕食者からいかに逃れるのか、
フグはなぜ自分の毒で中毒しないのか。
世界の海に潜って調査する気鋭の魚類学者が自らの体験をまじえ、
魚の進化・分類の歴史、紫外線ライトで見る不思議な海の世界、
群れ、音、色、狩り、毒、魚の思考力など、
魚にまつわるさまざまな疑問にこたえる。

- 通貨・銀行信用・経済循環
- ヘスース・ウエルタ・デ・ソト/蔵研也
- 春秋社(千代田区)
- ¥7150
- 2015年11月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
経済最優先を扇動する国家に未来はあるか。世界の経済はどこに行こうとしているのか。混迷を続ける経済危機の根底にあるもの、その正体を経済的・法的・歴史的な視点から探るダイナミックな処方箋。ミーゼス&ハイエク以来のオーストリア学派理論の集大成的労作。

- 森の健康診断
- 蔵治光一郎/洲崎燈子
- 築地書館
- ¥2200
- 2006年04月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
森林と流域圏の再生をめざして、森林ボランティア・市民・研究者の協働で行なう、手づくりの人工林調査のためのガイドブック。

- 人生と選択
- 西園寺昌美
- 白光真宏会出版本部
- ¥1760
- 2013年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
2004年に各地で行なわれた講演会の法話集の第1集。自分の望む人生を築くには瞬間瞬間の選択がいかに重要であるかを分かり易く説き明かす。

- DVD>れっしゃだいこうしん キッズバージョン(2026)
- ビコム
- ¥1980
- 2025年12月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 期限付き建築物設計指針第2版
- 日本建築学会
- 日本建築学会
- ¥3630
- 2025年02月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 【謝恩価格本】信州の建築家とつくる家15
- 日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会/JIA長野県クラブ
- 新建新聞社
- ¥1650
- 2020年06月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
信州を拠点に活躍する建築家の、住まい手に寄り添ってつくりあげた渾身の25の住宅作品を掲載。
特集は、地域と交わる家。積極的に地域と交流する空間や仕掛けを備えた家を取りあげ、住宅の一部を地域の人が集まる店舗として開く、縁側や土間といった昔からの近所づきあいの場を進化させるなど、地域コミュニティをつなぐ建築家の試みが垣間見られる家づくり。
地域で活躍する建築家とつくる、信州への移住希望者や地域との交流を生み出す家を多数紹介し、信州ならではの豊かな暮らしを再発見する一冊です。

- 微積分
- 味八木徹
- 科学新興新社
- ¥796
- 1990年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 我即神也
- 西園寺昌美
- 白光真宏会出版本部
- ¥1760
- 1996年01月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
あなた自身が神であったとは信じられないでしょう。あなたは本来神そのもの、内に無限なる愛と叡智とパワ -を秘めた存在だったのです。これからの時代は、誰も彼もがその真実の姿に立ち返らなければならないのです。
あなた自身を神そのものに目覚めさせる待望の書。

- 【輸入楽譜】エルガー, Edward: 行進曲「威風堂々」 第1番 Op.39/1/Birtel編曲
- エルガー, Edward
- ショット・ミュージック社/マインツ
- ¥1760
- 1970年01月01日頃
- 要確認
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)