デザイン の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1441 から 1460 件目(100 頁中 73 頁目) 

- デザインのネタ帳 プロ並みに飾る文字デザイン Illustrator+Photoshop
- エムディエヌコーポレーション
- ¥2640
- 2022年05月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- GARDEN DIARY No.04 宿根草のガーデンデザイン
- 手紙社
- 主婦の友社
- ¥1760
- 2024年03月21日
- 予約受付中
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
GARDEN DIARY[ガーデンダイアリー ] No.04 目次【巻頭】庭の花束【特集 宿根草のガーデンデザイン】風に揺れる草花を集めたペレニアルガーデン|一年草の春から宿根草の夏へ|環境に合った植物を選びありのままの姿で育てる|SPECIAL TALK「教えて、宿根草との付き合い方のコツ」平栗智子(服部牧場ガーデナー)× 本田直也(本田ハビタットデザイン代表)【第2特集 遠くても行きたい庭が素敵なガーデンショップ】ルーシーグレイ & ルーシーグレイボタニスク(神奈川)|日野春ハーブガーデン(山梨)|GARDENS(香川)【植物企画 アジサイ】アジサイのお茶会|アジサイ図鑑|品種選びのコツ|育て方Q&A|紫陽花の便りを届けませんか【GARDEN TO TABLE】おいしくいただく庭の恵み【バラ企画】育種家・木村卓功さんの「強く美しいバラを追い続ける終わりなき旅」|2024年春の最新品種

- ディジタル・デザイン・テクノロジ(no.5)
- CQ出版
- ¥2200
- 2010年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 毎日持ちたいおしゃれなデザイン! かぎ針編みのデイリーバッグ&ポーチ
- ブティック社
- ¥1540
- 2024年03月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- デジタル&デザイン・トランスフォーメーション
- 庄司貴行/斎藤明
- 創成社
- ¥2420
- 2023年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 都市デザイン 101のアイデア
- マシュー・フレデリック/ヴィカス・メータ/杉山まどか
- フィルムアート社
- ¥1980
- 2021年10月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
見慣れた街の見方が変わる!
都市空間をひもとき、
生活や社会を豊かにするヒントを手に入れよう
シンプルで楽しいイラストと、想像力をくすぐられるセンテンスで、本質をわかりやすく学べる〈101のアイデア〉シリーズ。同シリーズの1冊である本書は、都市デザインの世界に飛び込む最適で最高の入門書となっています。
都市計画やまちづくり、アーバンデザインについて知りたい学生や初学者にとって、専門的な学術書は難しく、高いハードルに感じてしまうかもしれません。そこで本書では、実際のデザインプロジェクトで使用できる具体的なツールを厳選し、複雑なコンセプトを明確で簡潔にまとめています。
都市空間、街路、歩行者体験、デザインプロセス、物理的なデザインの決定などがもたらす、心理的、社会的、文化的、経済的な影響について、大学やデザインスクールで教壇に立つ経験豊富な講師が解説していきます。
学生だけでなく、経験豊富な専門家、デザイナー、プランナー、都市管理者にも、そして日常生活や社会をよりよく生きていきたいと願う私たちにとっても、都市や地域への視座を更新する、多様なアイデアや思考をもたらしてくれるはずです。
【項目例】
◎都市デザインは建築ではない
◎街区ではなく街路をデザインする
◎都市は親しい人と見知らぬ人のためにある
◎乗車方法が交通システムを動かす
◎秩序は多様性を渇望する
◎時速5kmに合わせて設計する
◎都市には裏庭が必要だ
都市デザインのための幅広いアイデアが、私たちの日常のディテールを更新する。
生活者の視点から社会の新しいかたちを見出すために編まれた実践的ヒント集。

- 日本型多文化教育とは何か
- 松尾 知明
- 明石書店
- ¥2860
- 2023年12月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
2018年の入管法改定を契機に「移民時代」を迎えた日本では、多文化共生の課題は新たな段階を迎えている。本書は、それに対する考え方や進め方を具体的に構想し、「日本人性」の概念を問い直すことで、日本型多文化教育のグランドデザインを提案する。

- マルチクラウドネットワークの教科書 耐障害性と冗長性を実現するデザインパターン
- 宮川 亮
- 翔泳社
- ¥3740
- 2023年12月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
本書は複数のクラウドを活用した「マルチクラウドITシステム」を支えるネットワーク基盤の設計・構築について解説する書籍です。ITシステムでのマルチクラウド活用を想定した通信要件の整理、クラウドのネットワーク技術の解説と設計のポイント、非機能要件の実装について詳説します。

- DESIGN-R2020 つけ方マスター
- 田中マキ子/柳井幸恵
- 照林社
- ¥2860
- 2023年09月01日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
褥瘡状態評価スケールDESIGN-R2020は、すべての入院患者さんにつける必要のある必須スケールです。
2020年に改訂された最新版では、「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」「臨界的定着疑い」の項目が新たに追加されました。
これによって経過を追って褥瘡を診るには最適のツールになったのですが、「つけ方」が難しいという声もよく聞かれます。
この本では、DESIGN-R2020の各項目のつけ方の「基本」から「応用」まで、豊富な症例を用いて解説しています。
「症例エクササイズ」でご自分で採点したものを「回答欄」で確認できます。
スタッフを交えた褥瘡勉強会のテキストとしてもピッタリです。
Part1 DESIGNツールの進化を振り返る
Part2 DESIGN-R2020を読み解く基本
Part3 DESIGN-R2020の各項目のつけ方エクササイズ
Part4 褥瘡の経過を追ってアセスメント

- 道路・公共交通のくふう
- 徳田 克己
- 金の星社
- ¥3520
- 2023年01月07日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ユニバーサルデザインに配慮した乗り物や、バリアフリーに取り組んだ設備などの様々な工夫を、質問に答える形式でわかりやすく紹介。

- 2024年 カレンダー ハンガーカレンダー リフィル 1月始まり デザインフィル 31295006
- 〇デザインフィル
- ¥1100
- 2023年08月31日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ハンガーカレンダー専用リフィル。
ハンガーカレンダーはインテリアになじむシンプルなカレンダーです。
二つ折りにしたカレンダーリフィル本体(6枚)をハンガーパーツにかけて、使用します。
書き込めるスペースがたっぷりあり、家族の予定管理にも便利です。●寸法:パッケージサイズ/H307mmW440mmD6mm本体サイズ/H297mmW420mmD6mm●掲載期間:2024年1月〜2024年12月●素材:紙製●枚数:6枚●罫内容:壁掛/壁掛

- 声のデザイン
- 林重光
- ジー・ビー
- ¥1980
- 2024年01月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(3)
"全く同じことを話しても、声によって伝わり方が大きく変わる"
ということに気付いた世界のビジネスパーソンたちがいま、
ボイストレーニングに注目し始めています。
どんなに完璧に仕上げた資料も、
どれだけ優秀なマネージャーも、
「伝えるときの声」に無頓着だったらその真価が発揮されません。
・企画が採用されない
・熱意が顧客に伝わらない
・部下や同僚と上手にコミュニケーションが取れない
といった悩みを抱えるビジネスパーソンはぜひ、ご自身の声に着目してみましょう。
どういったシーンにどんな声が適しているのか。
いつでも安定した声を出し続けるには何が必要なのか。
誰もが生まれながらに持つ「世界にひとつの個声」を磨き、
あなたの真の魅力や伝えたいことが、より相手に伝わるようになる1冊です!

- ポスト資本主義社会のデザインーー生活のデザインを生活者自身の手に取り戻すために
- 野口尚孝
- 皓星社
- ¥3850
- 2022年11月09日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は現代のデザインのあり方に対する批判であるとともに、その背景にある現代資本主義社会への批判でもある。従来のデザイン論とはまったく異なる視点からのデザイン論である。いまデザインがかかえる問題は単にデザイナーという職能の問題だけではなく、それを含む社会全体のあり方に関わる大きな問題にまでなっている。(「はじめに」より)
買い替えが当然のように促され、エネルギー消費量や廃棄物が増え続ける現代社会。「持続可能な社会」と「経済成長」の間での対立的矛盾の中で、デザイナーが考えるべきこととは? 本書は、高度成長期に育ち、 工業デザイナー、そしてデザインの思考過程を主とする研究に取り組んできた筆者が、マルクスの資本論を手がかりに資本主義社会への疑問と矛盾の分析を試みる、まさに戦後デザイン史の「生き証言」である。
はじめに
第一部 生活のデザイン能力はどのように生活者から失われてきたのか?
第一章 問題提起
第二章 近代までのモノづくりの歴史と生活形態の変遷
第三章 二十世紀後半の東西冷戦下における社会生活形態とデザイン
第四章 二十一世紀の世界におけるモノづくりと生活形態の変貌
第一部のまとめ
第二部 生活者の手に取り戻すべき本来のデザインとはどのような能力か?
第五章 現代デザイン研究のあり方について
第六章 「デザインとは何か」をめぐって
第七章 「どうデザインするか」をめぐって
第八章 本来のデザインとはどのような行為なのか?
第二部のまとめ
第三部 生活者自身が生活のデザインを行なえる社会を目指して
第九章 ポスト資本主義社会に向けてのさまざまな試み
第十章 「ポスト資本主義社会」はどのようにデザインされるべきなのか?
おわりに
あとがき
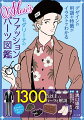
- Men’sモダリーナのファッションパーツ図鑑
- 溝口康彦/福地宏子/數井靖子
- マール社
- ¥1760
- 2021年04月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
レディースファッションに比べ、メンズは種類もデザインも少ないと思うかもしれませんが、歴史をたどり世界に目を向けると、実はメンズファッションはレディースに負けないくらい華やかで種類もたくさんあります。
本書は、襟や首回り、袖口のデザイン、ネクタイの結び方やアクセサリーの種類、帽子や靴などの小物類、スーツなどのセットアップ、着こなしやドレスコードにまつわるコラムなど、メンズファッションの用語や特徴をわかりやすく解説したイラスト図鑑です。
1300点以上のパーツそれぞれにイラストと解説が入っていますので、思い描くデザインを、イラストの形を見ながら探すことができます。
メンズのファッションに絞った内容ですが、レディースにメンズテイストを加えたり、ジェンダーレスなファッションの参考としても幅広く使えます。
ショッピングやコーディネイトはもちろん、イラストやデザインの参考にも幅広くお役立てください。
首(ネックライン)
襟(カラー)トップス用
襟(カラー)アウター用
ネックウェア
袖・袖付け
カフス・袖口
トップス
ボトムス
インナー
ベルト
ベスト
アウター
ポケット
セットアップ
オールインワン
手袋
レッグウェア
ボディウェア
水着
部位・パーツ名・装飾
アクセサリー
ヘアアクセサリー
携帯時計
サングラス・眼鏡
帽子
靴(シューズ)
バッグ
柄・生地
配色
作例イラスト
スーツの着こなし1 アンボタン・マナー
スーツの着こなし2 スーツの部位別寸法
スーツの着こなし3 ポケットチーフの折り方
ドレスコード
西欧の駆け足メンズファッション史

- 東日本大震災とグッドデザイン賞 2011-2021
- 日本デザイン振興会/編集
- フリックスタジオ
- ¥3300
- 2022年09月23日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「東北・茨城のグッドデザイン 2011-2021」
公益財団法人日本デザイン振興会は、2011年度から2020年度の10年間、グッドデザイン賞を通した東日本大震災からの復興支援を行ってきました。
本書では、「復興と新しい生活のためのデザイン」をテーマに、2021年度受賞も加えた11年間の東北6県および茨城県の受賞デザインに焦点を当てるべく、特に特別賞を受賞するなど高い評価を得たデザインや各県の特徴ある産業を中心に、受賞者や受賞デザイナーに改めて取材を実施。「手仕事をつなぐ」「創造的ものづくり」「地域価値の再発見」「建築」「コミュニティデザイン」「記憶の継承」という6つの視点から、受賞者ごとに72本の記事にまとめました。各地の文脈と震災後の時間軸のなかで、さまざまな課題にデザインがどう応えようとしてきたかをお伝えします。
デザインのちから/内藤廣
ーーーーーーーーーー
東北・茨城のグッドデザイン2011-2021
●手仕事を今の暮らしに
浅はち/サラダボール/洋鉢 [ブナコ株式会社]
KOFU 南部裂織 [株式会社金入]
プロ・アルテ シリーズ/南部鉄器急須 HEAT [株式会社岩鋳 ほか]
仙台箪笥 猫足両開き・壱番/コンソール 〜monmaya+/アップライトシリーズ 壁掛け[株式会社門間箪笥店]
他
●未来を拓くものづくり
安寿紅燈籠(クラブ制りんごブランディング)
浄法寺漆/ウルシトグラス/茶筒/角杯
「裂き織り」で眠っていた布に新しい命を吹き込む 「さっこらproject」
石巻工房/ISHINOMAKI BIRD KIT/石巻ホームベース
他
●そこにある価値を共有する
弘前シードル工房kimori
いわて羊を未来に生かす i-wool(アイウール)プロジェクト
東北食べる通信
ブルーファーム/ブルーファームカフェ/農ドブル/雄勝ガラス/有限会社ジャンボン・メゾン
他
●まちの未来をつくる建築
弘前れんが倉庫美術館
釜石市民ホール TETTO
釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館
釜石市の復興公営住宅(大町復興住宅1号、天神復興住宅)
他
●希望をつくるコミュニティのデザイン
王余魚沢倶楽部/3つのおきあがり小法師/浅めし食堂 [合同会社tecoLLC.]
いわてのテとテ
ヤタイ広場
ISHINOMAKI2.0/石巻VOICE
他
●記憶をつなぎ未来をつくる
高田松原津波復興祈念公園 国営 追悼・祈念施設
桜ライン311
おはなし木っこ・だれがどすた?
思い出サルベージ
他
ーーーーーーーーーー
東北・茨城のグッドデザイン 2011-2021全受賞デザイン
グッドデザイン賞クロニクル 2011-2021
地域を変えるデザインの可能性/立木祥一郎+松沢卓生+加藤紗栄+松村豪太+佐藤哲也
グッドデザイン賞から見る東北の10年/加藤紗栄
おわりに/謝辞

- Figma for UIデザイン[日本語版対応] アプリ開発のためのデザイン、プロトタイプ、ハンドオフ
- 沢田 俊介
- 翔泳社
- ¥2750
- 2022年11月14日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.8(5)

- バイオデザイン 第2版
- ポール・ヨック/ステファノス・ゼニオス/ジョシュ・マコーワー/トッド・ブリントン/ウダイ・クマール/ジェイ・ワトキンス
- 薬事日報社
- ¥15400
- 2022年08月01日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
原書である「BIODESIGN(2nd Edition)」は米国スタンフォード大学をはじめ、世界で実践されている医学・工学・ビジネスの3分野を連携させた医療機器開発のエキスパートを育成するための教育プログラム“バイオデザイン・プログラム”を書籍化したものです。
バイオデザイン・プログラムは、医療機器開発に必要な “課題解決型のイノベーション”に欠かせないデザイン思考やスキルを実践的に習得することを目的とした世界的に認められている人材育成プログラムです。
本書ではバイオデザイン・プログラムにもとづいた“医療機器イノベーション”を起こすために必要な「ニーズの探索・選択」、「コンセプトの創造・設定」、「開発戦略・計画立案・事業企画立案」などについて、具体的事例を交えながらシステマチックに学ぶことができます。
第2版では、基本骨格はそのままに、全体を通じて新しい動きなどを盛り込み大幅に内容を修正・刷新したほか、価値へのフォーカス、グローバルな視点、プロセスインサイトの項目が新設されました。
キーワードはアフォーダブル(affordable)、アフォーダビリティ(affordability)。この言葉は、適正な価格・手頃な価格などの意味であり、この感覚を持ちえないことには医療機器・医療技術は社会や医療保険に受け入れられないとされている。
【目次】
《序文》
・価値へのフォーカス
・グローバルな視点(アフリカ、中国、ヨーロッパ、インド、日本、ラテンアメリカ)
・プロセスインサイト
《パートI ニーズの特定》
ステージ1 ニーズ探索
1.1 戦略的フォーカス
1.2 ニーズ探求
1.3 ニーズステートメントの作成
アクラレント社ケーススタディ:ステージ1
ステージ2 ニーズ選別
2.1 病態の基礎
2.2 既存の解決策
2.3 ステークホルダー分析
2.4 市場分析
2.5 ニーズの選択
アクラレント社ケーススタディ:ステージ2
《パートII コンセプトの創出》
ステージ3 コンセプト創造
3.1 アイディア出し
3.2 最初のコンセプト選択
アクラレント社ケーススタディ:ステージ3
ステージ4 コンセプト選別
4.1 知的財産の基礎
4.2 許認可規制制度の基礎
4.3 保険償還の基礎
4.4 ビジネスモデル
4.5 コンセプト探求と評価
4.6 最終コンセプト選択
アクラレント社ケーススタディ:ステージ4
《パートIII 事業化》
ステージ5 開発戦略
5.1 知的財産戦略
5.2 研究開発戦略
5.3 臨床戦略
5.4 許認可規制戦略
5.5 品質マネジメント
5.6 保険償還戦略
5.7 マーケティング・ステークホルダー戦略
5.8 販売と流通戦略
5.9 競争優位性とビジネス戦略
アクラレント社ケーススタディ:ステージ5
ステージ6 事業計画立案
6.1 事業計画と財務モデル
6.2 戦略の統合とコミュニケーション
6.3 資金調達方法
6.4 代替出口戦略
アクラレント社ケーススタディ:ステージ6
・製作チームについて
・画像著作権
・用語解説
・索引

- 2024年 カレンダー カレンダー リング<M> ネコ柄 1月始まり デザインフィル 31271006
- 〇デザインフィル
- ¥990
- 2023年08月31日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
月間ブロックにちょっとした書き込みもできる『カレンダー 卓上リング<M>』
ダブルリング製でめくりやすさが特徴です。お気に入りの柄で部屋のインテリアとしてもおすすめです。
ネコ柄は、猫たちとともに季節の移り変わりを楽しめるカレンダー。生粋の猫好きであるイラストレーターの小泉さよさんによるやわらかな雰囲気のネコのイラストは、毎年すべて描き下ろしです。
とことん手描きにこだわったデザインは、罫線、日付の数字、各月の数字も手描きで、ほっとする雰囲気のカレンダーです。●寸法:パッケージサイズ/H178mmW187mmD10mm本体サイズ/H145mmW180mmD60mm●掲載期間:2024年1月〜2024年12月●素材:紙製●枚数:12枚●罫内容:卓上/卓上●:M

- 混合研究法の手引き
- マイク・フェターズ/抱井 尚子
- 遠見書房
- ¥2860
- 2021年04月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
質的アプローチと量的アプローチを統合することで,一方だけでは得られない相乗効果を生むことを目指す混合研究法アプローチ。
本書は,優れた混合型研究論文を読み解く(=トレジャーハントする)ことで,自然と混合型研究のキーポイント(=宝)を学ぶことができるユニークな入門書です。混合研究法にこれからチャレンジしてみたい方,より習熟したい方に必読の一冊。
第1章 トレジャーハント(宝探し)で学ぶ混合研究法 マイク・フェターズ
第2章 収斂デザイン論文のトレジャーハント 抱井尚子
第3章 説明的順次デザイン論文のトレジャーハント 河村洋子
第4章 探索的順次デザイン論文のトレジャーハント 稲葉光行
第5章 コミュニティを基盤とした参加型デザイン論文のトレジャーハント 井上真智子
第6章 介入デザイン論文のトレジャーハント 抱井尚子
第7章 多段階評価デザイン論文のトレジャーハント 河村洋子・尾島俊之
第8章 事例研究型デザイン論文のトレジャーハント 本原理子,榊原麗,エレン・ルビンスタイン,マイク・フェターズ
第9章 複合型評価研究デザイン論文のトレジャーハント エレン・ルビンスタイン,榊原麗,本原理子,マイク・フェターズ
第10章 トレジャーハントで学ぶ混合型研究論文の執筆と査読 マイク・フェターズ,抱井尚子

- 2024年 ダイアリー BM-4<B5> 2024 12月始まり デザインフィル 32912006
- 〇デザインフィル
- ¥1650
- 2023年08月31日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
見開き1ヶ月タイプ(前年12月から翌年3月まで収録)で、メモページが多くしっかり記録できるダイアリーです。
ビジネスに役立つ各種情報の付録もついています。●寸法:パッケージサイズ/H261mmW187mmD10mm本体サイズ/H261mmW187mmD10mm●掲載期間:2023年12月〜2025年3月●素材:表紙/耐寒性ビニールカバーPVC 製(銀箔押し)/MD PAPER●枚数:146p ●罫内容:ホリゾンタル/月間●:B5