性教育 の検索結果 ベストセラー 順 約 2000 件中 141 から 160 件目(100 頁中 8 頁目) 

- 遊びが学びに欠かせないわけ
- ピーター・グレイ/吉田 新一郎
- 築地書館
- ¥2640
- 2018年04月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.88(9)
異年齢の子どもたちの集団での遊びが、飛躍的に学習能力を高めるのはなぜか。
狩猟採集の時代の、サバイバルのための生活技術の学習から解き明かし、著者自らのこどもの、教室外での学びから、学びの場としての学校のあり方までを高名な心理学者が明快に解き明かした。
生涯にわたって、良き学び手であるための知恵が詰まった本。

- 発達障害の女の子のお母さんが、早めに知っておきたい「47のルール」
- 藤原美保
- エッセンシャル出版社
- ¥1650
- 2018年03月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.13(8)
思春期にある「発達障害の女の子」とその保護者を100組以上サポートしてきた著者が、
彼女たちが幸せにそして安全に生きていくために必要なことーー保護者や支援者が気をつけるべき点や、知識として理解しておくべき情報などを
「47のルール」としてわかりやすくまとめたのが本書です。
一般的に発達障害は、「男の子が8割、女の子が2割」といわれています。
女の子の場合は、おしゃべりが止まらずに仲間内で浮いていたり、逆におとなしすぎて目立たないなど、
男の子の場合とちがって周囲を困らせるというよりは、本人が困ってしまうことが多く、
また周囲がそれに気づかないケースも多く見受けられます。
発達障害とわからないまま地域の学校などに所属していると、思春期以降に、「性」に対する誤学習の影響などから
望まない妊娠や性の搾取といった危険な状況に置かれる事例が少なくありません。
実際、性産業には発達障害の女性が多いということが、最近のニュースやネット情報などから
一般に知られるようになってきました。
こうした状況は、性に関する正しい情報や、必要な生活習慣をきちんと身につけることで回避することができます。
しかし、保護者はどうしてもわが子の学校の成績などに目を奪われがちで、充分なケアができていないというのが現状です。
豊富な経験や、専門家からのアドバイスをもとに著者が作りあげてきた「発達障害の女の子たちが幸せに生きていくためのノウハウ」です。
ぜひご活用ください。
1章 診断や医療機関の上手な使い方について
2章 親としての心構え、親のとるべき行動
3章 日常生活での支援と療育について
4章 健やかな生活を送るための学校選び
5章 女の子に必要な「学び」--思春期と性教育
6章 療育支援Q&A
「何度注意してもやめてくれません」
「プライドが高くて注意するとパニックになります」
「新しい場所や新しいことが苦手です」……など。

- ピーター・ティール
- トーマス・ラッポルト/赤坂桃子
- 飛鳥新社
- ¥1731
- 2018年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.55(35)
シリコンバレーの大物は、みんな「この男」に学んでいる。ジョブズ、ザッカーバーグを超える無敵の男、その全戦略と破壊的思考法にせまる初の本!

- ワークシートから始める特別支援教育のための性教育
- 松浦賢長/千葉県立柏特別支援学校
- ジアース教育新社
- ¥3080
- 2018年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
小・中・高の12年間の系統性を持った性に関する指導。千葉県教育委員会の研究指定を受けて千葉県立柏特別支援学校が取り組んだ実践の成果を、性教育の第一人者である福岡県立大学の松浦賢長教授の協力を得て、一冊の本にまとめました。児童生徒の実態に即してすぐに使えるワークシート、そしてコマザキ先生の素敵なイラスト素材も豊富に収録したCD-ROM付きです。

- 0歳からはじまるオランダの性教育
- リヒテルズ 直子
- 日本評論社
- ¥1870
- 2018年06月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.29(17)
家庭で、学校で、性についてオープンに話し合う
オランダの性教育は、単に生殖に関するからだの仕組みを教えるといったものではありません。性についての正しい知識をありのままに伝えたうえで、子どもたち自身の意見を引き出し話し合わせるといった形の、リアルでアクティブな教育が行われています。
さまざまな文化・価値観をもつ人々が共存していくためには、互いの性意識をぶつけ合い、異質な存在を尊重する態度を養うことが不可欠です。それは、性的マイノリティの権利を認め、性暴力や望まない妊娠の危険を避けることにもつながります。
もちろん、性教育は学校だけでなく家庭でも行われます。赤ちゃんが生まれた時から親子間でスキンシップをし、つながりの感情を高め、性について何でも話し合える関係をつくることが、後になって子どもの性意識に大きな影響を与えるのです。本書ではこうしたオランダの性教育のあり方を、やさしく具体的に紹介します。
第1章 日本とこんなに違う、オランダ人の性意識
第2章 なぜオランダで性教育が義務化されたのか
第3章 生殖とセクシュアリティについての教育
第4章 〈性の多様性〉教育
第5章 障害児にこそニーズに沿った性教育を
第6章 性教育での教員の心得
第7章 性にオープンな社会への道ーータブーを打ち破ってきた人々
第8章 オランダの性教育から学べることーーこれからの日本の子どもたちのために

- あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠
- キャシー・オニール/久保尚子
- インターシフト
- ¥2035
- 2018年06月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.63(18)
:::: AI・ビッグデータの暴走を止めよ! ::::
全米を、世界を、震わせた人類への警鐘
★「必読です!」
ーー新井紀子(『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』)
待望の邦訳。ビッグデータとAIの被害に遭うのは「あなた」かもしれない
★「年間ベストブック」
ーーユヴァル・ノア・ハラリ(『サピエンス全史』)
魅了され、深く心をかき乱される 『ガーディアン』紙
いまやAI・ビッグデータは、人間の能力・適性・信用、
さらには善悪や身体までも評価し、選別し始めた。
問題は、こうしたAI・ビッグデータの仕組みや活用法の多くが、
偏見や誤りなどであふれていることだ。
中立・公正のように見えるアルゴリズムにも、
作り手の「見解」や「目的」が埋め込まれている。
数値化しにくいリアルな世界の複雑さや公平性を欠いたまま、
効率・収益を優先するアルゴリズムによって私たちの生活・社会が導かれていく。
さらに信用格付けが下がるなど、アルゴリズムによる評価を落とすと、
他分野にも影響がおよび、悪循環のフィードバックループが待っている。
私たちは、こうした破壊的なAI・ビッグデータとは何かを知り、
変えていくことによって、主導権を人間に取り戻さなくてはならない。
★ 世界的ベストセラー、年間ベストブック&賞、多数!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
::著者:: キャシー・オニール
データサイエンティスト。ハーバード大学で数学の博士号を取得。
バーナードカレッジ教授を経て、企業に転職し、金融、リスク分析、eコマースなどの
分野で、アルゴリズム作成などに従事。
ブログ「mathbabe」を開き、「ORCAA(オニール・リスク・コンサルティング&アルゴリズム・オーディティング)」を創設。
::訳者:: 久保尚子
翻訳家。IT企業勤務を経て、翻訳業に従事。訳書にスティーヴ・ロー『データサイエンティストが創る未来』、
マイケル・ブルックス&サイモン・ブラックバーン『ビッグクエスチョンズ 物理』など。
はじめに: AI・ビッグデータは破壊兵器になる
第1章[モデル] 良いモデル、悪いモデル
第2章[内幕] データビジネスの恐るべき真実
第3章[教育] 大学ランキング評価が多様性を奪う
第4章[宣伝] 弱みにつけこむオンライン広告
第5章[正義] 「公平」が「効率」の犠牲になる
第6章[就職] ふさわしい求職者でも落とされる
第7章[仕事] 職場を支配する最悪のプログラム
第8章[信用] どこまでもついて回る格付け評価
第9章[身体] 行動や健康のデータも利用される
第10章[政治] 民主主義の土台を壊す
おわりに: 人間だけが未来を創造できる

- レポート・論文の書き方入門 第4版
- 河野 哲也
- 慶應義塾大学出版会
- ¥1100
- 2018年07月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.3(17)
▼当社最大のベスト&ロングセラーを約15年ぶりに改訂!
▼高い評価を得ている明快さ・簡潔さはそのままに、解説と情報をリバイズ。
▼大学での初年次教育、新社会人教育にオススメ!
累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト・ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改訂。
好評を博した明快な語り口調やコンパクトにまとまった構成はそのままに、「テキスト批評」の解説の充実、「(レポート等の)指定文字数と内容との関係」への補足説明や、注の形式に関する説明の更新、参考文献とその解説の刷新など、より理解しやすく使いやすくなるための改良を加えた決定版。
1章 大学での勉強とレポート・論文の書き方
-はじめてレポートを書く人のためにー
2章 テキスト批評という練習法
3章 論文の要件と構成
4章 テーマ・問題の設定、本文の組み立て方
5章 注、引用、文献表のつけ方
付録1 「見本レポート」
付録2 接続語・接続表現による文の論理的結合
付録3 インターネットの利用法
参考文献
あとがき

- 性教育はどうして必要なんだろう?
- 浅井 春夫/艮 香織/鶴田 敦子
- 大月書店
- ¥1760
- 2018年08月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
ネットやスマホなど、さまざまな性情報に接してすでに“起きている”子どもたち。子どもを加害者にも被害者にもさせたくないという保護者のニーズ。だけど制約が大きすぎる現場…。それでも性教育にチャレンジしてみよう!!という現場のための必携入門。具体的なヒントも満載!

- 場面緘黙の子どもの治療マニュアル --統合的行動アプローチーー
- R・リンジー・バーグマン/園山 繁樹
- 二瓶社
- ¥1980
- 2018年07月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は場面緘黙のある特に幼児期児童期の子どもを対象にした心理治療マニュアルです。方法論としては刺激フェイディング法と段階的エクスポージャー法を中核的な技法とし、クリニックをベースに家庭や学校や地域場面で子どもと親と担任が協力して宿題を実施し、その達成度に基づいて次のステップを作成するというものです。この治療マニュアルの最大の特徴は、20 回のセッションを標準としている点です。監訳者の教育相談の経験では、学校場面で会話が可能になり、大きな困難が解消するためには、月1、2 回の来談で1 年以上を要することが一般的ですが、本書を読むと、刺激フェイディング法と段階的エクスポージャー法に基づき、スモールステップがきめ細かく設定されていることがよくわかります。また、子ども自身の達成感を確認しつつ、前に進む方法論であることがよくわかります。--「監訳者あとがき」より
第1 章 セラピストのための基礎知識
第2 章 治療開始前のアセスメントと心理教育(親セッション)
第3 章 セッション1:治療への導入とラポート形成
第4 章 セッション2:ラポート形成、ご褒美システム、感情チャート
第5 章 セッション3:クラスチャート、会話はしご、エクスポージャー練習
第6 章 セッション4 - 9:初期のエクスポージャーセッション
第7 章 セッション10:治療の中間セッション
第8 章 セッション11 - 14:エクスポージャーセッションの中間点
第9 章 セッション15:エクスポージャーの継続と主体性移行の開始
第10 章 セッション16 - 17:主体性の移行に留意したエクスポージャーの継続
第11 章 セッション18 - 19:エクスポージャーの継続と主体性の移行/これまでの進歩の振り返り
第12 章 セッション20:再発防止と終了
第13 章 治療に当たって考慮すべきこと
付録A エクスポージャー課題の具体例
付録B 治療の前に使用するもの
付録C 治療で使用する用紙

- 人間の傾向性とモンテッソーリ教育新版
- マリオ・M.モンテッソーリ/AMI友の会NIPPON
- 風鳴舎
- ¥2200
- 2018年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 腹膜透析・腎移植ハンドブック
- 石橋由孝/衣笠哲史
- 中外医学社
- ¥5940
- 2018年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
血液透析に加え、腹膜透析・腎移植を適切にオプション提示していくことが真のTotal Renal Careに通じる。その理想を体現するハンドブックがついに登場した。

- 2代目社長のための、成長率150%を可能にする会社経営
- 小田原 洋一
- ダイヤモンド社
- ¥1650
- 2018年11月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
はじめに
序 章 二代目経営者はどのように“家業”から“企業”へ脱皮したのか
父が創業した小さな印刷会社に戻った時の従業員は一名/借金がなくなったら家業をたたむ予定。ビジネスの未来は見えなかった/代表となり迎えた第二創業期。印刷通販で成功を収める/会社設立9年で1.5億円から、30億円企業に急成長した戦略とは
第1章 二代目の鉄則1今まで進出しなかった分野にまず手を出してみる
第二創業期。売上の足しになればとインターネットビジネスに進出/創業者がやってこなかった新規ビジネスに手を出してみる/これだ、と思ったらその分野をやりぬく覚悟を持つ/プリントネットは社員全員で「印刷通販」に方針転換/納期・品質には徹底的にこだわり信頼を維持する
第2章 二代目の鉄則2劇的な転換よりも、地道な社員教育
第二創業期を乗り越え、事業が拡大傾向にある中で必ず陥る「社員との歪」/人材の成長に沿った成長戦略を描かないと利益が付いてこない/プリントネットも売上が倍増した時期、一時的に利益が出にくい企業体質に陥った/二代目社長が考える「理想的な人材」を明確にして企業の方向性を定める/社長自らが自社に対する思いや方向性を熱く語り続ける
第3章 二代目の鉄則3他社にもない、創業者にもない独自性を生みだす
社員が一つになったら、次は会社としての独自性を打ち出す/「他社には絶対に負けないポイント」を生み、会社と経営者の特色を出す/プリントネットは「時間軸への徹底的なこだわり」を社内外に掲げた/簡単なことではないが、追求し続けることで必ず答えは出るはず
終 章 社長業に、近道はない
社長として「引き継ぐもの」「改革するもの」の見極め方/他社の真似をしない経営スタイルを貫く
おわりに

- 新書702 世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心
- ヤング吉原麻里子・木島里江
- 朝日新聞出版
- ¥891
- 2019年01月11日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.34(20)
今シリコンバレーで注目される、新しい人材の理想STEAM(スティーム)とは何か?アップル、エアビーアンドビー、ウーバーなど、革新的なイノベーションを生み出し続ける環境には共通項がある。それは、人間性を大事にするという「新しいヒューマニズム」の思想、科学技術とアートを融合する「イノベーターのマインドセット」、そして、論理よりも直感を重視する「デザイン思考」だ。シリコンバレーで、教育・人材育成の最前線に立って活動する著者たちが、21世紀型人材STEAMが生まれる条件に迫る。
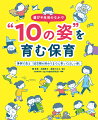
- 遊びや生活の中で10の姿を育む保育
- 幼少年教育研究所/關 章信 兵頭惠子 高橋かほる
- チャイルド本社
- ¥2200
- 2019年03月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
遊びや生活など、保育の中には「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」の要素がいっぱいです。
例えば「おにごっこ」なら……。
元気に走り回る姿は「健康な心と体」、
タッチでおに交代などルールを守って遊ぶ様子には「道徳性・規範意識の芽生え」、
逃げたり捕まえたりする方法を考えることには「思考力の芽生え」など、
色々な「10の姿」が見られます。
本書では、知っておきたい「10の姿」の基本をていねいに解説するとともに、
遊びや生活の中から「10の姿」を見いだすポイントや、保育者ができる配慮などを紹介。
たっぷりの事例で、わかりやすくお伝えします。
「10の姿」を育む保育がバッチリわかる一冊です!

- テレビ的教養
- 佐藤 卓己
- 岩波書店
- ¥1694
- 2019年01月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
テレビは本当に「一億総白痴化」をもたらしたのか? それとも、「一億総博知化」をもたらし得るものなのかーー。戦前・戦後にまたがる「放送教育運動」の軌跡を通して、従来の娯楽文化論/報道論ではなく、〈教養のメディア〉としてのテレビ史を論じ、その可能性を浮かび上がらせた画期的著作。(解説=藤竹 暁)

- 極めに・究める・内部障害
- 相澤 純也/田屋 雅信
- 丸善出版
- ¥3850
- 2019年01月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
超高齢社会のリハは重複疾患のオンパレード。心不全、呼吸不全、フレイルなどこれらに対処するのが「内部障害」リハ。苦手とするリハ専門職も多いという。本書は、国試クリアの先を見据えた、まったく新しい形の臨床指南書。あなたも心リハのエキスパートの声に耳を傾けてみてください。「難しくなんかない、大事なことは、本気になれるかどうかだ!」

- 苫米地英人コレクション8 人を動かす「超」書き方トレーニング
- 苫米地英人
- 開拓社
- ¥1430
- 2019年02月25日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(1)
◆異能の脳機能学者にしてオピニオンリーダー苫米地英人の名著復刊シリーズ!
◆復刊にあたって書き下ろしの「特別付録」を収録。苫米地英人ファン必携の永久保存版。
◆第4回刊行の本書は、ビジネスマンに必須のスキル、「書く」を根本から鍛え直す。
◆本当の意味で「文章上手」は、日本にほとんどいない。この本でライバルに差をつけろ!

- アインシュタイン150の言葉 新装版 (偉人の名言集)
- ディスカヴァー・トゥエンティワン
- ¥1430
- 2019年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
人生について、世界について、人間アインシュタインが勇気をくれる。

- すごい工場
- 出口弘親
- あさ出版
- ¥1650
- 2019年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(4)
見学者、学生が感動する愛知のすごい工場の秘密大公開!

- 人材育成ハンドブック 新版
- 眞崎 大輔/ラーニングエージェンシー
- ダイヤモンド社
- ¥4180
- 2019年04月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
第1章 理論編
アンドラゴジー(成人教育)、レディネス(学習準備性)、経験学習モデル、学習転移、行動変容、インストラクショナルデザイン、効果測定、コンピテンシー、トランジション(キャリアの転換期)、組織社会化、熟達化、大脳生理学、メタ認知、心理学、モチベーション、ビッグファイブ(性格スキル)、リーダーシップ論の変遷、能力モデル、世代概論、学習する組織
第2章 制度・手法編
人材要件・教育計画、サクセッションプラン、ジョブローテーション、OJT、メンター制度、マニュアル、ストレッチアサインメント、フィードバックとコーチング、ダイアローグ、研修の企画、研修の実施、研修のフォローアップ、アクティブラーニング、デジタルラーニング、資格取得支援、自己啓発支援、ワークプレイス、人事評価制度、人材育成に関する法律(助成金)、CLO
第3章 経営テーマ編
働き方改革、メンタルヘルス、健康経営、ダイバーシティ、女性活躍、高年齢者活用、外国人活用、グローバル人材、イノベーション人材、IT人材、デザイン経営、MOT、知的財産、CSR、コンプライアンス
第4章 研修編
研修のトレンド、内定者研修、新入社員研修、管理職候補者研修、管理職研修、幹部研修、ビジネスマナー、PCスキル、新入社員向け仕事の進め方、挨拶、電話応対、報連相、傾聴力、ビジネスライティング、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ビジネストーキング、プレゼンテーション、ファシリテーション、交渉、タイムマネジメント、リーダーシップ、チームビルティング、仕事の任せ方、人事評価者研修、面接官研修、セクハラ・パワハラ、セルフマネジメント、アンガーマネジメント、キャリアデザイン、PDCA、プロジェクトマネジメント、業務標準化、マーケティング、Webマーケティング、企画立案、営業、ホスピタリティ、クレーム対応、5S、技術者教育、経済・経営知識、財務知識、データの読み方、労務・法務・税務