PHP の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1581 から 1600 件目(100 頁中 80 頁目) 

- 相棒
- 五十嵐貴久
- PHP研究所
- ¥817
- 2010年10月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.85(65)
時は幕末、京の都ーー。大政奉還を目前に控え、徳川慶喜暗殺未遂事件が起こった。▼幕閣から犯人探索の密命を受けたのは、坂本龍馬と新選組副長の土方歳三。しかし二人に与えられた時間は、わずか二日間だった。▼いがみ合い、衝突しながら捜査を続ける二人が最後に行きついた人物とは?▼そして龍馬暗殺の真相を知った土方は?▼幕末維新のオールキャストでおくる、傑作エンタテインメント長篇小説。

- 「Why型思考」が仕事を変える
- 細谷功
- PHP研究所
- ¥1056
- 2010年08月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.74(66)
「地頭力」ブームを巻き起こした著者、待望の最新作が登場!▼「前例主義」「マニュアル人間」「ダラダラした会議」……仕事にはびこる思考停止のワナ。それらはすべて表面的な「What」にばかりとらわれ、「それはなぜか?」を突き詰めて考える「Why型思考」が欠けていることが原因だった。▼本書は、このWhy型思考の身に付け方およびビジネスでの活用法を説くもの。思考停止状態である「What型思考」と対比させつつ、頭を使って仕事をする「Why型思考」とはどういったものか、そして、それによってどんな成果が得られるのかを説いていく。そして、「鋭いアウトプットを出せる人=Why型思考」になるための具体的なヒントや鍛え方についても解説。▼いつも「もっと頭を使え!」と言われているビジネスパーソン必読の「思考力の鍛え方」。

- 自由の奪還
- アンデシュ・ハンセン/ロルフ・ドべリ/ジャック・アタリ/ネイサン・シュナイダー/ダニエル・コーエン/ダグラス・マレー
- PHP研究所
- ¥1012
- 2021年08月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.6(5)
●コロナ禍で揺らぐ民主主義、デジタル化で広がる経済格差……
●「社会の分断」に対処し、信頼ある社会を築くことができるか?
●世界の知性9人が説く「自由と民主を取り戻す」ための提言!
新型コロナウイルスは、民主主義国家における政治指導者たちのリーダーシップの欠如を容赦なく露呈させ、同時に、デジタル経済の発展と絡むかたちで、世界の格差拡大を著しく助長した。
さらには「個」の孤立が新たな不安を引き起こし、巷には陰謀論の数々があふれた。インターネットやSNSでいくらつながっていても、それだけでは「信頼感のある社会」を築くのは難しい。
これから人類は、国際的連携や信頼ある社会を、どのように取り戻していくべきだろうか?
本書は、国際ジャーナリスト・大野和基氏が9人の「世界の知性」に、「自由と民主の危機」の解決のヒントを訊ねた論考集である。多様な背景を持つ彼ら彼女らの最先端の知見には、我々が未来への希望や目的を失わないようにするための答えがあるはずだ。

- 一緒にいてラクな人、疲れる人
- 古宮 昇
- PHP研究所
- ¥836
- 2018年08月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(5)
一緒にいて「ラクな人」と「疲れる人」の違い、前者になるための最も効果的な方法とは? 現役セラピストにしか語れない人間関係の極意。

- ポケット版 宇宙の迷路
- 香川元太郎/縣秀彦
- PHP研究所
- ¥858
- 2017年03月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「宇宙基地」や「月の世界」にある迷路を通りぬけ、かくし絵をみつけよう! シリーズ累計260万部突破の迷路絵本のポケット版。

- 内定勝者 私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー2022 面接編
- キャリアデザインプロジェクト
- PHP研究所
- ¥1705
- 2020年11月19日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 1.0(1)
★★★15年以上売れ続けている、就活のバイブル!★★★
★★★大リニューアルで「新しい就活」完全対応!★★★
早期化・長期化する昨今の採用選考を勝ち抜くために、
「コミュニケーション能力の向上」は必須と言っても過言ではない。
だから、論理的な話し方や話す内容の整理が苦手な人こそ、
本書を使って「どんな面接も突破できる型と極意」を身につけよう。
「面接で差がつく4つの最重要ポイント」
「よく面接で聞かれる6つの分野を強化するコツ」
「人気企業の面接の共通点を完全再現した実例集」など、
面接スキルを高めるツールや、頻出質問別の面接実例を多数掲載。
さらに本年度版は、昨今の就活事情の変化を踏まえ、
通年採用、早期選考、インターンシップなどの、
「新しい就活」に完全対応し、18年ぶりに内容を大リニューアル。
本書を読めば、競争率100倍でも負けない「面接必勝の型」が身につく!

- 戦国の女たち
- 司馬遼太郎
- PHP研究所
- ¥628
- 2006年03月03日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.74(23)
戦国乱世の時代、闘っていたのは男だけではない。女性もまた、女性の戦(いくさ)を闘わねばならなかったーー本書は、戦国の女性を主人公にした司馬作品六篇を収録したオリジナル編集の短篇小説集である。▼豊臣秀吉の正室として位人臣を極め、夫の死後は二人で築いた豊臣家の行く末を決定づけた北ノ政所。兄・秀吉の思惑によって結婚のみならず離婚さえも強いられ、一生を翻弄され続けたが、その生涯を沈黙で染め抜いた秀吉の妹・旭姫。夫・細川忠興の異常な嫉妬によってがんじがらめの束縛を受けながら、毅然として己を貫き、関ケ原の折に最期を迎えたたま(ガラシャ)。▼このほか、変わり者の侍大将・渡辺勘兵衛に思いを寄せる藤堂家小姓頭の妻・由紀の慕情や、一夜の出会いを大切に抱き続けて生きようとする小若の純情、さらには夫を猛烈に働かせて財を築いた遊び好きの妻・小梅と、戦乱のなかに咲いた女性たちの人生を浮かび上がらせた珠玉の短篇集である。
●女は遊べ物語 ●北ノ政所 ●侍大将の胸毛 ●胡桃に酒 ●一夜官女 ●駿河御前

- 高齢者を知ろう!
- 平松 類
- PHP研究所
- ¥3520
- 2022年05月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
無口になる、昔の自慢話ばかりする、赤信号でわたる、声をかけても無視する、ひがみっぽい、不用品を捨てない……。高齢者の誤解されやすいこうした行動は、老化にともなう脳と体の変化が大きな原因です。それを理解すれば、豊かな知識と知恵をもつ人生の大先輩である高齢者と交流し、多くのことを学べます。本書では、高齢者の「なぜ?」をわかりやすく説明し、うまく会話をする方法を紹介します。
第1章 高齢者ってどんな人?
なぜ、高齢者とふれあう機会が少ないのか?/高齢者はどんな社会、どんな人生を生きてきた? 他
第2章 高齢者のなぜとなに
高齢者の行動は誤解されやすいってどういうこと?/老化? 認知症? それってなんですか?/ウルサイ!とどなるのに、自分の声が大きいのはなぜ?/物の名前は忘れるのに、昔の自慢話を忘れないのはなぜ? 他
第3章 高齢者の話をうまく聞くために
静かなところで、正面から低い声でゆっくりと話す/高齢者が聞きとりやすいことばと短い文で話す 他

- うちの神様知りませんか?
- 市宮 早記
- PHP研究所
- ¥770
- 2020年07月09日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
小説投稿サイト「エブリスタ」で現代ファンタジー部門総合1位を獲得した話題作が、待望の書籍化!
幼い頃の記憶を失っていることから、家族や友人たちと馴染めないでいた紗栄は、大学進学を機に、母方の実家の今は誰も住んでいない神社で一人暮らしを始めることに。そこで出会ったのは美しいが不愛想な妖狐の青年と、なぜか自分のことを知っている狛犬の少年だった。狛犬が言うには、この神社から神様が行方不明になっているらしく、そのせいでよからぬあやかしたちが神社の近くをうろついて困っているという。そのため、紗栄も神様捜しを手伝うことになるのだが……。
妖狐と狛犬と女子大生の三人が織りなす、感動の青春あやかし物語。
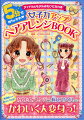
- アイドル&モデルみたいになれる 5分でめちゃかわ女子力アップヘアアレンジBOOK
- ZUSSO KIDS
- PHP研究所
- ¥1078
- 2020年03月21日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
女子力アップシリーズ第7弾! 毎日の学校生活や行事がキラキラ楽しくなるようなヘアアレンジをたっぷり紹介☆「寝坊しちゃったけど、ボサボサ頭で登校したくない!」「すぐにできる簡単アレンジがしりたい!」……一目でわかる「5分」マークでスピードヘアアレンジにもチャレンジ!
【内容】
<レッスン1 基本のヘアアレンジをしよう!>みつあみ/ポンパドール/サイド表あみこみ ほか
<レッスン2 シーン別ヘアアレンジレッスン>友だちとおそろいアレンジ…裏あみこみツインテール/運動会/遠足/浴衣で花火 ほか
<レッスン3 もっとヘアアレンジを楽しもう!>カチューシャであみこみ風くるりんぱ ほか
<レッスン4 ヘアケアでツヤツヤ髪に!>正しいシャンプーのしかた/寝ぐせの直し方 ほか
<レッスン5 ヘアも心もかわいくなろう!>これで迷わない毎日のヘア&コーデ例/私たちにできること…ヘアドネーションって何? ほか

- 教養としての「中国史」の読み方
- 岡本 隆司
- PHP研究所
- ¥1980
- 2020年09月19日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.08(12)
保阪正康氏、推薦!
「中国を知る最良の方法とは何か? それは中国特有の歴史構造を読み解くことだ。本書はまさにその最適な書である」
最も近接し、否応なくつきあわねばならない大国ーー中国。
中国を知ることは、日本人が現代の世界に生きていくうえで必須喫緊の課題であり、いま求められている教養です。
なぜ中国は「一つの中国」に固執するのか。
なぜ中国はあれほど強烈な「中華思想」をもつのか。
なぜ中国は「共産党一党独裁」になったのか。
なぜ中国はあれほど格差が大きいのか。
なぜ中国は「産業革命」が起きなかったのか。
「対の構造」をはじめとする中国の個性がわかれば、こうした疑問を解き明かす道筋が見えてくる!
東洋史研究の第一人者が明快に語る隣国の本当の姿。

- 50歳から花開く人、50歳で止まる人
- 有川 真由美
- PHP研究所
- ¥1485
- 2022年05月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.85(21)
50代からは「遊ぶように生きる」と、うまくいく。気負わず、無理せず、伸び伸びと、自分のために生きて、働く人生に変える知恵。

- 弟子・藤井聡太の学び方
- 杉本 昌隆
- PHP研究所
- ¥836
- 2019年03月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.6(5)
「思考力」「集中力」「忍耐力」「想像力」「闘争心」「自立心」「平常心」……これらはすべて将棋に強くなるためのみならず、人生を豊かに生きていくうえで必要な学びともいえるでしょう。
将棋盤を抱きかかえて号泣していた子どもが、史上最年少で中学生のプロ棋士に。プロデビュー後の29連勝、一年間で三つの昇段、朝日杯将棋オープン戦で史上二人目の連覇など、数々の記録を塗り替えた藤井聡太の師匠は、いかに弟子を導いたのか
「学び」の一例として◎二次元の将棋盤に対して三次元で考え抜く◎師匠の言葉を鵜呑みにするな◎ライバルは歓迎せよ◎子ども自身に発見させる、など
本書では、天才といわれる藤井聡太の学びの環境、兄弟弟子との交流、また師弟関係の源流である、著者・杉本昌隆の師匠・板谷進との師弟関係に言及することで、「真に学ぶこと」とは何かを考える手がかりとなります。第30回将棋ペンクラブ大賞(文芸部門)作品、待望の文庫化!

- 婚活食堂5
- 山口 恵以子
- PHP研究所
- ¥748
- 2021年05月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.03(40)
AI婚活×元占い師の女将!?
おでん屋の恵が常連客の幸せを応援!
心とお腹がホッとする大人気シリーズ
トマトの冷やしおでん、エビ雲吞、ピーマンの焼売、ナスと卵のよだれ鶏風ーー暑い夏でもさっぱり美味しい料理とお酒で、「めぐみ食堂」は大賑わい。
常連客のIT実業家・藤原海斗がAI婚活事業に乗り出したと聞き、興味を持った女将の恵は、食の好みも趣味も正反対の男女に利用を勧めるが……。
元占い師の女将の絶品料理とふしぎな力で、訪れる人がそれぞれの幸せを見つけていく人気シリーズ第5弾!
文庫書き下ろし。

- 世界の国ぐに大冒険
- 井田仁康
- PHP研究所
- ¥2750
- 2017年09月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
オリンピック基準で世界の国・地域を紹介! 写真とイラストも満載! 各国の地理、歴史、文化、雑学など幅広い知識が楽しく学べる。

- 風の陣【風雲篇】
- 高橋克彦
- PHP研究所
- ¥754
- 2010年10月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.28(28)
黄金の眠る陸奥が政争の道具として朝廷に搾取されることを避けるため、近衛府員外中将として都に仕える蝦夷・道嶋嶋足と、その嶋足を陰に陽に支える策士・物部天鈴は、朝廷を取り巻く権力抗争に巧みに入り込み、知略を尽くして蝦夷のために戦ってきた。しかし、自らが担ぎ上げた怪僧・弓削道鏡が称徳女帝を誑かし、予想外にも法王として朝廷の頂点を極めることに。▼だが、神護景雲四年(七七〇)四月に女帝が篤い病に臥したことで、道鏡の悪運にも翳りが生じ始めた。これを好機と捉えた天鈴は、左大臣・藤原永手、右大臣・吉備真備らを巻き込み、道鏡に反旗を翻そうと画策するのだが…。▼一方、陸奥では、専横を極める陸奥守と蝦夷の関係が悪化し、一触即発の状態になっていた。蝦夷を人とも思わない朝廷の扱いに憤る若き伊治鮮麻呂ら蝦夷たち。道鏡の栄華が夢と消え、新たな勢力が台頭する時代の大きなうねりの中で活躍する蝦夷の勇姿を描く歴史ロマン第四弾。

- 眼科医が教えるあきらめていた目もとのクマ・たるみは自分で治せる!
- 平松類
- PHP研究所
- ¥1430
- 2021年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 逃げない。
- 唐池 恒二
- PHP研究所
- ¥1760
- 2020年11月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.67(5)
ーリーダー学を学ぶ一番手っ取り早い方法は、リーダーの体験を数多くすることですー
その言葉どおり、高校・大学の部活動のキャプテンに始まり、日本中の鉄道会社に影響を与えた観光列車の開発、外食事業の躍進、悲願の新幹線開通、世界一の豪華列車の実現とさまざまなシーンでリーダーを務めてきた、“リーダーのベテラン”たる著者が満を持して書き下ろした70篇。
「孫子」などの歴史的な名書から得た視点にはじまり、著者が愛してやまない勝海舟論に松下幸之助論、古今東西の経済・経営界の偉人たちの教え、さらには豪華列車ブームの火付け役となった「ななつ星in九州」誕生秘話において発揮、さらに育まれることとなった自身のリーダー哲学がライブ感豊かにしるされています。
JR九州と同社グループ42社で働くリーダー的立場にある社員たちの顔を浮かべながら執筆に取り組んだというこの一冊は、今あなたの目の前にある迷いや悩みに対して明快かつ朗らかに解答をくれるものとなるかもしれません。

- 世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業
- 佐藤 優
- PHP研究所
- ¥858
- 2020年08月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.25(9)
哲学と宗教は、人間が生きていく上で不可欠な基本原理である。しかし、日本人エリートには、それらの知識と教養が欠如している。この点を改善することが、日本の社会と国家を強化するために有益なのではないだろうかーー。
本書は、このような問題意識を抱く著者が、筑波大学で「超優秀」な学生たちを対象に行った「哲学的訓練」と題する連続講義を、紙上で再現したものである。
具体的には、◎三四郎はなぜ名古屋で下車したのか? ◎噓をついても信頼が失われないケース ◎教皇は「会長兼社長」のようなもの ◎ムスリムは遅刻した時に何と言うか など、思わず興味をそそられるトピックが満載。
哲学や宗教の知識をまったく持たない人でも内容を十分に理解できるように、細心の配慮をしてまとめられているため、誰が読んでも、「超優秀」な学生たちが覚えた知的興奮が味わうことができる。世界レベルの教養を身につけたい人必読の1冊。

- 青鬼 調査クラブ5
- noprops/黒田 研二/波摘
- PHP研究所
- ¥825
- 2021年11月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
呪いの美術館に現れた幽霊と青鬼は敵? それとも味方?
【あらすじ】
優助。今回は『青の悪夢』を倒すわよ。
作者を含む関係者が次々と失踪したことで「呪いの絵画」として有名になった『青の悪夢』。この絵画を目玉の展示として、多数のオカルトな噂を持つ美術品が集められた企画展「オカルト美術展」にやってきたレイカと優助。ふたりが『青の悪夢』の前にたどり着くと、次々と不可解な出来事が起きて……。『青の悪夢』の謎を解き、呪われた美術館から脱出せよ!
『青鬼』ジュニアノベル、スピンオフシリーズ第5弾!
【目次】
青鬼調査レポート/碧奧美術館の見取り図/1 夏休みが明けて/2 オカルト美術展/3 青の悪夢/4 黒いドレスの女/5 現実じゃない場所/6 幽霊たちの世界/7 あふれた涙/8 ありえない助け/9 美術館の地下/10 怪物とともに/11 痛みの絵画/12 呪いの絵画/13 おしまいにしよう/14 一緒にいる/15 白い花束/青鬼調査レポート/碧奧美術館の見取り図 その2