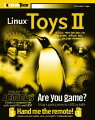Linux の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1641 から 1660 件目(100 頁中 83 頁目) 

- Software Design (ソフトウェア デザイン) 2020年 12月号 [雑誌]
- 2020年11月18日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
[内容紹介]
【第1特集】設計・データ永続化・セキュリティなどコンテナの定石を身につけよう
Dockerアプリケーション開発実践ガイド
今やコンテナベースのアプリケーション開発は定着しつつあり、大規模な環境での本番運用事例も少なくありません。その一方でコンテナの基本的な使い方は知っているものの、実際どのように活用すればいいのか、どうやってアプリケーションを実装すればいいのかがわからないという声も未だに耳にします。そこで本特集では、アプリケーション設計・複数コンテナの管理・コンテナデータの永続化・セキュリティという4つのポイントで、Dockerを使ったコンテナアプリケーション開発の定石を紹介します。初心者からステップアップするための第一歩としてぜひご活用ください。
【第2特集】AZ、VPCなどの概念と主要なサービスを再整理
設計に役立つAWSシステム構成図の読み方
AWS(Amazon Web Services)に関係する講演や技術記事では必ずと言っていいほど出てくる、AWSシステム構成図。システム全体を俯瞰するのに便利なツールですが、冗長化やネットワークの負荷分散などを考慮した本格的なシステムとなると、複雑で読み解くのに苦労することもあるかもしれません。
そこで、本特集ではアベイラビリティーゾーン(AZ)やVPCといった、AWSの構成要素のひとつひとつから、使用頻度の高い主要サービスまでをおさらいします。システム構成図の読み方を理解し、クラウドインフラの設計力を底上げしましょう。また、定石となる構築パターンについても要素を分解して詳しく解説します。
[目次]
■特集
【第1特集】Dockerアプリケーション開発実践ガイド
第1章 コンテナアプリケーションの設計セオリーを学ぶ/東口 和暉
第2章 複数のコンテナ環境を一括管理するDocker Compose/前佛 雅人
第3章 データボリュームでコンテナのデータを永続化しよう/仁科 俊晴
第4章 コンテナのセキュリティを強化する/須田 瑛大
【第2特集】設計に役立つAWSシステム構成図の読み方
第1章 AWSの構成単位を理解する/深澤 俊
第2章 システムの中核となるサービスを知る/恩塚 伸一郎
第3章 AWSシステム構成の基本パターン/門別 優多
■一般記事
MySQL Database Serviceの全貌/梶山 隆輔
[短期連載]Linuxカーネルの最強トレースツール「eBPF」を体感/近藤 宇智朗
■特別付録
ちょうぜつエンジニア めもりーちゃんステッカー
■連載
ITエンジニア必須の最新用語解説/杉山 貴章
Unveil it! 開ければわかる!/清水 洋治
結城浩の再発見の発想法/結城 浩
高校数学Tip of the Month/刀根 諒
VR勉強会のススメ/中島 凜
宮原徹のオープンソース放浪記/宮原 徹
めそ子が聞く!!/クラスメソッド 大前(作)、エクスデザイン ninnzinn(画)
チーム開発の視点が変わる アジャイル開発の新常識/実川 康則、椎名 愛里、梶原 直人(監修)
ディープラーニングではじめるソフトウェア高速化入門/二木 紀行
ひみつのLinux通信/くつなりょうすけ
ルータ実践活用「NextHop」/寺西 祐樹
DevOpsエンジニアのための節約・簡単・時短レシピ/星川 真麻
パズルで鍛えるアルゴリズム力/けんちょん(大槻 兼資)
Ansible問題解決マップ/杉村 貴士
作品で魅せるGoプログラミング/五嶋 壮晃
Visual Studio Code快適生活/職業「戸倉彩」
Vimの細道/mattn
月刊Fedoraジャーナル/平 初
Debian Hot Topics/やまねひでき
Monthly News from jus/大西 尚利
Hack For Japan+Code for Japan〜あなたのスキルは社会に役立つ/おくみか(奥村 美佳)第1特集 コンテナベースでこんなに変わる Docker アプリケーション開発実践ガイド 第2特集 主要サービスを整理して効率アップ! 設計に役立つAWSシステム構成図の読み方


- Software Design (ソフトウェア デザイン) 2020年 10月号 [雑誌]
- 2020年09月18日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
[内容紹介]
【第1特集】コードで実践、ビジュアルで納得
Pythonではじめる統計学
知識ゼロからわかるデータ分析の数学
統計学はデータ分析には欠かせない知識であり、それ以外にも資料作成やA/Bテストなど数多く活用の機会があります。
本特集はPythonコード(Jupyter Notebook形式)で統計学をインタラクティブに学べる入門記事です。
手持ちのデータを正確に表し、整理するための「記述統計」、サンプルデータを用いて分析する「推測統計」、データをもとに判断を行うための「仮説検定」など統計学のエッセンスを、コイン投げやガチャ、A/Bテストといった具体例で学びます。数式に抵抗があるという方でも、Pythonで記述した処理と、出力されたグラフを照らし合わせることで、納得して読み進められるでしょう。
【第2特集】チーム開発からCI/CDまで、ワークフローを自動化しよう
3ステップでマスターするGitHub Actions
CI/CDツールの大本命「GitHub Actions」が2019年11月に正式リリースになりました。
本ツールはCI/CDにとどまらず、GitHubに関わるさまざまな操作も、YAMLで設定ファイルを書くだけで簡単に自動化できます。
GitHub Actionsにはあらかじめ、そのまま使える自動化のためのテンプレートが用意されていますが、もちろん自分で作ることもできます。
本特集では、自分だけの自動化を実現できるようになることを目標に、ステップバイステップで自作部分を増やしていきながら、GitHub Actionsについて学びます。
[目次]
■特集
【第1特集】Pythonではじめる統計学
第1章 統計分析に必須のライブラリ/driller
第2章 平均からはじめる記述統計/松井 健一
第3章 シミュレーションで学ぶ確率分布/松井 健一
第4章 未知のデータを知るための推測統計/松井 健一
第5章 身近なテーマで理解する仮説検定/馬場 真哉
【第2特集】3ステップでマスターするGitHub Actions/宮田 淳平
ステップ0 GitHub Actionsをはじめよう
ステップ1 ワークフローのテンプレートを使ってみよう
ステップ2 ワークフローを自分で設定しよう
ステップ3 アクションを自作してみよう
■一般記事
[短期連載]Linuxカーネルの最強トレースツール「eBPF」を体感/森田 浩平
[短期連載]誰も信用しないゼロトラスト時代のセキュリティ/三好 俊介、古澤 慧
[短期連載]スタートアップのためのAWSテクノロジー講座/針原 佳貴
■連載
ITエンジニア必須の最新用語解説/杉山 貴章
Unveil it! 開ければわかる!/清水 洋治
結城浩の再発見の発想法/結城 浩
[試して理解]Linuxのしくみ/武内 覚
ちょうぜつエンジニアめもりーちゃん/田中ひさてる
宮原徹のオープンソース放浪記/宮原 徹
めそ子が聞く!!/クラスメソッド 豊崎(作)、エクスデザイン ninnzinn(画)
ルータ実践活用「NextHop」/小澤 昌樹
ひみつのLinux通信/くつなりょうすけ
DevOpsエンジニアのための節約・簡単・時短レシピ/星川 真麻
パズルで鍛えるアルゴリズム力/けんちょん(大槻 兼資)
MySQLアーキテクチャの探究/梶山 隆輔
Prometheusではじめるシステム監視入門/仲亀 拓馬
Ansible問題解決マップ/八木澤 健人
作品で魅せるGoプログラミング/森本 望
Visual Studio Code快適生活/職業「戸倉彩」
Vimの細道/mattn
月刊Fedoraジャーナル/平 初
Debian Hot Topics/やまねひでき
Monthly News from jus/横田 結菜
Hack For Japan+Code for Japan〜あなたのスキルは社会に役立つ/石井 哲治第1特集 Pythonではじめる統計学入門 第2特集 3ステップでマスター GitHub Actions

- Software Design (ソフトウェア デザイン) 2020年 07月号 [雑誌]
- 2020年06月18日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
【内容紹介】
[第1特集]一から学ぶログ分析
事業を成長させる分析基盤を作るには
顧客の行動や好みを的確にとらえ、サービス改善につなげたい̶そのひとつの手段として、Webサイトやゲームで日々蓄積されるユーザーの操作記録(ログ)が注目されています。リリース後の分析のために、サービスの開発段階からログや分析基盤について考慮されることもあるでしょう。
その一方で現場では、「せっかく分析基盤を作ったのに、使いにくい、利用されない」という悩みも尽きないようです。きちんと使われ成果を生み出す分析基盤を作るには、必要なデータを漏れなく蓄積することと、適切なデータと組み合わせて意味ある形に整えること、分析する人にとって使いやすいインターフェースを用意することが大切です。本特集でそのノウハウを解説します。
[第2特集]macOSの新・標準シェル
zsh<超>入門
bashとの違い、移行のコツ
ファイル操作、テキスト処理、そのほか小回りの利くスクリプトの開発など、エンジニアにとってシェルは必須のツールです。「シェルと言えばbash」という向きもありますが、今回紹介するのは高機能かつカスタマイズ性にも富んだ「zsh」です。macOS Catalinaからはデフォルトシェルとなったzshについて、環境ごとの導入方法からプラグインを使った設定方法まで、とくにbashとの比較に重きを置きながら、入門までの手引きを行います。bashしか知らない/使ったことがないという方は、ぜひこの機会に試してください。
【目次】
■特集
[第1特集]一から学ぶログ分析
第1章 Webアクセスログ、Webビーコンログの基礎と読み方/柳井 隆道
第2章 ログ分析基盤の構築で考えるべきこと/ゆずたそ
第3章 サービス成長に貢献する分析基盤の要件と構築実例/小川 詩織
第4章 使えるログの設計/小川 詩織
[第2特集]zsh<超>入門/高本 洋
第1章 zshをはじめよう
第2章 bashとzshの16の違い
第3章 zshをカスタマイズしてみよう
■一般記事
[短期連載]はじめよう、高速E2Eテスト/末村 拓也
[短期連載]スタートアップのためのAWSテクノロジー講座/Hara, Tori
[特別企画]Jamesのセキュリティレッスン/吉田 英二
■連載
ITエンジニア必須の最新用語解説/杉山 貴章
Unveil it! 開ければわかる!/清水 洋治
結城浩の再発見の発想法/結城 浩
[試して理解]Linuxのしくみ/武内 覚
ちょうぜつえんじにあめもりーちゃん/田中ひさてる
宮原徹のオープンソース放浪記/宮原 徹
めそ子が聞く!!/クラスメソッド 豊崎(作)、エクスデザイン ninnzinn(画)
ひみつのLinux通信/くつなりょうすけ
MySQLアーキテクチャの探究/梶山 隆輔
Prometheusではじめるシステム監視入門/仲亀 拓馬
Ansible問題解決マップ/齊藤 秀喜
iPhone&Androidで動く! スマホARアプリ開発入門/高橋 憲一
作品で魅せるGoプログラミング/生沼 一公
Visual Studio Code快適生活/職業「戸倉彩」
Vimの細道/mattn
Ubuntu Newsletter/あわしろいくや
月刊Fedoraジャーナル/長嶺 精彦
Web開発のためのネットワークはじめの一歩/川上 雄也
Monthly News from jus/りゅうちてつや
Hack For Japan+Code for Japan〜あなたのスキルは社会に役立つ/齋藤 善寛第1特集 一から学ぶログ分析 事業を成長させる分析基盤を作るには 第2特集 macOSの新・標準シェル zsh<超>入門








- WIRED (ワイアード) Vol.25 2016年 11月号 [雑誌]
- 2016年10月11日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
■特集「The Power of Blockchain ブロックチェーンは世界を変える」
10月11日発売の『WIRED』VOL.25は、「ブロックチェーン」特集。
未来学者ドン・タプスコットによるメッセージから、スペインのアナキストであるルイス・アイヴァン・クエンデの肖像、
岩井克人のビットコイン論、斎藤賢爾による5つの遠景、そして漫画家・西島大介による世界初(?)のブロックチェーン漫画まで、
インターネット登場以来の、もしくはそれ以上の衝撃とも囁かれるブロックチェーンの未知なるポテンシャルを読み解く。
さらに米国サイバー犯罪史上最も大がかりな捜査の果てに、ダークウェブとビットコインの存在を世に知らしめた
「Silk Road」事件の全貌を綴ったルポルタージュを20ページにわたって掲載する。そのほか、選挙と世論調査をデータで
リエンジニアしたスタートアップ「Civis Analytics」に学ぶこれからの民意の測り方、新しい本のエコシステムを構想する
内沼晋太郎とバリューブックスの挑戦を掲載。 ◆しんぴょうせいのたかいごうい:西島大介
SF漫画界の旗手である西島大介が挑む、世界初のブロックチェーン漫画。
20XX年、ブロックチェーンが浸透しきった未来を描く。 ◇ドン・タプスコットのメッセージ:ブロックチェーンは革命だ(あなたがそれを望むなら)
30年以上にわたってテクノロジーの最前線から世界を見続けてきた未来学者ドン・タプスコットは、
このムーヴメントは「本物」だと語る。AIよりもはるかに大きなインパクトをもたらすとさえ言わしめた、
その革命的アイデア、コンセプト、そして、それがもたらす未知なる世界像。 ◇ぼくはクリプトアナキスト:21歳の天才ハッカーがブロックチェーンにみる夢
父にもらったコンピューターと、Linux のフリーソフトウェア。
スぺインの片田舎で生まれ育った天才少年は、それらを通じて初めて世界に自分の居場所を見つけ、他者との接点をもつことができた。
テクノロジーの力でヒューマニティを奪還するべく権威と戦う男の肖像。

- Interface (インターフェース) 2016年 11月号 [雑誌]
- 2016年09月24日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
コンピュータ・サイエンス&テクノロジー専門誌☆プレゼント小冊子付き
「64ビット&IoT時代コンピュータ・アーキテクチャ 〜MIPSからのアプローチ〜」
世界の超定番プロセッサ&OS大研究&初体験!
☆特集 ラズパイ実験・64ビット・Linux ARM直伝解説
イントロダクション 高性能ARMコンピュータがこれからのキモ!
プレビュー1 特集で使った最新ARMプラットフォーム「ラズパイ3」
プレビュー2 特集の実験カラー・プレビュー
☆第1部 64ビット時代ARM用Linux大研究
◎そのうち出ると思うんですけど…待ちきれなくてやっちゃいました
第1章 マニアの挑戦! ラズパイ3×64ビットLinux初体験
Appendix1 64ビット用もOK! Linux作成ツールYocto
Appendix2 ラズパイ3フル回転! コンピュータ扇風機の製作
◎なるほどそうやって動くのか! リセット直後から丸はだか!
第2章 完全理解! ラズベリー・パイの32/64ビットLinux起動シーケンス
☆第2部 ARM直伝! 64ビット時代Cortex-Aプロセッサ大研究
◎今までと同じように使えて64ビット実行も追加
第3章 直伝1:これからのCortex-Aの基本! ARMv8-Aアーキテクチャ
Appendix3 IoT時代に向けてスッキリ! 最新ARMv8-Aのセキュリティのしくみ
◎64ビットも対応なのにコスト/性能/効率…バランス・バッチリ!
第4章 直伝2:ラズパイ3にも採用! 新定番Cortex-A53プロセッサ
◎内部回路を想像しながら性能を比べてみるととても面白いです
第5章 直伝3:新定番Cortex-A53の実力初体験
Appendix4 ARMテクノロジ速報…なんて大胆! 最大2048ビットの演算命令SVE
☆第3部 オレでもできるぜ! ラズパイ並列スパコンに挑戦
◎32台128コア! ホントに作った人がいた!
第6章 実験! ラズパイ並列スパコンのポテンシャルを探る
◎ネットワークにつなげていく定番クラスタ構成で意外と簡単!
ほか

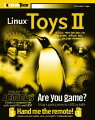
- Linux Toys II: 9 Cool New Projects for Home, Office, and Entertainment [With CD-ROM]
- Christopher Negus
- HUNGRY MINDS TRADE CO
- ¥7920
- 2005年
- 要確認
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
Builds on the success of the original Linux Toys, with new projects you can build using different Linux distributionsAll-new toys in this edition include a MythTV entertainment center, eMoviX bootable home movies, a BZFlag game client and server, and an Icecast Internet radio station, plus five more.Companion Web site, LinuxToys.net, provides information for further enhancing your Linux Toys II projectsIncludes a CD-ROM with scripts, packages, and code for the projects

- Linux Toys: 13 Cool Projects for Home, Office and Entertainment [With CDROM]
- Christopher Negus/Chuck Wolber/Chuck Wolber
- HUNGRY MINDS TRADE CO
- ¥7920
- 2003年
- 要確認
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
* Christopher Negus is the bestselling author of Red Hat Linux 8 Bible (0-7645-4968-5) and earlier versions, with more than 125,000 copies sold
* Readers learn to build sixteen fun and useful devices for home and office, using spare parts and free software
* Projects include transforming an answering machine into an e-mail converter, building an MP3 music jukebox, building a car entertainment center, and creating a TV video recorder/player
* Projects work with any version of Linux
* Companion Web site includes specialized hardware drivers and software interfaces, plus music and game software

- Linux Pocket Guide
- Daniel J. Barrett
- O'REILLY & ASSOC INC
- ¥1237
- 2004年
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- シリコンバレー精神
- 2006年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.68(39)
「シリコンバレーで今何が起ころうとしているのか、この目で見きわめたい。産業の大変革を身体で実感したい」。1994年10月、同地に移住した著者は、ネット革命とバブル崩壊の一部始終を目撃し、マイクロソフト帝国の変質と、リナックス、グーグルの誕生に注視する。技術と経営と投資家の幸福な結びつきと、その背後の「変化を面白がる楽天主義」を余すところなく伝える名著の、待望の文庫化。

- 【輸入盤】Live At Montreux 1974 / 1984
- Mahavishnu Orchestra
- Eagle Eye
- ¥3729
- 2007年10月30日
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
※こちらの商品は、US盤DVDとなります。
ジョン・マクラフリンがビリー・コブハム、ヤン・ハマーらと結成したマハヴィシュヌ・オーケストラの全盛期を捉えた、初の公式ライヴDVD!
モントルーにおける2回のパフォーマンスで構成された2枚組。Disc-1には84年のライヴを収めており、ビル・エヴァンス(sax)を含むラインナップの映像が楽しめる。また、Disc-2には3曲のみながら、74年の映像を収録。マクラフリン(g)以下、ジャン・リュック・ポンティ(vln)、ナラダ・マイケル・ウォルデン(ds)ら、総勢11名による演奏。さらにボーナスとして、74年のパフォーマンスから3曲のオーディオ・トラックを追加。このオーディオ・トラックは、マクラフリン自身がマスターテープからリミックスを施している超貴重音源。総収録時間は220分!
Disc-1:1984年
Jonh McLaughlin (g)
Bill Evans (sax)
Marsha Westbrook (sax)
Mitchell Foreman (key)
Jonas Hellborg (b)
Danny Gottlieb (ds)
Disc-2:1974年
Jonh McLaughlin (g)
Bob Knapp (fl,per)
Steve Frankovitch (horns)
Gayle Moran (org,vo)
Jean-Luc Ponty (vln)
Steve Kindler (vln)
Carol Shive (vln)
Phillip Hirschi (cello)
Ralphe Armstrong (b)
Michael Walden (ds)
レーベル : Eagle Eye
信号方式 : NTSC
リージョンコード : ALL
組み枚数 : 2
Powered by HMV