健康 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1721 から 1740 件目(100 頁中 87 頁目) 

- かみ合わせを正して全身健康
- 丸山剛郎
- 農山漁村文化協会
- ¥1361
- 2005年09月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)

- 兵庫県公立高等学校 予想テスト 2025年度受験用
- 英俊社編集部
- 英俊社
- ¥1870
- 2024年11月07日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●本書の特長
英俊社完全オリジナル。
問題構成(問題数・問題の配列),出題傾向(出題形式・難易度),配点の付け方,問題用紙・解答用紙のレイアウトなど,すべて兵庫の公立入試そっくりに作りあげた予想テストです。
1.5教科×3回収録
2.英語リスニングもオリジナルで3回分収録
3.採点しやすい別冊の解答用紙(1枚ずつ取りはずせます)
4.実際の入試に合わせた配点
5.分かりやすい解説(英語長文の全訳,古文の口語訳付)
●リスニング音声について
本書に掲載のリスニング音声は英俊社サイト内の専用ページ<リスもん>で再生することが出来ます。(無料)
※コードの使用期限: 2026年3月末日

- 免疫力を高めれば、薬はいらない!
- 安保 徹
- 三笠書房
- ¥847
- 2015年11月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(6)
「季節の変わり目に風邪を引いた」
「仕事が忙しくなると頭痛がする」
「健康診断で糖尿病と診断されてしまった」
こんな体の不調、「薬」で治そうとしていませんか?
じつは、あなたが本来持っている万能の癒しの力
「免疫力」を高めれば薬はいらないのです!
免疫力を高めれば、
・疲れない
・ストレスに負けない
・病気にならない
そんな理想の体がつくれます!
本書では、免疫学の世界的権威である安保徹先生が
免疫力を高める食事や生活習慣を紹介するとともに
さまざまな病気の予防対策法を徹底解説します!
たとえば……
頭痛ーーお風呂で体を温めれば、薬はいらない!
花粉症ーー「リンパ球を増やす食事」をやめよう
糖尿病ーー「食事制限」よりも「ストレス制限」を!
などなど、ちょっとした工夫でできる簡単健康法が満載!
今日から「医者いらず」「薬いらず」の体を手にいれましょう!

- 腎をさすると100%健康になる!
- 福辻鋭記
- シネマファスト
- ¥1540
- 2011年05月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)

- 猫から愛される本
- 笠倉出版社
- ¥539
- 2016年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- お坊さんが考案した、かんたん自然治癒力アップ体操
- 松本光平
- たま出版
- ¥1100
- 2012年07月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
「病気じゃないけど、なんだか調子が悪い…」そんなときは、体に毒素や疲労が溜まりすぎているのかもしれません。自然治癒力アップ体操で疲れをリセットし、身体の変化を実感してください。

- キウイを食べると腸が健康になる!
- 松生 恒夫
- 現代書林
- ¥1540
- 2019年06月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
腸の健康には、ヨーグルトよりキウイがいい!
あなたは知っていましたか?
4万人の腸を診てきた専門医が言います。
問題は、ヨーグルトに多く含まれる乳脂肪分だと。
腸の不調や便秘を改善しようと、
熱心にヨーグルトを摂っていると、
血中の悪玉コレストロールが増え、
脂質代謝異常症や高コレステロール血症になってしまうこともあるのです。
さて、キウイが腸にいい理由は、食物繊維です。
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維が2対1の割合で含まれています。
他の食材に比べて、水溶性食物繊維が豊富なのかポイント。
水溶性食物繊維が、いま注目の素材「酪酸」を腸の中で増やしてくれるのです。
潰瘍性大腸炎や便秘といった腸の健康だけでなく、
肥満の抑制や糖尿病の改善にも効果がある酪酸。
「世界一受けたい授業」で著者が紹介し話題となった
「キウイのオリーブオイルがけ」など、
キウイのおすすめの食べ方を掲載しています。
Part1.腸を健康にするには、なぜヨーグルトよりキウイがよいのか?
Part2.腸を健康にする、いま注目の酪酸とは?
Part3.腸を元気にするキウイの食べ方
Part4.食物繊維と酪酸だけじゃない! キウイが健康にいい理由
Part5.腸が元気になる生活習慣のコツ

- 男の独り料理
- 婦人之友社
- 婦人之友社
- ¥1430
- 2000年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.33(3)
まずはちゃんと食べる(食事が大切だということを知る)。健康を維持できる栄養をとる。つくってみる、食べてみる(テクニックはあとからついてくる)。経済的である。上手な手抜き法を身につける。肉とたっぷりの野菜が入ればおかずは一品でいい(手づくりはおいしいし、楽しい)。ひとり暮らしが豊かになる(人とのコミュニケーションだって広がる)。こんな料理なら、やってみたくなりませんか。
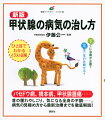
- 新版 甲状腺の病気の治し方
- 伊藤 公一
- 講談社
- ¥1650
- 2018年03月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(3)
バセドウ病、橋本病、甲状腺腫瘍など、ほとんどの甲状腺の病気は、命にかかわることはありません。治療により甲状腺の機能が正常になれば、健康な人と同じような生活ができます。ですが、一生薬をのみ続けなければならない方もいますので、病気とのつきあい方を知ることも大切です。本書では、甲状腺疾患の基礎知識から、病気の見極め方、最新治療までを徹底解説。体調に合わせて生活や環境を整えるコツも紹介します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【すぐに治療が必要? 薬は一生のみ続ける?】
ほとんどの甲状腺の病気は、命にかかわることはありません。
治療によって甲状腺の機能が正常になれば、健康な人と同じような生活ができます。
初めは、なかなか治療の効果が現れなくて、落ち込んだりあせったりする方もおられるでしょう。
なかには一生薬をのみ続けなければならない方もいらっしゃいます。
甲状腺の病気とのつきあい方を知って気長にコントロールしていきましょう。
本書では、バセドウ病、橋本病、甲状腺腫瘍などの甲状腺疾患の基礎知識から、
病気の見極め方、最新治療までをわかりやすい図解で紹介しています。
【主なポイント】
■バセドウ病/甲状腺が働きすぎて心も体も全力疾走状態に
*首の腫れや目の異常、動悸が代表的な症状
*治療法には、薬物療法、アイソトープ療法、手術の3つがある
■橋本病/慢性的な炎症で甲状腺の細胞が壊れていく
*症状がわかりにくく、初めは首の腫れだけ、元気がなくなることも
*治療の基本は定期的な受診。症状があれば薬を使う
■甲状腺腫瘍/しこりができる
*良性腫瘍なら経過観察、悪性腫瘍なら手術で切除するのが基本
*悪性腫瘍には六つのタイプがあるが、進行が遅い「分化がん」がほとんど
【本書の内容構成】
第1章 甲状腺と病気について知ろう
第2章 甲状腺が働きすぎるーバセドウ病とわかったら
第3章 甲状腺が働かないー橋本病とわかったら
第4章 しこりができるー腫瘍が見つかったら
第5章 体調に合わせて生活や環境を整える

- からだノート
- 田中 久美子
- 健学社
- ¥1760
- 2012年05月25日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
身近な心身の健康問題について、子どもたちが自らの力で適切に判断し対応できる能力と態度を育てたい。
本書はイラストを主体に多様な指導方法を駆使した「ワークシート」形式になっており、子どもが楽しく学ぶことができます。

- ひざ痛・変形性ひざ関節症 整形外科のスーパードクターが本音で教える最新最強自力克服大全
- 吉原 潔
- 文響社
- ¥968
- 2020年02月06日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.83(6)
潜在患者も含めれば今や3,000万人超が悩むとされる国民病「変形性ひざ関節症」。着地のたびにひざに激痛が走り、「歩けない」「階段や坂道が怖い」「正座できない」「ひざがはれる」「水がたまる」などの症状がいっこうによくならず、長年苦しみつづけている患者さんは、あなただけではありません。
整形外科の「最新手術」と「運動療法」の両方に精通する名医が、現代の診療の問題点を浮き彫りにしながら、ひざ痛の自力克服法を中心に、新薬や低侵襲手術、再生医療などの最新治療の情報まで網羅し、「自分が患者なら迷わずこう治す」という観点で、最新・最強の対策を本音で解説する待望の一冊。これ一冊あれば、ひざ痛対策はもう万全!
新発見!手術の回避例が多数!
寝たまま・座ったまま1分でOK! ズボラでも続く「ひざ痛克服エクサ」
◆ひざが伸びない人のひざ痛▶︎「1分ひざゆるめ」
◆太もも筋が衰えた人のひざ痛▶︎1分ひざトレ「テーブルスクワット」
◆O脚・X脚の人のひざ痛▶︎1分ひざ正し「ゴロ寝足上げ」
◆正座できない人のひざ痛▶︎「1分ふわ曲げストレッチ」
やり方ポスター付録つき
発見!よくなる患者さん・悪化する患者さんの決定的な違い
あなたの治療法が◯か×かわかる!
世界的治療ガイドライン「OARSI」推奨治療ランキングつき
ロキソニン・インドメタシン・ジェネリックなど
病院の薬全ガイド
飲み薬・貼り薬・再生医療 丸わかり
後悔しない!ひざ痛の最新手術
手術の効果・種類・メリット・デメリット
入院期間・費用の疑問に全回答!
【本書の特徴】
1座ったまま、寝たまま、1分程度で誰でも簡単にできる高効率で最楽のすぐ効く改善体操が、悩みの症状・タイプ別にわかる。
2自分が今受けている治療やケアの問題点が浮き彫りになり、なぜ自分はひざ痛がよくならないのか、その原因を見つけやすい。
3世界的治療ガイドライン「OARSIの推奨治療ランキング」も掲載し、自分が受けている治療は適切かどうかもわかる。
4注目の新薬や、軟骨の修復を促すと今話題の「再生治療」、低侵襲手術の効果、メリット・デメリット、かかる費用などについて本音をまじえながら解説。
5スクワットはひざに悪い?水抜きはクセになる?人工関節は危ない?など「本音のQ&A集」
6壁に貼って毎日実践するのに役立つ「ひざ痛克服エクサやり方ーポスター付録」つき

- 長寿脳
- 白澤 卓二
- ダイヤモンド社
- ¥1650
- 2022年12月08日
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(5)
「人生100年時代」という言葉に慣れてきたところで、実際に100歳近く生きる人は珍しくなくなり、「120年生きたい」というニーズが高まっていると感じます。もちろん寝たきりや認知症にならずに、です。
この本は、認知症専門医で自身も認める超・健康マニアの白澤卓二先生が、健康に120歳を目指すため必要だと思うことを、全部まとめたものです。
120年生きるにはかなりストイックな生活を送る必要があるのかと思いがちですが、答えはノーです。
世界中の論文や、クリニックの患者、高齢者施設での利用者の状況などから導き出された結論は、意外と知っていればできそうなことです。
とくに脳の状態を健康に保つ方法として、「個性的な脳を個性のままに使う」というのは目からウロコですが、誰もが実践できるし、実践したいことではないでしょうか。
多くの人が、本当の健康に気づけて、それを実践できる本になっています。
●第1章 長寿脳 120歳まで健康に生きる方法
ストレスが敵、個性的な脳を個性のままに使う
病理学的に健康な脳は、食事によって作られる
テロメア120年説の違和感と延命ドリーム
脳は200年働けるようにデザインされている
健康な120歳に到達する段取り
お酒と脳細胞の深い関係
タバコは誰にとっても有害か
性ホルモンは脳と体を元気にする
江戸時代の平均寿命は35〜40歳程度
人生の最終章、どう幕を引くか
日野原重明先生と三浦敬三さん、長寿の神髄
アルツハイマー病治療薬が普及しない原因と対策
●第2章 食事を変えて長寿脳になる
食べるものにこだわるべき理由/脳に必要な栄養
長寿脳を作る食材と簡単レシピ
シーフードスープカレー/寝かせ玄米/大根おろし/納豆キムチ/サーモン海苔巻き/いわしとレモンのマリネ/玉ねぎすき焼き/酢卵ドリンク/丸鶏蒸し
●第3章 疲れをとると長寿脳になる
疲れ知らずという結論
長生きするとしがらみから解放される
睡眠/運動/生活の質を維持するコツ
北欧の高齢者向けプログラム
●第4章 病気を遠ざけて長寿脳になる
腸内環境、口内環境、血液と血管
うつ病には出口がある
●第5章 認知症リスクを下げて長寿脳になる
認知症の種類
緑内障、難聴、頭部外傷、高血圧と肥満、お酒の飲みすぎ、脊柱管狭窄症
認知症患者の半数は転倒・骨折から
転倒は夜中のトイレで起きる
●第6章 本能に従うと長寿脳になる
コミュニケーションと認知機能低下の関係
妻に先立たれた男性は寿命が縮まる
ペットが脳に影響するのは本当?
体力がなくてもできる趣味を作っておく
人にとって孤独がいちばん不幸というのは嘘

- 成功する自己採点式ダイエット
- 吉武信二
- 大学教育出版
- ¥1540
- 2007年04月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 【バーゲン本】1日10分押すだけ疲れ・痛みがスッと消える耳のツボ健康法
- 小田 博
- (株)幻冬舎
- ¥440
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
耳ツボを研究していくと、整形外科的にも理にかなったメカニズムが多く、疲れ・痛みを消すことに役立つことがわかりました。さらには、肩や腰は自分で押すことは困難ですが、耳の裏のツボであれば自分で押せる場所にあるため、毎日のケアにも適しています。そこで本書では、難しい知識・技術をもっていなくても、安全、安心、確実な方法で耳のツボを刺激して疲労を回復、肩こりや腰痛などの痛みを取り去る「耳のツボ健康法」をレクチャーします。

- アレルギーは自力で治る!超健康レシピ
- 市川晶子
- ハート出版
- ¥1650
- 2010年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
春夏秋冬・四季折々の素材を活かした応用の利く基本献立59。今すぐ始められる、お金のかからない“かしこい”方法。アレルギー以外にも“副作用”で家中みるみる健康に。

- 栄養とカラダ
- 石倉ヒロユキ/金子光延
- 偕成社
- ¥2640
- 2018年02月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
マンガとイラストでたのしく学べる知識絵本シリーズの2巻目。それぞれの栄養素のはたらきや、カラダに吸収されるしくみなどを紹介します。

- めざせ!ピン!ピン!きらり!
- 根本 賢一
- オフィスエム
- ¥1650
- 2019年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- マンガでわかる健康方程式!
- 井上敬/赤池キョウコ
- 日本経営LINK
- ¥1430
- 2015年05月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
H=O+S+Tが分かれば、あなたの体は変わる!あらゆる健康法を凌駕した究極の健康哲学がマンガになった!

- 医療人類学
- アン・マケロイ/パトリシア・K.タウンゼンド
- 大修館書店
- ¥6050
- 1995年07月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
グローバルな視野でしかも生物学的・社会文化的・政治経済的に書かれた、包括的な医療人類学の入門書。さまざまな文化的背景をもつ人々の生活を考えた国際保健医療が注目されている今日、今後の国際保健医療を探っていく…まさに必読の書。

- Taoのセラピー
- アダム・J.ジャクソン/長谷川淳史
- 春秋社(千代田区)
- ¥1650
- 2008年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
病気に関する「原因と結果の法則」を知れば、おのずと“癒やしの道”がひらかれる。自然治癒力をもっとも高める方法とは?身体の眠れる力を目覚めさせる10の秘密を伝授。