芸術 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1721 から 1740 件目(100 頁中 87 頁目) 

- 芸術の生まれる場
- 木下直之
- 東信堂
- ¥2200
- 2009年03月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
芸術生成の新たなトポスミュージアムを全開する。「作品」は観客の眼を通じて初めて「芸術」として開花する。作品と観客出会いの場・ミュージアム等に見る、芸術と社会の新たな関係性。日本学術振興会人社プロジェクトの成果。

- ピアノ演奏芸術
- ゲンリッヒ・グスターヴォヴィッチ・ネイガ/森松皓子
- 音楽之友社
- ¥4950
- 2003年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(4)
名教師として名高いネイガウス教授による、モスクワ音楽院在籍40余年にわたるピアノ教育の神髄を披瀝した歴史的名著の改訳・新訂版。
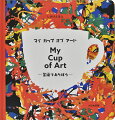
- マイ カップ オブ アートー芸術であそぼうー
- カテリーナ・カロリク/藤村奈緒美
- 大日本絵画
- ¥2420
- 2022年09月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
カップなんて、だれでももっているような、ごくありふれたもの。
偉大な芸術家たちも、ごくありふれたものをえがきました。
この本では、ピカソやゴッホ、草間彌生など、9 名の芸術家たちの作品をもとに、
さまざまなしかけを施されたカップが登場します。
何かを、新しいやり方、思いがけないやり方で表現する。
それがアートのおもしろさです。
自分ならどうえがくか、偉大な芸術家になったつもりでページをめくってみませんか?

- いしかわ舞台芸術祭2025 公式ガイドブック 通常版
- かなざわ演劇人協会
- ¥1699
- 2025年09月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
石川県で開催される舞台芸術祭「いしかわ舞台芸術祭」の公式ガイドブック。「人間はおもしろい説。」をテーマに、ミュージカル、演劇、ダンス、音楽など様々な観劇の魅力を発信する。本書では、全21プログラムの出演者や作り手へのインタビューを交えながら、舞台芸術に対する想いを深く掘り下げる。
俳優、お笑い芸人、タレント、オペラ歌手、ミュージカル俳優など、第一線で活躍する出演者の貴重なインタビューと撮り下ろし写真。また石川県を拠点に活動する演劇団体の紹介も多数掲載し、演劇の奥深さが感じられる一冊。
[特集]
・いしかわ舞台芸術際 2025アンバサダー梅津瑞樹さんに聞く舞台芸術の魅力
・我ら宇宙の塵 EPOCH MAN 小沢道成×梅津瑞樹
・東映ムビ×ステ 死神遣いの事件帖 終(ファイナル)鈴木拡樹×安井謙太郎(7ORDER)
・special interview 田淵累生
・あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜 藤井直樹×岡崎彪太郎
・劇団四季 三代川柚姫
・オペラ「高野聖」演出 原純
・Golpe2025 今井翼
・ENGEKI WORK SHOP 新田さちか
・ダウ90000 第7回演劇公演「ロマンス」
・「山里亮太の140」山里亮太
Contents
いしかわ舞台芸術祭2025アンバサダー
03 梅津瑞樹さんに聞く 舞台芸術の魅力
13 我らの宇宙の塵 EPOCH MAN
小沢道成 × 梅津瑞樹
東映ムビ×ステ
17 死神遣いの事件帖 終(ファイナル)
鈴木拡樹 × 安井謙太郎
Special interview
21 田淵累生
24 「あの夏、君と出会えて」
〜幻の甲子園で見た景色〜
藤井直樹 × 岡崎彪太郎
27 劇団四季[三代川柚姫]
29 オペラ「高野聖」
原 純
Special interview
31 Golpe2025
今井 翼
ワークショップ&トークライブ
33 “Healing Harmony Project”[由水南]
35 いしかわ人形劇フェスティバルinあなみず
37 謎解き「バック・トゥ・ザ・バックステージオンファイア」
〜失われた市民の声(レジスタンス)〜
41 金沢学院大学演劇部・金沢大学劇団らくだ
43 劇団アンゲルス
45 chiroru market
47 演劇ユニットMasa&Kou
49 大杉ミュージカルシアター
51 パルケ・血パニーニャ
53 劇団羅針盤
55 演劇ユニット浪漫好ーRomance-
57 meototo
59 朗読小屋浅野川倶楽部
いしかわストリートシアター
59 toRmansion/刀祭
ワークショップ
63 ENGEKI WORK SHOP
新田さちか
67 第7回演劇公演「ロマンス」
ダウ90000
Special interview
70 「山里亮太の140」
山里亮太
73 大場さやかエッセイ
81 いしかわ舞台芸術祭2025公演プログラム 公式グッズ

- 生誕120年芸術写真の神様 塩谷定好とその時代
- 塩谷定好展実行委員会
- 今井出版
- ¥2970
- 2019年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 続芸術家の年賀状
- 山田俊幸
- 二玄社
- ¥2750
- 2006年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
芸術家の年賀に込めた美の世界。個性あふれる芸術家73名の年賀状、277通を一挙公開。

- 芸術家たち(1)
- 河内タカ/SANDER STUDIO
- オークラ出版
- ¥1650
- 2019年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(3)
ようこそ、建築とデザインの世界へ。楽しみながら、読んで学べる、入門者のためのアートエッセイ第一弾!教養として知っておきたい、時代をつくった建築家とデザイナーたち。

- 芸術愛好家たちの夢
- 佐藤直樹
- 三元社
- ¥5280
- 2019年09月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
愛好家(ディレッタント)こそ理想の芸術家ーー
日々の糧のためでなく、純粋に芸術を愛し実践した彼らは近代的な理想的芸術家像の原形となった。包括的研究がされてこなかったディレッタントたちの芸術活動に美術史、音楽学、文学、美術教育学など多様な視点から迫る。
序章 ディレッタント研究のために
ディレッタント研究序説ーーその歴史と展開の見取り図 8
佐藤 直樹
1章ディレッタント前史ーー工房、宮廷、サロン
ルネサンス期における最初のディレッタント肖像画、あるいは素描を教えるベルナルディーノ・リチーノ 36
ウルリヒ・フィステラー 岩谷 秋美 訳
王族たちの美術活動ーーザクセン宮廷の素描と旋盤細工 60
佐藤 直樹
一八世紀フランスのディレッタンティズムーー美術愛好家による作品制作をめぐって 83
船岡 美穂子
2章 ディレッタンティズムの転換点
ヴァイマル古典主義の文脈におけるディレッタンティズムの様相 112
ヤナ・ピーパー、トルステン・ファルク 橘 由布季 訳
ヴァイマル公妃アンナ・アマリア作曲《エルヴィンとエルミーレ》を巡って 128
大角 欣矢
愛好家のための方法ーー一七六〇〜七〇年代におけるアルファベット式芸術事典 170
山口 遥子
ゲーテのディレッタンティズムーー「収集家とその友人たち」と「ディレッタンティズムについて」 190
眞岩 啓子
一八〇〇年頃の侯爵夫人と女性市民階級ーーディレッタンティズムにおける共通点はあるのか? 218
コルドゥラ・ビショッフ 杉山 あかね 訳
3章 「天才=ディレッタント」
作曲家メンデルスゾーンの素描と水彩画ーースイス旅行を例にして 244
星野 宏美
ディレッタントの芸術としての「ランドスケープ・ガーデニング」--ピュックラー=ムスカウと『親和力』の世界 277
尾関 幸
カール・グスタフ・カールスのディレッタンティズムと近代社会 303
仲間 裕子
終章 「新しい芸術家=ディレッタント」の未来
教育学から見たディレッタンティズムの可能性 338
小松 佳代子
あとがき 363
人名索引 1
資料:フリードリヒ・フォン・シラー「ディレッタンティズムに関する見取り図」 6
引用図版出典一覧 8
Die ersten Dilettanten-Porträts der Renaissance, oder: Bernardino Licinio unterrichtet im Zeichnen 12
Ulrich Pfisterer
Erscheinungsformen des Dilettantismus im Kontext der Weimarer Klassik 24
Jana Piper | Thorsten Valk
Vereint im Dilettantismus? Fürstinnen und Bürgerinnen um 1800 33
Cordula Bischoff

- マニエリスム芸術論
- 若桑みどり
- 筑摩書房
- ¥1760
- 1994年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.0(2)
マニエリスムとは何か。それは危機の時代の文化である。世界調和と秩序の理念が支配した15世紀は、黄金のルネサンスを生み出した。だが、その根本を支えてきたキリスト教的世界像が崩れ、古き中世が解体する16世紀は、秩序と均衡の美学を喪失する。不安と葛藤と矛盾の中で16世紀人は「危機の芸術様式」を創造する。古典主義的価値をもつ美術史により退廃と衰退のレッテルを貼られてきたこの時代の芸術の創造に光を当て、現代におけるマニエリスムの復権を試みた先駆的な書。

- 版画芸術203号
- 阿部出版
- ¥2750
- 2024年03月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
この度、2024年7月から使用される新千円札の裏面に、葛飾北斎の代表作である浮世絵版画連作「冨嶽三十六景」から《神奈川沖浪裏》が採用されました。本特集ではこの機会に「冨嶽三十六景」全46図と、さらに北斎が「富士」を描いた傑作を中心に取り上げ、その魅力に迫ります。
代表作である「冨嶽三十六景」全46図を1図1頁で紹介する第1章では、作品の解説とともに、可能な限り、初期の摺りと摺り違い、類似作例を並べて掲載しました。
第2章では「冨嶽三十六景」に続いて8年がかりで出版された絵本『富嶽百景』から代表的な作品を抜粋して掲載。第3章では70年に及ぶ画業を主たる画号で6つに分け、それぞれの時期に制作した「富士山」の作品を紹介しました。

- 芸術家たち 2
- 河内タカ/サンダースタジオ
- オークラ出版
- ¥1870
- 2020年10月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.25(5)
芸術家の人生を読んで知る。より多くの人がアートに親しみ、楽しむきっかけを作る1冊です。
約30年間をアメリカで過ごし、ニューヨークを拠点にアートや写真のキュレーション、そして写真集の編集を数多く手がけてきた河内タカ氏が、世界の建築家・デザイナー総勢31名をピックアップし、それぞれのアーティストについて作家同士のつながりやネットワークとストーリーを交えて語ります。そして、イラストレーターのサンダースタジオによる独自の視点で切り取った各アーティスト、いわゆる一般的なポートレートではなくそのアーティストにまつわる要素がしっかりと表現されたイラストでご紹介。河内氏の軽妙な語り口と、サンダースタジオによるユーモア溢れるポートレートのコラボレーションです。
敷居の高い“アート”ですが手に取りやすい内容、デザインになっているため、より多くの人がアートに親しみ、楽しむきっかけを作りたいと考えております。第2弾目は、ミッドセンチュリーで活躍していたアーティストたちのお話しです。

- ギャラリーフェイク名品集 愛の芸術
- 細野不二彦
- 小学館
- ¥427
- 2019年03月01日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- イサム・ノグチ 庭の芸術への旅
- 新見 隆
- 武蔵野美術大学出版局
- ¥3520
- 2017年12月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
抽象彫刻の泰斗イサム・ノグチ。彫刻のみならず、マーサ・グラハムのための舞台美術でも名を馳せたアーティスト。日本人詩人・野口米次郎を父に、作家であるアメリカ人レオニー・ギルモアを母に、1904年ロサンゼルスで生まれた彼は、終生、自らの「居場所」を探して旅をした。若き日は、肖像彫刻で生活費を得ながら、早くも1933年に「プレイマウンテン(遊び山)」を構想。生涯をかけてノグチはこの構想を温めつづける。
1949年、45歳のノグチは奨学金を得るため、ボーリンゲン財団に「レジャー環境の研究についての申請」を提出する。「私は長く、彫刻と社会とのあいだに、新しい関係がつくりだされなければならないと考えてきた」と始まるこの趣意書には、彫刻の意義を問いつつ、レジャー(余暇)環境そのものの質を変えていくのは、美に関する課題であるとした。ノグチは彫刻を媒体として、人々のくつろぎの場、愉しみの場をつくり出そうと試みていた。
1950年に来日したノグチは、建築家・谷口吉郎のもとで、慶應義塾大学・新萬來舎の内装と庭を手がける。団欒の場の創出、日本との短い蜜月のはじまりだ。51年には広島平和公園の2つの橋の欄干の設計を依頼され、その途中に寄った岐阜で「あかり」のイメージとなる岐阜提灯に出会う。52年には、北鎌倉の北大路魯山人の土地の一隅に、新妻となった女優・山口淑子とともに移り住み、焼きものに没頭するノグチ。掌にのるような彫陶作品「私がつくったのではない世界」が生まれる。国籍も年齢も問わず、いつでも誰でも受け入れられる場としての「庭」。ノグチの魂の旅を鎮める「庭」であった。
日本、アメリカ、イタリア、各地で彫刻家としての仕事をしながら、1960年代には、イエール大学バイネッケ稀覯書・写本図書館、チェイス・マンハッタン銀行の沈床園、イスラエルのビリー・ローズ彫刻庭園などの名作を生む。その一方で、ルイス・カーンとの協同によるニューヨークのリヴァー・サイド・ドライヴの公園計画は、実現に至らなかった。ノグチの「公園」が初めて実現したのが65年、大谷幸夫との協同による横浜「こどもの国」であった。
日本では、庵治石で有名な香川県にアトリエを構える。移築された古い民家に手を加えて、ゆるやかな起伏を活かした庭をつくりつつ、「真夜中の太陽」「エナジー・ヴォイド」などの名作がここで生み出された。
札幌のモエレ沼公園マスター・プランを設計した1988年、この年の暮れにノグチは永遠の旅に出る。起伏だけでつくられた庭園。そこは人々のつどう場であり、風であり、身体である。渺々と風をまとうプレイマウンテンがモエレ沼公園に完成したのは、1996年であった。
作品図版55点とともに、インドに始まり、21世紀の庭の芸術を求める旅。

- ゴシック芸術に学ぶ現代の生きかた
- 近藤存志
- 教文館
- ¥1320
- 2021年06月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
20 世紀を代表する美術史家ニコラウス・ペヴスナーと、ゴシック・リヴァイヴァルを主導した19 世紀の建築家A. W. N. ピュージン。中世ゴシック芸術の名もなき職人たちの謙遜を称揚する2 人の言葉から、神律的社会から乖離した現代における生のあるべき姿を考える。現世的欲求にとらわれない、真に価値ある生きかたとは?

- ヴァレリーにおける詩と芸術
- 三浦信孝/塚本昌則
- 水声社
- ¥5500
- 2018年08月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
作品よりも作品を作る精神の機能を探求しつづけたポール・ヴァレリー。明晰な批評意識をもつがゆえに〈ヨーロッパ最高の知性〉と呼ばれた詩人は近年、知性と感性の相克に懊悩するその実像が明らかになっている。
本書では、ヴァレリーの肖像に迫る第1部にはじまり、〈他者とエロス〉の問題に肉薄する第2部、そして第3部〜第5部では芸術論の三つの諸相(絵画、音楽、メディウム)に焦点をあて、新たな読解の道筋を切り開く。

- 力動指向的芸術療法
- マーガレット・ナウムブルグ/内藤あかね
- 金剛出版
- ¥7370
- 1995年10月25日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
原著者ナウムブルグ女史は、それまでの精神分裂病の表現病理に焦点づけられた理論や創造性を軽視した作業療法的な方法ではなく、精神分析的理解に基づく今日的芸術療法の創始者として、あるいは「なぐりがき法(scribble technique)」の提唱者としてしられる。本書には芸術療法の啓発的な総論に続いて、「なぐりがき法」をも含め、長期にわたって芸術療法によって治療された3例の詳細な事例報告が、多数のカラーを含む描画とともに提示されている。

- 文学的芸術作品新装版
- ロマン・インガルデン/滝内槇雄
- 勁草書房
- ¥6490
- 1998年05月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 三輪田米山の芸術
- 三輪田米山/小池邦夫
- 清流出版
- ¥2200
- 2008年11月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
大酒を飲んでは、個性を爆発させた米山!その書は、飲むほどに、酔うほどに、魅力を増した。

- 新装改訂版 続剣道藝術論
- 馬場 欽司
- 体育とスポーツ出版社
- ¥2860
- 2021年12月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
あなたは剣道の大黒柱をどこに置いてやっていますか。芸術か、競技性か。その価値観の違いで不老の剣になるかどうかが決まる。
著者は「剣道は芸術」と断言し、「芸術性がある」と表現しない。剣道は芸術の分野にあって、競技性も備えているという考え方だが、ここのところが最も誤解を生みやすいところであり、おのずと剣道の質も違ってくる。一般人が剣道を芸術として捉えてくれるようになれば、剣道の評価が高まる。一般人にもぜひ読んでもらいたい。
はじめに
第一章 五島の剣
第二章 剣道家の迷走
第三章 相和する
第四章 戦いの手順
第五章 優雅
第六章 稽古の本源を探る
第七章 原点からの出発
第八章 危機一髪の臨機応変
第九章 有効打突の研究
第十章 大道透長安(私の眼に映じた第38回京都大会)
第十一章 点を線で突く ”突き技” の極意
第十二章 氣を錬る
第十三章 感性を育てる
第十四章 目の付けどころ
第十五章 三殺法
第十六章 全日本剣道選手権大会再検証
第十七章 上段
第十八章 母について
第十九章 剣道は芸術である

- ミューズと芸術の物語 下
- ルース・ミリントン/菊池 由美
- 原書房
- ¥2640
- 2024年01月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
ミューズ=画家と恋愛関係にあった美女、ではない。ポーズをとるだけの従属的な存在でもない。作品の製作にたずさわり、作家の方向性を決定づけ、美術史に残る名作を生み出す力となったミューズの真相と功績を解き明かす。