言葉 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 1761 から 1780 件目(100 頁中 89 頁目) 

- 宇宙につながると夢はかなう【新装版】
- 浅見帆帆子
- フォレスト出版
- ¥1320
- 2016年12月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.17(8)
20万部突破のベストセラーが装い新たに!
「負けそうになる時、つらい時、そんな時にちゃんと
行くべき方向に光を射してくれる本。
これでもう大丈夫って思えた」
(30代・女性)
発売以来、全国から反響が続々と届き
20万部の大ヒットとなった
浅見帆帆子『宇宙につながると夢はかなう』が
ポケットサイズになって装い新たに新登場!
本書は、宇宙につながる生き方、考え方、行動を33の法則にまとめた
浅見帆帆子さんの金字塔的作品。
「すべてが同じ方法でよくなっていく! 」と
変化を感じられた読者の声が多く寄せられましたが
いつの時代、どんな場所でも
人生が「なぜかうまくいっている」人たちは、
宇宙に応援されているような生き方、考え方をしています。
「宇宙とつながっている」
「流れに乗っている」
という感覚は、その人の仕事の大小には関係なく、
もちろん、主婦や学生、こどもにもあるものです。
もし、あなたが、
「何かが足りない」
「何をしていいかわからない」
「何かを変えたい」
「仕事に悩んでいる」
「人間関係に悩んでいる」
・・・などを日々感じているのであれば、
ぜひ、読んでください。
手に収まるポケットサイズだから
大切なあの人へのギフト、プレゼントにもぴったり。
毎日バッグに忍ばせて持ち歩く心強いバイブルにも。

- 博報堂で学んだ負けないプレゼン
- 須藤亮
- ダイヤモンド社
- ¥1650
- 2018年07月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.33(3)
トヨタ自動車、花王、全日空、ケンタッキー・フライド・チキン、マクドナルド、パナソニック、味の素、アステラス製薬…など大型案件をつぎつぎ獲得!1000回以上プレゼンした達人が教えるシンプルメソッド!この通りにやれば誰でもうまくいく。

- シェイクスピア名詩名句100選
- 関口篤
- 思潮社
- ¥1078
- 2006年06月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
智慧の花園ソネット、アントニーの情念の仇討ち、断固決断するハムレット…。「読む者は誰でも自分の分身に出会える」というシェイクスピアの劇と詩の精髄を伝える名句名言を選び抜き、原文と訳と解説を配した画期的一冊が登場。

- 右脳+左脳トレーニングドリル ことば
- 市川 希
- ひかりのくに
- ¥935
- 2022年03月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
パズルを解くように楽しく学べる!
1日3問12日間でIQ20アップも期待できる
評価が一眼でわかる超総合評価チャートが付いています
入学前の能力開発におすすめ
■ 概念(言葉)の領域とは
□ 思考の手がかり:言葉の意味で考えたり覚えたりする能力
□ 好きな遊び:ごっこ遊び、カルタ、紙芝居、絵本、しりとり
□ 得意学科:国語、社会、外国語
□ 向いてる職業:政治家・アナウンサー・教師
■ 知能研究所とは
知能教育学を提唱した肥田生次郎によって1965年に創設された研究機構。同時に全国で初めての知能教室を開設。以来、脳生理学・教育学・心理学などを基礎にした人間の知能と行動(知能教育学)の研究と教材の開発を中心に行なっている。その教材は幼児から小学校・大人の脳トレーニングまで網羅。さらに指導者の育成・小学校受験など活動は多岐にわたる。

- 発達に心配のある子が座れる!まねる!ことばが育つあそびうた
- コロロ発達療育センター/久保田小枝子
- コロロ発達療育センター
- ¥2750
- 2014年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉
- 浅野 みや
- 自由国民社
- ¥1540
- 2021年08月02日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
◆コロナ禍で相談殺到。個別相談は即、満席に!
「どうしたらいいんだろう?」「私の子育て、間違っている?」
「私ってダメな親?」「このままでいいのかな?」
「周囲の目や言葉がつらい」「子育てが苦しい」
……そんなあなたのための本です。
(目次)
第1章 教えて! どうしたら子育ても心ももっと楽になる?
第2章 子育ての常識、子育て神話の呪い
第3章 呪いのようにお母さんを縛る言葉
第4章 心配、悩み、解消しましょう──学校生活、しつけの思い込み
第5章 ホントにそう? 見直したい、学校・先生からの言葉の縛り
第6章 意外と強力? 夫、家族、専門家、ママ友からの何気ない言葉の縛り

- 祈りの泉
- ジーン・ヒントン/光原百合
- 女子パウロ会
- ¥1650
- 1998年07月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
ここに集めたのは、多くのクリスチャンがみずからの霊的探求の旅の中で得た洞察をつづったことばです。…祈るにあたって今までの方向に進んでよいか確信させてくれる、あるいは今まで知らなかった新たな方向を指し示してくれる、道路標識のようなものです。月ごとにテーマを設け、月の初めにはそのテーマに関する導入文、あとは一日ひとつ、短いことばを載せてあります。

- 新俳句年鑑(2018)
- 小島哲夫
- 北溟社
- ¥2750
- 2018年01月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 将棋語辞典
- 香川 愛生
- 誠文堂新光社
- ¥1760
- 2020年02月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
羽生善治九段の永世七冠や国民栄誉賞受賞、藤井聡太七段の29連勝など、大きな話題となった将棋界。
さらに近年は、20代・30代の若手棋士のタイトル奪取やプロ棋士YouTuberの誕生など、新たな波が起こっています。
将棋のルールが確立したのは江戸時代といわれており、日夜トッププロの棋士たちが研究、研鑽に励んでいますが、それでも81マスの盤上のなかでの展開は無限であるといいます。
また、長い歴史とインターネットやAIの発展などにより、将棋をとりまく世界も、驚くほど多様で個性豊かなものです。
本書では、「王手」「成金」「高飛車」など日常でも聞かれる言葉から、「歩のない将棋は負け将棋」などの格言、「穴熊」「無敵囲い」など数ある戦法、棋士の愛称やエピソードに至るまで、将棋にまつわるあれこれをイラストで楽しく紹介します。
一度ルールを覚えてしまえば、老若男女誰もが楽しめる奥深いボードゲームである将棋。
新時代の将棋界をのぞいてみませんか?
■目次抜粋
はじめに
この本の楽しみかた
将棋のきほんの「き」
【将棋語辞典】あ〜わ
【コラム】
・守り方いろいろ! 囲いカタログ
・将棋カフェってどんなところ?
・将棋駒書体カタログ
・<女流棋士スペシャル対談>香川愛生×北尾まどか
・将棋界ゆかりの宿
・詰将棋を解いてみよう! ほか
********************************
はじめに
この本の楽しみかた
将棋のきほんの「き」
【将棋語辞典】あ〜わ
【コラム】
・守り方いろいろ! 囲いカタログ
・将棋カフェってどんなところ?
・将棋駒書体カタログ
・<女流棋士スペシャル対談>香川愛生×北尾まどか
・将棋界ゆかりの宿
・詰将棋を解いてみよう! ほか

- 「ビジネスマナー」のきほん
- TNB編集部/松本昌子
- 翔泳社
- ¥1408
- 2015年03月12日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
みだしなみや挨拶、電話対応、訪問・接客、ビジネス文書・メール作成、冠婚葬祭など、多岐にわたるビジネスマナーから、必ず知っておきたいことを厳選して紹介。新入社員の方から、社会人2〜3年目の転職者まで、これ一冊で社会人として恥ずかしくないマナーがしっかりと身につきます。
ビジネスマナーとは
1ビジネスマナーってなんだろう
27つの違いと5つのマインド
3何のために働くのか
新人社員の1日
基本のマナーを知っておこう
1第一印象は重要
2あいさつは何のため?
仕事の進め方を知ろう
1会社はチームである
2ホウレンソウの基本
言葉使いをマスターしよう
1会話の基本
2敬語をマスター
3ビジネスに適した言葉
電話対応を身につけよう
1電話の基本
2携帯電話の基本
コラム:今日からできる仕事を始めよう
来客対応の基本
1受付対応の基本
2席次を知ろう
3お茶を入れる
4お見送りの手順
訪問時の基本
1アポイントを取る
2初回訪問の流れ
3名刺交換をする
コラム:初対面の相手の心を掴む会話術
基本の文書とメール作成術をおさえよう
1メールの基本
2ビジネス文書の基本
3英文レター・メールの基本
その他のマナーとモラルを知ろう
1社会人のマナーとモラル
2結婚式のマナー
3お葬式のマナー
4退社のマナー
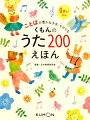
- くもんのうた200えほん
- 公文教育研究会
- くもん出版
- ¥3520
- 2017年10月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.63(106)
お子さまのことばの世界は、赤ちゃんの時期からの語りかけや、絵本やうたを通したことばのやりとりによって、はぐくまれます。
とくに「うた」は、心地よいメロディーやリズムとともに、ことばが記憶に残りやすいといわれます。
うたがすきな子ども、たくさんのうたをおぼえた子どもは、ことばも豊かにそだっていきます。
『くもんのうた200えほん』は、KUMONが大切にしてきた、こうした子育ての知恵を、ご家庭で実践していただくために生まれました。
公文式教室でも長く歌われてきたうたを中心に、ことばの世界を広げるのに最適なうたを、
なつかしい童謡から子どもたちに人気の曲まで、バラエティ豊かに200曲セレクトし、
美しい絵とともに収録しています。
『くもんの うた200えほん』で、今日から、うたのある楽しい子育てをはじめてみましょう。
※収録曲CD(別売)『ことばの豊かな子をそだてるうた200アルバム1』『ことばの豊かな子をそだてるうた200アルバム2』もございます。また、主要音楽配信サイトより、ダウンロード版を配信しております。(CD版、ダウンロード版の曲目・音源は同じものです)

- まるごとパズルスケルトン
- ニコリ
- ¥880
- 2015年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
スケルトンパズルは、リストアップされた言葉たちをうまくワクの中に全部詰め込もうというパズルです。言葉のパズルですが、知識は不要。言葉の長さや交差する部分がヒントになって、気楽に解き進められます。この本にはそんなスケルトンパズルを57問収録しました。

- 0〜6歳児 「言葉を育てる」保育
- 日本国語教育学会
- 東洋館出版社
- ¥1980
- 2021年03月22日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(3)
0〜6歳、心も体も大きく育つ、この時期だからこそ、
言葉を大切にして、言葉の力を育てたい!
大きく育つのは、体だけじゃない!
保育者なら、誰もが実感したことのある幼児の成長スピードの速さ。
0〜6歳の間には、1年ごとに約5〜10cmずつ身長が伸びていきます。
生後3・4か月ごろには首がすわり、あっという間にハイハイ、つかまり立ちをするようになり、1歳を過ぎるころには歩き始める子どももいます。
子どもの体が大きくなったり、動きが複雑化したりすると、「大きくなったな〜」と成長を実感することが多いでしょう。
幼児期の子どもにとって、急激に成長するのは体ばかりではありません。
言葉も大きく、そして急激に育っています。
「アー」「ウー」から、日常会話ができるようになる6年間
よく知られているように乳幼児の言葉の始まりは「アー」「ウー」という喃語(なんご)。
その後、「ワンワン」「ブーブー」など単語を話すようになり(一語発話)、2歳ごろには「ワンワン、いる」「クック、はく」のように単語と単語とを組み合わせて話すようになります(二語発話)。
言葉の発達には個人差がありますが、たった6年で「アー」「ウー」という発話から、日常会話ができるようになり、書き言葉にも興味をもち始めます。
このころの子どもたちは、できるようになることがたくさんあり、好奇心がいっぱいです。
それは「言葉」に関しても同様です。
こんなに大きく「言葉」が育つ時期だからこそ、子どもの意欲を大切にした保育者の積極的な関わりで、6歳以降の「後伸びする力」を育みましょう。
試行錯誤する「言葉」
こんなふうに思ったことはありませんか?
○幼児音や幼児語がなかなか消えない子どものことが心配になる
○自分の話ばかりする子どもに「聞く」ことを教えたい
○わざと乱暴な言葉を使っておもしろがる子どもに困惑してしまう
大人から見ると、心配になったり困惑してしまったりする子どもの言葉。
実は、子どもは話せるようになった喜びもあり、言葉を使って試行錯誤しているのです。
そのような時期の子どもに、どのように関わればいいのでしょうか?
本書では、このような言葉に関するギモンや困りを40のQ&Aにまとめ、解決方法を提案しています。
さらに、変身言葉やかくれんぼ言葉など、夢中で楽しめ、言葉を育てる、とっておきの言葉あそびも20例収録しています。
本書を参考に、子どもの言葉の発達を支える保育について考えてみませんか?

- ジェイン・オースティンの言葉
- 中野康司
- 筑摩書房
- ¥968
- 2012年06月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
ジェイン・オースティンの長篇小説を全訳した著者が、作品の中で語られる含蓄ある名言を紹介する。皮肉とユーモアを愛するオースティンが小説にこめた深い意図を新たに発見するきっかけになる一冊。普遍的な人生の言葉として受け止められるものもあれば、作中の登場人物をよりよく理解するためのキーワードもある。オースティンの真髄を映す読書案内として最適の書。

- 孤独にやられそうなときに読む100の言葉 悩みながら生きていく
- ニャン
- KADOKAWA
- ¥1485
- 2021年04月21日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(2)
著者累計10万部超え!
自分を愛する方法と
孤独との付き合い方
「誘われない自分」「嫌われる恐怖」「愛想笑い」「沈黙が怖い」…そんな自分を卒業したいと思うのは、きっとあなただけではない。SNSでたくさんの若者の悩み相談に答えてきたニャンが、自身も悩み苦しんだ孤独との向き合い方のヒントを贈ります。
・誰にでもいい顔をする人は、誰かの特別になれることは絶対にありません。
・なぜか周りから好かれる人は、長所を見つけるのがうまい
・彼の行動や言葉に意味を探してしまう。それは愛されていない証拠だ
・恋人なんて51点で十分。60点あれば万歳。
・目標は低いところから始める
・「マウンティング」は一種の自己防衛
・他人を許せば、世界は生きやすくなる
・死にたい夜に限って、愛されたくなってしまう
・SNS格差社会
・死のうと思って遺書を書いた話
・自分の得意分野を人と比べるな
・学校は勉強する場ではない。社会的適応性を見極める試験場だ
・集団孤独症候群…etc.
タダで変われるほど、優しい世界じゃない。
でも、変わらずにでも生きていける、程々に優しい世界だ
■第1章 恋人論
・好きでいて欲しいなら、相手に全てを知られてはいけない
・I LOVE YOUの訳し方
・誰にでもいい顔をする人は皆から好かれますが、誰かの特別になれることは絶対にありません
・寂しさに勝てない夜
・恋なんて51点で十分。60点あれば万歳。恋人に100点満点の完璧を求めるのは地獄の始まりだ
■第2章 幸せの再定義
・目標は低いところから始める
・正しい道を選ぶより、選んだ道を正解にする努力の方が大切です
・「普通」なんて存在しません
・人間は、自分の嫌いな人間の成功を願えない。たとえそれが自分自身でも
■第3章 死にたい夜に読む言葉
・人の心には必ず穴が空いていて、その穴の大きさがその人の孤独の大きさだ
・死にたい夜に限って、愛されたくなってしまう
・SNS格差社会
・「幸せ」は誰かと比べるものではない
■第4章 過去を乗り越える
・「劣等感」は誰にでもある。それをガソリンにして生きていかないといけない時期も、人生にはきっとある
・どこかが凹んでも、他の部分が尖って「個性」になる
・嘘つきは孤独の始まり
・優しさって想像力のことかもしれない
■第5章 ありのままで生きていく勇気
・集団孤独症候群
・「愛想笑い」は心からのSOS
・大切なのは、仮面の数ではない。仮面を外せる人間の数だ
・偽りの自分」を愛されるより、「本当の自分」を嫌われた方がいい
・孤独を知っているから愛情の温かさが分かる
#not gifted

- 社会人が身に付けたい ビジネスルールと仕事の基礎の基礎
- ジェイック
- 労務行政
- ¥1650
- 2023年09月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 一年生になるまでに
- 井上修子
- エイデル研究所
- ¥1442
- 1996年04月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書は、著者が長い間の一年生との日々を通して、今何が一ばん大切なのか、子育て中の家庭に話したいことを書いている。

- 言葉は凝縮するほど、強くなる
- 古舘伊知郎
- ワニブックス
- ¥1540
- 2019年08月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.59(12)
短く話せる人になる!凝縮ワード。

- 1日10分で国語の成績が上がる!小学生の語彙力が伸びる「言いかえトレーニング」
- 齋藤達也
- あさ出版
- ¥1650
- 2025年05月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
国語の成績が良い子とそうでない子を比べると、その差の大部分は語彙力にあります。たとえば、語彙力のない子は自信満々に選択肢を選びますが、「この言葉の意味を知っている?」と聞くと、「知らない」と答えることがあります。意味を知らないのに答えているーーそんなことが、実際によくあるのです。お子さんが選択問題で「変な答え」を選ぶのも、語彙力が足りないからかもしれません。国語力の根幹にあるのは「語彙を知っているかどうか」です。本書では、語彙を増やして定着させるための方法として、「言い換え」に焦点を当てました。たとえば、「嬉しい」という言葉を言い換えてみると、「楽しい」「幸せ」「心がおどる」など、さまざまな表現が思い浮かぶでしょう。このように、一つの言葉を別の表現に置き換える習慣をつけることで、自然と語彙が増え、言葉の使い方が身についていきます。本書では、具体的な言い換えの方法や、それを学習習慣に組み込むコツを紹介します。「言い換え」はシンプルですが、確かな効果をもたらす方法です。ぜひ、お子さんと一緒に楽しみながら、語彙力を高める習慣を身につけていきましょう。

- 決定版 ママ、言わないで!子どもが自信を失う言葉66
- 曽田照子/速水えり
- 学研プラス
- ¥1430
- 2020年05月21日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.5(2)
「毎日同じことを言っている」「何度叱っても変わらない」。思い通りにいかずに、ついわが子に言ってしまうキツイ一言が、さらに子どもを傷つけてしまいます。「子育てNGワード」の専門家が、「いい方法」を教えます!