食欲 の検索結果 標準 順 約 580 件中 341 から 360 件目(29 頁中 18 頁目) 

- 子どもの心の診療シリーズ(3)
- 斉藤万比古/本間博彰
- 中山書店
- ¥4180
- 2010年06月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- がんサバイバーの毎日ごはん
- 千歳 はるか
- 小学館
- ¥1430
- 2019年04月18日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 1.5(2)
術後のままならない体調でも自分で作れる!
がんサバイバー(がんを経験して生きる人)、その家族のために、
がん専門病院の管理栄養士が考えたレシピ集。
ふたりにひとりががんになるといわれます。
そして手術や治療ののちも、人生は続きます。
がん専門病院の管理栄養士として日々、サバイバーやその家族と接する著者は、
“その後も続く人生”のスタート地点でもっとも切実な問題は「食べること」だといいます。
食に悩んでいるのは、胃や大腸など消化管の手術を受けた人に限りません。
術後の低握力で思うように買い物や調理ができなかったり、
抗がん剤治療の副作用で食欲不振や吐き気、口内炎などを発症し、食事が辛いと感じる人も・・・・。
だからついつい、毎日コンビニおにぎりで済ませる人も少なくない、と。
栄養が欠ければ体力が落ち治療に支障をきたします。
また食生活を楽しめないと、生活のリズムや心のハリも失いがち。
「とにかく、食べる。毎日、自分で作って食べる。
そうすることで、体も心も上向きになってほしい」
という気持ちから本書は生まれました。
レシピには、国立がん研究センター東病院で10年続く「柏の葉料理教室」からのリアルな声を反映しています。
【編集担当からのおすすめ情報】
このレシピ本、かなり他の本とはおもむきが異なります。なぜなら・・・・
◎調理時間の目安は5分。食材はキホン2つだけ。
◎めんどうな包丁作業「千切り」「みじん切り」ナシ。
◎食欲不振や吐き気、口内炎や便秘などの困った症状にも対応。
◎加熱は、ワザや経験がいらない電子レンジをフル活用。
◎缶詰、レトルト食品、冷凍食品、コンビニで売っている調理済みの食材も使ってヨシ。
そう、とくに最後のは「え、いいんですか!?」と何度も著者に確認しました。
著者いわくーー「できあいのものを買い、それにひと手間プラスするだけでも立派な自炊。
このレシピをひととおり作って食べていけば、必ず料理のヒントやカンをつかめます。
そしてままならない時期を乗り越えて体調がよくなれば、
安全性を意識して自分で食材を選んで買い、調理にチャレンジしようという気持になるはず。
本書がそのきっかけになれれば幸いです」

- ジェニー牛山先生の美と健康のレシピ
- ジェニー 牛山
- 講談社
- ¥2200
- 2018年03月27日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
メイ・ウシヤマ、ジェニー牛山親子が長年にわたってとりくんだ、自然食の研究と実践を、美容に関連づけて春夏秋冬で解説。

- 脳機能と栄養
- 横越 英彦
- 幸書房
- ¥7150
- 2004年03月18日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
誕生から死までの一生の期間、全ての人間の生活活動は脳によって支配されている。そして脳そのものの充実と機能化の構築に食べ物が大きく関係していることが解明されてきた。本書は脳の仕組みから脳を支える栄養素、脳機能の反映した行動と栄養との関わり、そして脳機能に影響を及ぼす食品成分について取り上げた。高ストレス社会、高齢化社会の中で、充実した人生を最後まで尊厳をもって全うするためには健全な脳機能を維持していくことは極めて重要である。本書は脳にとっての最適な栄養条件とは何かという事について随所にその方向性を示した最新の書である。
第1章 緒論ー食べ物と人間の行動
第2章 脳の仕組みと神経細胞
第3章 脳機能を支える栄養素
第4章 脳機能と栄養条件ー脳と栄養の接点
第5章 脳機能活性で注目される食品成分

- ココまで読める!実践腹部単純X線診断第2版
- 西野徳之
- 中外医学社
- ¥9900
- 2015年02月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
目の前の腹部単純X線写真に隠れた様々な情報ー患者の身に起きている今のできごとーを、「マニュアル」に頼るのではなく「自分の心」ですくい上げるための思考の方法・手順・注意点ー「臨床推論」能力を高めるためのコツをていねいに説明。今までありそうでなかった視点で書かれた診断書。

- 脚マッサージで、ベストカップル
- Akira
- 中央アート出版社
- ¥1026
- 2007年10月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
パートナーとの愛を育む足道法。一人より二人。身体も愛も癒される、カップルのためのLove Therapy。

- 基本的知識と症例から学ぶ がん緩和ケアの薬の使い方
- 岡本 禎晃/荒井 幸子
- じほう
- ¥3520
- 2019年06月24日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●痛み、悪心、便秘、倦怠感、せん妄、高Ca血症、不安・うつ…よくある症状・訴えのマネジメントに自信がつく
●緩和ケアのエキスパート薬剤師が教える正しいアセスメントと薬の処方提案
●基本的知識+症例の構成だから初学者の学びにもベテランのブラッシュアップにも役立つ
吐き気にメトクロプラミド、便秘に酸化マグネシウム…そんなパターン化した処方を提案していませんか? 緩和ケアの薬を正しく使いこなすには、正しいアセスメントが肝心です。
本書は、がん患者のさまざまな苦痛症状に対する緩和薬物療法をテーマに、エキスパート薬剤師が基本的知識をわかりやすく解説。豊富な症例を通じてアセスメントのポイントや処方提案の実際を教えます。知識だけでなく、臨床で本当に使える力が身につく1冊です。
痛みシリーズ
Lesson1 軽度の痛みに対応する 宗像千恵/龍 恵美
Lesson2 オピオイドの導入と患者・家族への対応 千原里美
Lesson3 オピオイドが必要な持続する痛みに対応する 大矢浩之/藤本英哲/佐野元彦
Lesson4 突出痛に対応する 岡本禎晃
Lesson5 オピオイドが効きにくい痛みに対応する 久原 幸/佐々木理絵
Lesson6 スペシャルポピュレーションに対応する 国分秀也
その他の症状シリーズ
Lesson7 悪心・嘔吐に対応する 村井 扶
Lesson8 便秘に対応する 槇原洋子/池末裕明
Lesson9 全身倦怠感・食欲不振に対応する 伊勢雄也
Lesson10 せん妄に対応する 宮部貴識/所 昭宏
Lesson11 不安・抑うつに対応する 田中育子/中嶋真一郎
Lesson12 高カルシウム血症に対応する 矢野琢也
Lesson13 苦痛緩和のための鎮静 嶽小原 恵/池永昌之

- 問診から選べる漢方薬ツールキット
- 樫尾明彦/長瀬眞彦
- カイ書林
- ¥2200
- 2020年11月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- ケーススタディで学ぶ がん患者ロジカル・トータルサポート
- 片山 志郎/平井 みどり/高瀬 久光/井手口 直子
- じほう
- ¥3520
- 2017年05月29日頃
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
●できる!問題解決のためのプロファイル作成力
ロジカル・トータルサポートとはがん患者への告知、治療、寛解、再発等の過程における心理の変化に対し、どのように患者を支援していくかを考える上で必要な医療コミュニケーションのひとつといえます。がんの症状緩和に導く薬物療法では包括的な患者背景や生活環境の情報収集が必須です。カルテ情報は患者情報の一部に過ぎず、医療スタッフ間でディスカッションを重ね、刻々と移り変わる病状を把握し患者のプロファイルを作成することで隠された情報抽出が可能になります。医療情報では、さまざまな仮説を立て論理的に薬物療法を検討、処方設計をするロジカル・トータルサポートを行うことの重要性が増しています。
本書は、ロジカル・トータルサポートの指南書であり、患者とのコミュニケーションを通じて患者の病状に応じた論理的かつリスクマネジメントにつなげる「先読み臨床力」を身につけるためのヒントとなり、ケーススタディを通じて患者の状態をロジカルに読み解き、その知見をもとに処方設計を行って医師・看護師とのカンファレンスで薬学的な視点で提案するまでを解説します。

- 画像・シェーマで納得!「つらい症状」のもとが見える
- 斎藤真理/水越和歌
- 青海社
- ¥3080
- 2015年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
本書に登場する医療スタッフたちと、12名のがん患者さんの「つらい症状」を画像で理解し、ケアにつなげていく。豊富な画像とシェーマで、単純X線、CT、MRIによる画像診断の基礎が理解できる。専門医師による緩和ケアにすぐに役立つ「おさえておきたい」トピックスも掲載。

- こども漢方
- 草鹿砥 宗隆/佐藤 大輔
- 源草社
- ¥2750
- 2015年06月15日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.5(2)
漢方の視点から小児医療にアプローチ
初めての本格的“小児漢方”専門図書!
地元・横浜で保育園の嘱託医を務めるなど、地域医療に密着しながら漢方医療を推し進める著者(草鹿砥)だから書けた、具体的な症例と詳細な考察。
西洋医学と漢方医学を対比した記述で、初学者から理解が可能。
各章にきめ細かな服薬指導ガイドを収載。家族用「こどもマッサージ」手技解説付き。
近年社会問題化している、こどもの“心の問題”にも深く斬り込んだ画期的な1冊。
はじめに 1
服薬指導時におけるアドバイス、注意点について 6
おすすめ食材 6
やさしいママのこどもマッサージ / 基本手技 8
ローションの作り方 11
第 1章 発熱・急性感染症 13
発熱・急性感染症対応の現状 14
漢方医学的アプローチ 〜外感病をどう捉えるか 16
こどもマッサージ〈発熱〉 26
服薬指導/使用処方 28
第2章 便秘症 29
小児便秘症対応の現状 30
漢方医学的アプローチ 〜便秘解消のストーリーをどう描くか 31
小児便秘症の症例 33 こどもマッサージ〈便秘〉 42
服薬指導/使用処方 44
第3章 下痢 45
下痢症状対応の現状 46
漢方医学的アプローチ 〜急性と慢性の心得 47
下痢症状の症例 50
こどもマッサージ〈下痢〉 58
服薬指導/使用処方 60
第4章 食欲不振 61 食欲不振対応の現状 62
漢方医学的アプローチ 〜漢方らしい細やかな配慮 63
食欲不振の症例 65 こどもマッサージ〈食欲不振〉 74 服薬指導/使用処方 76
第5章 慢性・反復性炎症症状 77
慢性・反復性炎症症状(中耳炎)対応の現状 78
漢方医学的アプローチ 〜標治と本治を同時に考えていく 79
慢性・反復性炎症症状の症例 81
服薬指導/使用処方 92
第6章 ・慢性的呼吸器症状 93
咳・慢性呼吸器症状対応の現状 94
漢方医学的アプローチ 〜本治を目指す柔軟な対応 95 咳・慢性呼吸器症状の症例 97
こどもマッサージ〈咳〉 108
服薬指導/使用処方 110
第7章 皮膚症状 111
皮膚症状対応の現状 112
漢方医学的アプローチ 〜治療原則と留意点 112
皮膚症状の症例 115
服薬指導/使用処方 124
第8章 夜泣き/ 夜驚症 125
夜泣き / 夜驚症対応の現状 126
漢方医学的アプローチ 〜頻用処方から読み解く 127
夜泣き / 夜驚症の症例 129
こどもマッサージ〈夜泣き〉 134
服薬指導/使用処方 136
第9章 冷え症状 137
冷え症状対応の現状 138
漢方医学的アプローチ 〜漢方的特質からの分類 138
冷え症状の症例 141
服薬指導/使用処方 152
第10章 心の問題 153
心の問題対応の現状 154
漢方医学的アプローチ 〜患児側との信頼関係 157
心の問題の症例 159
服薬指導/使用処方 166
こども薬膳レシピ 167
参考文献 175

- たそがれ食堂(vol.3)
- アンソロジー
- 幻冬舎コミックス
- ¥583
- 2017年10月16日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(1)
秋の行楽、運動会の思い出など「お弁当」が特集。今すぐ食べたくなるメニューが満載のオール新作グルメコミック!!

- 生物学者と料理研究家が考える「理想のレシピ」
- 福岡 伸一/松田 美智子
- 日刊現代
- ¥1760
- 2024年01月31日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(2)
私たち人間の体は、私たちを構成する分子のレベルで考えると、一秒たりとも休むことなく生まれ変わっている。一年足らずで私たちの体は、「まったく別人のように」変わってしまう。にもかかわらず、私たち人間はそうした変化を感じることもないし、決して動きを止めることのない変化に混乱なく生命を維持し続ける。こうした生命の在りようを著者の生物学者福岡伸一氏は「動的平衡」と呼ぶ。
「動的平衡」の在りようをわかりやすく示した表現として、福岡伸一氏は鎌倉時代に鴨長明が著した『方丈記』の冒頭の一節をあげる。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」
当然のことながら、そうした人間の「動的平衡」状態を維持するためには「食」が必須条件である。そして、その「食」がいかなる「材」と「質」と「加工」によって構成されているかが、人間という生命の「動的平衡」の健全度、健康度を大きく左右することになる。
本書の前半部では、第一線の生物学者である福岡伸一氏が、この「動的平衡」についてわかりやすく解き明かしながら、人間にとっての「食」の意味、理想の「食」のあり方を生物学的観点から解説。後半部では、福岡伸一氏の主張を踏まえながら、料理研究家である松田美智子氏が「理想のレシピ」を紹介。そのレシピ、食材についての福岡伸一氏が解説。

- 「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき
- 坪井 貴司
- 講談社
- ¥1210
- 2024年09月19日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.9(12)
記憶力の低下、不眠、うつ、発達障害、肥満、高血圧、糖尿病、感染症の重症化……
すべての不調は腸から始まる!
腸と脳が情報のやり取りをしていて、
お互いの機能を調整している「脳腸相関」と呼ばれるメカニズムが、いま注目を集めています。
〈乳酸菌飲料を飲んで睡眠の質が上がる〉
〈ヨーグルトを食べて認知機能改善〉
……という謳い文句の商品もよく見かけるようになりました。
腸内環境の乱れは、腸疾患だけでなく、
不眠、うつ、発達障害、認知症、糖尿病、肥満、高血圧、免疫疾患や感染症の重症化……と、
全身のあらゆる不調に関わることがわかってきているのです。
腸が、どのように脳や全身に作用するのか。
最新研究で分子および細胞レベルで見えてきた驚きのしくみを解説します。
■おもな内容
・記憶力に関わる脳部位と腸内細菌の関係
・腸内環境が変化したら肥満になった
・「ある種の乳酸菌」が自閉症の症状を改善させる可能性
・「長生きできるかどうか」に関わる腸内代謝物
・ビフィズス菌で脳の萎縮が抑えられ、認知機能アップ?
・腸内環境が変わると不安行動が増える
・「腸の状態」が感染症の重症化を左右するわけ
・睡眠障害が肥満や大腸がんを引き起こすからくり
・うつ病患者の腸で減少している2つの細菌種
・腸内環境を悪化させる「意外な食べ物」 ……ほか
【なぜ腸が全身の不調を左右するのか?「脳腸相関」の最新研究で見えてきた!】

- テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2003 AUGUST
- (ラジオCD)
- (株)ドリーミュージックパブリッシング
- ¥1826
- 2008年02月27日
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2003年4月から文化放送でスタートした人気番組をCD化したシリーズ。人気テニス・アニメ『テニスの王子様』のキャラクターが2人ずつパーソナリティとして参加、歌声を披露するなど素顔の王子様を堪能できる。

- ヘルスケア・レストラン(2020 3)
- 日本医療企画
- ¥1210
- 2020年02月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)

- 看護過程に沿った対症看護 第5版
- 高木 永子
- 学研メディカル秀潤社
- ¥5060
- 2018年09月26日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(1)
言わずとしれたベストセラー書籍臨床が8年ぶりに症状のメカニズムや検査・診断・治療やケア内容など最新知見から見直しを行い大改訂.臨床現場で頻繁に遭遇する症状50項目を取り上げ,より見やすく・使いやすくなった.
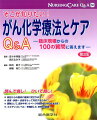
- そこが知りたい!がん化学療法とケアQ&A第2版
- 新井敏子/春藤紫乃
- 総合医学社
- ¥3740
- 2014年09月
- 取り寄せ
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
脳神経外科看護の要点を簡潔にまとめています!患者・家族へ 自信をもって対応するために!原則として, 読みやすい2ページの読み切りのQ&A方式!『エビデンスレベル』を明記して, EBMに配慮!

- うつ病の毎日ごはん
- 功刀浩/今泉博文
- 女子栄養大学出版部
- ¥1430
- 2015年04月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 2.5(2)
「食」生活をととのえることがうつ病改善の近道です。

- バンクーバー発!4コマ漫画で体感するから身につくほんとに使えるリアルな英語フレー
- 米田貴之
- 明日香出版社
- ¥1650
- 2014年01月15日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(4)
“Let’s see how it goes.”“It’s on me today.”“24/7”“That’s awesome!”食べて、飲んで、笑って、泣いて、恋に悩んで、ケンカもして…使うシーン&話す時の表情まで一瞬でつかめる!!