LGBT の検索結果 レビュー多 順 約 420 件中 1 から 20 件目(21 頁中 1 頁目) 

- にじいろガーデン
- 小川糸
- 集英社
- ¥1540
- 2014年10月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.69(127)
別居中の夫との関係に苦しんでいた泉は、両親との関係に悩み、命を絶とうとしていた千代子と出会う。戸惑いながらも、お互いをかけがえのない存在だと気づいたふたりは、泉の一人息子・草介を連れて、星がきれいな山里「マチュピチュ村」へと駆け落ち。新しい生活が始まるー。特別なようでいてどこにでもいる、温かな家族の物語。

- LGBTを読みとく
- 森山 至貴
- 筑摩書房
- ¥968
- 2017年03月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.82(34)
最近よく見かける「LGBT」という言葉。メディアなどでも取り上げられ、この言葉からレズビアン、ゲイの当事者を思い浮かべる人も増えている。しかし、それはセクシュアルマイノリティのほんの一握りの姿に過ぎない。バイセクシュアルやトランスジェンダーについてはほとんど言及されず、それらの言葉ではくくることができない性のかたちがあることも見逃されている。「LGBT」を手掛かりとして、多様な性のありかたを知る方法を学ぶための一冊。
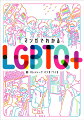
- マンガでわかるLGBTQ+
- パレットーク/ケイカ
- 講談社
- ¥1430
- 2021年04月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.41(32)
ーー「知らなかった」を言い訳にして、誰かを傷つける時代を終わらせよう
イマサラ聞けないLGBTQ+のギモンに答える入門書!
〇内容紹介
最近よく聞く「LGBTQ+」ってなに?
カミングアウトされたら、どうすればいいの?
カミングアウトするときに、気をつけなければならないのはどこ?
日常生活において、どういった不都合が生じているの?
職場ではどんな質問が「ハラスメント」になるの?
なぜ、同性での結婚は認められていないの?
法律で同性では結婚できないっていうけれど、パートナーシップ制度ではだめなの?
どうしたら、みんながより快適に過ごせる環境をつくれるの?
フェミニズムとLGBTのかかわりって?
本書は、いまさら聞けない「LGBTQ+」の基本から、最新の情報、お互いにできることまで、19の体験談を含む22のマンガを読みながら楽しく学べる作品です。各章には解説やよくある質問FAQもついているので、なんとなく興味がある人にも、詳しく知りたい人にもぴったり! 各章にワークもついていて、手を動かしながら理解を深められます
下記のような方々にオススメです。
・「LGBTQ+」について知りたい人、もっと学びたい人
・性に関する悩みがある人、モヤモヤしている人
・生徒の教室での居心地をよりよくしたい学校関係者
・職場で無意識にハラスメントしていないか気になる上司 など……
早稲田大学文学学術院 准教授 森山至貴氏 解説
第1章:LGBTQ+って、なんだろう?
ーさまざまな性のあり方を知って、理解を深めよう!-
自分のセクシュアリティをより深く理解できるワークシート付★
第2章:体験談から考える、さまざまなシチュエーション紹介
ーされるほうも、するほうも。カミングアウトで気をつけたいこと。-
カミングアウトされたら、どうすればいいの? カミングアウトしたいときはなにに気をつけるべき?
第3章:男らしさ、女らしさから解き放たれて
ー「らしさ」を押し付けて、知らないうちに誰かを傷つけていませんか?-
「女の子なのに料理ができない」のはダメなこと?、恋愛と友情のちがいがわからない……、身のまわりで起こる、モヤッとした「あるある」続出!
第4章:LGBTQ+と法律
ー同性婚できなくても、パートナーシップ制度があるからいいのでは……? そう思っていませんか?-
現在ある法律の問題点を整理し、なにが問題なのか考えよう! パートナーシップ制度と法律婚のちがいもわかりやすく解説!
第5章:これからの社会と多様な性のあり方
ー性のあり方についてもすこしずつ理解が進みつつある今、これから私たちは何ができるでしょうか?-
体験談や世界での事例をもとに、身のまわりでもっと良くできそうなことを考えてみよう。

- 爽年
- 石田 衣良
- 集英社
- ¥1540
- 2018年04月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.65(23)
映画化(R18指定)で話題の「娼年シリーズ」最終章
最後の、夜。
ー始まりはこのバーだった。
娼夫として7年もの歳月を過ごしたリョウ。御堂静香の後を引き継ぎ、非合法のボーイズクラブLe ClubPassion(「クラブ・パッション」)の経営を一手に引き受けるまでに。男性恐怖症、アセクシュアル…クラブを訪れる女性たちにも様々な変化が。
リョウは女性の欲望を受けとめ続ける毎日の中で、自分自身の未来に思いを巡らせ始めた。
性を巡る深遠な旅の結末に、リョウが下した決断とは……。
大ヒットシリーズ『娼年』『逝年』続編。

- 13歳から知っておきたいLGBT+
- アシュリー・マーデル/須川 綾子
- ダイヤモンド社
- ¥1650
- 2017年11月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.29(17)
自分の居場所を探す人、誰かの居場所をつくりたい人へ。約40名のLGBT+のインタビューを収録!

- LGBT BOOK
- 日本放送協会
- 太田出版
- ¥1361
- 2010年08月
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(16)
NHK教育テレビで放送中の福祉番組「ハートをつなごう」では、「性同一性障害」「ゲイ/レズビアン」「LGBT」と、2006年から4年間にわたって、性に関するシリーズを継続的にお届けしてきました。性の多様性について考えることは、「普通」について考えることにつながっています。

- 差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える
- 神谷 悠一
- 集英社
- ¥902
- 2022年08月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.82(15)
思いやりを大事にする「良識的」な人が、差別をなくすことに後ろ向きである理由とはーー。
「ジェンダー平等」がSDGsの目標に掲げられる現在、大学では関連の授業に人気が集中し企業では研修が盛んに行われているテーマであるにもかかわらず、いまだ差別については「思いやりが大事」という心の問題として捉えられることが多い。なぜ差別は「思いやり」の問題に回収され、その先の議論に進めないのか?
女性差別と性的少数者差別をめぐる現状に目を向け、その構造を理解し、制度について考察。
「思いやり」から脱して社会を変えていくために、いま必要な一冊。
「あなたの人権意識、大丈夫?
“優しい"人こそ知っておきたい、差別に加担してしまわないためにーー。
価値観アップデートのための法制度入門!」--三浦まり氏(上智大学教授)、推薦!
◆目次◆
第1章 ジェンダー課題における「思いやり」の限界
第2章 LGBTQ課題における「思いやり」の落とし穴
第3章 「女性」vs.「トランスジェンダー」という虚構
第4章 ジェンダー課題における制度と実践
第5章 LGBTQ課題における制度と実践
◆著者略歴◆
神谷悠一(かみや ゆういち)
1985年岩手県生まれ。
早稲田大学教育学部卒、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。
LGBT法連合会事務局長、内閣府「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」構成員、兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。
これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、自治研作業委員会「LGBTQ+/SOGIE自治体政策」座長を歴任。
著書に『LGBTとハラスメント』など。

- そういう生き物
- 春見 朔子
- 集英社
- ¥1430
- 2017年02月03日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(13)
薬剤師の千景とスナック勤めのまゆ子。10年ぶりに再会した二人は、思いがけず一緒に暮らし始める。高校の同級生である二人が心に秘めた過去とは? 愛と性、心と体のままならなさを印象的に描く傑作。

- はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで
- 石田仁
- ナツメ社
- ¥1760
- 2019年01月07日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.4(13)
LGBTにまつわる基礎的な知識を、はじめて学ぶ人にも理解しやすいようにまとめた書籍です。「性自認」「性的指向」といった基本的な用語解説のほか、カミングアウトや学校教育、当事者の健康、法律上の問題、地自体の取り組み、市民生活など、さまざまなアプローチからLGBTについて論じています。
プロローグ 「性」は多様
第1章 自分の性はどう伝える? 周りはどう受け止める?
第2章 どうしたら学校は過ごしやすい場所になる?
第3章 性的マイノリティの心と体の健康
第4章 性的マイノリティをとりまく法律上の問題を考える
第5章 自治体の取り組みと課題
第6章 社会生活ではどんな問題が起こっている?
第7章 生物学的性別も男女の2つでは語れない
第8章 未定
特別編 LGBTについて調査・研究するとき
エピローグ LGBT言説のその先

- LGBTとハラスメント
- 神谷 悠一/松岡 宗嗣
- 集英社
- ¥902
- 2020年07月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(13)
「“知らなかった"と“知ってるつもり"が“知って良かった"に変わる、必読の一冊です」--小島慶子氏(エッセイスト)推薦!
いわゆる「パワーハラスメント防止法」が二〇一九年に成立し、あらゆる企業がLGBTに関するハラスメント対策をとり、プライバシー保護の対応を行うことが義務化された。
しかし、未だLGBTに関わる政治家の失言やネットでの炎上事例は後を絶たない。
本書では「よくある勘違い」を多くの実例をもとにパターン分けし、当事者との会話において必要な心構えを紹介。
また、職場における実務面での理解も促す構成となっている。
知っているようで知らない、LGBTの「新常識」がここにある。
◆目次◆
序章「性の多様性」についての基礎知識
第一章「LGBT」へのよくある勘違いーネガティブ編
第二章「LGBT」へのよくある勘違いー一見ポジティブ編
第三章「LGBT」に限らないよくある勘違い
第四章「SOGIハラ・アウティング防止」法とは
第五章 LGBTをめぐる「人事・労務制度」
巻末付録「パワハラ防止指針」
◆著者略歴◆
神谷悠一(かみや ゆういち)
一九八五年岩手県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。
労働団体の全国組織本部事務局を経て、現在は約一〇〇のLGBT関連団体から構成される全国組織、通称「LGBT法連合会」事務局長。
松岡宗嗣(まつおか そうし)
一九九四年愛知県生まれ。明治大学政治経済学部卒。ライター。政策や法制度などのLGBT関連情報を発信する一般社団法人fair代表理事。

- みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT
- 遠藤 まめた
- 筑摩書房
- ¥902
- 2021年06月10日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.4(12)
恋愛における変なルール、個性を押さえつける校則、家族は仲が良くないといけない…。性の多様性を考えることで、「当たり前」から自由になれる。

- LGBTの不都合な真実 活動家の言葉を100%妄信するマスコミ報道は公共的か
- 松浦大悟
- 秀和システム
- ¥1650
- 2021年09月17日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.33(10)
性的少数者を表すLGBTに対する差別や権利擁護が社会問題としてマスメディアで大きく報道されるようになった。
しかし、一方で、LGBTに対する無理解や差別が大規模な炎上事件に発展するケースも増えてきている。
社会的な無理解や差別は、当然是正されるべきである。だが、少しでも自分たちと意見の異なる相手に対して「差別主義者」というレッテルを貼り、SNS上で激しく攻撃や罵倒を繰り返す、という状況は生産的ではない。
本書は、自身ゲイであることを公表している元参議院議員の著者が、このような現状を打破し、異なる考えを持つ人々とも対話の回路を確保するために、あえて急進的LGBT活動家が触れたがらない不都合な真実もあぶり出し、保守の立場からの新しいLGBT論を提唱する。
【章目次】
第1章 『新潮45』騒動とは何だったのか
第2章 LGBT活動家の言葉は、常に正しいのか
第3章 LGBTをめぐる報道と現実の落差
第4章 保守の立場から説く、新しいLGBT論
第5章 日本が持つアドバンテージを活かす
第6章 LGBTに対する理解を深めるために
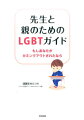
- 先生と親のための LGBTガイド
- 遠藤まめた
- 合同出版
- ¥1980
- 2016年06月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(9)
LGBTの子どもの悩みをキャッチできる先生になる、親になる。
もくじ
◆「LGBTフレンドリー」チェックシート
第1章 LGBTってどんな人びと? いまさら聞けない10のギモン
◦ 同性を好きになるって、どのような感じでしょうか?
◦LGBTは先天的なものですか? それとも後天的なものですか?
◦同性を好きになることは、思春期の一過性なものでしょうか?
◦LGBTは治療すれば治るのでしょうか?
◦LGBTの人は、まわりにいないと思うのですが……?/ほか
第2章 LGBTの子どもたちの悩みごと
◦性別違和のめばえ
◦「同性が好きな自分」が怖い
◦トイレに入れない、更衣室で着替えられない
◦およそ7割がいじめや暴力を経験している
◦教師のホモネタ発言でいじめがひどくなる/ほか
第3章 教師・大人ができること
◦「ホモネタ」やいじめのサインを見逃さない
◦カミングアウトはされる側も動揺する
◦まずはプライバシーを守る
◦保護者の理解を得るようにはたらきかける
◦子どもたちが安心するアドバイス/ほか
第4章 大人へのインタビュー LGBTの子どもと向き合う
◆息子からゲイであることを打ち明けられた清水尚美さん
(NPO法人「LGBTの家族と友人をつなぐ会」理事)
◆子どもたちの性へのギモンに答え続けてきた徳永桂子さん
(思春期保健相談士)
第5章 もっと知りたい方へ
◦日本にLGBTに関係する法律はありますか?
◦LGBTの問題について国連ではどのような取り組みがされていますか?
◦トランスジェンダーが受けられる医療行為にはどのようなものがありますか?
◦LGBTについて児童・生徒にどのように教えればよいでしょうか?
付録 今日から使える! LGBT対応のための資料集

- 愛と差別と友情とLGBTQ+
- 北丸 雄二
- 人々舎
- ¥2860
- 2021年08月20日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.29(9)
紀伊國屋じんぶん大賞2022 第2位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2025年韓国語版出版決定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
※本書の定価は、2,600円+税となります。
※全国の書店にて、定価でのお取り寄せ購入ができます。
世界を知り、無知を知り、人間を知る。
偏見を助長してきた言葉や文脈を更新し、日本で流通してきた「LGBTQ+」情報の空洞を埋める希望の書。
彼らは世界で何が起きているのかをほとんど知らない。日本で流通している日本語だけの情報で満ち足りて、そこから出ることも、その外に世界が存在することも考えていない。日本の世間は日本語によって護られているつもりで、その実、その日本語によって世界から見事に疎外されているのだ……。
──第4章「クローゼットな言語」より
〈推薦文〉
頭が沸騰した。アメリカの「LGBTQ+」百年の歴史の豊饒を受け止めた著者の目に、すべての私たちの未来が映っている。
──池田香代子(翻訳家)
どのような過去が、現在を作り上げてきたのかーー。蓄積と切り離された、安易な現状肯定は、手痛い揺り戻しを招きかねない。日本とアメリカを行き来し、各コミュニティの内と外を見てきたジャーナリスト。彼だから描ける、歴史と、その先。
──荻上チキ(評論家)
この本にあふれる愛は、日米を問わぬ遍きマイノリティへの讃歌でもある。小さき者たちがこの半世紀、歯を食いしばってクリエイトしてきた歴史や文化を再発見した。
──津山恵子(ニューヨーク在住ジャーナリスト)
以前、島根県隠岐之島に歌いに行った時に頂いた小学生からの手紙に、「うまれてはじめてオカマさんをみました」と書かれていた。その時感じた素直さと違和感。その間を埋めるものがこの本にはある。
──中村 中(歌手・役者)
本書は厳密な意味で、「ゲイ」の歴史学であり、社会言語学であり、政治学であり、社会学であり、哲学だ。一つの視座から捉え切れない全体性を描き出している。最後に著者は当事者として一つの公式に到る。恋愛=ヘッセ的友愛+贈与としての性行為。友愛の力を欠けば、恋愛を持続することも差別せずにいることも不可能だ──僕は全面的に賛同したい。
──宮台真司(社会学者)

- LGBT初級講座 まずは、ゲイの友だちをつくりなさい
- 松中 権
- 講談社
- ¥924
- 2015年05月21日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.33(8)
今、必修のキーワード「LGBT」は、L(レズビアン)G(ゲイ)B(バイセクシャル)T(トランスジェンダー)というセクシャル・マイノリティの総称です。本書は、ゲイであることをカミングアウトし、現役電通マンと認定NPO法人の二足のわらじを履いて活躍する著者が、自らの生い立ちも赤裸々に語りながら、LGBTといっしょにハッピーな世の中をつくりましょうと問いかける一冊。ゲイ能力を身につければ、絶対得します。
まえがき
第一章 セクシュアリティはグラデーション
第二章 自分へようこそ!
第三章 同じ人生はひとつもない
第四章 身につければハッピーなゲイのチカラ
第五章 未来のためにカミングアウトしよう
第六章 ゲイの友だちをつくる醍醐味
●おすすめLGBTムービー・ベスト10
あとがき

- 職場のLGBT読本
- 柳沢正和/村木真紀
- 実務教育出版
- ¥2200
- 2015年07月22日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.63(8)
今や、最先端の経営課題!性的マイノリティと共に気持ちよく働く職場づくりのための、初のハンドブック!

- 改訂新版 LGBTってなんだろう?
- 藥師 実芳/笹原 千奈未/古堂 達也/小川 奈津己
- 合同出版
- ¥2200
- 2019年05月13日頃
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.0(8)
体育やプール、制服、学校行事、友だち関係、カミングアウト……
LGBTの子どもたちにとって、日常生活の中にもたくさんのつらい場面や不安な要素があります。
そんな時、身近に一人でも相談できると思える人がいることが何よりも力になります。
教育に携わる人はもちろん、子どもとかかわるすべての大人に読んでもらいたい1冊です。

- LGBTってなんだろう?
- 藥師実芳/笹原千奈未
- 合同出版
- ¥1980
- 2014年09月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.6(7)
LGBTは、20人に1人いるといわれています。学校生活、友だち関係、いじめ、将来への展望、カミングアウトなど、LGBTの子どもたちは、毎日、不安に押しつぶされそうになりながら生活しています。子どもたちとかかわるすべての大人に知ってもらいたい、LGBTの子どものこころに寄り添うための本。

- カラフルなぼくら
- スーザン・クークリン/浅尾敦則
- ポプラ社
- ¥1650
- 2014年07月31日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 4.2(6)
20人に1人がLGBTといわれるこの時代に、自分の「性」と向き合うということ。6人のティーンが語る、LGBTの心と体の遍歴。

- LGBTQを知っていますか?
- 日高庸晴/星野慎二
- 少年写真新聞社
- ¥1540
- 2015年12月
- 在庫あり
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 3.6(6)