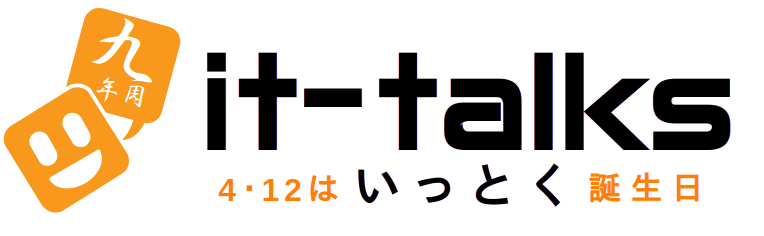アメリカのドラマを見るようになってから、アメリカの図書館に興味を持っていた。
例えば『ホワイト・カラー』では、逃亡準備用に買った新しいID類一式の中に、図書館カードが入っていた。そして彼のその図書館カードがいかに重要な「実在証明」になるのかが、売り手側から語られた。ていねいに数年かけて実際に使い、利用履歴の中身まできちんとある「ほんもの」のカードなのだと。
また、『クリミナル・マインド』のどれだったか、分析官のガルシアが「おかしいんですよね、クレジットやケータイの履歴も社会保障番号も追えない、おまけに図書館カードの利用すらないなんて、ありえない」と首をかしげてたこともあった(はず)。
図書館カードは、どんな人間でもアメリカ人なら持ってるのが当たり前のものらしい。どうして?
それは図書館が、生活必需品、欠くことのできない公共インフラのひとつだからだ。「情報」についての。
冒頭、リチャード・ドーキンスが、世代を超えて知の集積ができていくことが人間の特徴、というような話をしていたのだけど、それが映画の底の底で効いてるように思う。
ニューヨーク公共図書館は、まるで巨大な公民館のようだ。ただしそこには膨大な蔵書・資料があり、有能で熱意ある企画運営スタッフがおり、民主主義への絶対の信頼と誇りがある。
映画には図書館の多様な活動と企画、イベント、講座が出てくる。講師やゲストの多様さやその語りのタブーのなさそのものが、自由を象徴しているように感じた。宗教も政治も性も歴史解釈も、他人にさえぎられることなく語られる。老若男女という「立場」も関係なく。
あらゆる人があらゆる情報に触れ、それによって自由に生きることができるように手助けする。そういう基本的な指針が底にあり、活動を決定しているのがよくわかる。
図書館の資料で何ができるか、なされるか、それは、過去の見解の見直し、比較、検証、改定、改訂、その他。一方の見解のみを採用するのでは、それはできない。すべての見解を資料として平等に扱わなければ意味がないのだ。
そういったことを、監督は、ストーリーでもなくまたセリフでもなく、撮影したエピソードの選択と編集で語らせているように思った。見終わって、わたしはまた、冒頭のトーク企画でドーキンスの語った話を思い出していた。
決して、単なる図書館ツアーの映画ではない。「公共」とは何かを考えるための映画、だった。
※追記
印象的だったところ。
各分館スタッフ・ミーティングで、女性スタッフが「みんなでここまでやってきた、でもまだ先がありますよ、またやってきましょう」という趣旨のことを語りかけるところがあるのだけど、そこ見てて、ラブリーガルのジェーンを思い出した。なんというか、あーほんとにリアルに、ドラマや映画のダイアログでなくまた女優でもなく、こういうミーティングでこういうふうに語りかけてもりあげる人がいるのか、と、驚かされた。すごいプレゼン能力というべきか。