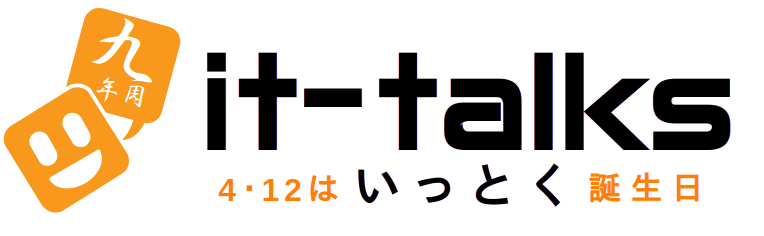「NHK語学講座」というアプリで過去2週間分の「ラジオ英会話」を聴いてて、①英語耳をつくる、②毎日3つの英作文だけやる、という方針が見えてきたので、約20年ぶりにテキストを買ってきた。この間に、恐ろしく世の中は便利になっていて、「らじる★らじる」や上のアプリで約2週間分の放送が聴けるようになっていて驚いた。とにかく楽しんで、まずは慣れるところからはじめたい。
![]() お話しするにはログインしてください。
お話しするにはログインしてください。
日常のことを語る
自分(id:happysweet55)のことを語る
自分で英語の単語帳をつくる時に、品詞を次のように省略表記すると便利だなと思ったのでメモ。わりと日本の和英辞典の巻頭にはいいことが書いてあって、便利です。
n.:noun 名詞
C:countable noun 可算名詞
U:uncountable noun 不可算名詞
v.t.:transitive verb 他動詞(T)
v.i.:intransitive verb 自動詞(I)
auxil.v.:auxiliary verb 助動詞
adj.:adjective 形容詞
adv.:adverb 副詞
prep.:preposition 前置詞
conj. :conjunction 接続詞
sing.:singular 単数形
pl.:plural 複数形
abbr.:abbreviation 略語
ちなみに『Oxford Advanced Learner’s Dictionary』には、このほかに「sb.(somebody)」「sth.(something)」といった省略語が解説文の中に多用されていて、上とともに完璧に理解していないと、何が書いてあるのかが分からない構成になっています。さすが上級学習者向けの英英辞典って唸ったけれど、初めはチンプンカンプンでした。
自分(id:happysweet55)のことを語る
すこし上のレベルの英単語2000語で、よく理解できていない単語は600語程度あると予測した。1日20個覚えれば、1ヶ月で1周できるのだ(間違えたものは3回まわすので実際は2、3ヶ月かかる)。30分で100個テストして、残り30分で間違えたものを辞書で引いて、例文を読んで頭に叩き込む。①まず問題を解く、②間違えたものは必ず辞書を引く、③間違えたものだけ3回復習するが10個くらいの資格試験を通して学んだよい学習方法だ。とはいえ、楽しくなかったら続かないので、いろいろ回り道や寄り道も楽しんでいきたい。
日常のことを語る
モレスキンの赤いポケットノートが届いた。何となくハードカバーではなくて、ソフトカバーのほうが手に取って書き込みやすそうという理由で注文したんだけど、いい感じ。ただ2000単語のうち、知らない英単語ってどのくらいあるんだろうか?192ページあって、1ページあたり約20行ある。仮に分からない単語が1000語あるとして、詰めて書いて50ページ、1行空きで100ページを使用することになり、ちょうどいい感じだ。『カムカム』の虚無蔵さんの名言、「どこで何をして生きようと、お前が鍛錬し、培い、身につけたものはお前のもの。決して奪われることのないもの」「されどその宝は、分かち与えるほどに、輝きが増すものと心得よ」という言葉を胸に一生愛用していきたい。
日常のことを語る
とあるネット記事の見出しに「東洋の真珠」という表現があって、めっちゃ昭和を感じた。ただ、デヴィ夫人がそう言われた以外、具体的にどこの国のどの場所を指している言葉なのか分からなかった。調べてみると、フィリピンのマニラ、マレーシアのペナン島、香港を指すことが多いらしい。昭和の人たちは真珠を有り難がっていたけれども、令和の人たちは何を有り難がるだろうか。最近「ビーチグラス」というものを知ったんだけれど、そういうものだったらいいな。「それを見つけた人にしか、その美しさや感動は分からないのだ」と。
日常のことを語る
何となく自分の実力よりすこしだけ上の英単語を2000語くらい覚えようと、アプリで勉強し出したら、分からない単語をストックするための小さなノートが欲しくなってポケットサイズのモレスキンを2冊買ってしまった。一つは英単語帳で、もう一つは特に用途を決めていない。久しぶりにとてもワクワクした。何でかはよく分からないけれども。スマホが普及する前にはこういうのが結構あった気もする。
日常のことを語る
前の投稿と逆かその通りのことかもしれないけれど、いらないサブスクを全部止めて、NHKオンデマンド(月額980円)を契約して、『映像の世紀〜バタフライエフェクト〜』を全話観ることにした。すこし前に放送されていた「ゼレンスキーとプーチン ウクライナとロシアの100年」の回が本当に衝撃的だったのだ。ぼくは高校生の時に図書館で『映像の世紀』を全巻見て、いつか世界に出て、広く深くこの世界について知りたい、考えたいと思っていたんですが、もう一度その心を取り戻したいと思う。ちなみに、ぼくはもう20年ぐらいテレビがない環境で暮らしているので、スマホやタブレットで『ドキュメント72時間』、『新プロジェクトX』、『魔改造の夜』、『新日本風土記』が観れるだけでも最高で、本当にありがたいです。
仕事のことを語る
起業してから、ずっと人の家に転がっていたScanSnap1500を使っていたんだけれど、つい最近壊れてしまったのでScanSnap iX1600を購入した。1回東京や大阪に勉強会や講習会へ行くと万単位のお金がかかるので(仕事に合わせて交通費を貰いながら行くのだ)、判断に迷いはなかった。しかし、今年はこういう必要不可欠なもの以外は徹底的に買わずに、人に会いに行ったり、視野や見聞を広げることにお金を使おうと思った。モノを買っても、人はパワーアップも成長もしないんだと肝に銘じたい。
自分(id:happysweet55)のことを語る
今日ふとポーランド、モルドバ、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、スロバキア、セルビア、コソボ、北マケドニア、ギリシア、トルコ、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンと黒海周辺の国の位置関係を頭の中で確かめていたんだけれど、「バルカン半島」という概念がないとヨーロッパの地図は描けないし、「南コーカサス」という概念がないと黒海とカスピ海の位置関係すら曖昧になると思った。さらにこの辺の歴史となると、ぼくは20世紀と中世と古代のほんの一部しか分からないと思った。というわけで、トルコとギリシア、バルカン半島、南コーカサスの国についてもっと知りたいなと思った。どうでもいい知識や好奇心が、何かを深く理解する時に役立つこともあると信じて。
自分(id:happysweet55)のことを語る
眠れないので、NHKプラスで『坂の上の雲』を観た。最近100年という時間をよく考えるんだけれども、自分の祖父は1925年生まれだったことに初めて気づいた。普通選挙法が制定され、アメリカは好景気で、日本がソ連と基本条約を結んだ年だった。日露戦争は、それより20年も前の出来事であることに改めて驚く。明治が始まって、たった36年でロシアと戦ったのだった。祖父は18、19歳で戦争へ行ったけれど、31歳の時には「もはや戦後ではない」という時代(1956年)を生きていた。色んな見方はあるけれど、「30年あれば、色んな物事は大きく変わる」のだと思った。暗く混沌とした世の中だからこそ、ぼくはよい希望を持っていたいと感じた。
自分(id:happysweet55)のことを語る
また静かに雪が降りだした。前回、今季の最強寒波とか言われていたけれど、ぼくの住んでる場所では冬に2、3回の大雪が降って然るべきなのだ。雪が降らないと、山々に水が溜まらないし、木も大きく育たないし、草花も早く芽を出してしまうし、様々な生き物の卵も間違った時期に孵化して死んでしまうのだ。去年の秋、息絶え絶えなカマキリが、毎年ヤバいくらい雪が積もる郵便ポストの上という最悪な場所に産みつけた卵を見るたびに(その時に一瞬、目が合った気がするのだ)、とてつもなく大きな自然の中で自分もまた生きてるのだと思うのだった。春にカマキリたちが無事に孵化するまで、ぼくは雪かきをするのだ。
自分(id:happysweet55)のことを語る
ちなみに、この機会に『日本書紀』(色々ガバガバな)についての歴史も追っていたのだけれど、口伝がまとめられたのが6世紀(たぶん500年代半ば〜後半)で、620年に聖徳太子らが『天皇記』『国記』としてまとめたんだけれど、645年の大化の改新で蘇我氏が燃やしてしまい(7世紀)、720年に完成したらしい。同じく『旧約聖書』もモーゼの時代(紀元前16世紀か13世紀と言われる)から、正式に定まったのが1世紀と言われているし、仏教も三蔵法師まで約1000年なので、何でも何かが定まるのには1000年かかるんだなと思った。1000年くらい前のことを伝えていく人類の営みに頭がクラクラしたのだった。
自分(id:happysweet55)のことを語る
旅行中、神武東征(『日本書紀』によれば紀元前667年-660年)が、自分の想像より1000年も早いことを知って、ずっと考えていた。しかし、紀元前1000年には権力者の誕生を可能にする水稲が日本に伝播していたので、あながち間違いではないと感じた。ぼくは単純に卑弥呼なき後の邪馬台国の人たちが3、4世紀に大和地方へ移り住んでいった、または権力の中心が移ったと考えていたんだけれど、それよりもずっと早く別の九州の人たちが大和地方に移り住んだ可能性のほうが高いと感じた。というのは、248年の卑弥呼の死後(3世紀半ば)、3世紀後半にはもう大和地方には古墳ができ始めていたし、4、5世紀にはヤマト王権は全国的な関係を持ち影響力を持っていたからだった。邪馬台国がどこにあったかは分からない。だけれども、大和地方にはどこかから移り住んできた人たちが、同時期にもっとすごい国を造っていたと考えたほうがいろいろと納得がいくのだった。
日常のことを語る
6時間かけて、紀伊半島の先から帰ってきた。8時にホテルを出て、1時間くらい広い海を座って眺めて、ガソリンと気合いを入れて、クタクタになって帰ってくるのが恒例だ。また年末に行こう。年の瀬が押し迫る静まりかえった時期に熊野灘を見に行きたいと思う。
日常のことを語る
今日はホテルに連泊することにして、午後から「海の熊野古道」と呼ばれる海岸を数キロ歩いた。熊野灘の多くの浜はだいたい砂のない玉砂利の礫岸で、1〜2mくらいの大きな波が打ち寄せている。一回でも波にさらわれたら終わりだなと思いつつ、冬の冷たく澄んだエメラルドグリーンの大きな波と深い太平洋のブルーの色合いの美しさに見惚れてしまう。たまに外洋を行くタンカーや漁船が小さく見える。石ころだらけの海岸を歩いて、座って海を眺めて、また歩いて過ごした。ぼくは時々こんな風に海を見ないといけない人なのだ。
日常のことを語る
7年ぶりに熊野本宮大社へ参拝した。熊野山地自体が神聖な雰囲気を持っているんだけれど、本宮はその中心に相応しい空気に包まれている。熊野本宮はもともと三つの川の中洲に建っていて、「此岸」と「彼岸」を感じさせる場所だったのだ。今の本宮は移設された後のものだけど、旧宮社があった場所に建てられた大鳥居で、その神々しい雰囲気をひしひしと感じることができる。来るべき時に、来るべくして、ぼくは熊野大社本宮へ参拝してるんだな、と実感するよい時間になった。
日常のことを語る
お腹が空いていたので、ホテルでひと休みしてから、馴染みのお鮨屋さんに行って、今日一番いい魚のお刺身を造って貰って、日本酒を一合頼んだ。ぼくは年一回、ここでしか呑まないので、すぐに酔っ払った。白子のぽん酢、カキフライ、太刀魚の塩焼きと順に頼んで、時間をかけて味わった。地場で獲れた、冬が一番美味しいものを食べるのだから外しようがない。〆はマグロの巻き寿司にした。また一年後に来ますと行って、ポカポカした気持ちで自電車を押して帰ってきたのであった。
日常のことを語る
特に予定を決めず、車で5時間かけて、紀伊半島の先まで来た。毎回のことだけど、奥伊勢から熊野までは山の上を走ってる感じで、そこはかとなく『日本書紀』の匂いを感じる。諸説あるけれど、4、5世紀の頃には、のちに大和朝廷に続く人がこの深い山と森の中を歩きまわっていたのだと想像するとワクワクする。で、紀勢道の最終地点で降りると、ほぼ雲と同じくらいの高さまで聳える海が見えて、いつも胸を打たれるのだった。視覚効果だけれど、ぼくはその空くらい高い海が見たくて、この地に足を運んでいるのかもしれない。冬の熊野灘の色は、見る人の心を強く打つのだった。
自分(id:happysweet55)のことを語る
ジャズ寄りのアーティストのライブでよく使われている椅子のような楽器がほしいなと思って調べたら、「カホン」という楽器だった。ぼくはギターとピアノを入手すると、廃人になるまで触ってる自信があるので、パーカッションくらいがいいのかなと思う。作曲した曲の強度を確かめるためには、一定のリズムを叩いて、唄ってみるのが一番いいのだ。しかし、カホンがあったら、ますますクリーンなエレキギターで多重録音したくなるはずなので、グッと我慢なのであった。
音楽のことを語る
関西に多いスーパー、平和堂でよく流れているテーマ曲「かけっことびっこ」にインスパイアされたAメロが思い浮かんだので、3日間ずっとメロディだけ口すさんでいたら、Bメロ、Cメロまである昭和のアニメソング(歌詞つき)ができてしまった。いつも基本的にぼくはギターリフやドラムパターンから脳内作曲をしてるので、J-POPってこうやってつくってるのかと感動してしまった。というか、ギターかピアノで弾いて歌いたくてしょうがないのであった。